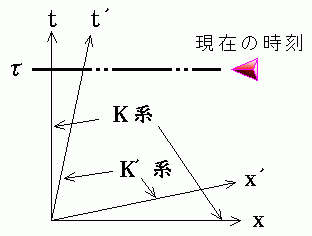
《実在性》という概念を軸にした場合、《時間》の概念は、次の3つのタイプに分類されるだろう:
以下の議論では、《過去》《現在》《未来》の区別を実在的なものとして扱う(i)と(ii)の立場が、物理学の観点から反駁されることを示し、科学的に支持される時間概念は、3分法を採用しない(iii)だけであることを明らかにする。
一言注意しておきたい。《時間》についての見解には、そもそも1次元的な時間軸の存在を認めないなど、哲学や神学の議論として、ここに述べた以外にもいろいろなタイプのものが提出されている。また、「分岐する時間」や「振動する時間」のように、SF的なアイデアも数限りなくあるだろう。しかし、これらの諸説については、一般に、論理の基盤となる基本的な前提を明らかにしておらず、以後の考察を進めるに当たって科学的方法論を援用できないという理由で、ここでは敢えて取り上げない。この方針は、およそ学問的な議論を展開するには、論理を組み立てるための足場を確保する必要上、明確に述べられた何らかの仮説を導入しなければならないはずだという方法論的立場に依拠している。実際、宗教的啓示を通じてのみ与えられるような観念や、SF作家の奔放な想像力が生み出したアイデアについて、どのようにして学問的に語れば良いのだろうか。時間についての議論を意味あるものにするためには、自然科学で扱われる時間概念――すなわち、「物理量の関数的表現に引き数の形で現れる、局所的に実数体と同型な、有限または(半)無限の1次元的バラメータとしての」時間――か、あるいは少なくとも洗練すればこれに近づくようなイメージに基づいて考察すベきだろう。この論考で《時間》が語られるときには、こうした方針に則って、過去から未来へ伸びた1次元的な時間のイメージが念頭に置かれていると考えていただきたい。
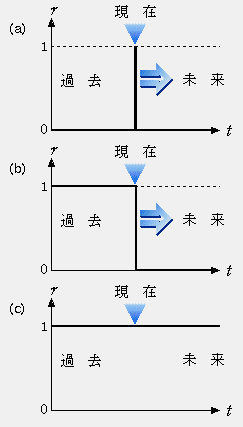
実在性に準拠する《時間》の捉え方としての前記3タイプは、《実在度》という便宜的なパラメーターrを導入すると理解しやすいだろう。ここで《実在度》とは、物理的に厳密に定義される量ではないが、考えている状態が実在する場合はr=1、実在しない場合はr=0と置き、0<r<1の範囲は仮想的な“半実在”の状態を表すものとする。ただし、「実在」の何たるかについては、全ての物理量が一意的に定まっていて変更不能だという性質を要求するにとどめておこう。このパラメーターを用いれば、《現在》のみが実在すると見なす(i)の見解は、実在度rが《現在》にパルス状のピークをもつ上図のグラフ(a)で表される。同様に、《現在》と《過去》の双方に実在性を認める(ii)の見解はグラフ(b)で、また、《過去》から《未来》までの全時間が実在していると仮定する(iii)の見解はグラフ(c)で表現されることになる。なお、これ以外にも(パルス状関数やステップ関数ではなく滑らかな関数形にするなど)グラフの形としていろいろなものを選択する自由度は残されているが、この段階では《実在度》はあくまで便宜的なバラメーターと見なされており、その関数形に物理的な意味はないので、ここであげた以外のグラフについては考察しない。
上のグラフから見て取れるように、《過去》《現在》《未来》の区別が実在的だとすると、時間軸上の状態Ψ(世界の物理的状態を決定するために必要十分な情報のセット)は、《現在》を指定する時刻τを境にして、「物理的に」変化しているはずである。厳密に言えば、τは全空間領域で一意的に定まるものではなく、4次元多様体内の超平面として定義すべきかもしれないが、ここでは、それほど理論的な議論をする必要はないので、“常識的に”《現在》の時刻が定まるとしておこう。こうした事情をあらわに書けば、実在的な状態はΨ(τ)のように記され、時刻τが《現在》であるような世界の状態を表すことになる。
物理学的にみて問題としなければならないのは、このτが、時間軸上の任意の値を取り得る「変数」ではなく、実在する唯一の時刻たる《現在》を表すべく、特定の値に固定されている「物理量」だという点である。うっかりすると、τを変化させるだけで異なる時刻を《現在》とする状態が得られると考えてしまいがちだが、そのような「実在を更新する」ダイナミクスは、既存の物理理論ではそもそも想定されていないのだ。しかも、Ψ(τ)が「時間的に厚みがない」――すなわち、実在する《現在》が一瞬にすぎず、微小な時間間隔δτだけ隔たっている2つの時刻の状態の問に何の共通部分も見いだされないため、ある瞬間τから次の瞬間τ+δτへと状態が“遷移する”には、Ψ(τ)が忽然と消失して、その代わりにΨ(τ+δτ)が現れるという。物理的には理解できない状況を考えるしかない。まさに、「《過去》は何処に去り、《未来》は何処から来たらんや」である。
既存の物理学理論は、物理的状態を実在度によって区別することはせず、全時刻の状態を同等に扱っていたため、こうした問題が生じる余地はなかった。例えば、量子力学以前の力学や電磁気学では、ある瞬間における系の状態を定めれば、それ以後の任意の時刻での状態が決定できるという意味での(物理学的な)因果律が成立しているが、このような因果律の成立する理論では、過去から未来にわたるすべての状態を1つの「軌道」として表記する形式が整備されており、系の記述から「時間の流れ」という概念を完全に排除することが可能になっている。この場合、《時間》とは「軌道」上の位置を指定する単なるパラメータにすぎない。実在性を有する《現在》が「時間の流れ」という形で軌道に沿って移動していくというプロセスは、フォーマリズムからして理論的記述の中に入り込むべくもないのである。
さらに、瞬間的な《現在》だけが実在すると考える立場からみれば、人々がしばしば自明だと見なす「《過去》の揺るぎない既定性」すらも疑わしいものとなる。なぜなら、この見方では、《過去》は非=実在の彼方へ消え去ってしまうため、“かつて”その状態が実在したことを示唆するのは《現在》に残されている事跡のみとなり、何ら痕跡をとどめないような《過去》の出来事については、《現在》のデータのみによって細部を確定できなくなるからである。しかも、実在性が認められるのが《現在》という一瞬間に限られているため、その“薄っぺらな”内部に宇宙始まって以来の全ての情報が蓄積されているとは考えにくく、不十分なデータに起因する不定性が《過去》に生じていると見るのが順当である。もっとも、《現在》の状態だけから《過去》が確定できないからと言って、《過去》が実際に特定の状態をとっていなかったと主張する根拠にはならないとする反対意見もあるだろう。だが、この反論が成立するためには、《過去》から《現在》に到る各状態の間に因果の連鎖(あるいは「時間を流れさせる」ダイナミクス)が存することが必要である。さもなければ、τを《現在》とする状態Ψ(τ)は、他の状態とは何の繋がりもないままに自足してしまい、《過去》などなくてもかまわないはずである。ところが、時空連続体としての世界を時間軸に垂直に“スライス”して、その中の特定の瞬間だけに実在性を認めるという発想は、まさにこうしたダイナミクスの存立する余地を奪うものであり、したがって、「過去の出来事の痕跡」という“物証”がない限り、異なる時刻の状態を結び付けることはできなくなる。こうして、《現在》から見た《過去》は、(単に知り得ないのではなく)本質的な不定性を抱懐すると結論されてしまう。
この(―種の)バラドクスを回避するには、《現在》がある程度の拡がりをもっていると仮定するのが最も簡単だろう。こうすれば、実在と非=実在の境となる時刻に物理的な“界面”が生じ、《現在》内部の相互作用を通じてこの界面が《未来》の方向へダイナミカルに“前進”すると考えることによって、時間が流れる過程を理解できるようになるかもしれない。しかし、この仮定は、こんにちの科学的知見から余りに乖離しており、素直に受け入れる訳にはいかない。具体的に言えば、現代物理学の基本的な時空観の下では、《時間》は軸方向の並進に対して不変性のある一様な座標と解釈され、この性質に基づいて(ネーターの定理を使って)エネルギー保存則を導き出している。したがって、こうした枠組みの中に、《現在》の内部に(実在と非=実在の間の物理的な界面としての)不均一な構造を有し相互作用を介して力学的に流れるという。ダイナミカルな《時間》の概念を組み込むのは、およそ不可能である。もちろん、科学的知識は決して絶対的なものでなく、将来の科学革命によって現行の時間観が大幅に変更される可能性もあるだろう。しかし、現代科学がさまざまな分野との情報交換を通じて徽密に体系化されており、理論の基幹部分での修正が予想もつかない方面へ影響を及ぼすという現状を考えれば、こうした変革を、これまでの科学的研究の成功を偶然の産物に帰せしめないようにしながら行うことは、きわめて困難な作業だと言わざるを得ない。
以上の議論に基づき、《現在》のみを実在すると見なす(先の(i)で述べた)時間観は、物理学的に容認できないと結論することができる。
もはや動かし得ない既定の事実として全ての《過去》を実在的と見なす一方、《未来》はいまだ定まらざる状態として非=実在的とする見解は、おそらく、一般の人々の間に最も広く流布している時間観だろう。直観的な言い方をすれば、時間の流れは、未定状態にある“相”が既定状態の“相”へと相変化していく過程であり、2つの相の界面が《現在》に相当すると解釈される。
しかし、この見方に対しても、現代の物理学は、容赦のない批判を提出する。まず、既に(i)の見解に対する批判として述べたように、既定の《過去》と未定の《未来》の界面としての《現在》が移動していくダイナミクスは、こんにちの科学的自然観とは共立しがたい。上の相転移のアナロジーは、なるほど直観には訴えるものの、実在していないはずの《未来》が物理的状態を表す“相”に擬えられるという・科学的に了解不能な言明を含んでおり、この相転移を実現するための物理的機構を既存の科学用語をもとに記述するのは、想像することすら困難な作業である。
さらに決定的なのは、《過去》と《未来》の物理的な界面として《現在》を定義する理論は、その正当性がきわめて高い精度で認められている特殊相対論の知見と真っ向から対立するという点である。このことは、次のようにして示される。《過去》および《現在》の実在的な状態を表す記号的表現Ψは、《過去》を記述するための時間座標を与える時間的バラメータtと、この座標軸の特定の値を指示する《現在》の時刻τの2つを含む。このうち、tは地球の自転や分子振動をもとに適当に定めた起点からの経過時間を表すもので、一般的な用語法での「時間」と同一視して、形式的に《未来》へ外挿することが可能である。これに対して、τは《現在》が時間軸上のどの点に位置するかを決定するもので、《現在》が既定と未定の界面としての物理的な意味をもつ系では、τの値が物理量として測定可能でなければならない。ところが、このような特別な時刻――正確には、空間的超平面――が存在する場合、特殊相対論が要求するローレンツ変換に対する理論の不変性と矛盾が生じる。ここで。ローレンツ変換とは、(光速c=1としたときの)時間座標tと空間座標xが、等速度運動をする観測者からみて、
に置き換えられることを指し、特殊相対論の主張は、このような変換を施しても物理法則は形式的な同一性が保たれるという内容である。ところが、《過去》と《未来》の境に物理的な界面がある場合、この界面がt=(―定)の超平面で表される座標系だけが世界の物理的状態を最も適切に反映しており、この座標にローレンツ変換を施して得られる他の座標系は。《現在》が“傾いている”(=場所によって《現在》の時刻が異なる)虚構的な表現しか与えないことになる(下図)。このような物理的システムは、明らかにローレンツ変換に対して不変でない。現在の知見では、ローレンツ不変性は(ジェット機に原子時計を積んだ直接的な実験から、特殊相対論に基づく素粒子論や宇宙論の成功などを含めて)多くの分野でほぼ確実に実証されており、これに違背する理論は、よほどの整合性がない限り直ちに棄却されるべきだろう。
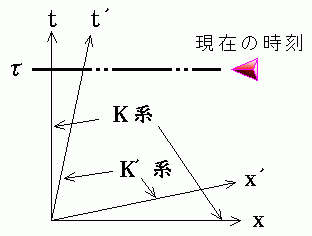
ローレンツ不変性に関する議論は、次のように形式的に表現することができる。すべての物理的自由度を4次元座標(x,t)の関数としてφ(x,t)と表すと、《現在》が時刻τ(より正確にはτで指定されるある空間的超平面)であるような世界の状態は、τをあらわに含む汎関数Ψ([φ];τ)で記述される。「時間の流れ」が物理学的な法則に従うとすれば、「現在」が異なる状態への遷移を与える“時間の流れ演算子U”が存在し、
Ψ([φ];τ') = U(τ',τ)・Ψ([φ];τ)
と書かれることになる。ところが、こうした演算子Uは、特別な座標系を指示するτという量を直接的に参照するため、一般に、(x,t) の座標変換に対する共変性はない。したがって、
… Ψ(x,t;τ) → Ψ(x,t;τ') → Ψ(x,t;τ") …
と表される「時間の流れ」を持つ世界では、相対論は成り立たないはずである!
なお、ローレンツ不変性のような物理学的な知見に頼らずとも、《現在》を表す時刻τが時間座標tとは別個に存在するという命題を反駁する論拠は、τを測定する手段の欠如に求められる。素朴に考えれば、《現在》の時刻は、眼前の時計を見さえすれば測定できると思われるかもしれない。 しかし、時計の針がある時刻を指しているという事態は、それが《過去》 のものになっても《現在》にあったときと同様の存在様式を示しており、《現在》と《過去》を弁別する指標とはならない。例えば、「時計の針が午後8:00を指している」という事態は、8:00に実地に観測しても、8:1Oに10分前の記憶として回想しても、実質的に同一のものであり、《現在》の時刻が異なっている状態――すなわち、Ψ(τ=8:00)とΨ(τ=8:10)――に属する別個の事態として識別することはできないはずである。これに対して、現に観測している場合は「生き生きとした」実感が付随しているはずであり、この実感が《現在》と《過去》を分ける要素になると主張する者があるかもしれない。しかし、《過去》を実在するものとして認めている以上、こうした実感自体が《過去》にも存在し、《過去》の私が生き生きとした実感をもって時計を見ていると想定しても何の矛盾もないため、この実感をもって《現在》を《過去》から峻別する根拠とすることはできない。このように、《現在》を表す時刻τが、いかなる手段を用いても現実に測定できないばかりか、その測定方法すら思いつかないという事情は、そもそもこの量が虚構の(実在しない)存在であることを強く示唆する。
以上の議論から、《現在》および《過去》は実在するものの《未来》はいまだ実在していないとする(ii)の見解は、物理学的には妥当でないことが結諭される。
©Nobuo YOSHIDA
info@scitech.raindrop.jp