
量子もつれ(entanglement; 「絡み合い」とも言いますが「もつれ」の方が広く使われていると思います)は、量子力学の中でも際だって難解な話題であり、その内容を一般の人に伝えようとすると、どうしても過度の単純化や歪曲を行うことになります。その結果、舌足らずでミスリーディングな解説が多くなり、専門的な知識のない人は混乱してしまうようです。
ここで強調しておきたいのは、「物理的な作用は光速以上の速さでは伝わらない」という現代物理学の基本前提が、量子もつれの現象でも破れていないという事実です。量子力学の基盤になるのは「場の量子論」と呼ばれる理論であり、そこでは、作用の伝達を表すのに伝播関数と呼ばれる関数が使われます。この関数は、光速を超えなければ到達できない領域ではゼロになるように定義されているので、場の量子論が正しいならば光速を超える作用はないはずです。もし、光速を超えて作用が伝わったとすると、量子力学の基盤が崩壊することになり、世界中の物理学者が浮き足立つはずですが、そんな話はついぞ耳にしません。量子もつれがある場合でも、作用が光速を超えることは不可能です(したがって、質問にある選択肢から選ぶとすれば、(3)が正解です)。
それでは、なぜ一部の人が量子もつれは超光速の現象を伴うと思っているかと言うと、この現象についての一般人向け解説がミスリーディングだからです。質問にある実験は、下図のような装置を使って行うことになりますが、ここに描いた通りの実験は行われておらず、「これとほぼ同等な実験」が実施されただけです。物理学者ならば、「一方には当てはまるが他方には当てはまらない性質がある」といった2つの実験の違いを理解することができますが、専門家以外に、そうしたことはわからないでしょう。このため、「2光子の運動量がもつれ合っている場合、左側の光子がどちらのスリットを通過するかを測定すると、右側の光子による干渉縞が観察されなくなる」、あるいは、もっと素朴に、「左側の光子でもつれを壊すと、その瞬間に右側の光子の干渉性が失われる(?)」と誤解してしまうのです。
実際に行われる実験では、多くの場合、光子の偏光が利用されます(運動量のもつれあいを利用することもありますが、実験が難しくなります)。あるタイプの光学結晶にポンピング光を照射すると、偏光状態がもつれあった2つの光子が発生することがあります。偏光状態は、互いに直交する面 V と H のどちらに偏光しているかによって、|V> あるいは |H> と表されますが、偏光面が一致するようにもつれあった2つの光子の場合は、
( |V>
1 |V>
2 + |H>
1 |H>
2 )/√2 (添字の1,2 は光子1と光子2を表す)
となります(実際には、2つの項の間に位相の差がありますが、ここでは無視します)。量子もつれが興味深いのは、測定する偏光面を V と H に限る必要はなく、例えば、それよりθだけ傾いた V
θ と H
θ で測定することもできるという点です。この偏光状態を用いれば、2光子の状態は、
( |V
θ>
1 |V
θ>
2 + |H
θ>
1 |H
θ>
2 )/√2
と表せます。この式は、偏光状態を V と H で表した先の式と数学的に同一です。2光子光源から飛び出した光子は、|V> あるいは |H> といった特定の偏光状態ではなく、これらが混じり合った重ね合わせの式でしか表せないというのが、量子力学の基本的な性質です。
さて、偏光面がもつれあっている2光子を使った量子もつれの実験とは、偏光状態に依存するビームスプリッタや偏光面を回転させる半波長板などを組み合わせて、2つの光子の偏光状態の相関を調べるというものです(実験装置の詳細は省略します)。例えば、光子1で偏光状態が V
θ または H
θ のいずれかになるとき、光子2の偏光状態は V と H のどちらになるかを調べます。ただし、光子1個1個を測定するのは困難なので、干渉計のセットアップを変えたときの強度変化に基づいて相関を求めます。
2つの光子を完全に分離させる実験の場合、量子もつれがあると言っても、一方の光子に対して行う測定が他方の光子に物理的作用を及ぼすことはありません(量子コンピュータなどでは、もつれあっている対象が完全に分離していないので、結論が異なります)。まず、θ=0 として、同じ偏光面で2つの光子の偏光状態を測定する場合を考えましょう。偏光面が一致するようにもつれあっているとき、光子1が V 偏光だと測定されると、その瞬間に、光子2も V 偏光だとわかりますが、これはもちろん、光子1の測定結果が超光速で伝わって光子2の偏光状態を変化させるわけではありません。一方が V 偏光のときには他方も V 偏光になるように相関しているだけです。この相関は、実験終了後に測定結果をつきあわせたとき、2つの光子の偏光状態の組が「 V - V 」または「 H - H 」になる割合が100%、「 V - H 」または「 H - V 」になる割合が0%という形で表されます。
量子もつれの特徴が顔を出すのは、θがゼロでないときに、測定結果をつきあわせた場合です。光子1でどのような測定を行おうと、光子2の状態に何ら変化は現れません。しかし、光子1の偏光面が V
θ か H
θ かに応じてデータを分け、偏光状態の相関を、「 V
θ - V 」が何%、「 V
θ - H 」が何%、「 H
θ - V 」が何%、「 H
θ - H 」が何%というような結果が得られます。問題は、この相関が、2つの光子の偏光状態が放出された当初から確定していたという仮定と矛盾する点です。偏光状態が当初から何らかの内部変数によって確定していたとすると、偏光状態の組が生じる割合がある範囲になければならないことが理論的に示されます(最も有名なのが、「ベルの不等式」と呼ばれる不等式を満たすべきだという要請です)。ところが、量子もつれのある光子ペアの測定結果をつきあわせると、この範囲を逸脱していることがわかります。つまり、物理的状態は初めから確定しているという古典論の考えではどうしても説明のできない振舞いが見られ、光子が発生した段階では2つの偏光状態の量子力学的な重ね合わせになっていたとしか解釈できないのです。
量子もつれを持つ系が示すこうした特徴的な相関は、「長距離相関」−−あるいは、最初にこの問題を提起したアインシュタイン=ポドルスキー=ローゼンの頭文字をとって「EPR相関」−−と呼ばれています。長距離相関は、2つの粒子についてのデータを事後的につきあわせたときに存在が浮かび上がるものであり、一方の粒子だけを見ているだけでは姿を表しません。
長距離相関は、直観的にわかりやすいものではありません。光子1にある操作を行った瞬間に、ずっと離れたところにある光子2の状態が突如として変化する−−といったことはないのです。相関が現れる舞台も、「スクリーン上の干渉縞」ではなく、「同時計数器などで得られたデータを示すグラフ」です。古典論の考えに基づいて計算を行い、2粒子の状態間にこうした相関が現れるはずだと予測しても、その通りにはならない−−その結果が、まるで2つの粒子が示し合わせているかのようなので、物理学者にとっては、とても興味がそそられる現象なのです。もっとも、一般の人が期待するほどドラマティックな現象ではないことも、また事実です。
長距離相関が生じる理由を人間の知性で理解できるように説明することは、まだできていません。今のところ、「自然界とはこういうものだ」と言えるだけです。しかし、これは、光速を超えて物理的な作用が及ぶ「長距離相互作用」とは質的に異なるものです。長距離相互作用があるならば、物理学を根底から作り替えなければなりませんが、長距離相関だけならば、量子力学によって完全に記述できます。その意味で、理解はできないけれども、それほど“spooky(気色の悪い)”なものではないでしょう(ちなみに、“spooky”とは、アインシュタインが量子力学を批判するときに使った言葉だと言われています)。
量子力学の面白さを人々に知らせようとするあまり、かえって誤解を生みだしているケースは、決して少なくありません。最近、耳にする機会の多い「量子テレポーテーション」も、正しく理解していない人が多いようです。量子テレポーテーションとは、量子もつれを利用すると、ある量子状態のコピーを別の場所に作り出すことができるというものです。ただし、そのためには、もつれあった2つの量子系を、それぞれコピー元とコピー先に送信しなければなりません。コピー元で相互作用させて特定の結果が出れば、コピー先に送った系の状態がコピー元と同じ状態(コピーされた状態)であることが判明するというわけです。もちろん、コピー元で特定の結果が出たかどうかは、後で情報を交換しなければわかりません。これをテレポーテーションと呼ぶことは、ほとんど言葉遊びでしかないような気がします。
【Q&A目次に戻る】

幽霊や神、さらには、超能力、UFO、UMAなどのいわゆる超常現象に関して通常の科学者が研究対象としないのは、科学的方法論で扱うのが困難だからです。科学的方法論とは、仮説演繹法と呼ばれるもので、(1)まず、対象を記述するための仮説を提示し、(2)その仮説から演繹的にいくつかの帰結を引き出し、(3)これを実験・観察で得られたデータと比較して、(4)仮説の妥当性を検証する(妥当でなければ仮説を棄却する)−−という段階を踏んで進められます。私の見たところ、職業科学者はこの方法論を学生時代から身につけており、これを適用できない対象を嫌忌する傾向があります。
科学的方法論で重要なのが、たとえ仮説を信じていなくても、演繹的な推論ならできるという点です。「この仮説は間違っているとしか思えないが、仮に正しいとすると、こういう結論が導けるはずだ」と言えることが、科学的議論の要諦です。もし、その仮説から引き出せる帰結が観察データと合致し、他の仮説からの帰結が合致しないならば、気にくわない仮説であっても、信憑性を認めざるを得ません。どうしてもその仮説を受け入れたくなければ、データと合致する帰結を引き出せる別の仮説を考案する必要があります。
たとえ幽霊や神の存在を仮定しても、それを信じていない人にとっては、そこから何も演繹できないので、科学的議論を始めることができないのです。
ある田舎町の一軒家に都会から引っ越してきた一家全員が、原因不明の体調不良に苦しめられたという話があります。ある人は、それを、この家に憑いている幽霊のせいにするでしょう。しかし、科学者は、そういう発想はしません。体調不良の原因について、いろいろな仮説を立ててみます。曰く、「建材に含まれていた化学物質によってシックハウス症候群になった」「飲み水が農薬などで汚染されていた」「飲み水にクリプトスポリジウムなどの病原体がいた」「屋内にカビが繁殖して病原性の胞子を放出していた」「裏庭に有毒なアルカロイドを持つ植物が生えていた」「近所の工場が低周波振動を発しており物理的ストレスとなった」「近所の送電線が低周波電磁波を発しており物理的ストレスとなった」「近所につきあいにくい人がいて心理的ストレスとなった」などなど。さらに、次の段階として、この仮説から演繹的に引き出せる帰結を考えてみます。例えば、「シックハウス症候群なんかであるわけがない」と思っている人でも、仮に体調不良の原因がホルムアルデヒドによる化学物質過敏症だとすると、屋内のホルムアルデヒド濃度が有意に高いはずだという帰結が引き出せます。濃度測定を行って以前の居宅と同じレベルならばホルムアルデヒド原因説は棄却され、濃度が高ければ、次の帰結とデータの比較−−例えば、パッチテストなどによってホルムアルデヒドに対する過敏性の有無を調べる検査−−に移ることになります。こうして、ある仮説の信憑性が充分に信頼できるほど高まったところで、原因が解明されたと言えます。もちろん、思いつく仮説を全て調べてみても、結局、どの仮説も検証されるに至らないこともあります。そうした問題は、科学的に解明できなかった謎として将来の課題になります。
一方、体調不良の原因を幽霊のせいにした場合、こうした議論ができるでしょうか。仮に幽霊が家に憑いていると仮定するならば、何が演繹されるのか。エクトプラズムが検出される? 夏でも外気より5℃は低くなる? 写真を撮影すると奇妙な画像の乱れが生じる? 夜となく昼となくラップ音が聞こえる? 幽霊の存在を信じている人ならば、写真に奇妙な乱れがあった場合、それを霊の証拠だと言い張るかもしれません。しかし、幽霊を信じていない人は、そもそも「幽霊がいるならば写真に乱れが生じる」という推論を正当だと認めないので、霊の証拠だとは考えません。幽霊が存在しない証拠を出せと言われても、演繹的推論が行えない以上、そもそも何が証拠になるかについての共通理解がないのです(「それが確認されれば幽霊が存在しない証拠になる」と大多数が認めることがあれば、教えてください)。
もっとも、科学的方法論が適用できないことだけが、科学者が超常現象を嫌う理由ではないでしょう。芸術作品の評価にも科学的方法論は使えませんが、多くの科学者は芸術を愛していますから。
科学者が特に疎ましく思うのは、幽霊や超能力の存在を主張する人に、思考停止とも言える態度が見え隠れすることです。「あの家族が病気になったのは幽霊のせいだ」−−その仮説に何らかの信憑性が認められたとしても、それだけで他の仮説を棄却することはできません。さまざまな可能性を考慮しながら対策を講じていくのが適切なやり方だと思われます。これに対して、「それならばお祓いを」という一つの対策しか示せないとしたら、問題を充分に考察していないと誹られても仕方ないでしょう。自分が信じている仮説が誤っている可能性を念頭に置きながら、どこまでも考え抜くことをやめない−−それが科学者の理想なのです。
【Q&A目次に戻る】

人工衛星から送信されてくる時刻情報を元に場所を特定する衛星測位システムを利用するためには、最低でも3個の衛星の電波を受信する必要があります。アメリカが軍事目的で打ち上げた約30個のGPS衛星は、常時24個以上が稼働して地球全域をカバーしてはいますが、都市部や山間部では、電波の遮断やマルチパス(ビル外壁での反射などにより受信器に到達するまで経路が複数になること)のせいで精度が落ちてしまいます。また、アメリカの都合によってGPSの利用が制限されることも予想されます。このため、GPSを補完する何らかの方法を開発する必要があります。
最もストレートなやり方は、日本から見た天頂付近に常に衛星が位置するように、複数の人工衛星を新たに配備することです。現在、準天頂衛星システムと呼ばれる計画が進行中であり、うまくいけば、2009年に最初の準天頂衛星が打ち上げられる予定です。しかし、莫大な予算が必要になることから、必ずしも順調ではありません。
位置が判明している地上の基地局を利用する方法も考えられます。現在でも、携帯電話がどの基地局と交信しているかによって、大まかな位置を突き止めることができますが、複数の基地局から正確な時刻情報を受信できるようになれば、さらに位置を絞り込むことが可能です。ただし、マルチパスによる誤差の問題は解決できませんし、膨大な電波が飛び交うことによる電磁干渉を心配しなければなりません。
幹線道路に限れば、1次元的な距離情報だけで位置がほぼ特定できるので、単一基地局との交信によって自動車や歩行者のナビゲーションが行えるはずです。もっとも、現在利用されている光ビーコンによる交通情報提供システム(近赤外線で車載機と双方向通信を行うシステム)は、精度も到達距離も測位に利用できるレベルではありません(真下を通過したという程度の情報しか得られません)。交通管制センターに原子時計を設置し、道路上の送信機から伝送遅れを補正した時刻情報を送信し続けるシステムが開発できれば、もう少し役に立つかもしれませんが、費用対効果がリーズナブルなものになるかどうかは、かなり疑わしいと言えます。
【Q&A目次に戻る】

粉塵爆発とは、加熱された粒子から放出された可燃性気体によって火炎が伝播し、連鎖反応的に燃焼が起きる過程です。燃える“粉”が立ちこめているからと言って、すぐに爆発するわけではありません。炭の粉塵の場合、揮発成分が多いほど激しい爆発になり、5%以下だと粉塵爆発は起きないことがわかっています。
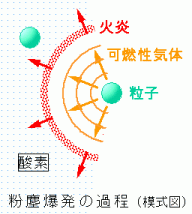
粉塵爆発が生じるプロセスは、次のようなものです。
(1)空気中に浮遊する粒子の表面に熱エネルギーが与えられると、揮発や熱分解などによって可燃性気体が放出される。
(2)周囲に拡散していく可燃性気体と空気中の酸素が適度に混合する領域で気相燃焼が生じ、火炎が形成される。
(3)拡がっていく火炎が、近隣の粒子に接近して熱エネルギーを与える。
何らかの着火源(スパークなど)があって反応が始まると、上の過程が増幅する連鎖反応となって繰り返され、爆発的な燃焼となります。爆発に至るまでには多くの条件が絡んでいるので、何がどうなったときに爆発するかは簡単にはわかりません。可燃性気体が発生する場合でも、反応速度が遅かったり燃焼熱が小さかったりすると爆発にはなりません。また、可燃性気体の燃焼だけではなく、放射熱が重要な役割を果たしているという見方もあります。粉塵爆発は、ガス爆発などに比べて理論的な解析が難しく、完全に解明できているわけではありません。
金属の粉塵でも、条件が整えば粉塵爆発を起こします。例えば、マグネシウムやアルミニウムは融点が低い(Mg:650℃、Al:660℃)ので、微粒子が急激に加熱されると、溶融した表面から金属蒸気が拡散し、気相で燃焼(燃焼熱はいずれも比較的大きい)して爆発を引き起こします。何年か前、テレビなどの筐体にマグネシウムを使うことが流行った際、加工に慣れていない作業員が多かったため、家電工場では珍しい粉塵爆発が相次いだことがありました。
【参考文献】『粉じん爆発・火災対策』(日本粉体工業技術協会粉じん爆発委員会編、オーム社)
【Q&A目次に戻る】

CERN(欧州合同素粒子原子核研究機構)の新型加速器LHC(the Large Hadron Collider)は、陽子や陽イオンを正面衝突させて内部構造や新粒子を測定する装置で、2007年11月に稼働し、2008年中頃から本格的な実験を始める予定です。
LHC では、陽子同士の衝突で 7TeV (7×10
12電子ボルト)まで加速することが可能です。これは、素粒子の標準模型に関する実験を行うには充分なエネルギーですが、アインシュタインの関係式 E=mc
2 を使って質量に換算すると、わずか 10
-23kg でしかなく、プランク質量 10
-8kg の1000兆分の1 にすぎません。衝突の際に圧縮されると言っても、量子力学的な不確定性関係によって、せいぜい 10
-19m 程度が限界であり、標準的な理論の範囲では、ブラックホールを形成することは不可能です。しかし、もし膜理論(M理論)やその他のいくつかの理論が予測するように、空間が3次元よりも大きな次元を持っているとすると、距離が小さくなったときの重力の増加が3次元空間よりも遥かに急激になるため、小さな質量でもブラックホールができる可能性があります。いくつかのグループが計算を行っていますが、最も楽観的な予測によれば、LHC のエネルギーでもマイクロブラックホールができる可能性があります。
加速器内部でマイクロブラックホールが形成されると、ホーキング効果によって、10
-26秒程度で“蒸発”して消えてしまうと予想されています。陽子同士の衝突によって新粒子ができた場合、その崩壊パターンは、この粒子が持つ量子数と運動量によって特徴づけられます。例えば、ヒッグス粒子が生成されたときには、μ粒子対への特徴的な崩壊パターンが観測されるはずであり、その飛跡が観測できれば、ヒッグス粒子を他のものから識別できると考えられます。これに対して、マイクロブラックホールの蒸発の際には、自然界に存在するあらゆる粒子が全方位に均等に放出されることになります。これは、通常の粒子の崩壊パターンとはかなり異なっており、充分に同定可能だと思われます。
本当のところ、多くの物理学者は、LHC での実験でマイクロブラックホールが見つかる可能性はかなり低いと考えているようです。フェルミ研究所の研究者300人を対象に行った調査によると、LHC における新発見のオッズは次の通りです(Science 315 (2007) 1657-):
| 標準的なヒッグス粒子 | 2倍 |
| 予想外の事象 | 2倍 |
| 超対称性 | 5倍 |
| 余剰次元 | 14倍 |
| 電子の内部構造 | 14倍 |
| レプトクォーク | 49倍 |
| 新発見なし | 7倍 |
【Q&A目次に戻る】

時間の単位となる秒を定義するためには、いくつかの理論を基本前提として仮定する必要があります。現代的な秒の定義に際しては、原子状態間の遷移によって一定の周波数を持つ電磁波が吸収・放出されるという量子力学の法則を前提としています。この法則を用いた原子時計にはいくつかのタイプがありますが、その中で特に正確さに優れたセシウム原子時計によって1秒を定義し、これと比較することで他の原子時計の周波数(電磁場の振動の何回分が1秒になるか)を決定しています。
量子力学によれば、定常状態のエネルギーは確定した値を持ち、定常状態間の遷移によって吸収・放出される電磁波の周波数νは、振動数条件:
ν = |E
2-E
1|/h
で与えられます(E
1とE
2 は2つの準位のエネルギー、h はプランク定数)。エネルギーの不確定性が問題になるのは、状態が定常的でない場合、すなわち、放っておいても状態が変わってしまうような不安定な場合です。このとき、状態が変化するまでの平均的な時間(寿命)τとエネルギーの不確定性ΔE の間に、
τΔE 〜 h
という不確定性関係が成り立つので、νから決める1秒の定義には、(振動数条件の E
2 を E
2+ΔE に置き換えればわかるように)1/τν程度の不確定性がつきまといます。しかし、セシウム原子の場合、超微細構造の励起状態の寿命はきわめて長く(10
18秒以上)、この関係式に由来する不確定性は無視できます。原子の運動に起因するドップラー効果(相対論的な横ドップラー効果)の影響は残りますが、原子を絶対零度近くまで冷却することにより、かなりの程度まで取り除けます。
実際にセシウム原子時計を使って1秒を定義するには、次のような方法が用いられます。まず、半導体レーザによる光ポンピングを利用して、超微細構造の基底状態と励起状態で適当な分布を持つセシウム原子の集団を作り出します。これに、空洞共振器から放射される92億Hz程度のマイクロ波を当てて、透過したマイクロ波の強度を検出します。共振器の設定を変えていくと、ちょうど超微細準位間の振動数条件に合致したときに検出強度が急変するので、「定義によって」周期が1秒の91億9263万1770分の1であるマイクロ波が放射されていることがわかります。後は、周波数カウンターを使ってマイクロ波の振動回数を数えることにより、秒を単位とする時間の測定が可能になります。この方法により、現在では、10
-15の精度で1秒を決めることが可能になっています。
こうした1秒の定義は、「大人の肘から指先までの長さを1尺とする」というのと同じように、単に、測定の基準を決めるだけであって、時間概念の定義にまで踏み込んでいるわけではありません。物理学や数学の理論は、大部分が自明の前提とされています。セシウム原子による1秒の定義も、地球の自転に基づく1秒の定義をより精密にした技術的なものだと考えてください。
【Q&A目次に戻る】

チタンが生体に何らかの影響を及ぼすことを示すデータは、ほとんど見あたりません。論文検索で調べてみても、「チタンの生物学的機能は見いだされていない」「チタンおよびチタン酸化物の毒性はきわめて小さい」「発ガン性があるとは認められない」「チタンによるアレルギーの報告はあるが確認されていない」といった内容ばかりで、良いにせよ悪いにせよ、化学的な作用は無視できるレベルだと思われます(ただし、光触媒として用いられる二酸化チタンは、紫外線を照射されるとOHラジカルなどを生成して、有機物の分解や殺菌効果を示します)。むしろ、生体への影響がないことを利用して、チタン製のインプラント(人工歯根・人工骨)が利用されているほどです。
それでは、チタンの装着が物理的な作用を介して生体機能に影響を与えることがあるのでしょうか。チタンは、磁石にわずかに引き寄せられる程度の弱い常磁性体で、質問文にあるような強い磁場は発生しません(そもそも、磁場が生体にどのような影響を与えるのかも、よくわかっていませんが)。チタン鉱石には放射性物質が含有されていますが、チタン製品に放射能はありません。また、電気伝導度・熱伝導度も金属としては小さく、健康状態を左右するほどの物理的作用があるとは考えられません。科学的に断定できるほどのデータはありませんが、私ならば、「チタンのネックレスで肩こりが治った」のはプラシボ効果(効き目があると信じることで治癒力が生じる心理的効果)だという主張に1票を投じます。
チタンは、軽く強靱で耐食性に優れており、戦闘機や潜水艦にも利用される先端的素材です(メカゴジラや宇宙戦艦ヤマトは、スペースチタニウム(宇宙チタン?)という未知の物質ででできているとか)。このため、「チタン=よくわからないがすごい物質」というイメージが生まれ、そこから健康にも有効だという連想が生じたのではないでしょうか。1920年代には、強い放射能を持つラジウムが「神秘のエネルギーを秘めた物質」と誤解され、飲料や化粧品に添加されて健康被害を引き起こしたことがあります。幸いチタンにはラジウムのような危険性はありませんが、ゲルマニウムやトルマリンなどと並んで擬似科学に利用されやすい物質であり、宣伝をうかつに信じない方が良さそうです。
【Q&A目次に戻る】

水などの液体が他の気体中へと蒸発する過程には、液体表面での気体の動きが大きく関係しており、簡単な数式では表せません。
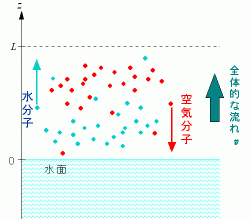
まず、統計物理学の考え方を記しておきましょう。z=0 の水面から z=L まで安定した境界層があり、上方の大気に向かって一方的に水蒸気が拡散している(水が空気を吸収しない)場合を考えます。このとき、物質は全体として上に移動していることになるので、上向きの空気の流れ v[m/s] が存在します。水蒸気の流束(単位面積・単位時間あたりの移動質量)F は、この流れによる質量の移動ρrv と、(水蒸気以外の)空気と水蒸気の相互拡散J の和となり、
F = ρrv + J
と表されます。ただし、ρは空気密度、r は空気中の水蒸気の質量分率です(水蒸気の質量分率は、飽和水蒸気圧と相対湿度から計算することが可能で、気温25℃、相対湿度25%の場合は、r=0.005 になります)。一方、水蒸気以外の空気は定常状態を保つため、上向きの流れと相互拡散(水蒸気と空気の入れ替わりなので-J)が釣り合うことになり、
ρ(1-r)v - J = 0
という関係式が成り立ちます。また、拡散の流束J は、相互拡散係数D (温度などに依存する量で、理論的な近似式がある)を用いて
J = - ρD(dr/dz)
と表されます。これらを組み合わせれば、
F = -ρD(dr/dz)/(1-r)
となります。境界層内部では流束F は一定なので、この式を z=0 から z=L まで積分すれば、
FL = ρD ln (1-r
L)/(1-r
0) ≒ ρD(r
0-r
L)
が得られます。ただし、r
0 と r
L は、それぞれ、z=0 と z=L での水蒸気の質量分率で、通常、r
0 は飽和状態に、r
L は環境の湿度に対応します。
さて、水蒸気の流束F の公式は導けましたが、これだけでは、実際の蒸発速度を求めることはできません。境界層の厚さL がわからないからです。
実際の水面付近では、空気の流れは必ずしも定常的ではなく、乱流と呼ばれる不安定な振舞いを示しており、微小な空気塊が絶えず上下に移動しています。境界層の性質は、こうした空気の動きに左右されるので、理論的な解析は困難なのです。半理論的・半経験的な計算式によると、蒸発量は、水面付近の平均風速に比例することが知られていますが、現実にはその他の多くのファクター(日射量など)が絡んでくるので、一般的な式はあまり意味がありません。教科書などに蒸発速度の公式が載っていないのは、そのためです。
【Q&A目次に戻る】

液体の電磁物性(特に磁性)に関する教科書・解説書の類は、固体に比べて少ししかありません。理由の1つは、単に難しいからです。液体の場合は、電磁場の方程式と運動方程式を連立させなければならず、電磁場が及ぼす影響は一般に非線形になります。簡単な式で振舞いを分析できず、コンピュータ・シミュレーションに頼らざるを得ないため、大学の講義などで取り上げにくい話題です。磁気流体力学と呼ばれる研究分野はありますが、これは、熱核融合やMHD発電の基礎過程、あるいは、宇宙空間でのプラズマの振舞いを研究することを主たる目的とするもので、通常は媒質の透磁率を1と置いた電導性流体(プラズマや液体金属)を対象としています。また、エレクトロニクスの分野で固体デバイスが盛んに利用されているのに対して、液体の応用は範囲が限られており、製品開発の現場から研究がインスパイアされることもあまりありませんでした。
しかし、こうした状況は、近年、大きく変わりつつあります。磁性流体と呼ばれる新素材が、さまざまな方面で応用されるようになってきたからです。
磁性流体とは、ナノサイズの強磁性体微粒子に界面活性剤を吸着させ、溶媒中に安定的に分散させたコロイド溶液で、磁場によってダイナミックに運動を制御することができます。もともとは、アポロ計画の際に無重力状態で燃料を送るための素材としてNASAで開発されたもので、結局、ロケットには使われませんでしたが、その後、磁場で一定の形を保持できる液体シールとして利用されるようになりました。例えば、強磁性体のシャフトの周囲に生じる強い磁場で磁性流体を保持すると、固体接触がないためほとんど摩耗しない軸受けとなります。このほか、薬剤を適当な位置に誘導・保持するのにも利用できます。
最近では、磁場の変動に伴ってまるで生き物のように姿を変える「液体彫刻」として、アートの分野で磁性流体が注目を集めています。無数のスパイクを持った黒光りする液体が、重力に逆らうように螺旋状に盛り上がっていく光景は、一度見ると忘れがたい印象を受けます。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
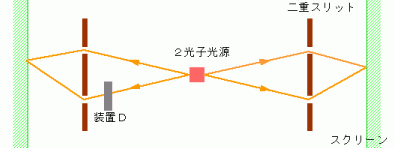
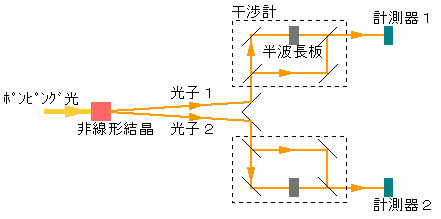

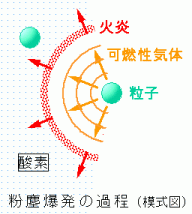 粉塵爆発が生じるプロセスは、次のようなものです。
粉塵爆発が生じるプロセスは、次のようなものです。
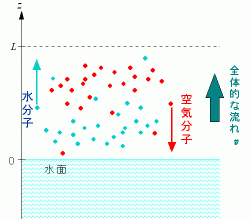 まず、統計物理学の考え方を記しておきましょう。z=0 の水面から z=L まで安定した境界層があり、上方の大気に向かって一方的に水蒸気が拡散している(水が空気を吸収しない)場合を考えます。このとき、物質は全体として上に移動していることになるので、上向きの空気の流れ v[m/s] が存在します。水蒸気の流束(単位面積・単位時間あたりの移動質量)F は、この流れによる質量の移動ρrv と、(水蒸気以外の)空気と水蒸気の相互拡散J の和となり、
まず、統計物理学の考え方を記しておきましょう。z=0 の水面から z=L まで安定した境界層があり、上方の大気に向かって一方的に水蒸気が拡散している(水が空気を吸収しない)場合を考えます。このとき、物質は全体として上に移動していることになるので、上向きの空気の流れ v[m/s] が存在します。水蒸気の流束(単位面積・単位時間あたりの移動質量)F は、この流れによる質量の移動ρrv と、(水蒸気以外の)空気と水蒸気の相互拡散J の和となり、