
劣化ウランの健康被害に関しては、何らかの結論を下せるだけのデータがありません。現状では、「まだ白黒つけられないが、一部マスコミで報じられているほどの健康被害が発生するとは考えにくい」という程度のことしか言えないでしょう。
劣化ウラン(Depleted Uranium)とは、一般に、天然ウランに0.7%ほど含まれるウラン235を核燃料用に3〜4%にまで濃縮した後の残りの物質を指しています(「劣化」という語は訳として不適切だと思います)。劣化ウランの大部分は放射能の弱いウラン238で、ウラン235も0.2〜0.3%ほど含まれていますが、このほかに、α崩壊する微量の(0.001%程度の)ウラン234や、製造の際に混入したり自発核分裂などで生成されたりしたごく微量の放射性核種も存在し、全体として、天然ウランの60%ほどの放射能を有しています。放射線は主にエネルギー5MeV程度のα線であり、皮膚の角質層で遮断できるので、外部被曝の影響はほとんど無視できるものの、体内に摂取されると内部被曝の危険性が生じます。ただし、プルトニウムのように長期にわたって体内に残留することはなく、たとえ血中に移行しても数日以内に腎臓で濾過されて排泄されるので、その影響は比較的小さいと考えられます。
重金属であるウランには化学毒性もありますが、毒性の強さは鉛よりやや弱い程度だとされています。ウランの毒性による健康被害としては、腎機能の低下があります。ウランが(有機水銀のように)食物連鎖を通じて生体中に濃縮され、環境被害を引き起こすという報告はありません。
日本では、劣化ウランは核燃料物質として使用が法的に規制されていますが、国によっては、密度が高いという特性を生かして、航空機などのおもりや放射線の遮蔽材として利用されます。近年、マスコミで取り上げられて話題になっているのが、湾岸戦争やイラク戦争でアメリカ軍が用いた劣化ウラン弾です(ボスニアやコソボの紛争でも使用されました)。劣化ウランを弾芯とする弾頭は、比重が大きいために厚い鋼板を貫くほどの貫通力を持つことに加えて、衝撃によって微粒子になったウランが発火して焼夷弾としても機能するので、対戦車用砲弾として有効だとされています。
劣化ウラン弾が使用された地域で、小児白血病の増加や帰還兵の健康被害(いわゆる湾岸戦争症候群)が見られるという報告もありますが、劣化ウランとの因果関係やデータ自体の信頼性について、明確な結論が出ていません。アメリカ政府が健康被害を否定するのは、自己弁護と見なされてもしかたないでしょう。しかし、WHO(世界保健機関)、UNEP(国連環境計画)、IAEA(国際原子力機関)といった比較的中立性の高い機関も、劣化ウランによる健康被害は見いだせないという立場を取っており、今のところ、劣化ウラン被害が確認されたケースはないと言えます。例えば、NATO軍が劣化ウラン弾を使用した地域を含むボスニアの15地点でUNEPが行った調査の報告では、高性能放射線測定器によって劣化ウラン弾の残留物が3地点で発見されたものの、その汚染レベルはきわめて低く、放射能ないし化学毒性によって人体または環境に悪影響が生じるリスクは充分に小さいと結論されています。ただし、劣化ウランの悪影響に関しては科学的に不確かな部分があるため、今後も調査を続けるべきだとの留保をつけています。
一度に大量の劣化ウランを体内に取り込んだ場合は、健康被害が生じる可能性もあります。NHKスペシャル『調査報告・劣化ウラン弾』
(2006年8月放送;この番組自体は取材がずさんでNHKらしからぬ浅薄な内容でした)では、湾岸戦争の際に、味方の誤射で劣化ウラン弾に被弾した戦車の運転士が紹介されていましたが、砲弾の破片が数多く体に突き刺さっただけでなく、高濃度のウラン粉塵を吸い込んでおり、これが帰還後の体調不良(腕の腫瘍、全身の痛みなど)の原因になったのかもしれません。しかし、劣化ウラン自体は放射能も化学毒性もそれほど強くないので、大気中に飛散して濃度が低下した場合は、たとえ土壌や水系を汚染して体内に経口摂取されたとしても、劣化ウラン弾のせいだと指摘できるほどの悪影響が見られるとは思えません。
湾岸戦争・イラク戦争などでは、住民や帰還兵にさまざまな疾患が見られたことが知られています。しかし、その原因が何かを特定することは、かなり困難です。劣化ウラン弾以外にも、(1)医療施設の破壊や医薬品不足による医療水準の劣化、(2)戦時特有の有毒物質の発生(煙幕を作る際のダイオキシンの発生や建築物倒壊によるPCBの飛散など)、(3)毒ガスなどの軍事用化学物質の使用ないし漏出、(4)戦時ストレスによる免疫機能の低下−−といった原因も考えられます。劣化ウラン弾だけを槍玉に挙げるのではなく、科学的なデータに基づいてさまざまな可能性を追求していく方が、戦争の実態を明らかにする上で、より有意義な態度だと言えるのではないでしょうか。
【Q&A目次に戻る】

簡単に言ってしまえば、「遺伝子治療は、当初期待されたほどの成果はあげていないが、実用化に向けて地道な研究が進められている」という状況です。
遺伝子治療を開始するに当たって、最も期待されたのは、ガンへの応用です。例えば、ガン患者の多くでガン抑制遺伝子p53に異常が発見されたことから、正常なp53遺伝子を何らかの方法で患部に導入すれば、ガンの治療が可能になると考えられたのです。しかし、一部の患者でガン組織の縮小が見られたものの、めざましいと言えるほどの治療効果は上がりませんでした。
ガンとともに遺伝子治療が有効だとされたのが、遺伝子の欠損によって特定の酵素が作れなくなる病気です。世界最初の遺伝子治療は、1990年にアデノシンデアミナーゼ(ADA)という酵素の欠損による免疫不全症の患者に対して行われました。これは、患者から取り出したリンパ球にADAの遺伝子を導入して、また患者の体内に戻すというものです。この治療は、ある程度の効果を上げたようです(定量的な評価は行われていない)が、遺伝子を導入したリンパ球は数年で寿命が尽きてしまうので、何度も繰り返し行わなければならないという不便さがあります。実際には、症状が深刻だった年少期に遺伝子治療と酵素補充療法を併用して行い、長じてからは酵素補充療法のみに切り替えたということで、遺伝子治療は、あくまで補助的な役割しか果たしていません。
遺伝子治療の問題点を浮き彫りにする事件も、相次いで起きています。1999年、米ペンシルベニア大で遺伝子治療を受けた患者(18歳男子)が4日後に死亡しましたが、これは、遺伝子を導入するために利用したアデノウィルスの使用量を誤った人為的なミスでした。
2002年にフランスで起きた事件は、遺伝子治療が持つ潜在的な危険性をあらわにするものでした。リンパ球が作れないために重度免疫不全症に罹っていた小児患者11人に対し、造血幹細胞(リンパ球などを作り出す元になる細胞)に正常な遺伝子を導入する治療を行ったところ、9人に症状の劇的な改善が見られたものの、治療後しばらく経ってから、2人に白血病が発症したことが報告されたのです。この原因は、レトロウィルスを使って造血幹細胞の染色体に挿入した遺伝子が、増殖に関与する遺伝子の近傍に入り込んでしまい、その結果として増殖機能に異常が生じたためだとされています。遺伝子を挿入する染色体の部位を制御できないという現在の遺伝子治療の限界が露呈したとも言えるでしょう。この事態を受けて、フランスでは、遺伝子治療が全面凍結されました。
こうして、遺伝子治療に対する過大な期待は急速にしぼんでいきましたが、それでも、遺伝子治療の可能性が否定されたわけではありません。大阪大学などの治験によると、血管の増殖を促すHGFの遺伝子を導入する治療法は、閉塞性動脈硬化症の患者に対して一定の成果をあげています。最近では、食道ガンを休眠状態にするタンパク質NK4の遺伝子を導入する治験を、千葉大学が計画しているという報道がありました。遺伝子治療に関しては、まだ不明な点がたくさんあるので、動物実験を中心にしながら一部で治験(臨床試験)も行い、少しずつ知識を蓄えて将来に備えているといった段階でしょうか。
【Q&A目次に戻る】

高高度で核兵器を爆発させたときに、強力な電磁パルスが発生することは、実際に報告されています。ただし、質問文にある記事は、かなり誇張した内容になっています。
原水爆などの核兵器を爆発させると、核反応によって大量のγ線(波長のきわめて短い電磁波)が発生します。高度100km以上の気体密度の薄い領域では、このγ線はそのまま直進していきますが、高度数十km程度になると、気体分子中の電子をコンプトン散乱によってはじき出し、ガンマ線とほぼ同じ向きの高速の電子の流れを発生させます。こうして生じた爆発地点を中心とする球殻状の電子流は、地磁気からのローレンツ力を受けて横方向に加速され、その結果として、持続時間が10ミリ秒以下のパルス状の電磁波を作り出します。この電磁パルスが、電子機器に悪影響を及ぼすと考えられています。
ある地点に到達する電磁パルスの強度は、爆発の高度と規模、その周辺での地磁気の強度と向き、爆発地点と観測地点の位置関係によって変わります。電磁パルスを球面波と仮定すると、電場・磁場の強度は距離に反比例して弱くなります(エネルギーではなく波の振幅なので、距離の2乗ではなく1乗に反比例する)が、それ以外のファクターに対する依存性の計算は、そう簡単ではありません。さまざまな状況に応じた具体的な計算は、1975年に行われました(L.W. Seiler : A CALCULATIONAL MODEL FOR HIGH ALTITUDE EMP, AD-A009 208, 1975)。例えば、中緯度地方の上空100kmで1メガトンの核爆弾が爆発し、その0.1%のエネルギーがγ線として放出されたとすると、爆発地点直下の地表で電界強度のピーク値は、35,000〜45,000 V/m 程度になることが導けます。ただし、計算の元になる仮定が正当でないという批判も提出されています。論文をざっと読んだ限りでは、核爆発によって生じた電子流が地磁気でいっせいに曲げられて強い電磁波を作り出すという仮定に疑問を感じますが、断定的なことは言えません。
実際のデータとしては、1962年に高度400kmで行われた1.4メガトン爆弾の核実験(Starfish Prime)のものがあります。このとき、爆発地点直下のジョンストン島では 52,100 V/m、1400km離れたハワイ諸島付近でも 22,000 V/m のピーク値を持つ電磁パルスが到達したと言われています。もっとも、こうしたピーク値が持続するのはナノ秒(10億分の1秒)のオーダーであり、当時のオシロスコープで正確に観測できたわけではありません。実際のピーク値は、これよりかなり小さかった可能性が指摘されています。「カウアイ島で電話が不通になった」「オアフ島で1万を越す街灯が消えた」「ホノルルでは盗難警報機が誤作動した」「オーストラリア向けラジオ放送が20分中断した」といったエピソードが流布していますが、その一方で、「ハワイの電力会社では送電トラブルはなかった」「電話・ラジオ・テレビの中断は報告されていない」「一部で見られたトラブルは短期間で復旧した」という話もあります。ちょっとした出来事が誇張されて語られているのかもしれません。
一般的に言って、軍関係者は、軍事的な被害について過大な予測を行い、政府に防衛能力の増強を進言する傾向があります。彼らの話は、すぐに真に受けない方が良いでしょう。
高度数百kmでメガトン級の核爆弾が炸裂した場合、その直下から1000km以上離れ、爆風や熱線の心配のない地点でも、瞬間的なピーク値が数千 V/m に達する電磁パルスが到達する可能性は、充分にあります。通常の電子機器で想定されている電磁ノイズはせいぜい数十 V/M ですから、遮蔽が不十分な装置では、絶縁破壊によって誤作動したり機能停止したりするかもしれません。こうした電磁パルスに対する防御策は、近隣への落雷対策と同程度のものですので、核兵器が使用されるかどうかといった心配とは別に、高い信頼性が要求されるシステムでは、積極的に採用するべきでしょう。
【Q&A目次に戻る】

超新星は、銀河系内部でも100年に1回程度しか起きない稀な現象なので、1つの望遠鏡の視野角に18個もの超新星が写るということは、かつては考えられませんでした。しかし、すばる望遠鏡のように数十億光年の彼方まで観測できる高性能望遠鏡では、決して不思議な出来事ではありません。
国立天文台の発表によると、2002年11月3日に撮影された画像には、9月30日〜10月1日の時点ではなかった天体が写っており、このうち13個が分光学的に超新星だと確認されました(分光学的に確認できないものが、さらに5個あります)。13個の超新星は、赤経が 2:16:23.93〜2:18:53.20、赤緯が 4:26:38.9〜5:09:51.2 の範囲に分布しています。赤経の1分は角度の15' に相当することに注意すると、この範囲は、およそ 40'×40' の立体角内になります。
さて、ここにはいくつの銀河が存在するのでしょうか。ある立体角内に存在する銀河の個数は、暗いもの(一般的には遠くにあるもの)ほど多くなります。見かけの等級が18等級のものは 1度×1度の範囲に平均して7〜8000個、19等級で1万5〜6000個、20等級で2〜3万個になります(逆に、16等級より明るいものになると1〜2個です)。すばる望遠鏡では、24等級より暗い銀河も発見されていますが、超新星を観測するためにはもう少し近くにある銀河でなければならないので、せいぜい19等級かこれより少し明るい程度までです。したがって、1度×1度の範囲に3万個弱、40'×40' では1万数千個といったところでしょうか。
超新星は、1つの銀河に100年に1個の割合で現れると言われています。超新星は、爆発によって急激に光度を増した後、数十日程度の半減期で暗くなっていきますが、放出するエネルギーが大きいので、しばらくの間は観測が可能です。そこで、ちょうど観測を行った日に、ある銀河内部の超新星が見える確率を計算しましょう。仮に、爆発が起きてから20日間は超新星が見えるとすると、この確率は、
20/(365×100) = 1/1800
程度になります(少し乱暴な近似ですが)。したがって、観測できる銀河が1万数千個もあれば、超新星が平均して6〜7個は見つかる計算になります。もちろん、肉眼で探していたのではらちが明きませんが、現在では、コンピュータを利用して、以前に撮影した画像との違いを自動的に検出することができます。とすれば、全天のあちこちを探査しているうちに、一度に18個の超新星が輝いている領域を見つけたとしても、必ずしもおかしなことではありません(全天は 40'×40' の領域が9万区画以上あり、平均値6.5のポアソン分布を仮定すれば、18以上の超新星が存在するのは、そのうちの10区画程度であることがわかります)。
上の計算は大ざっぱすぎて、あまり当てにはなりません(天文学の専門家におしかりを受けるかもしれません)が、それでも、充分に高性能の望遠鏡を用いれば、一度にたくさんの超新星を見つける可能性があることはわかるでしょう。ポイントは、遠方にある多数の銀河が観測できるので、サンプル数が稼げることです。
【Q&A目次に戻る】

質問にあるのは、次の論文のことだと思います:
J. B. Pendry, D. Schurig, and D. R. Smith : "Controlling Electromagnetic Fields" (Science 312 (2006) p.1780-)

これによると、電磁波の波長より小さい構造を持った“メタマテリアル”と呼ばれる素材を用いれば、電磁波を自由に操ることが可能であり、「負の屈折率を持つレンズ」や「物体を見えなくする透明マント」も作れると主張されています。もっとも、実験で成功したのはきわめて限られたケースにすぎず、現実の製品に応用するには、まだ多くの障害が残されています。
メタマテリアルは、素材の内部に微細な回路を集積させて作ります。こうした回路は電磁波の波長より充分に小さいことが必要であり、これまでの実験では、波長が数センチ〜数ミクロンの電磁波に対応する数ミリ〜数百ナノ程度の回路が用いられています。
主に研究が進められているのは、C形の「リング共振器」を集積したメタマテリアルです。この共振器は、リング状の部分がコイル、切れた部分がコンデンサーとして機能するため、それ自体が小さなLC共振回路になっています。リングを貫くように磁場が加えられると、電流が流れて誘導磁場が発生しますが、入射磁場に対するその応答特性は、リングの形状を変えることで調節できます。したがって、メタマテリアルの透磁率μは、内部に集積されたリング共振器の形状に応じて任意の値に設定することが(理論的には)可能です。また、棒状の微小回路を用いれば、誘電率εも自由に調節できると考えられています。一般に、媒質の屈折率nは、透磁率μ、誘電率εと、
n = (εμ)
1/2

という関係で結ばれているので、εとμが自由に変えられるならば、メタマテリアル内部で光線を好きな方向に曲げられます(正確に言えば、εとμを個別に操作することにより、ポインティング・ベクトルを任意の方向に向けられます)。この性質を利用すれば、隠したい物体を誘電率・透磁率をうまく調節したメタマテリアルで覆うことによって、光線が物体を迂回するように通過することも可能なはずです(右図)。
ただし、この「透明マント」は、物体を完全に見えなくするものではありません。現在の技術では、可視光線を自由に操れるような微細加工を施すことは困難であり、せいぜい波長が一定範囲に限られたマイクロ波を迂回させられるだけです。また、マイクロ波は特定の向きに偏光していなければなりません。さらに、迂回は完全ではなく、反射したり影が生じたりします。そもそも、多数の微小回路を集積した大きなメタマテリアルを制作すること自体が、技術的にきわめて困難です。
こうした技術上の問題はあるものの、メタマテリアルは光学の分野に革命を起こす潜在的なパワーを秘めています。実用的な製品が開発されるまでには、まだ地道な研究を続けなければなりませんが、10〜20年後には、メタマテリアルを応用した何らかの製品が作られているのではないでしょうか。
【Q&A目次に戻る】

コンピュータによる円周率πの計算には、一般に、級数展開か反復計算が用いられます。1980年代まで、最も広く利用されていたのが、アークタンジェントの級数展開です。
タンジェントの逆関数であるアークタンジェントは、
π/4 = arctan(1)
のような関係式で円周率と関係しており、さらに、
arctan(1/x) = Σ(-1)
n/(2n+1)x
2n+1 (Σはnに関して0から∞まで和を取る)
という無限級数で表されます。したがって、この級数和を低次から順にコンピュータで計算していけば、近似的にπの値が求められます。ただし、arctan(1) を使っていたのでは、収束がひどく悪いため、10次まで計算しても π=3.232… といった粗い近似にしかなりません。収束を良くするには、加法定理を使って、アークタンジェントの引数が小さくなるような公式を見つける必要があります。特に有名なのは、1706年にマーチンが発見した次の公式です:
π = 16 arctan(1/5) - 4 arctan(1/239)
この公式は、世界初の実用コンピュータ ENIAC を使った円周率の計算(1949)で利用されました。
収束の良いアークタンジェント公式の大部分は、18〜19世紀に発見されましたが、1982年になって高野喜久雄が次の公式を発見しました:
π = 48 arctan(1/49) + 128 arctan(1/57) - 20 arctan (1/239) + 48 arctan(1/110443)
これを使うと、級数展開の最初の1項だけで、π = 3.141958… と良い近似になります。
2002年に東京大学情報基盤センターの金田康正のグループが、1 兆 2411 億桁(10進)という円周率計算の世界記録を更新したときには、高野の公式を用いています。ただし、この公式は、総計算時間を短くするには有効ではありません(1兆桁の計算には日立製のスーパーコンピュータで約600時間掛かっています)。金田教授によれば、「単純に日本人が発見した公式と新しい計算方法を使いたかった」ということです。
πの級数展開には、アークタンジェント以外にもいくつかあります。1914年にインド出身の天才数学者ラマヌジャンは次のようなタイプの公式群を見いだしました:
1/π = 8
1/2 Σ(4n)!(1103+26390n)/4
4n(n!)
499
4n+2
この級数は、n が大きくなると各項が急激に小さくなるため、少ない計算回数で高精度の結果を得ることができます。このタイプの級数では、チュドノフスキらが発見したものが、1996年の80億桁の計算に使われています。
反復法としては、1976年にサラミンとブレントが独立に発見した次の算術幾何平均法が有名です。まず、初期値として、次の値を代入します:
A
0=1, B
0=1/2
1/2, T
0=1
この後、次の代入操作を n=0 から順に必要な回数だけ行います:
A
n+1 = (A
n+B
n)/2 (算術平均)
B
n+1 = (A
n*B
n)
1/2 (幾何平均)
T
n+1 = T
n - 2
n(A
n-B
n)
2
このとき、円周率πは、近似的に
π = (A
n+B
n)
2/T
n
という式で表されます。計算を1ステップ行うだけでも、π=3.140579…と、かなり良い近似になっています。
1989年に金田グループが行った10億桁の計算(当時の世界記録)をはじめ、多くの円周率の計算が、このサラミン=ブレントの公式を使って遂行されています。
世界記録に挑戦するような計算では、上に示したような主計算公式に加えて、計算速度を増すためのさまざまなアルゴリズムが用いられています。良く知られているのが、高速フーリエ変換と呼ばれるアルゴリズムで、計算速度向上には欠かせない方法です。このほかにも、計算の効率化・高精度化のためのさまざまな工夫が凝らされているようですが、この方面に関してはあまり詳しくありません。インターネット上に研究者による資料が公開されているので、そちらを参照してください。
【参考文献】金田康正著『πのはなし』( 東京図書)
【Q&A目次に戻る】

アスペらの実験結果が何を意味するかについては、物理学者の間でも、必ずしも意見の一致を見ていません。彼らが得たデータによれば、量子論的なもつれ(entanglement)のあるシステムでは、いわゆる「ベルの不等式」が成り立っていないことが示されます。しかし、この結果が直ちに量子力学の非局所性を導くわけではありません。
ベルの不等式が成立するには、「時間発展を一意的に決定するような局所的な変数が存在し、システムの状態が与えられると、この変数がある範囲内の値を取る確率測度が正定値で与えられる」ことが(十分)条件となります。
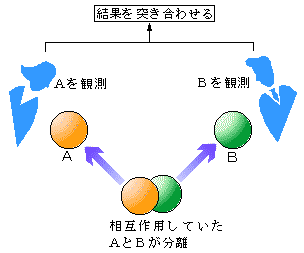
こうしたシステムでは、はじめに特定の状態にあったシステムが2つに分裂し、充分に遠ざかったところで別々に測定がなされるような場合(右図)、各分裂片が相互作用しなくなった段階で、さまざまな測定をしたときにどのような結果が得られるかが確定しているはずです。たとえ測定する物理量を(x方向のスピンからy方向のスピンというように)直前に変更したとしても、分裂後に決まっていた「ある測定をしたときの結果」が変わることはありません。しかし、量子もつれのあるシステムでは、ベルの不等式が成り立っていない以上、このような形で測定結果が決まっているわけではないと考えられます。
ここで問題になるのは、ベルの不等式の不成立をどう解釈するかです。ベルの不等式が成立するための条件が満たされていないことは確実ですが、破れているのが「局所性」なのか(時間発展が一意的に決定されるという意味での)「因果性」なのか、はっきりしません。量子力学的なシステムでベルの不等式の証明が破綻する理由を調べてみると、特定の測定結果が得られる確率の計算式の中に、マイナスの項が含まれているためだとわかります。古典力学的なシステムでは、局所変数の範囲が異なる状態からの確率への寄与は、確率測度の正定値性によって常にプラスの値になるため、ある不等式が満たされますますが、量子力学で同じ確率を求めるには、射影演算子によって物理量がある範囲内に入る状態へと分割しなければならず、どうしても状態間の干渉が生じてマイナスの寄与分が発生します。これがベルの不等式が成り立たなくなる原因なのですから、「確率測度の正定値性」の破綻が量子力学的システムの特性とも言えます。しかし、それが何を意味するかは、そこから量子力学が導けるような基礎的な理論を構築しない限り、断定的な結論は得られないでしょう。
質問にあるような−−局所性も因果性も破れており、(何を測定するかを含めて)結果がはじめから全て決まっているという−−考え方も、一つの解釈として成り立ちます。ただし、科学的な主張は、そうでない対立的な主張との差異が明確でなければ、誰も耳を傾けません。「この考え方が正しいとすれば、こうした実験を行ったときにしかじかの結果が得られる」と言えるならば、その実験をやってみようかと考える科学者も現れるでしょう。しかし、「どのような結果であっても、それははじめから決まっていたことだ」となると、実験をする意味がありません。どうすればその考えを検証できるかというところまで考えて、はじめて科学的な主張と言えるのです。
【Q&A目次に戻る】
 決定論に関する論文
決定論に関する論文の中で、シマウマの恐怖の準備についての話がありました。これと関連して、猿や人間などのヘビに対する恐怖についてはどうお考えでしょうか? 私は基本的機構は似ていると思うのですが、ある心理学の実験で、親が恐れる恐怖対象をヘビではなく花にすると、子供が単純には花恐怖を形成しづらいそうです。恐怖学習の先天性に関する考えをお聞かせいただけないでしょうか。【その他】

恐怖対象の学習に当たって生得的な要素がどの程度の役割を果たしているかについては、心理学者の間でいろいろと議論があります。私は専門家ではないので断定的なことは言えませんが、恐怖反応の獲得に差をつける遺伝的プログラムがあることは事実のようです。ただし、(ヘビか花かといった)恐怖の対象を特定するようなプログラムではなく、より形式的な差異を判定するものではないかと推測しています。
質問にある実験は、1984年から89年にかけてミネカがアカゲザルを使って行った一連の実験のことだと思います。動物園育ちで一度もヘビを見たことのないアカゲザルは、ヘビを怖がりません。しかし、ヘビ(現実のヘビ、あるいは、ヘビの形状をしたもの)に対して恐怖反応を示す野生のサルのビデオ映像を複数回見せたところ、ヘビに対する強い永続的な恐怖を獲得しました。そこでビデオを編集して、ヘビをおもちゃのワニやウサギ、花に差し替えたビデオを見せたところ、アカゲザルの子供はワニを怖がるようにはなったものの、花やウサギに対する恐怖は獲得されなかったそうです。
さて問題は、この結果をどう解釈するかです。ヘビやワニを恐怖対象としやすい性質がサルに生まれつき備わっているようにも見えますが、ヘビやワニに関する情報を遺伝的にコードできるのかという根本的な疑問が残ります。こうした実験では、映像をヒョウやキリン、ケンタウルスやゴジラに変えるなどして、もう少しデータを集めてくれないと、クリアカットな議論はなかなかできません。
私の個人的な考えでは、恐怖反応に違いが生じたのは、新規性といった対象の形式的な性質に差があるからです。
恐怖反応は、危険をいち早く察知して逃走などの回避行動に迅速に移るために必要な生得的機能であり、新しい危険因子にも対応できることが望ましい反面、あまり頻繁に生じると生活に障害をきたします。そこで、恐怖反応のトリガーとなる対象には、遺伝的プログラムによっていくつかの条件が課せられているはずです。当然のことながら、生まれてすぐに目にするものは、恐怖反応のトリガーから除外されるでしょう(自己免疫反応を起こさないためのクローン選択と似た過程です)。生後しばらく恐怖を感じない期間が続いた後に、恐怖を学習するための準備が整います。ここで、恐怖対象に課せられる条件の1つが、「経験によって得られた対象のパターン(ゲシュタルト)と類似しているものの、いくつかの重要なポイントで新規性が認められる刺激であること」ではないでしょうか。
サルを含む多くの哺乳類は、目(2つ並んだ円状のもの)に鋭く反応し、目を持つものを動物と認識しているようです。したがって、動かないおもちゃであっても、目が描かれたヘビやウサギは、動物だと認めて注意を向けるでしょう。ここで、丸っこく毛の生えているウサギと異なり、細長く毛のないヘビやワニは、目があるので動物のカテゴリーには入るものの、経験的に得られたパターンから逸脱した新規な存在であるため、恐怖の対象になり得ると考えられます。花は、「目がないので動物でない」あるいは「生まれたときから見慣れている」といった理由で、恐怖対象から除外されたのではないでしょうか。
「あるカテゴリーに属する新規なものが恐怖の対象になる」という傾向は、人間には特に顕著に見られます。人間一般についてのイメージができあがった生後6〜7ヶ月の乳児は、見知らぬ人間(人間一般に含まれる新規な対象)に対して恐怖反応を示します(いわゆる人見知り)。見知らぬ人間についての情報が遺伝的にコードされているわけがありませんから、これは、形式的な差異に基づいて異なる反応をしている例だと言えます。また、はいはいをしている幼児が、ガラスの板を渡して落ちないようにしてある穴の縁まで来ると、一度も転落した経験のない幼児であっても、恐怖反応を示して先に進もうとしなくなりますが、これも、それ以前に認知された空間のパターンとは異なる「自分の下方に拡がった空間」を目にしたためだと考えられます。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
 これによると、電磁波の波長より小さい構造を持った“メタマテリアル”と呼ばれる素材を用いれば、電磁波を自由に操ることが可能であり、「負の屈折率を持つレンズ」や「物体を見えなくする透明マント」も作れると主張されています。もっとも、実験で成功したのはきわめて限られたケースにすぎず、現実の製品に応用するには、まだ多くの障害が残されています。
これによると、電磁波の波長より小さい構造を持った“メタマテリアル”と呼ばれる素材を用いれば、電磁波を自由に操ることが可能であり、「負の屈折率を持つレンズ」や「物体を見えなくする透明マント」も作れると主張されています。もっとも、実験で成功したのはきわめて限られたケースにすぎず、現実の製品に応用するには、まだ多くの障害が残されています。
 という関係で結ばれているので、εとμが自由に変えられるならば、メタマテリアル内部で光線を好きな方向に曲げられます(正確に言えば、εとμを個別に操作することにより、ポインティング・ベクトルを任意の方向に向けられます)。この性質を利用すれば、隠したい物体を誘電率・透磁率をうまく調節したメタマテリアルで覆うことによって、光線が物体を迂回するように通過することも可能なはずです(右図)。
という関係で結ばれているので、εとμが自由に変えられるならば、メタマテリアル内部で光線を好きな方向に曲げられます(正確に言えば、εとμを個別に操作することにより、ポインティング・ベクトルを任意の方向に向けられます)。この性質を利用すれば、隠したい物体を誘電率・透磁率をうまく調節したメタマテリアルで覆うことによって、光線が物体を迂回するように通過することも可能なはずです(右図)。
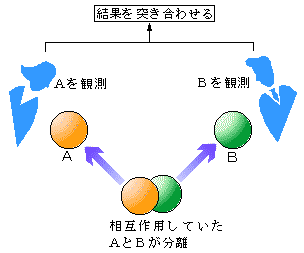 こうしたシステムでは、はじめに特定の状態にあったシステムが2つに分裂し、充分に遠ざかったところで別々に測定がなされるような場合(右図)、各分裂片が相互作用しなくなった段階で、さまざまな測定をしたときにどのような結果が得られるかが確定しているはずです。たとえ測定する物理量を(x方向のスピンからy方向のスピンというように)直前に変更したとしても、分裂後に決まっていた「ある測定をしたときの結果」が変わることはありません。しかし、量子もつれのあるシステムでは、ベルの不等式が成り立っていない以上、このような形で測定結果が決まっているわけではないと考えられます。
こうしたシステムでは、はじめに特定の状態にあったシステムが2つに分裂し、充分に遠ざかったところで別々に測定がなされるような場合(右図)、各分裂片が相互作用しなくなった段階で、さまざまな測定をしたときにどのような結果が得られるかが確定しているはずです。たとえ測定する物理量を(x方向のスピンからy方向のスピンというように)直前に変更したとしても、分裂後に決まっていた「ある測定をしたときの結果」が変わることはありません。しかし、量子もつれのあるシステムでは、ベルの不等式が成り立っていない以上、このような形で測定結果が決まっているわけではないと考えられます。