
光速度が一定であることを示す実験・観測について述べる前に、相対論において「光速度不変の原理」がどのような地位にあるかについて触れておきます。
よく知られているように、特殊相対論は、「全ての慣性系において物理法則は同一形式で表される」という相対性原理と、「光速は光源の速度によらず一定になる」という光速度不変の原理を前提としています。ただし、この2つの原理は、理論の構築において同等の重みを持つものではありません。光速度不変の原理は、慣性系の間における座標変換の形を決定するための“補助的な”前提であり、座標変換としてローレンツ変換を用いることが決まれば、原理としての重要性が省みられることはほとんどなくなります。実際、もしマクスウェルの電磁気学を“完全な”理論として認めるならば、全ての慣性系で光速が同一になることは、(マクスウェル方程式が全ての慣性系で成立することを要求する)相対性原理の直接的な帰結であり、わざわざ光速度不変の原理を持ち出す必要はありません。アインシュタインは、光量子論の研究を通じて、マクスウェル方程式が完全ではないことを知っていたので、相対論を構築するときに、あえてマクスウェル方程式を用いず、光速度不変の原理を掲げたのです。
実は、光速度の不変性は、相対論にとって必要不可欠というわけではありません。本当に必要なのは、4次元幾何学における不変量の定義であり、物理的には、
r を空間的な間隔、t を時間的な間隔として、
r2−c
2t
2 が一定になることです。ここで、c は空間の単位と時間の単位を換算するために使われる換算定数で、その値は、人為的な単位の定義によって決まります。光の速度が c と一致するのは理論的な必然ではなく、光速が c と異なるような(アインシュタインのものと少し違う)「相対性理論」を作ることも、簡単にできます。「光速度が不変だという観測事実が、相対論の正当性の根拠となっている」というわけではないのです。多くの物理学者は、こうした背景を知っているので、相対論の参考書を書くときに、光速度の不変性を検証するデータをあまり重視しないのでしょう。
さて、光速度不変の原理を検証する実験・観測に話を移しましょう。ここで注意していただきたいのは、光速度の不変性とは、「光速度が
光源 の速度によらない」ことであって、「観測者の速度によらない」という意味ではない点です。観測者とは特定の慣性系で観測を行う人のことなので、マクスウェルの理論が相対性原理を満たしてさえいれば、「光速度が観測者(および光源)の速度によらない」ことは直ちに言えます。マクスウェルの理論が相対性原理を満たしていることは、宇宙空間を猛スピードで運動している地球の上で、マクスウェル方程式がそのまま使えるという経験事実から確かめられます(有名なマイケルソン=モーレーの実験も、光速度不変性ではなく、マクスウェルの理論が相対性原理を満たしていることの検証と言えます)。「光速度が光源の速度によらない」という光速度不変性を確認する必要があるのは、マクスウェルの理論がそのまま使えるかどうかわからない天文学的なスケールか、量子効果が現れるミクロのスケールでの現象です。
天文学的なスケールでの光速度不変性は、二重星のデータをもとに確認できます。このことは、1913年にオランダの天文学者ドジッターによって最初に指摘され、その後、繰り返し確認されてきました。
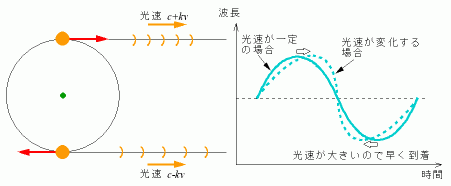
簡単のため、円軌道を描く恒星を真横から見る場合を考えましょう。恒星の視線速度が周期的に変化するため、ドップラー効果によって光の波長が変化します(ドップラー効果とは、波源が遠ざかるときには波長が引き延ばされ、近づくときには押し縮められる現象です)。光速度が恒星の運動によらない場合、波長の時間変化は正弦関数で表されます。しかし、恒星が速度 v で近づくときには光速が c+kv に、遠ざかるときには c-kv に変化するならば、光が地球に到着するまでの時間に差が生じるため、正弦関数からずれるはずです。このずれが観測されなければ、誤差範囲内で k=0 となり、光速度が光源の速度によらないことが示されます(実際には、恒星はケプラーの法則に従って楕円軌道を描いているので、その分を補正する必要があります)。
1913年のドジッターの論文では、k=1 とすると観測データと矛盾することが示されただけですが、1914年の報告では k<10
-6 、1977年の報告では k<2×10
-9 となっています。
ミクロの領域での光速度不変性は、素粒子反応で生成された光子を使った実験で確認できます。
1964年にCERNで行われた実験では、静止している原子核内部の核子に高エネルギーの陽子をぶつけることによって、光速の99.975%の速度を持つπ
0 を生成し、これが瞬間的に崩壊して生まれる2個の光子を利用しました。最初の陽子ビームは、適当な時間間隔を挟んでパルス状に照射されるので、光子が作られる時刻は、小さな誤差範囲内で確定できます。一方、飛び出した光子は、30メートルの通路を抜けた後に光電子増倍管で捉えられるので、捉えた時刻から飛行時間が求められ、光子の速度が計算できます。この実験では、ほぼ光速で運動する物体から放出された光子の場合、k<10
-4 という結果が得られました。
このほか、電子・陽電子の対消滅で作られる光子を使った実験も行われています。
【Q&A目次に戻る】

ドーキンスは、自己複製子とその乗り物(ヴィークル)を対立的に扱い、生存に有利な変異を後代に伝えられる自己複製子が主で、自己複製子の指令通りにしか作られない乗り物を従としています。しかし、こうした明確な対立図式ができあがるのは、おそらく、原始的な生命が誕生して、かなり時間が経ってからではないかと思われます。それ以前の段階では、自己複製子(遺伝子)と乗り物(細胞)は、単純な主従の関係にはないと言えるでしょう。
素朴な議論では、有機物が多量に含まれた熱い原始の海で多様な分子反応が繰り返され、数億年に及ぶ化学進化の後に、自己複製能力のある分子−−RNAワールド仮説に従えばRNA−−が生み出されたことになっています。しかし、どれほど有機物が含まれていたとしても、分解と拡散が支配的な海水中で、自己複製子が生み出されるまで化学進化が続いたとは、ちょっと信じられません。むしろ、化学進化によってさまざまな合成・分解を行う分子機械が作られた後に、膜で包まれたり液滴の内部に取り込まれたりすることによって、コンパートメント内部で安定的に代謝が行われるようになったと思われます。このように安定した代謝を行う原始的細胞は、長期にわたって存続できるため、他の細胞と分子機械を交換する機会も増え、最終的には、自己複製が可能になる分子機械のセットを獲得して、最初の生命になったのではないでしょうか。
こうした考えが正しいとすると、まず細胞が形成され、しかる後に、自己複製能力を持つ遺伝子の仕組みが完成したようにも見えます。しかし、試験管内で裸のRNA分子を化学進化させる実験が成功したとの報告もあり、そう単純に割り切るべきではないでしょう。むしろ、複製機能の獲得とコンパートメント化は同時並行的に進んだ、あるいは、遺伝子と細胞は共進化を遂げたと考えた方が良いのかもしれません。
そもそも、生命の起源に関しては、いまだ議論が紛糾しています。最初の生命が誕生した時期(40億年以上前〜20数億年前)、場所(浅い海辺〜深海熱水孔周辺)、元になる有機物の起源(地球上で合成〜隕石に乗って飛来)などについても意見が分かれています。それだけに、新しいアイデアをいろいろと試してみる余地が残っており、思考の冒険が可能な分野でもあります。
【Q&A目次に戻る】

1989年にポンスとフライシュマンが発表して大騒ぎとなった「常温核融合」とは、卓上装置を使って大量に核融合反応を起こし、膨大なエネルギーを発生させるというものでした。現在では、こうした小型の装置で核融合を起こしても、巨大なエネルギーは生み出せないという見方が一般的です。一方、質問にある「放電型核融合」は、小型の装置を使って核融合を起こすという点では常温核融合と同じですが、エネルギーの発生を目的とせず、中性子(あるいは陽子)のビームを作るためのものです。
こんにち、対人地雷の撤去は急を要する国際的課題となっています。通常は、地雷を探し出すのに金属探知器が用いられますが、無数の金属片が埋まっている地帯での探索や、プラスチックないしセラミック製の地雷に対しては、あまり有効ではありません。そこで、中性子ビームを使って、地中の火薬そのものを発見する方法が考案されました。ある素材に中性子ビームを照射すると、原子核との反応を通じて、元素組成に対応したスペクトルを持つガンマ線が発生します。火薬の組成は種類によって決まっている(例えば、TNT火薬は、水素:炭素:窒素:酸素の比が、3:7:3:6 になる)ので、ガンマ線の分析を行うことにより、特定の火薬の有無が判定できるわけです。
ここで問題になるのは、中性子ビームをどうやって作るかです。実験室では、線形加速器などが用いられますが、こうした装置を地雷原まで運ぶことは困難です。そこで、核融合を利用して中性子ビームを発生させる小型装置の開発が進められています。
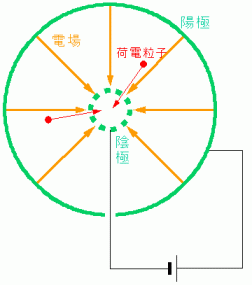
この装置には、「慣性静電閉じこめ」という難しそうな技術が使われていますが、要は、電場だけで荷電粒子を閉じ込めておく方法で、原理自体は、1950年代に考案されています。球状の真空容器の内側を陽極とし、中心近くにグリッド状の陰極を設置すると、正に荷電した粒子は、内向きの電場によって中心に向かって加速されます。陰極の面積を充分に小さくしておけば、加速された荷電粒子はそのまま陰極を素通りしていきます。大部分の荷電粒子は、いったん陰極の外側に出た後に再び電場の作用で中心部に戻されるといった運動を繰り返しますが、中心付近で高エネルギーの荷電粒子同士が衝突することもあります。荷電粒子として重水素の原子核(d)を使えば、こうした衝突の際に、ときに核融合反応
d + d →
3He + n
が生じて、2.45MeV の中性子(n)が発生します。京都大学で制作された装置では、直径20cm程度の真空容器に数十kV の電圧を加えることによって、毎秒10
8個程度の中性子を作れたそうです。
内部で核融合が起きているとはいえ、そこで生まれるエネルギーはごくわずかでしかありません。電場から加えられたエネルギーは熱となって失われるため、装置を作動させるには、外部からエネルギーを供給し続ける必要があります。したがって、この装置はあくまで中性子源でしかなく、エネルギー発生装置としては利用できません。
【Q&A目次に戻る】

宇宙が膨張する際に、たかだか天体程度のスケールの物体に関しては、原子間隔をはじめ、圧力・温度・応力などの性質が変わることはありません。これは、物質の性質を決めているのが、重力より何十桁も強い電磁気力や核力であり、空間計量のわずかな変化は、物性に全くといって良いほど影響を与えないからです。例えば、原子のサイズの基準となるのはボーア半径
a = ε
0h
2/πme
2 (MKS単位系)
ですが、この式の形からわかるように、量子電磁気学だけで決定されます。
宇宙の膨張は、宇宙論的なスケールで見ると、銀河分布がしだいに疎になる過程として現れますが、天文学的なスケールでは、他の銀河からの重力が弱くなるというきわめて微弱な効果しかありません。それに、仮に宇宙の膨張とともに原子間隔なども一斉に大きくなるとすると、そもそも膨張しているという事実を観測できないはずです。
天の川銀河から観測すると、他の銀河はハッブルの法則に従って遠ざかっていくように見えますが、これは、天の川銀河が膨張の中心にあるというわけではありません。このことは、宇宙を球面状の空間と仮定する「閉じたフリードマン模型」で考えると、わかりやすいと思います。閉じたフリードマン模型では、多くの銀河は、図のように球面上にほぼ同じ密度で分布しています(実際の空間は3次元ですが、それでは図示できないので、ここでは2次元球面のように描いています)。この空間が膨張すると、球面上での各銀河の位置がそのままでも、銀河間の間隔は増大していきます。その結果、どの銀河にいても、他の銀河は全て自分から遠ざかるように見えることになり、宇宙に特別な場所がないという宇宙原理は満たされています。
【Q&A目次に戻る】

「1+1=2」というのは、計算をしやすいように人間が決めた約束事です。これとは別の約束事に従う数の体系では、この関係は必ずしも成り立ちません。
「1+1≠2」となる代表的な例は、2進法です。コンピュータの内部では、ある素子での電荷の有無という2種類の内部状態をもとに演算を行っているので、全ての数値は、「0」と「1」の2つの数字しかない2進法で表されます。2進法では、10進法における「0,1,2,3,4,…」に対応する数列が「0,1,10,11,100,…」となり、足し算も、
1 + 1 = 10
となります。
もう1つの例が、ブール代数です。自然数の体系の場合、「+1」という演算は「次の数」を与えることを意味します。任意の自然数に「次の数」が存在することは公理であり、「+n」という演算は「+1」の繰り返しとして定義されます。これに対して、論理的な関係を演算で表すブール代数では、「+」を論理和(or)の意味に解釈します。「1」と「0」が、それぞれ命題が真と偽であることを表すとすると、ブール代数の計算規則は、
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1 + 0 = 1
1 + 1 = 1
と与えられます。最後の式は、命題Aと命題Bが真である場合、「AまたはB」という命題も真であることを意味します。
【Q&A目次に戻る】

結論から言うと、富士の樹海のものも含めて、溶岩の磁力は方位磁石を狂わせるほど強くはありません。
溶岩が残留磁気を帯びているのは、内部に含まれる強磁性体の鉱物が磁化されるからです。強磁性体は、1個1個の原子が小さな磁石になっています。キュリー温度(磁鉄鉱の場合は580℃)を超える高温では、熱運動のために、これらの微小磁石がバラバラの方向を向いているために、全体としては磁化されていませんが、温度が下がってくると、近隣にある微小磁石は、互いに同じ向きに配向するように相互作用します。このとき、外部磁場があると、多くの微小磁石がその向きに揃うため、磁性体全体で磁化されるのです。こうした磁化は、微小磁石同士の相互作用で維持されるので、外部磁場がなくなっても、半分以上が残留磁気として残ります。
溶岩が噴出するときには、温度が900〜1200℃なので磁気は帯びていませんが、冷えて固まる過程で、地磁気の向きに微小磁石が配向します。ところが、地球の磁場は、数十万年に1回の割合でN極・S極が反転していますし、大陸移動や地殻変動によって、溶岩の向きが変わることもあります。こうして、現在の地磁気とは異なる向きの残留磁気を持つ溶岩が存在するのです。
外部磁場が小さくても、微小磁石が全て同じ向きに揃った飽和磁化の状態になっていれば、きわめて強い磁力が発生します(磁鉄鉱の飽和磁化は480ガウス=48 mT)。しかし、磁鉄鉱などの磁性鉱物は、溶岩の内部に小さな粒状の塊となって点在しており、大部分の磁力線は、その内部や周囲で閉じてしまうので、溶岩の外に漏れる磁気はあまり強くありません。東大の研究チームが三宅島やキラウエア火山でポータブル磁力計を用いて地表から1〜2メートルの地点での磁気異常を測定したところ、場所による変動が大きかったものの、最大で数十ミリガウス(数μT)だったそうです。地磁気の強さは200〜600ミリガウス程度ですから、溶岩地帯の磁気異常は、それより1桁以上小さいと考えられます。富士の樹海で方位磁石が狂うというのは、迷信だと考えて良いでしょう。
ただし、落雷などの影響で局所的に強く磁化された岩石が見つかることもあります。
【Q&A目次に戻る】

1936年にチューリングが考案した演算装置(いわゆるチューリング・マシン)は、データの記録媒体(テープ)、記録媒体に対して読み書きをするヘッド、装置の内部状態を記憶するメモリから構成されており、内部状態と読み取られた情報に応じて、状態の遷移と記録媒体へ読み書きを行う仮想的な機械です。チューリングは、こうした装置を使えば、あらゆる数学的な演算が遂行可能になることを示しました。ただし、この装置自体はあくまで概念的なもので、具体的にどのような素材から作られるかは特定されていません。現在のコンピュータは、半導体などの電気的素子を用いて、このチューリング・マシンの機能(の一部)を実現したものですが、これが演算装置の唯一の形というわけではなく、他のさまざまな素材を用いた装置が可能です。核酸とタンパク質の相互作用が論理演算と似ていることから、これらを用いて一種のチューリング・マシンを作れないかというアイデアは、1990年代から提出されています。
生体高分子を用いた演算装置の実例は、シャピロとベネンソンが示しています
(*)。制限酵素
Fok I は、GGATG という配列と特異的に結合し、そこから9塩基だけ下流の部分を切断して、末端の塩基4つ分を露出させます。そこで、
Fok I に結合するGGATGの配列を持ち、スペーサとなる2塩基対を挟んで末端の4塩基が露出している短い2本鎖DNA分子を、遷移規則を定める「ソフトウェア」として利用することができます(遷移規則は、露出している塩基の並びによって決まります)。
Fok I にソフトウェアDNAを結合させた分子装置を含む溶液に、末端の4塩基が露出している2本鎖DNA分子を入力データとして投入します。すると、ソフトウェアDNAの露出部分に相補的な配列を持つデータDNAが分子装置に結合し(データの読み取り)、
Fok I の作用によってデータDNAが切断され、新たに4塩基が露出します(状態の遷移とデータの書き込み)。露出した4塩基は、他の
Fok I +ソフトウェアDNA に読み取られるデータ部分となります。この簡単な装置によって、データDNAに特定の配列があるかどうかといった「イエス・ノー問題」を解くことができます。
生体高分子を用いた「分子コンピュータ」に関する研究は、近年、急速に進んでいるようです。シャピロらのモデルでは、制限酵素を用いているために、演算を進めるに従ってDNA分子は短くなっていきますが、逆に、演算の結果として特定のDNAを作り上げていくことも可能です。
核酸とタンパク質の相互作用による演算装置の特徴は、その自律性にあります。電気的素子を用いたコンピュータでは、ハードディスクからデータを読み取る際に、アクチュエータを電気的に駆動させなければなりません。しかし、シャピロとベネンソンの演算装置では、データの読み取りに相当するハイブリダイゼーションは、溶液中で自律的に進行していき、エネルギーもほとんど消費しません。反応速度が遅いという短所はありますが、エネルギーに関して、分子コンピュータはきわめて効率的な演算装置と言えます。
ただし、生体高分子の相互作用を一種の分子コンピューティングと見なせるのは、あくまで特定の側面に限ります。あらゆる演算と同等な機能を端的に実現するためには、データをコードしているDNA(あるいはRNA)に対して、切断や結合をかなり幅広く行えることが必要ですが、こうした便利な酵素はまた見つかっていません。生体内では、DNAの切断や結合はごく限られた形でしか行われず、チューリング・マシンのメモリや状態遷移に相当する一般的な過程はありません。逆に、論理的な演算装置とは異なり、DNAは環境と柔軟に相互作用しており、カスケード的に伝わるさまざまな生体内シグナルに対応して、遺伝子の発現を制御しています。こうしたことを考慮すると、実際の生体高分子の相互作用は、「部分的に論理演算とのアナロジーが成り立つ」という程度ではないでしょうか。
(*)E.シャピロ/Y.ベネンソン「病気を治すDNAコンピュータ」(日系サイエンス2006年8月号)
【Q&A目次に戻る】

ES細胞は、培養細胞で損耗した組織を補修する「再生医療」の切り札とされています。再生医療とは、臓器を人工的に丸ごと作り出すのではなく、あくまで単純な構造の組織を作って、これを損耗した部分に移植するというやり方です。
再生医療に期待されるものの一つに、心筋梗塞の治療があります。心筋梗塞は、現在のところ有効な治療法がありません。しかし、ES細胞を心筋に分化させる方法が確立すれば、シャーレの中で薄いシート状の心筋組織を作り出し、これを重ねて患部に移植することが可能になります。移植された心筋組織が生着すれば、内部に血管が入り込んで、正常な心臓の一部となります。また、手術などで骨が大きく欠損した場合は、小さな骨組織の集合体を欠損部に詰め込んでおくと、(折れた骨がつながるのと同じメカニズムで)周囲の骨と結合して骨が復元される可能性があります。このほか、神経や軟骨の組織を移植することにより、脊髄損傷や関節炎も治療できるようになるかもしれません。
さらに野心的な試みとして、培養した細胞をカプセルに充填し、ハイブリッドタイプの人工臓器として体内に移植する方法も考案されています。ただし、この方法は、あまりうまくいっていません。例えば、ランゲルハンス島の細胞を多孔性の膜で覆われたカプセルに入れて体内に埋め込めば、糖尿病の症状が改善されるはずですが、大型動物を用いた実験はことごとく失敗に終わりました。カプセル内は低栄養・低酸素状態であるために細胞が充分に活動できなかったことが原因のようです。
ES細胞による再生医療は、まだ研究が始まったばかりの段階で、いくつかの危険性も指摘されています。マウスにES細胞を注入した実験では、奇形腫と呼ばれるガン細胞が作られたケースも報告されています。また、ES細胞は、不妊治療で利用されなかった受精卵やヒトクローン胚から作り出すため、倫理的な問題点もあります。このため、通常の治療にES細胞が使われるようになるとしても、10年以上先の話だと思われます。
【Q&A目次に戻る】

核融合炉で高温が必要となるのは、核反応の頻度を充分に高くしなければならないからです。
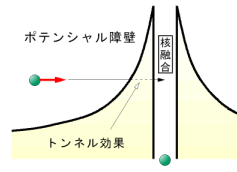
核融合反応は、二重水素や三重水素の原子核が接近したときに生じます。ここで、電気的な斥力によるポテンシャル障壁を、熱運動の運動エネルギーだけで乗り越え、核力の及ぶ範囲とされる10
-15メートル程度まで接近する場合を考えてみましょう。このとき必要となる運動エネルギーK は、大ざっぱな近似で
K 〜 e
2/r (r〜10
-15[m])
で与えられます。
K = 3kT/2
と置いて、この値が平均運動エネルギーとなる温度T を求めると、約100億度となりますが、実際には、これほどの高温は必要ありません。量子力学的なトンネル効果によって、運動エネルギーがポテンシャル障壁の最大値より小さくても、障壁を通り抜けることが可能だからです(右図)。しかし、通り抜けなければならないポテンシャル障壁が大きくなるほど核融合が起きる確率は小さくなります。充分なエネルギー発生率を実現する実用的な核融合炉では、温度は数億度以上になることが要請されます。
核融合が起きる頻度を高くするには、他の条件を整えることも必要です。通常の核融合炉では、希薄な電離気体であるプラズマを高温に保つことによって核融合を起こそうとしていますが、核融合が起きるほど原子核同士が接近する頻度は、一定の領域内部に原子核が「多く」かつ「長く」存在するほど高くなります。このため、実用的な核融合炉を作るためには、プラズマの密度が大きく、閉じ込め時間が長いことが必要です。フランスに建設が計画されている国際熱核融合実験炉(ITER)では、温度〜1億度、密度(電子の個数で表します)〜10
20個/m
3、閉じ込め時間〜6秒程度を達成し、熱出力100万kW程度(瞬間値)を実現することを目標としています(ITER の設計にはいくつかの提案があり、タイプによって数値が異なります)。
一方、恒星中心部のエネルギー発生率は、核融合炉よりも遥かに低くなります。太陽の場合、中心温度は1500万度にすぎず、トンネル効果によって核融合は起きるものの、その確率はきわめて低くなります。実際、太陽中心部でのエネルギー発生率を概算すると、1グラム当たり10
-6W 程度というわずかな値でしかなく、ITER とは十数桁の開きがあります(人体に比べても数千分の1です)。しかし、太陽の場合、巨大な重力によって物質がぎゅうぎゅうに押し込まれているので、中心部分での密度は10
32個/m
3に達していおり、単位質量当たりの発熱量はごくわずかでも、単位体積当たりの発熱量はそこそこに大きくなります(それでも、1m
3で電球1個分)。また、核融合炉が断続的にエネルギーを発生するのに対して、太陽内部の核融合は間断なく進みます。そして何よりも、太陽はとてつもなく巨大です。太陽の質量は 2×10
30kg もあるため、放出する総エネルギーは 4×10
26W に達します。これは、出力100万kWの ITER 40京基分に相当する量です。つまり、太陽では、その巨大さが、エネルギー発生率の低さを凌駕しているのです。
【Q&A目次に戻る】

『
この世界についての仮説・概要』にある「ピークの構造における複雑さの度合いが充分に高くなった“亜世界”が主観的世界である」という仮説のもと、客観的世界と主観的世界を同一の物理的世界の異なるアスペクトとして解釈する試みについて、質問があります。高次元量子系のピークあるいはピークを作り出す前の全状態数の中に、主観を表現しうる次元がすでに含まれているとお考えでしょうか? この議論には、主観を扱うための新たな次元を導入する必要性は示されていないように思われました。とすれば、主観的世界におけるリアルは、客観的世界のプロセスの産物ということになります。客観的世界の次元数がきわめて大きなものであることが、主観のリアルを扱えることとどうして結びつくのか、教えてくださればと思います。チャーマーズの分類するところの“難しい問題”を議論されているのでしょうか? それとも“易しい問題”しか議論しない立場なのでしょうか?【その他】

チャーマーズの“難しい問題”(the Hard Problem)は、「物質的な過程と感覚質(クォリア)はどのような関係にあるか」というものだと解釈しますが、感覚質とは何かを明確に定義することができていない以上、問いの立て方としてあまりに曖昧で、直接答えることは困難です。さらに、「脳からなぜ心が派生するか」という問いにしてしまうと、機能を解明するために措定された空間内存在である《脳》を議論の前提とするので、単なる機能ではない《心》と結びつけようがなく、原理的に解答不能な擬似問題となります。解答の方向性だけでも見いだすためには、問題を整理・分割して、段階的に答えていくことが必要です。
私が本質的な論点と考えるのは、感覚質の「抽象性」を説明できるかどうかです。感覚質というと、しばしば主観性と表裏一体の問題として捉えられがちですが、現実の意識に「私が−赤いと−感じる」という分節的な構造は見られず、「私の世界にある赤さ」だけがリアルだと思われます。したがって、主観性については後回しにして、まずは、「赤さ」という抽象的なものがなぜリアルであり得るのかを論じることから始めるべきでしょう。
現在の物理学的な知見によると、物質的過程は全て、構成要素の振舞いをもとに記述することができます。例えば、「キラキラした金属光沢」は、自由電子と電磁場の相互作用という形式で書き表されます。「波のうねり」のようなホリスティックに見える性質も、集団運動における変数分離の手法を用いれば、分子という構成要素の運動に還元可能です。一般的に言って、物質に見られる複雑な性質は、構成要素の単純な過程が複合的に組み合わされることによって実現されています。ところが、感覚質は、そうではありません。「赤さ」は、それを構成する要素の組み合わせに還元することはできないはずです。物と心が同じ何かの2つのアスペクトであると主張するためには、このギャップが埋められなければなりません。
もし、物質世界を記述する理論として、真空内部を粒子が飛び回りながらくっついたり離れたりしているという機械的原子論が正しいとすれば、物と心は全く相容れないものだと言えるでしょう。しかし、現代物理学によれば、こうした素朴な原子論は誤っており、物質世界が膨大な次元数を持つ量子系であることが明らかにされています。量子系を構成する1つ1つの次元は、その内部の状態が単純な関数で表されるような“つまらない”ものですが、(1立方センチ当たり10
100個というような)とてつもない個数の次元が集まることによって、多様で複雑な世界が実現されているわけです。この理論(場の量子論ないし素粒子論と呼ばれています)は、大部分の物理現象を正確に記述できる信頼性の高いもので、まだ完全ではありませんが、将来、重力を含むあらゆる物理現象を包括する「万物の理論」が完成した暁には、時間や空間は、これらの次元同士の結びつきが生み出す派生的なものと解釈されることになります(完成しないかもしれませんが)。それでは、こうした高次元量子系としての世界において、還元不能な抽象的性質がリアルになることはあるのでしょうか。
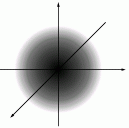
『
この世界についての仮説・概要』では、この問題を、ベンゼンの例を用いて説明しています。ベンゼンを原子核と電子からなる量子系として扱うと、その振舞いは162次元の世界における現象として記述されますが、最も安定な状態にあるときの全体的な性質は、はるかに次元数の小さい12次元世界の出来事として表されます。特に、炭素原子核が正六角形の頂点に位置するという性質は、ベンゼンの状態を表す関数が、正六角形になっていることを示す点でピークを示すことに対応します。こうしたピークは、右図(都合上3次元にしています)のように関数値に対応する濃淡を使って表すと、多次元世界の中にある“塊”のように見えます。われわれは、ペンやボールのような空間内部にある“塊”を現実に存在する物体として認識しますが、「ベンゼンが正六角形であること」のように多次元世界のピークとなる性質は、それと同等の正当性をもって「現実に(リアルに)存在する」と言えるでしょう。このとき、性質の「複雑さ」はピークが存在する多次元世界の構造に含まれており、性質自体は、ピークという単純な形で実現されています。
「量子(quanta)」という言葉は、もともとエネルギーや角運動量のような物理量がとびとびの値になることに由来しています。例えば、原子の輝線スペクトルは、離散的なエネルギーを持つ光子(light quanta)の集まりとして扱えます。しかし、量子系の特性は、それだけではありません。単に物理量を離散化するだけではなく、(正六角形性のような)抽象的な性質を多次元世界内部にある“塊”として実現することもできるのです。こうした「性質を表す塊」は、「量子(quanta)」と対になる概念として、「質子(qualia)」と呼ばれてしかるべきものです。
中枢神経系の機能を担っているのは、高分子の構造変化とそれに伴う輸送現象であり、量子論的な効果によって実現されています。したがって、量子系の特性に従って、(バックグラウンドとなる場の揺らぎなどを無視した)有効な次元数だけでも億を超える多次元空間の中に、さまざまな性質の塊が存在していると推定されます。次元数がきわめて大きいので、かなり複雑な性質も実現可能であり、「(私の世界にある/私が感じている)赤さ」のような感覚質も、次元数のきわめて多い世界にまたがる「質子(qualia)」としてリアルに存在するのではないでしょうか。これを客観的世界の現象として見ると、個々の次元とその内部の状態という構成要素の振舞いに還元され、主観的世界の現象として見ると、多次元世界の単純なピークという還元不能な事態になります。こうして、客観的世界と主観的世界が同一の世界の異なるアスペクトであることが可能になるのです。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
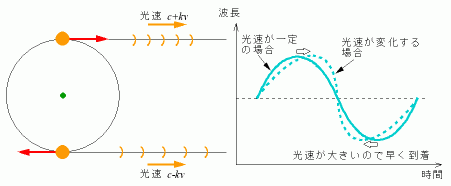 簡単のため、円軌道を描く恒星を真横から見る場合を考えましょう。恒星の視線速度が周期的に変化するため、ドップラー効果によって光の波長が変化します(ドップラー効果とは、波源が遠ざかるときには波長が引き延ばされ、近づくときには押し縮められる現象です)。光速度が恒星の運動によらない場合、波長の時間変化は正弦関数で表されます。しかし、恒星が速度 v で近づくときには光速が c+kv に、遠ざかるときには c-kv に変化するならば、光が地球に到着するまでの時間に差が生じるため、正弦関数からずれるはずです。このずれが観測されなければ、誤差範囲内で k=0 となり、光速度が光源の速度によらないことが示されます(実際には、恒星はケプラーの法則に従って楕円軌道を描いているので、その分を補正する必要があります)。
簡単のため、円軌道を描く恒星を真横から見る場合を考えましょう。恒星の視線速度が周期的に変化するため、ドップラー効果によって光の波長が変化します(ドップラー効果とは、波源が遠ざかるときには波長が引き延ばされ、近づくときには押し縮められる現象です)。光速度が恒星の運動によらない場合、波長の時間変化は正弦関数で表されます。しかし、恒星が速度 v で近づくときには光速が c+kv に、遠ざかるときには c-kv に変化するならば、光が地球に到着するまでの時間に差が生じるため、正弦関数からずれるはずです。このずれが観測されなければ、誤差範囲内で k=0 となり、光速度が光源の速度によらないことが示されます(実際には、恒星はケプラーの法則に従って楕円軌道を描いているので、その分を補正する必要があります)。
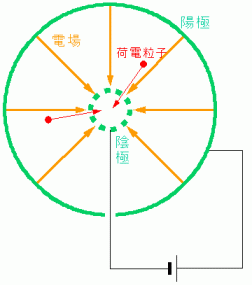 この装置には、「慣性静電閉じこめ」という難しそうな技術が使われていますが、要は、電場だけで荷電粒子を閉じ込めておく方法で、原理自体は、1950年代に考案されています。球状の真空容器の内側を陽極とし、中心近くにグリッド状の陰極を設置すると、正に荷電した粒子は、内向きの電場によって中心に向かって加速されます。陰極の面積を充分に小さくしておけば、加速された荷電粒子はそのまま陰極を素通りしていきます。大部分の荷電粒子は、いったん陰極の外側に出た後に再び電場の作用で中心部に戻されるといった運動を繰り返しますが、中心付近で高エネルギーの荷電粒子同士が衝突することもあります。荷電粒子として重水素の原子核(d)を使えば、こうした衝突の際に、ときに核融合反応
この装置には、「慣性静電閉じこめ」という難しそうな技術が使われていますが、要は、電場だけで荷電粒子を閉じ込めておく方法で、原理自体は、1950年代に考案されています。球状の真空容器の内側を陽極とし、中心近くにグリッド状の陰極を設置すると、正に荷電した粒子は、内向きの電場によって中心に向かって加速されます。陰極の面積を充分に小さくしておけば、加速された荷電粒子はそのまま陰極を素通りしていきます。大部分の荷電粒子は、いったん陰極の外側に出た後に再び電場の作用で中心部に戻されるといった運動を繰り返しますが、中心付近で高エネルギーの荷電粒子同士が衝突することもあります。荷電粒子として重水素の原子核(d)を使えば、こうした衝突の際に、ときに核融合反応
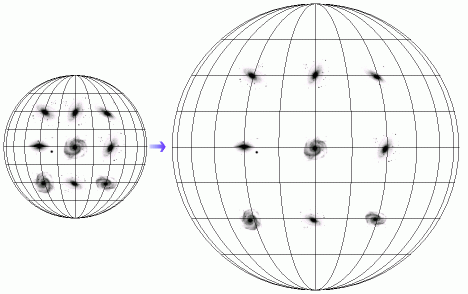
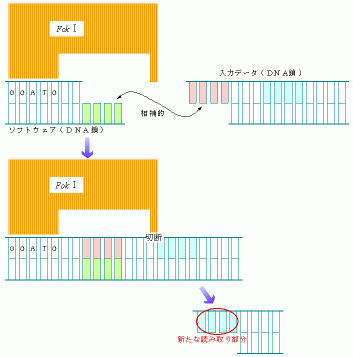
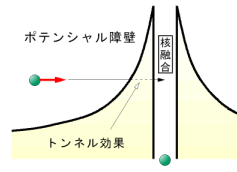 核融合反応は、二重水素や三重水素の原子核が接近したときに生じます。ここで、電気的な斥力によるポテンシャル障壁を、熱運動の運動エネルギーだけで乗り越え、核力の及ぶ範囲とされる10-15メートル程度まで接近する場合を考えてみましょう。このとき必要となる運動エネルギーK は、大ざっぱな近似で
核融合反応は、二重水素や三重水素の原子核が接近したときに生じます。ここで、電気的な斥力によるポテンシャル障壁を、熱運動の運動エネルギーだけで乗り越え、核力の及ぶ範囲とされる10-15メートル程度まで接近する場合を考えてみましょう。このとき必要となる運動エネルギーK は、大ざっぱな近似で
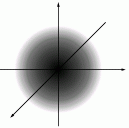 『この世界についての仮説・概要』では、この問題を、ベンゼンの例を用いて説明しています。ベンゼンを原子核と電子からなる量子系として扱うと、その振舞いは162次元の世界における現象として記述されますが、最も安定な状態にあるときの全体的な性質は、はるかに次元数の小さい12次元世界の出来事として表されます。特に、炭素原子核が正六角形の頂点に位置するという性質は、ベンゼンの状態を表す関数が、正六角形になっていることを示す点でピークを示すことに対応します。こうしたピークは、右図(都合上3次元にしています)のように関数値に対応する濃淡を使って表すと、多次元世界の中にある“塊”のように見えます。われわれは、ペンやボールのような空間内部にある“塊”を現実に存在する物体として認識しますが、「ベンゼンが正六角形であること」のように多次元世界のピークとなる性質は、それと同等の正当性をもって「現実に(リアルに)存在する」と言えるでしょう。このとき、性質の「複雑さ」はピークが存在する多次元世界の構造に含まれており、性質自体は、ピークという単純な形で実現されています。
『この世界についての仮説・概要』では、この問題を、ベンゼンの例を用いて説明しています。ベンゼンを原子核と電子からなる量子系として扱うと、その振舞いは162次元の世界における現象として記述されますが、最も安定な状態にあるときの全体的な性質は、はるかに次元数の小さい12次元世界の出来事として表されます。特に、炭素原子核が正六角形の頂点に位置するという性質は、ベンゼンの状態を表す関数が、正六角形になっていることを示す点でピークを示すことに対応します。こうしたピークは、右図(都合上3次元にしています)のように関数値に対応する濃淡を使って表すと、多次元世界の中にある“塊”のように見えます。われわれは、ペンやボールのような空間内部にある“塊”を現実に存在する物体として認識しますが、「ベンゼンが正六角形であること」のように多次元世界のピークとなる性質は、それと同等の正当性をもって「現実に(リアルに)存在する」と言えるでしょう。このとき、性質の「複雑さ」はピークが存在する多次元世界の構造に含まれており、性質自体は、ピークという単純な形で実現されています。