 コペンハーゲン解釈について調べていて素人考えで疑問に思ったことがあるので質問します。
コペンハーゲン解釈について調べていて素人考えで疑問に思ったことがあるので質問します。
- コペンハーゲン解釈では、粒子は波動関数の示す場所に同時に存在するとする説明をよく見掛けますが、正しいでしょうか? 違っているとすると、原子核の周りを回る電子が落ち込まないことをコペンハーゲン解釈で説明出来るのでしょうか? 同様に、エヴェレット解釈では原子核を回る電子はどうなるのでしょうか?
- 粒子と波の二重性について、粒子と波は同じ座標に存在しないといけないのでしょうか? 波は波動関数が示す広がりを持つが粒子は一点に存在すると考えれば波動関数の収縮は必要なく、常に粒子と波の性質が同時に観測されると思いますが、それは間違っているのでしょうか? たとえば、二重スリットの実験では単に粒子としても波としても矛盾しない結果が出ただけとは考えられないのでしょうか? 波としては波動関数で表されるが、粒子としてはスリット通過後の初期方向が一様でなく軌道も直線でないと考えれば、知ることはできなくても軌道は確定したものとして辻褄が合わせられそうな気がしますが、どうでしょうか? Wheeler の選択遅延実験も、粒子としても波しても矛盾しない結果が出るだけと考えれば、未来が過去を決定したとする矛盾はなくなると思いますが、どうでしょうか?
【現代物理】

最初にお断りしておきますが、「コペンハーゲン解釈」とは何かについて、完全な合意ができているわけではありません。一般には「ボーアの下に集まった物理学者たちが作り上げた解釈」とされていますが、例えば、ハイゼンベルグとパウリでは随分と考え方が異なっていますし、量子力学の教科書でも、細かな点(これは、しばしば哲学者が本質的と考える点です)には見解の相違があります。ここでは、多くの物理学者が標準的と見なしている解釈を「コペンハーゲン解釈」と呼ぶことにします。
「コペンハーゲン解釈」では、シュレディンガー方程式の解となる波動関数は、あくまで「測定を行った場合に得られる結果」についての確率振幅でしかなく、測定前の系が“実際に”どのような状態にあるかは、標準的な量子力学の定式化では記述できないと見なされています。「粒子が波動関数の示す場所に同時に存在する」と解釈されているわけではありませんが、「どこかに存在する」とも言えません(そもそも記述できないのです)。原子核の周りの電子は、シュレディンガー方程式の解として与えられる特定の定常状態(時間とともに変化しない状態)にあり、定常解の存在が「電子が原子核に落ち込まない」ことの理由になると考えられています。
「粒子が波動関数の示す場所に同時に存在する」というのは、むしろ「多世界解釈」に近いものです。この解釈では、何らかの相互作用によって互いに干渉しない(物理的に無関係と言える)状態に分岐した場合、全ての分岐が対等に扱われます。例えば、電子の位置が確定していない系で、ガンマ線照射による位置測定を行うことを考えましょう。このとき、確率分布ψψ
*の拡がりに対応して、さまざまな場所で電子が観測される可能性があり、どの位置で発見されたかによって、異なる分岐へと状態が変化していきます。もともとの「コペンハーゲン解釈」では、測定以後の系の時間発展を考える際に、このうち1つの分岐を表す状態関数を初期条件として新たにシュレディンガー方程式を立てることが要請されるのに対して、「多世界解釈」によると、各分岐を混合したままで扱うことが許されます。この場合、測定前のψψ
*の拡がりは、電子がさまざまな場所にあり、それぞれが異なる分岐に変化していく状態だと解釈されます(厳密に言うと、位置は連続変数なので、互いに干渉しないような分岐を扱うのは難しいのですが)。
「多世界解釈」にはさまざまなバージョンがあり、全ての分岐を実在的なものと見なす“強い”多世界解釈を主張する学者(ドイッチュなど)もいます。こうした解釈を採用する人が積極的に量子力学の通俗書を出版するので、学界でも支持を集めていると錯覚する読者もいますが、実際には、それほど有力ではありません。また、「多世界解釈」に「エヴァレットの」と冠することもありますが、エヴァレット自身が多世界解釈の立場を取っていたわけではありません。エヴァレットの定式化は、それまで量子論的な対象と古典論的な測定装置に峻別されていたものが、ひっくるめて量子力学の枠内で記述できることを示したものです。これによると、いちいち新しい初期条件を使ってシュレディンガー方程式を立てなくてもかまわない上に、ソフィスティケートされた現代的な測定(例えば、あるものが測定
されないことによって系の状態がわかるといった)にも対応できるので、実にスマートです。「コペンハーゲン解釈」を“拡大解釈”して、エヴァレットの定式化を組み込んでしまう人もいます。
粒子と波の二重性に関しては、少し誤解があるようです。量子力学で記述される現象に、粒子的な側面と波動的な側面があるのであって、粒子と波を分けて考えることはできません。通常、時間発展のダイナミクスでは(干渉が見られるなど)波動的な振舞いが顕著になり、高エネルギー散乱などのカイネティクスを考える場合は粒子的な扱いが便利です。粒子性と波動性は一般に相補的であり、1つの現象の異なる側面として現れるため、例えば、「粒子と波は別個の実在であり、粒子の運動を波が先導している」と考えるのは不自然です(この立場を貫こうとすると、全宇宙の粒子間における遠隔相互作用を仮定するといった通常の解釈より遥かに信じがたい見解を受け入れなければなりません)。粒子と波の二重性を奇妙に感じるのは、おそらく、粒子としてビリヤード球のような古典力学に従う物体を想定しているからでしょう。量子力学の発展型である「場の量子論」によると、量子力学的な対象は、空間の中に自存する物体ではなく、場の励起状態であって、古典的なイメージが全く通用しないものなのです。
量子力学の非因果性は、“強い”多世界解釈を採用しない限り、理論の本質的な要素だと考えざるを得ません。局所的な因果律(ある時刻の状態がその系の未来の状態を完全に規定しているという原理)が成り立っていないことを示す実験は、すでにいくつも行われています。ただし、これは、未来が過去を規定しているというのではなく、過去に規定されない未来があることを意味するもので、それほど不可解ではありません。
【Q&A目次に戻る】

太陽で外部に光を放出している部分は、光球と呼ばれる厚さ数百kmの層(対流層と彩層に挟まれた層)で、平均密度が 2×10
-7 g/cm
3 程度の希薄なガスでできています。密度がきわめて低いため、光球を構成する物質の大部分は中性の原子(主に水素原子)であり、たまに起きる衝突によって、ごく一部の水素原子が電離して陽子と電子になっています。内部からの光は希薄なガスの層を素通りしそうですが、こうした荷電粒子が放射のエネルギーを吸収するため、ジンワリと加熱されて、平均温度は6000K(層の上部と下部で差があります)になっています。水素原子、陽子、電子の衝突頻度は低いものの、長時間にわたる相互作用によって実現されたほぼ定常的な状態なので、局所的にはほぼ熱平衡状態と見なすことができ、熱輻射(熱放射)の公式が当てはめられます。
太陽のエネルギー源となっているのは、中心部で起きる核融合であり、この反応によって、ガンマ線のような波長の短い電磁波が放出されます。しかし、太陽の中心部は密度が高く、ガンマ線は1mmも進めずに吸収されて、より波長の長いX線に変換されます。X線もすぐに吸収されて紫外線に変わり…というように、内部からの放射は、吸収・放出を繰り返しながら外側に進んでいき、20万年近くをかけて対流層の下部に到達します。対流層は放射に対してほとんど不透明で、その名の通り対流によって熱を伝えています。ここまでくると、中心部の核反応で生み出されたエネルギーは、もはや純然たる(統計力学で記述されるような)熱エネルギーに変わっています。対流層の下部は200万Kの高温ですが、上部の境界面では8000〜9000Kに下がっており、そこから放射によって光球にエネルギーを与えています。
【Q&A目次に戻る】

話を簡単にするために、ボーズ粒子間の相互作用が小さいとして、1粒子波動関数 ψ
k を使う近似で考えることにしましょう。状態kにある粒子数を n
k とすると、粒子の総数がNであるという条件は、
N = Σ
k n
k
と表されます。また、系全体の波動関数は、各粒子の波動関数 ψ
k(x
i) を掛け合わせ、さらに、「各粒子が区別できない」という条件から、これを対称化することで得られます。例えば、2個の粒子が状態kと状態jにある場合は、
Ψ(x
1,x
2) = const. { ψ
k(x
1)ψ
j(x
2) + ψ
j(x
1)ψ
k(x
2)}
となります。
ボーズ・アインシュタイン凝縮とは、特定の状態 ψ
0 に、巨視的な数の粒子が入ることです。ここでは、Nに近い N
0 個の粒子が ψ
0 の状態にあるとしましょう。このとき、凝縮相の粒子密度を考えます。どれか1個の粒子がxにある確率は、 |ψ
0|
2 ですから、 N
0 個の粒子が ψ
0 にある場合の粒子密度は、
N
0|ψ
0|
2
で与えられます。重要なのは、これが量子力学的な確率ではなく、統計力学によって与えられる密度そのものだということです。個々の粒子は |ψ
0|
2 の確率でこの場所に存在したりしなかったりしていますが、粒子の個数が充分に多いときは、実際に、この確率で与えられた通りに分布するからです。これをさらに拡張して、凝縮相全体の振舞いを規定する統計力学的な波動関数
Ψ(x) = (N
0)
1/2 ψ
0(x)
を定義することができます(細かい議論を端折っていますが、詳しくは大学院レベルの教科書を参照してください)。こうした定義が可能になるのは、 N
0 個の粒子が全て同じ状態 ψ
0 にあるためです。
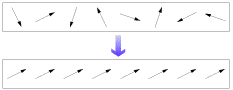
ここで、「粒子が互いに区別できない(粒子を交換しても波動関数の形が変わらない)」という性質が、大きな意味を持っています。古典力学のように粒子が区別できる場合は、単に確率密度が等しければ同じ状態と見なされるのに対して、量子力学では、さらに、1粒子波動関数の位相まで等しくなることが要求されます。波動関数の位相因子 e
iφ は、複素平面上での偏角φによって決まるので、これを2次元単位ベクトルの向きとして表すことができます。凝縮していないときは、このベクトルの向きは何であっても良かったのですが、ひとたび凝縮すると、全てのベクトルが同じ向きに揃うことになります。これは、ちょうど2次元の強磁性体が磁化する際に回転対称性を失うのと同じであり、ボーズ・アインシュタイン凝縮によって、位相に関する対称性が破れたと言えます。
波動関数の位相を変えても物理現象に変化がないという対称性は、しばしば「ゲージ対称性」と呼ばれます。場の量子論では、ゲージ対称性は場の変数に関する局所的な対称性に拡張されており、スカラー粒子が空間中に一様に凝縮することによって局所ゲージ対称性が破れ、素粒子が質量を獲得すると考えられています。
【Q&A目次に戻る】

「高さ(高度)」は地表面(厳密にはジオイド面=全地球的な平均海面)を、「距離」は主に地球の中心を基準にしたときの間隔を表すもので、両者を区分する物理的な根拠はありません。大ざっぱに言って、地球の半径6400kmと比べたときの大小で、言葉を使い分けているようです。例えば、スペースシャトルは、地表から200〜300kmの(遠くから見ると地面すれすれの)低い軌道を飛んでいるので、「高度」で表すのが自然です。静止衛星になると、赤道上空の高度3万5800km、地球中心から測って4万2200kmの軌道を周回しており、気象衛星・通信衛星として地上基地との交信を考えるときには「高度」を使った方がわかりやすいのですが、軌道の形などを問題とする場合には、地球の中心からの距離で表記することもあります。月は、地球からの平均距離が38万kmにもなるので、地表から測った高度を考える意味はありません。しかし、木星に最も近い衛星であるメティスは、木星の半径が7万1500kmであるのに対して、平均軌道半径がたったの12万7600kmであり、将来、木星探査の基地などに利用する場合は、「高度」表記を使うかもしれません。
衛星軌道上にあるスペースシャトルの内部は「無重力状態」になっていますが、これは、高度が充分に高くなって地球の重力圏を脱したからではなく、軌道を周回することによって生じる遠心力と、地球からの重力がちょうど釣り合ってうち消しあっているからです。地表付近でも、自由落下する飛行機の内部では、落下の加速度による慣性力が重力の作用を相殺するので、無重力(正確には無重量という)の状態になります。飛行機内部に作り出される無重量状態は、宇宙飛行士の訓練に利用されます。
遠心力などの慣性力が重力をうち消すことによる無重力状態は、天体の世界にもあります。例えば、月に加わる力を計算すると、地球からの重力よりも太陽からの重力の方が大きくなっており、月は地球の重力圏の外側にあると言うことも可能です(地球からの重力の方が大きくなるのは、地球から26万km以内の範囲です)。しかし、通常は、そうした言い方はしません。月は地球と一緒に太陽の周りを公転しており、その遠心力が太陽からの重力をうち消しているため、地球の重力だけを考えてもかまわないからです。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
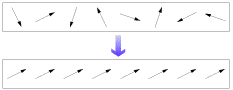 ここで、「粒子が互いに区別できない(粒子を交換しても波動関数の形が変わらない)」という性質が、大きな意味を持っています。古典力学のように粒子が区別できる場合は、単に確率密度が等しければ同じ状態と見なされるのに対して、量子力学では、さらに、1粒子波動関数の位相まで等しくなることが要求されます。波動関数の位相因子 eiφ は、複素平面上での偏角φによって決まるので、これを2次元単位ベクトルの向きとして表すことができます。凝縮していないときは、このベクトルの向きは何であっても良かったのですが、ひとたび凝縮すると、全てのベクトルが同じ向きに揃うことになります。これは、ちょうど2次元の強磁性体が磁化する際に回転対称性を失うのと同じであり、ボーズ・アインシュタイン凝縮によって、位相に関する対称性が破れたと言えます。
ここで、「粒子が互いに区別できない(粒子を交換しても波動関数の形が変わらない)」という性質が、大きな意味を持っています。古典力学のように粒子が区別できる場合は、単に確率密度が等しければ同じ状態と見なされるのに対して、量子力学では、さらに、1粒子波動関数の位相まで等しくなることが要求されます。波動関数の位相因子 eiφ は、複素平面上での偏角φによって決まるので、これを2次元単位ベクトルの向きとして表すことができます。凝縮していないときは、このベクトルの向きは何であっても良かったのですが、ひとたび凝縮すると、全てのベクトルが同じ向きに揃うことになります。これは、ちょうど2次元の強磁性体が磁化する際に回転対称性を失うのと同じであり、ボーズ・アインシュタイン凝縮によって、位相に関する対称性が破れたと言えます。