
複素数は代数方程式に関して閉じた体系を作っていますが、これを拡張することができないわけではありません。演算規則を変えれば、複素数を部分系として含むような数の体系を構成する方法もあります。ただし、あまり実用的ではないので、数学の授業ではほとんど取り上げられません。
実数は数直線で表されますが、この直線は、加法の単位元0によって正負の領域に分断されており、x
2のような関数は正の領域にしか値を持たないので、実数の範囲では、方程式 x
2=-1 に解はありません。これに対して、複素数は数平面(ガウス平面)で表され、乗法は、
z
1z
2=r
1exp(iθ
1)r
2exp(iθ
2)=(r
1r
2)exp{i(θ
1+θ
2)}
のように、絶対値は積を、偏角は和を取るという形で定義されます。このため、z
2 のような関数でも、zの絶対値と偏角を少しずつ変えることによって、全ガウス平面を掃くことができ、方程式
z
2 = a
は、必ず解を持ちます。きちんとした証明ではありませんが、複素数の範囲で代数多項式が解を持つことは、任意の代数関数f(z)の値が、zの絶対値と偏角を少しずつ変えたときにガウス平面上を連続的に動いていくと考えると、肯けるのではないかと思います(きちんとした証明は、「|f(z)-a| の最小値が0でないと仮定すると矛盾が生じる」といった形で与えられます)。
複素数を拡張する方法はいくつかありますが、最も良く知られているのは、4元数(クォータニオン、ハミルトン数)を考えるというものです。これは、3つの虚数単位 i, j, k によって
a + xi + yj + zk (a, x, y, z は実数)
という形で表される数です。i, j, k は2乗すると -1 になり、互いに次の関係で結ばれています:
ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik = j
この関係からわかるように、4元数は、乗法の交換法則(ab=ba)を満たしておらず、その集合は、非可換体と呼ばれる体系になっています。4元数は、3次元空間のベクトルと密接な関係を持つことが知られています。虚部を表す3次元ベクトル
V=(x, y, z) を使って、4元数を (a,
V) と書くことにすると、
P = (0,
V)
R = (cos(θ/2), sin(θ/2)
n) (
n:単位ベクトル)
から得られる4元数
RPR
* = (0,
V')
の虚部のベクトル
V' は、
n を軸として
V をθだけ回転させたものになっています。4元数が乗法の交換法則を満たしていないのは、ベクトルの外積と同様です。
4元数は、ロボット制御や3次元CGの制作などに利用されているようですが、複素数ほど幅広く役に立つものではありません。8元数、16元数もありますが、これらは、まずお目にかかることがないでしょう。
【Q&A目次に戻る】

電磁気現象を含む力学過程を物理学的に記述するためには、通常、力学で必要な長さ[m]、時間[sec]、質量[kg] に加えて、もう1つ、電磁気に関する単位が必要となります。一般に用いられるSI単位系やMKSA単位系では電流[A] が、静電単位系では電荷が、それぞれ基本単位とされています。力学単位に加えて電磁気の単位を導入しなければならないのは、電磁気現象の起源についてなんら制限を加えない場合、電荷や電流を任意の値に設定することができるからです。
全ての電荷は素粒子に担われており、その値は電気素量の定数倍(一般に整数倍)に限られ、電場・磁場は運動する電荷から作られるとすれば、電磁気の単位を省略することも可能です。例えば、クーロンの法則は、
F = Q
1Q
2/4πε
0r
2
と表されますが、電荷が電子と陽子だけに担われているとすると、
Q = en (e:電気素量、n:陽子数−電子数)
となり、微細構造定数α(e
2/2ε
0hc=1/137.036… ; h:プランク定数、c:真空中の光速)を使って、
F = αhc n
1n
2/2πr
2
のように、電磁気の単位を含まない式で表すことができます。電場の強さは、電場を生み出している電荷から電場を測定するためのテスト電荷に作用する力を使って定義されるので、やはり、電磁気の単位は必要ありません。電流や磁場についても同様です。
ただし、電場や磁場が素粒子の電荷だけから作られるという仮定は、現実的ではありません。実際には、電子のスピン(自転のようなもの)によっても磁場が作られるからです。スピンが任意の値にならず既知の物理定数から導ける量になることを言うためには、さらに、素粒子が量子力学に従っているという条件を付け加える必要があります。
一般に、自然界が従っている物理法則を決定すると、現象を記述するのに必要な単位の数を減らすことができます。例えば、熱を現象論的に扱う場合には、温度[K] を基本単位として導入する必要がありますが、熱力学は統計力学から導かれるとの立場をとれば、温度はエネルギーと同じ単位で表されます。同様に、相対論を認めれば時間と長さが、量子力学を認めればエネルギーと時間の逆数が、同じ単位になります。さらに、物理学の基本方程式が特定の数学的形式を満たしていると仮定すると、新たな相互作用が発見されても、微細構造定数と同じような無次元の定数を付け加えさえすれば、これまでと異なる単位を導入しなくても済みます。クォーク間の相互作用を媒介するグルーオン場が存在するからといって、グルーオン場強度を表す単位は必要ありません。現在の物理学的な枠組みが正しいと仮定するならば、必要な単位はただ1つ、
[長さ]=[時間]=[質量]
-1=[エネルギー]
-1=[温度]
-1
の単位です。
【Q&A目次に戻る】

一般に、伝播する波は、波源の大きさに比べて波長が長くなるほど指向性が悪くなります。音波の場合、人間の耳に聞こえる可聴周波数は20Hz〜20kHz 程度なので、その波長は17m〜17mmとなり、波長が数百ナノメートルしかない可視光線と違って、可聴領域の音波を使って“音のスポットライト”を作ることは、簡単にはできません。
低周波成分をカットした高音域の音だけにすれば、スピーカアレー方式を利用することにより、ある程度の指向性を実現することは可能です。スピーカアレー方式とは、位相を制御できる小型スピーカを配列して、ちょうど光の回折格子と同じように、特定の方向に伝播する音の回折波を作るというものです。とは言っても、低音域がないので音が不自然になりますし、指向性もそれほど良いものではありません。例えば、美術ギャラリーの天井に設置したスピーカを使って、特定の絵の前に立っている人だけに解説を聞かせるといったことが可能です。
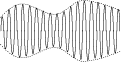
長い間、波長の長い音波で細いビームを作ることは技術的に困難だと考えられていましたが、1975年にテキサス大学の研究者によって新しい方法が開発されました。これは、それ以前に利用されていた水中音波探知機の技術を空気中を伝わる音波に応用したもので、具体的には、超音波を搬送波として可聴波を送るというものです。
超音波とは、周波数が20kHz以上の耳に聞こえない音波で、波長が短く高い指向性を持っているので、小さな音源でも細いビームを作ることができます。この超音波ビームの振幅を可聴周波数で変調させると、変調された波形で周囲の空気を振動させるため、伝播する過程で耳に聞こえる音を作り出します。この原理に基づいて、松下を初めとするいくつかの日本企業が超指向性を持つスピーカの開発に着手しましたが、製作コストが高くつく上に、音がひどくゆがんでしまうために、1980年代の終わり頃までに開発を断念しました。
しかし、1990年代に入って、アメリカで画期的な技術改良がなされます。音がゆがんだ原因は、空気の非線形性によって伝播する過程で波形が変化するためですが、どのようにゆがむかは理論的に予測できるので、最終的に実現されるべき波形から逆算して超音波を放射すれば良いわけです。こうして、2002年には、幅1m以下のビームを数十メートル以上離れた地点に送る音のスポットライトが完成したとアナウンスされました。この技術は、いくつかのイベントに使用されたほか、敵に偽りの音を聞かせて戦闘意欲を喪失させるという軍事目的での応用が検討されています
(イヤですね)。
【Q&A目次に戻る】

現在、時間の基本単位となる“秒”は、「セシウム133の基底状態の2つの超微細準位間の遷移に対応する放射の9,192,631,770周期の継続時間」として、長さの基本単位となる“メートル”は、「光が真空中で299,792,458分の1秒の間に進む距離」として定義されています。しかし、こうした定義は、メートル原器などに代わって標準時間や標準長を決定するために採用された実用的な基準にすぎません。物理学者が時間や長さの真の基準になると考えているのは、物理法則の不変性です。
おそらく、ビッグバンの直後においても、量子力学や相対論の基礎方程式が、現在と同じように成り立っていると考えて良いでしょう(そうでないとすれば、ビッグバン理論の前提が崩れてしまいます)。真空中の光速度cやプランク定数hも、今と変わらぬ定数であるはずです。cの単位は「長さ/時間」、hの単位は「質量×(長さ)
2/時間」なので、質量でもエネルギーでもかまわないから何か1つ次元を持つ量を与えさえすれば、それとcやhを組み合わせることにより、長さ・時間の単位を作り出せます。例えば、宇宙初期の何回かの相転移を経て、電子の質量mは今の値に確定したと考えられていますが、このmから得られる h/mc という長さの次元を持つ量(コンプトン波長)は、電子が関与する現象における長さの基準となります。素粒子同士の相互作用を考える場合は、さらに、理論の定義に含まれる無次元の結合定数を使う必要があります。電磁気的な相互作用の結合定数は微細構造定数αと呼ばれ、1/α=137.0…となります(電気素量はαとhやcから作られる誘導定数です)。電子が電気的に束縛されるとき、軌道の大きさの基準となるのはボーア半径aですが、これは、
a = λ/2πα (λ:電子のコンプトン波長)
として与えられます。このように、原子が形成されていなくても、質量の定まった素粒子さえあれば、長さの基準を作ることができます。
それでは、相転移が起きる前、電子やクォークが質量を持たなかった時期には、長さの基準は決められるのか、不審に思われるかもしれません。この時期の状況に関しては、物理学者の間で必ずしも意見が一致しているわけではありませんが、重力が何らかの形で関与していることはほぼ確実です。これは、ニュートンの万有引力定数Gを使って、
(hG/2πc
3)
1/2
という長さの次元を持つ量を作れるからです。大きさが1.6×10
-35 m と、こんにち研究されているいかなる素粒子の拡がりよりも小さいこの長さは、プランク長と呼ばれており、空間や時間の最小の拡がりと関係する量ではないかと考えられています。宇宙の最初期における拡がりは、このプランク長を基準にして記述されます。
【Q&A目次に戻る】

質問にあるように、多くの液体で、屈折率は温度の上昇とともに低下します。有機溶媒では、温度が1℃上昇すると、屈折率が約0.0005低下低下することが知られています。ただし、水の場合は、屈折率の温度依存性が小さく、1℃の上昇に対して0.0001しか下がりません。
屈折率の温度依存性
| |
15℃ |
30℃ |
| エタノール |
1.36332 |
1.3573 |
| 水 |
1.33345 |
1.3318 |
屈折率は、真空中の光速cを媒質中の光速(位相速度)vで割ったものとして定義されますが、マクスウェル理論によれば、この値は、比誘電率εと比透磁率μを使って、次のように表されます。
n = c/v =(εμ)
1/2
通常の媒質では、比透磁率は1に等しいと置けるので、結局、屈折率は、近似的に比誘電率の平方根に等しくなります。誘電率は電磁場の振動数に依存しています。液体の場合、静電場に対する誘電分極は主に極性分子の配向によって生じますが、可視光領域の振動数では、分子は電磁場の変動に追随して動けないので、その寄与はほとんどなくなり、代わって、電子分極からの寄与が支配的になります。電子分極とは、原子内で電子の位置が変位することによって生じる効果で、近似的に、各原子ごとに分極率と密度の積を加えたものになります。ここで、温度によって大きく変化するのは密度であり、温度が上昇するほど熱膨張によって原子密度が希薄になるので、誘電率、ひいては屈折率が低下します。エタノールの膨張率は水の約5倍になるので、屈折率の低下も同程度に大きくなります。
【Q&A目次に戻る】

反応を起こす物質のサイズが小さくなるほど解放されるエネルギーが大きくなるのは、電気的な力の大きさが電荷間の距離の逆2乗に比例して大きくなるからです。
化学反応に関与するのは、正の電荷を持つ原子核と負の電荷を持つ電子です。分子レベルでは、これらが、10
-9メートル(10億分の1メートル=1ナノメートル)程の範囲に集まっているため、個々の電荷同士が及ぼし合う力は、きわめて巨大なものになります。実際、陽子と電子が 10
-9 メートルに近づいたときに作用するクーロン力は、2.3×10
-10 ニュートンですが、これは、電子に地表の重力加速度の2800京倍にもなる加速度を引き起こすものです。もちろん、実際には、正電荷と負電荷が入り混じって存在しているため、それぞれの電荷からの力が相殺されて、電子が急激に加速されることはありません。分子レベルで原子核と電子がどのように配位されるかは、量子力学によって決定されますが、通常の分子では、力が釣り合って安定した状態が実現されています。しかし、化学反応によって電子の配位が変化すると、この釣り合いが破れて電子や原子核が運動を始め、場合によっては、反応によって生じた分子全体が電気的な力で加速されて、大きな速度で動き出すこともあります。これが化学的な発熱反応であり、このとき放出されるエネルギーは、陽子と電子が1ナノメートルに接近したときの電気的なエネルギー
E
0 = 2.3×10
-19 ジュール
と同程度の大きさとなります。
原子核は、分子よりもさらに5桁ほど狭い範囲に正電荷を持つ陽子(と中性子)を詰め込んだものなので、そこに潜んでいる電気的なエネルギーは、分子の場合の何十万倍にもなります。原子核内部の陽子同士は、強い電気的な斥力を及ぼしあい、互いに遠ざかろうとしています。これを引き留めているのが核力と呼ばれる力です。核力は、距離と力の大きさの関係が湯川型と呼ばれるものになっており、10
-15 メートル程度に近づけるときわめて強い作用を及ぼしますが、距離が大きくなると急激に弱くなるものです。核分裂を起こすウラン235の原子核には、陽子が92個、中性子が143個含まれており、陽子間の斥力があまりに大きくなって、バラバラになる寸前で何とか留まっているような状態にあります。これに中性子をぶつけて核を少し変形させると、部分的に核力が弱くなり、全体をまとめることができなくなって核分裂を起こします。分裂した破片(2つの原子核)は、きわめて強い電気的な斥力によって急速に加速されて飛び去るので、巨大なエネルギーが解放されることになるのです。ウラン1個あたりの解放エネルギーは 3.2×10
-11 ジュールであり、上のE
0の約1億倍の値になっていますが、これは、陽子間の距離が近いことと数が多いことを併せた結果です。
核分裂以外の核反応や素粒子反応で解放されるエネルギーの大きさも、電荷間の距離をもとにおおよその値を求めることができます。例えば、中性子が電子、陽子、ニュートリノに変化するベータ崩壊では、 10
-13 ジュールのエネルギーが解放されますが、これは、電子と陽子を中性子の大きさ程度の距離に離したときの電気的エネルギーとほぼ等しくなっています(ただし、こうした評価はあくまでおおよその目安を与えるもので、厳密には正しくありません)。
それでは、陽子や中性子のような素粒子をバラバラにすれば、核反応よりもさらに巨大なエネルギーが解放されるのでしょうか。陽子や中性子は、電荷を持ったクォークが3個結合されたものなので、核分裂と同様に分裂させられれば、電気的な斥力による分裂片の加速を通じて、エネルギーを外部に取り出せそうです。しかし、これはうまくいきません。なぜなら、クォーク同士をつなぎ止めている力は、電気的なクーロン力とは反対に、長距離で強く短距離で弱いという「漸近自由性」を持っているからです。原子核をまとめている核力は、少し距離を広げると急激に弱くなるので、2つに分裂させることが可能でしたが、クォークの場合は、引き離そうとすればするほど互いに引き寄せあう力が強くなり、決してバラバラにできないのです。宇宙空間にある反物質を利用するといったケースを別にすると、われわれが周囲にある物質の内部から解放できるエネルギーは、核反応によるものが最大だと考えて良さそうです。
【Q&A目次に戻る】

1998年に、遠方の超新星の明るさが理論的な予想値より暗いことが判明し、これを説明するのに、宇宙の膨張速度が加速していて、光が予想以上に長い距離を伝播してきたのではないかという仮説が提唱されました。その後、マイクロ波の背景放射に見られるゆらぎの観測においても、加速膨張仮説を支持するデータが得られています。宇宙が本当に加速膨張しているのか、また、加速膨張しているとしても、宇宙開闢以来、加速膨張を続けているのか、以前は減速膨張していたのに50〜60億年前から加速膨張に転じたのか、必ずしも確定した結論は得られていません。しかし、宇宙論研究者の間では、加速膨張しているとの見方が優勢であり、また、途中から加速膨張に転じたと考えた方が面白いという意見が多いようです。
それでは、こうした加速膨張は、エネルギー保存則に反していないのでしょうか。結論から言うと、保存則を満たすようにエネルギーを定義しているため、エネルギー保存則は常に成り立ちます。
宇宙全体の変化を記述する一般相対論をはじめとして、物理学の基礎的な理論は、いずれも、ハミルトンの原理(最小作用の原理)に従っています。詳しい解説は解析力学の教科書に譲りますが、この原理に従う物理理論では、連続的な対称性が存在すると、それに対応して保存則が存在することが知られています。特に、時間の原点を変えても物理法則が変わらない(時間は一様である)という対称性から導かれる保存則が、エネルギー保存則と呼ばれ、この保存則が成り立つように、エネルギーという量が定義されます。このほか、空間の一様性から導かれるのが、運動量の保存則です。ちなみに、質量の保存は対称性からは導かれません。質量保存則は厳密には成り立っておらず、質量エネルギーmc
2 を含めた全エネルギーの保存則の中に組み込まれます。
ニュートンの重力理論では、2つの質点は互いに引力を及ぼしあうため、重力だけが作用している場合、それぞれの速度は、2質点が近づくと大きく、遠ざかると小さくなります。この運動エネルギーの変化を相殺するように、質点が近づくと小さく、遠ざかると大きくなる重力エネルギー U = -GmM/r を考え、全力学的エネルギーを運動エネルギーとポテンシャル・エネルギーの和として定義すれば、エネルギー保存則が満たされます。加速膨張する宇宙では、空間それ自体が負のエネルギーを持っており、膨張して体積が増せば増すほど空間全体のエネルギーが小さくなる(負で絶対値が大きくなる)ため、これを相殺するように、物質の運動エネルギーが増えていくのです。ちなみに、減速膨張から加速膨張に転じるのは、途中で空間の状態が変わってエネルギーが負になるためですが、このとき放出される余分なエネルギー(相転移の潜熱に相当するもの)は、物質の運動エネルギーになるとも、新たな質量エネルギーになるとも考えられます。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
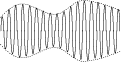 長い間、波長の長い音波で細いビームを作ることは技術的に困難だと考えられていましたが、1975年にテキサス大学の研究者によって新しい方法が開発されました。これは、それ以前に利用されていた水中音波探知機の技術を空気中を伝わる音波に応用したもので、具体的には、超音波を搬送波として可聴波を送るというものです。
長い間、波長の長い音波で細いビームを作ることは技術的に困難だと考えられていましたが、1975年にテキサス大学の研究者によって新しい方法が開発されました。これは、それ以前に利用されていた水中音波探知機の技術を空気中を伝わる音波に応用したもので、具体的には、超音波を搬送波として可聴波を送るというものです。