
渦巻き銀河における恒星の公転速度は、中心核の近傍では中心からの距離とともに大きくなり、外縁部になると一定値に近づく傾向が見いだされています。銀河の腕を構成している星には、回転に遅れて脱落していくものと、前方でゆっくりしていたために飲み込まれていくものとがあり、全体としてみると、渦巻きの形が崩れないでいるのです。必ずしも角速度一定で運動しているわけではありません。
太陽系の場合、惑星は太陽からの重力の圧倒的な影響の下で運動しています。半径r、速度vの円運動と仮定すると、遠心力 mv
2/r と太陽からの重力 GmM/r
2 が等しいという条件から、回転速度vは、太陽から遠ざかるほど距離の平方根に反比例して小さくなることがわかります。これに対して、銀河の場合、各恒星は公転軌道の内側にある全ての天体からの重力を受ける──球対称からのずれが大きい場合はそれ以外の天体の重力も影響を及ぼします──ため、中心からの距離に対する速度の値は、惑星の場合ほど速やかに減ることはありません。しかし、目に見える恒星からの重力を全て足し併せても、観測されている速度−距離関係を説明することはできず、かつては天文学における最大の謎の1つと言われてきました。
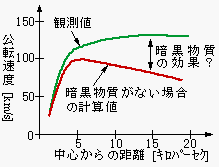
現在、主流となっているのは、観測可能な恒星や星間ガス以外にも、暗黒物質(ダークマター)と呼ばれる見えない物質が大量に存在しているという学説です。暗黒物質による重力が銀河の中心に引っ張る力を生み出しており、それと釣り合う大きな遠心力を得るために、恒星や星間ガスの分布から予想されるよりも回転速度が大きくなるわけです。例えば、NGC2403という銀河の場合、速度−距離関係の観測値と(目に見える天体だけが存在するとしたときの)計算値の間には図のようなズレがあり、これを説明するために、多くの天文学者は、中心から離れた領域では観測されない暗黒物質の方が大量にあると仮定しています。
ただし、「暗黒物質仮説」とは異なる学説を主張している物理学者も少数ながらいます。例えば、ミルグロムは、加速度が力に比例するというニュートンの運動方程式を変更すべきだと考えており、加速度が小さい範囲では小さな力しか必要ないとする修正ニュートン力学によって、各銀河に見られる速度−距離関係を“見事に”説明しています。
【Q&A目次に戻る】

それほど厳密さが要求されない範囲では、全反射の際に位相の変化はないと仮定してかまいません。しかし、正確に言うと、臨界角に達しない通常の反射では位相の変化がゼロかπであるのに対して、全反射の場合は、連続的な変化を示すことが知られています。
マクスウェル方程式をきちんと解くとわかるように、境界面で完全に光が反射されるわけではなく、わずかにクラッド内部に進入します。この進入波(エバネッセント波)は、境界面から離れると急速に(指数関数的に)減衰しますが、ファイバの軸方向にほんの少しだけエネルギーの流れを持っており、その結果として、全反射の反射点が進行方向に少しシフトすることになります。これを、発見者の名前を取って、グース・ヘンヒェン・シフトと呼びます。グース・ヘンヒェン・シフトの効果は、式の上では、反射の際の位相のずれφとして現れます。φの導き方は、大学院レベルの電磁気学の参考書に載っていますが、ここでは、電場が入射面に垂直な場合の結果だけを記しておきます。
tan(φ/2) = - (n
12cos
2θ - n
22)
1/2/n
1 sinθ
光ファイバ内部の位相には、2つの考え方があります。1つは、境界面で反射を繰り返している個々の光線に沿って見たときの位相で、角振動数ω、角波数k=ω/c、光が進む距離L を使って ωt-kn
1L と表されるもの、もう1つは、多数の光線の干渉によって軸方向には進行波、直交する方向には定常波になると仮定し、電磁場F(= E,Hの各成分)の座標依存性を、
F(x,y,z,t) = F(x,y) exp i(ωt-βz)
と表したときの ωt-βz です(座標の取り方は上図参照)。z方向の位相速度が一致しなければならないことから、
kn
1 cosθ = β
となります。また、モードを決定する条件としてy方向に定常波を作る条件が要請されます。図のP点からQ点まで進む間に、光線に沿った位相の変化は、2回の全反射におけるグース・ヘンヒェン・シフトの効果2φを考慮して、
Φ
1 = 4kn
1a/sinθ + 2φ
で与えられます。一方、z方向の進行波の位相は、
Φ
2 = 4aβ/tanθ
だけ変化します。y方向に定常波ができる条件は、Φ
1とΦ
2の差が2πの整数倍になることなので、
4kn
1a/sinθ + 2φ - 4aβ/tanθ = 2nπ (nは整数)
と表されます。これらの式を組み合わせれば、nの値によって定まる各モードでの反射の角度θと位相定数βが求められます。
干渉計では、スプリットした光線の光路長が重要になります。マルチモードのファイバでは、θの異なる複数の光線が混在することになり、ジグザグに進んだときの光路長に差が生じてしまうので、各モードをきちんと分離しなければ、干渉実験が行えません。このため、干渉計には、通常、シングルモードの光ファイバが利用されます。
【参考文献】大越孝敬ほか著『光ファイバ』(オーム社)
【Q&A目次に戻る】

レーダーに探知されるのを避けるには、次の3つの方法があります。
- 吸収:レーダー波を吸収する電波吸収材を表面に塗布する。
- 散乱:レーダー波を入射方向とは異なる方向に散乱する。
- 相殺:反射されるレーダー波を逆位相の波で相殺する。技術的に難しい。
ステルス戦闘機は、主に、機体の形状を工夫してレーダー波を散乱することによってステルス性を獲得しており、補助的に電波吸収材を用いていると言われています。電波吸収材としては、フェライト(酸化鉄を主成分とした磁性酸化物)がよく知られていますが、ステルス戦闘機には、有機複合材を利用した特殊なレーダー波吸収材が用いられているようです(詳しくはわかりません)。
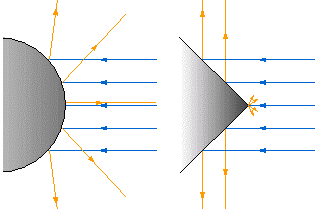
写真を見たことがある人はご存じだと思いますが、ステルス戦闘機は、丸みを帯びた部分が少なく、折り紙で作ったような平面的な機体が特徴になっています。ロッキードF-117の場合、機体は18の平面的な区画から成っており、大きな面の向きは4つに限られているそうです。一定の方向から入射するレーダー波が反射の法則に従って反射される場合、丸い機体からはさまざまな方向に反射されるのに対して、F-117では、4方向にだけ強い反射波が生じ、それ以外の向きにはあまり反射されなくなります(右図)。レーダーで監視していても、機体がたまたま反射面を基地に向けたとき以外は、反射波が返って来ないために探知できないのです(思い切り単純化した説明なので、全面的に真に受けないで下さい)。
ただし、ステルス戦闘機の機体は、航空力学的にはかなり無理のある形状になっており、飛行性能も他の戦闘機に比べて劣っています(F-117の最高速度はマッハ0.9と旅客機並です)。ノースロップB-2に至っては垂直尾翼すらなく、いかにも安定性が悪そうで、コンピュータで制御しなければ安全に飛ぶことはできそうもありません。戦闘機と言うよりは、探知されずに目的地に赴き、爆弾を落としてすぐに帰投する爆撃機と考えるべきでしょう。
【参考文献】D. C. Schleher : "Electronic Warfare in the Information Age" (Artech House)
【Q&A目次に戻る】

粉体の統計力学は、1990年代から研究が盛んになってきましたが、まだ完成にはほど遠い状態です。主に研究されているのは、重力などの外力が作用していない空間内で、浮遊している粉体の粒子が互いに合体することなく衝突を繰り返しているという「粉体ガス」です。一見すると、気体分子運動論と同じように理論が構築できそうですが、実際には、さまざまな障害があって、理論的な扱いは格段に難しくなっています。
障害の1つは、はねかえり係数が衝突の相対速度に依存して変化するという点です。高校物理では、はねかえり係数は一定の値になると仮定されていますが、非弾性衝突をする物体を用いて実験すると、相対速度が大きくなるにつれて、はねかえり係数が小さくなる傾向が見られます。場合によっては、斜め衝突する際に粒子の回転エネルギーが並進エネルギーに転化され、はねかえり係数が1より大きくなることもあります。はねかえり係数eの速度依存性は、簡単なケースに限って理論的に求められます。2つの球体が接触して変形した後、粘性が作用しながらゆっくりと元に戻るという仮定の下で計算すると、
e 〜 1 - const.×v
0.2
となります。また、接触面での圧力が一定の臨界圧力を越えたときに、衝突のエネルギーがある割合で塑性変形に使われると仮定しても、はねかえり係数と速度の関係が求められます。しかし、必ずしも一般的に成り立つ関係式ではありません。
「はねかえり係数eは相対速度に依存せずに一定である」というかなり粗っぽい近似を用いたとしても、なお障害は残ります。衝突の過程で、
|ΔE| = (1-e
2)mv
2/4 (v : 相対速度の共通法線成分)
だけ運動エネルギーを失うため、気体分子運動論と同様に粒子の運動エネルギーの分布を元に粉体ガスの温度Tを定義すると、Tが時間とともに減少していくことになり、「部分系の温度が等しい平衡状態に漸近する」という描像が成り立ちません。このため、平衡状態(マクスウェル分布)を基準に摂動論展開を行うという気体分子運動論の手法が使えず、計算がきわめて難しくなります。温度でリスケールする(例えば、速度vをv'=v/T
0.5で置き換える)ことによって、温度が低下しても関数形が一定に保たれるような基準分布関数を用いることもできますが、計算の厄介さは変わりありません。また、速度分布関数fを使って、
H = ∫dv f ln f
のように定義したH関数は、気体分子運動論とは異なり、単調減少にはなりません。粒子の内部状態まで考慮しなければ、エントロピー増大の法則は成り立たないのです。
粉体ガスが時間とともにどのように変化するかを理論的に予測することは難しく、コンピュータ・シミュレーションに頼らざるを得ません。それによると、粉体ガスは通常の気体のように一様な状態にはならず、粒子がフィラメント状の領域に集まった空間構造を形成する性質があるようです。
【参考文献】早川尚男著『散逸粒子系の力学』(岩波書店)
【Q&A目次に戻る】

航空力学の観点からすると、巨大な「空飛ぶ円盤」は、人間や貨物を運ぶ飛行物体としてはありそうもないものです。
通常の航空機は、ジェットなどの推進力によって前進する際に、主翼の上面と下面で気流の速さに差を生じさせることによって、機体を持ち上げる力(揚力)を作り出しています。空気抵抗に対する揚力の最大値は翼の形状によって決まり、大ざっぱに言って、(翼長)
2/(翼面積) の値が大きい方が、効率的に揚力が発生します。この値は、最も高性能なグライダーでは40程度、揚力が小さくてもかまわない戦闘機でも5近くになります。ところが、直径Rの円盤では、
R
2/π(R/2)
2 = 4/π = 1.27…
と小さく、翼としての能力はあまり大したものではありません。フリスビーのようなスポーツ用の円盤は、軽い素材で作られているために、かなり長い飛距離を出すことができますが、人間が搭乗可能な乗り物とするにはあまりに効率が悪く、実用化しようと考える技術者はまずいないでしょう。
もう1つの問題は、機体の安定性をいかに保つかです。航空機には、何らかの外力が作用して機首が下がったときに、水平尾翼に下向きの力が発生して再び機首を持ち上げ平衡状態を保つという安定性が備わっていますが、ただの円盤にはそうした作用がなく、機体が傾き始めると、そのまま傾きを増して墜落してしまいます。こうした難点を克服するほとんど唯一の方法は、円盤を高速回転させることです。そうすれば、角運動量の保存則によって機体が不安定に傾くことを防げます(コマのような歳差運動が生じることがあります)。しかし、機体全体が回転していると人間は目が回って乗っていられませんし、内側のコックピットだけ静止させようとすると、機構が複雑になる上に、角運動量が小さくなって安定化の効果が相殺されてしまいます。また、重心と揚力の中心が一致しないために生じるモーメントは、円盤が回転している結果として進行方向に対して横向きに押すような作用となり、まっすぐ進まずにフリスビーのように自然とカーブしてしまうはずです。
こうしたことから、円盤状の飛行体が実用的な乗り物になるとは、ちょっと考えられません。まあ、反重力光線のように、全ての物理学者がひっくり返るような超科学的現象があれば話は別ですが…。
【Q&A目次に戻る】

私は心理学の専門家ではないので、あまり本格的な議論はできませんが、人間にとっての記憶が、生き残るための手段としてストラテジック(戦略的)に利用されていることは指摘して良いでしょう。何かを体験した際、入力された(視覚や聴覚などの)感覚データがそのまま記憶されるのではなく、いったん特徴分析が施され、それ以前の学習記憶との比較に基づいて整理・統合されています。したがって、映画のフィルムになぞらえられるような完全にニュートラルな記憶というものは存在しません。多かれ少なかれ意味づけされ、行動のプラニングの際に参考になるものとして想起されます。最も基本的な記憶のタイプは、身体に危険が迫った体験に関するもので、恐ろしい出来事として記憶され、類似した状況に置かれたときにフラッシュバックとして蘇り、行動を規制します。しかし、大半の記憶は、それほど明確に意味づけされておらず、行動への影響も間接的なものです。
体験された内容がどのような形で整理・統合されるかは、身体的な快・不快と直接的に結びつく場合を除くと、遺伝的に規定されているわけではないでしょう。社会的な生活を送る上でのストラテジーは、幼少期のさまざまな体験を通じて後天的に形成されるものだと考えられます。思うに、過去への郷愁とは、比較的幸福な幼少〜青年期を送った人が、その状況を望ましい理想型として記憶に取り込んだことに起因するものではないでしょうか。さらに、現実の状況が理想型から乖離している場合、形の上で不足分を補おうとして、完璧なコレクションへのこだわりが生まれるのかもしれません。ただし、この辺りのことは、学問的にあまり煮詰まっていないようです。
認知機能にどの程度の性差があるかは、心理学的なテストによって調べられています。例えば、同じ文字で始まる単語を列挙するテスト(L なら Love, Lift, Lever, Load などと挙げていく)では女性の方が成績が良く、複雑な図形の中に隠された単純な図形を発見するテストは男性の方が得意だとされており、脳の発生過程における性ホルモンの影響を指摘する説もあります。しかし、フェティシズムのように高度に社会的な性向に関しては、信頼できる実験データは見あたりません。私は、性差があるとしても純粋に文化的なものだと思いますが、明確に主張するだけの根拠がないというのが実状です。
【Q&A目次に戻る】

日常的に使用される巨視的な(目で見えるほど巨大な)磁石は、全て原子から形作られています。原子の中心部には正電荷を帯びた原子核が、その周囲には負電荷を帯びた複数の電子が存在しており、全体として見ると電気的に中性なので、摩擦などによって電子を移動させない限り、2つの物体がはっきりと観測できるような電気的な引力や斥力を及ぼしあうことはありません。しかし、原子の大きさと同程度の距離まで近づけると、原子核や電子の電荷による電気的な相互作用が顕著になってきます。巨視的な観点から見たときの「接触力」は、こうした電気的な相互作用です。2つの物体を完全に接触させようとしても、原子核の正電荷による斥力が強く作用し、原子のスケールで見てぴったりとくっつけることはできません。電気は磁気よりもはるかに強い力を及ぼすので、磁気的な相互作用で2つの磁石がくっついているように見えても、原子のサイズよりは離れた地点に留まっているのです。
それでは、原子サイズ以下の微視的な磁石ではどうなるでしょうか。例えば、電子やクォークのような素粒子は、それ自体が小さな磁石であることが知られています。N極/S極だけの単磁極ではないためクーロンの法則ではありませんが、こうした2つの素粒子が接触するまで近づいたときの相互作用は、磁気にせよ電気にせよ無限大になりそうです。実は、現在の標準的な物理学では、この問題に答えることはできません。2つの素粒子が接近していった場合、力の強さがどこまでも強くなるのではなく、何らかの理由で有限にとどまると考えられていますが、具体的な理論は未完成です。今の物理学に可能なのは、素粒子同士を現在の装置で可能なぎりぎりのところまで近づけたときに何が起きるかを(「くりこみ」と呼ばれる計算テクニックを使って)予測することであり、接触寸前まで近づけたときに何が起きるかはわからないというのが実状です。
【Q&A目次に戻る】

現在、潜水艦の最高速度は時速140km程度、最速の魚と言われるマグロの場合、身に危険を感じたときに最大で時速160kmほど出すという説もあります(正確な数字はわかりません)。しかし、摩擦抵抗が空気の1000倍も大きい水中では、当然ながら、空気中ほど速く動くことは困難です。私自身、水中の音速(時速5400km)はもちろん、空気中の音速(時速1200km)を越えて水中を自力航行する構造体を作ることは技術的に不可能だと思っていました。ところが、少し前の日経サイエンスに、スーパーキャビテーションの技術を応用すると、水中を時速数百km以上、場合によっては、時速5400kmを越えて超音速で移動する魚雷やミサイルを製造できるという論文が掲載され、驚かされました。それによると、ロシア海軍は、すでに最高時速370kmの高速魚雷「シェクバル」を実戦配備しており、フランスや中国もロシアから購入したとされています。さらに、大型水中ミサイル、小型水上艦、高速潜水艦の開発も計画されているようです。
スーパーキャビテーション技術とは、物体を低密度の気泡で包んだような状態にして、摩擦抵抗を小さくする技術です。水中を物体が動く場合、流速が速い領域で部分的に水圧が蒸気圧以下になって水が水蒸気へと相変化する「キャビテーション」が起きることは良く知られていますが、気泡が壊れるときの衝撃波によって物体が損傷するために、多くの技術者は厄介者扱いしてきました。しかし、キャビテーションをうまく制御すると、単一の巨大気泡(スーパーキャビティ)が生じ、移動する物体を完全に包み込んで摩擦抵抗を大幅に低減することも可能になります。1960年代から、潜水艦や魚雷に応用する方法が研究されてきました。ロシア製高速魚雷シェクバルは、先端部に周縁を鋭くした円盤状のキャビテーターが取り付けられており、そこから魚雷全体を包む滑らかなスーパーキャビティが発生するとのことです。
スーパーキャビテーション技術は、主に兵器に応用されているせいか、詳しい技術情報は得られませんでした。核弾頭を搭載したスーパーキャビテーション魚雷が配備されると西側の防衛網は無力化されるという話もあり、かなり物騒です。
【参考文献】S.アシュレー「謎の新兵器 超音速魚雷」(日経サイエンス 2001年8月号 p.44)
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
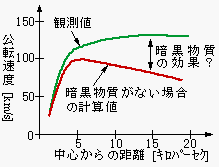 現在、主流となっているのは、観測可能な恒星や星間ガス以外にも、暗黒物質(ダークマター)と呼ばれる見えない物質が大量に存在しているという学説です。暗黒物質による重力が銀河の中心に引っ張る力を生み出しており、それと釣り合う大きな遠心力を得るために、恒星や星間ガスの分布から予想されるよりも回転速度が大きくなるわけです。例えば、NGC2403という銀河の場合、速度−距離関係の観測値と(目に見える天体だけが存在するとしたときの)計算値の間には図のようなズレがあり、これを説明するために、多くの天文学者は、中心から離れた領域では観測されない暗黒物質の方が大量にあると仮定しています。
現在、主流となっているのは、観測可能な恒星や星間ガス以外にも、暗黒物質(ダークマター)と呼ばれる見えない物質が大量に存在しているという学説です。暗黒物質による重力が銀河の中心に引っ張る力を生み出しており、それと釣り合う大きな遠心力を得るために、恒星や星間ガスの分布から予想されるよりも回転速度が大きくなるわけです。例えば、NGC2403という銀河の場合、速度−距離関係の観測値と(目に見える天体だけが存在するとしたときの)計算値の間には図のようなズレがあり、これを説明するために、多くの天文学者は、中心から離れた領域では観測されない暗黒物質の方が大量にあると仮定しています。
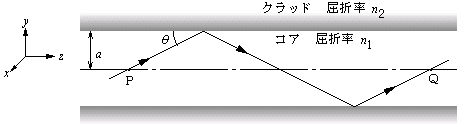
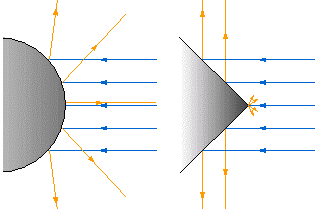 写真を見たことがある人はご存じだと思いますが、ステルス戦闘機は、丸みを帯びた部分が少なく、折り紙で作ったような平面的な機体が特徴になっています。ロッキードF-117の場合、機体は18の平面的な区画から成っており、大きな面の向きは4つに限られているそうです。一定の方向から入射するレーダー波が反射の法則に従って反射される場合、丸い機体からはさまざまな方向に反射されるのに対して、F-117では、4方向にだけ強い反射波が生じ、それ以外の向きにはあまり反射されなくなります(右図)。レーダーで監視していても、機体がたまたま反射面を基地に向けたとき以外は、反射波が返って来ないために探知できないのです(思い切り単純化した説明なので、全面的に真に受けないで下さい)。
写真を見たことがある人はご存じだと思いますが、ステルス戦闘機は、丸みを帯びた部分が少なく、折り紙で作ったような平面的な機体が特徴になっています。ロッキードF-117の場合、機体は18の平面的な区画から成っており、大きな面の向きは4つに限られているそうです。一定の方向から入射するレーダー波が反射の法則に従って反射される場合、丸い機体からはさまざまな方向に反射されるのに対して、F-117では、4方向にだけ強い反射波が生じ、それ以外の向きにはあまり反射されなくなります(右図)。レーダーで監視していても、機体がたまたま反射面を基地に向けたとき以外は、反射波が返って来ないために探知できないのです(思い切り単純化した説明なので、全面的に真に受けないで下さい)。