
回転している台の上では、まっすぐ進もうとしても台が回っているために進行方向が曲げられてしまいますが、この効果をもたらす「見かけの力」がコリオリの力です。地球のように、回転していることが実感されない場合には、物体の運動を説明するのに役に立つ概念です。コリオリの力は、台が回転する角速度をベクトル表記で
ω(向きは右ねじの法則による)、運動する物体(質量m)の速度をvとすると、
-2m
ω×v
で与えられます(
×はベクトル積を表す)。緯度φの地点で流体に働く単位質量あたりの力(水平方向のさまざまな流れの向きについて平均する)は、2ωv sinφ となります。
ω = 2π/(24×60×60[s])
を使って東京(緯度φ=35°)でのコリオリの力を計算すると、
v×8.3×10
-5
となり、流速が秒速1m程度のときは、重力に比べて10万分の1程度の弱い力にしかなりません。大気の流れのように、流体が充分に長い距離を運動する場合には、微弱な力であっても少しずつ向きが曲げられて、最終的には巨大な渦巻きが形成されますが、洗面台の排水口程度の大きさでは、コリオリの力による転向作用はほとんど現れないと言って良いでしょう。排水口で見られる渦巻きの向きは、シンクの形状などに依存するものであって、北半球では反時計回りになるというものではありません(ちなみに、我が家の洗面台は歪んでいるせいか、いつも時計回りの渦ができます)。
【Q&A目次に戻る】

重力の伝播速度が光速に等しいという結論は、一般相対論の運動方程式から導かれたもので、単なる類推ではありません。
ニュートンの重力理論では、重力源から距離Rの地点での重力は 1/R
2 に比例すると仮定されており、空間を一瞬のうちに伝わる直達力だと見なされていました。これに対して、アインシュタインの一般相対論では、(直観的な言い方をすると)重力は時間・空間のゆがみの現れであり、重力源となる質量が運動すると、時空のゆがみが周囲に伝播していくとされています。具体的なの計算は、かなり難しいので詳細は省略します(一般相対論の教科書を参照してください)が、光速に比べてゆっくり運動している物体が作る弱い重力場の場合、電磁気学におけるリエナール・ヴィーヒェルトのポテンシャルと同じような遅延ポテンシャルの形で表されることが示せます。すなわち、重力場の微小な変動分から作った量をψ
ijと表すと、
ψ
ij = const×∫dV [τ
ij]/R
となります。ただし、τ
ijは物体の運動状態に依存する(エネルギー運動量テンソルから作られる)量、Rは積分される地点から左辺の地点までの空間的な距離、[ ]は被積分項の時刻が左辺の時刻より R/c だけ以前になることを表します。この式は、物体が運動することによる重力場の変動が R/c だけ遅れて伝わることを意味しており、(多くの近似を行っているものの)重力場の伝播速度は光速に等しいと結論できます。
重力場の伝播速度が光速に等しくなるのは、一般相対論が、重力場の弱い極限で特殊相対論と一致するように作られているからです。一般相対論の運動方程式は重力場に関する2階の微分方程式になっていますが、重力場が弱く線形近似が成り立つ場合は、微分演算の側に含まれる重力場をミンコフスキ計量で置き換えて、近似的に、特殊相対論の下で不変な2階微分を作用させる方程式になるはずです。この条件を満たす微分演算は、
∂
x2 - (1/c
2)∂
t2
しかないため、同様の方程式を満たす電磁場と同じように、場の変動が光速で伝播するという結論が出てくるわけです。
なお、宇宙開闢直後のインフレーション期には宇宙が超光速で膨張していたと考えられていますが、これは、重力の伝播速度が光速に等しいことと矛盾しません。空間の膨張は、それぞれの地点に存在するエネルギーによって引き起こされており、どこか別の場所のエネルギーの影響が伝播してきたわけではないからです。
重力が光速で伝播することが観測によって確認されれば、確度の高い一般相対論の検証になります。この観測にはまだ誰も成功していませんが
(*)、現在、超新星爆発の際に放出される重力波を検出するプロジェクトが進行中です。
(*)2002年にアメリカの研究チームが、クェーサーからの光が木星の重力によって曲げられるときのデータを分析し、木星の運動によって周囲の重力場が変化するときの伝播速度が20%の誤差範囲内で光速cと一致すると発表しましたが、その正当性に関しては異論が提出されています。
【Q&A目次に戻る】

地震は、プレートの移動などによって生じた応力に耐えきれなくなり、岩盤が急激に滑ることによって発生するものです。マグマという物理的実体が上昇して起きる火山噴火と異なり、「どこまで耐えられるか」という臨界現象を解明しなければならないため、発生時期の予知はかなり難しいと言えます。また、地震の規模も、1回の巨大地震になるのか、小規模な群発地震で終わるのか、一般にはわかりません。日本では、一部の学者が「東海地震は予知できる」と主張、その見解に基づいて1978年に大規模地震対策特別措置法が施行されましたが、予知の可能性に疑問を投げかける人も多く、2003年には、突発的に発生した場合に備えた東海地震対策大綱が策定されています。
ただし、地震予知が全くできない訳ではありません。数日前に確度の高い予知を行うことは、現在なお困難だと考えられていますが、地震発生を予測するいくつかの方法があります。例えば、過去に起きた地震の規模や間隔に関するデータを集め、地震の発生を確率過程として扱うモデルに当てはめて「今後10年間にマグニチュード6以上の地震が起きる確率は30%」といった長期的な確率予測を行うことは可能であり、すでにいくつかの地域で試みられています。このほか、次のような方法による地震予知が研究されています。
- (1)高精度GPS
- 現在では、高精度GPS観測網によって、mm単位の地殻変動が測定可能となっており、このデータの解析を通じて、さまざまな異常を早期に発見することができます。2001年春頃から浜名湖付近で以前とは異なる動きが検出され、注目を集めましたが、これは、固着していた直下のプレート境界がゆっくりと動く「スロースリップ現象」が起きたためだと解釈されています。スロースリップは東海地震の前兆であるとの見方もあり、動きが加速する傾向が見られないか、観測が続けられています。
- (2)数理モデル
- 近年、地震予知を可能にするかもしれない新しい数理モデルが次々と提出されています。2つのプレートが強く固着している領域はアスペリティと呼ばれ、大地震の直前には、他の部分がゆっくり滑ることによってアスペリティに応力が集中していますが、最新の数理モデルでは、アスペリティの分布がフラクタル的であるとの仮定の下に、小さなアスペリティから少しずつ壊れ始め最終的にプレート境界が滑るまでの過程が数式化されています。このほかにも、微小地震の発生数のゆらぎを臨界現象に関する数学的なモデルに当てはめて、臨界点(地震の発生)を予測する理論もあります。こうした最新モデルの信頼性は必ずしも高くありませんが、改良を加えていけば、役に立つものになる可能性があります。
- (3)電磁的な前兆現象
- 地震学者の間では評判が良くありませんが、地震の直前に発生すると言われる電磁的な異常現象を予知に利用することができるかもしれません。大地震の直前には岩石の微小破壊が進行しており、この過程で電磁放射などの現象が生じると考えられるからです。ただし、これまでのところ、電磁異常が地震の前兆となることを示す信頼に足るデータは得られておらず、地震雲や動物の異常行動が電磁異常に由来するとの見解にも確たる根拠がありません。1996年から5年にわたって理化学研究所が行ったVAN法(地電流の異常から地震を予知する方法でギリシャで実績を上げたと言われる)の研究は、大した成果を上げられないまま打ち切られています。もう少し、地道な研究を続ける必要がありそうです。
【Q&A目次に戻る】

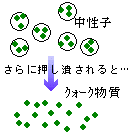
中性子は原子核を構成する粒子の1つですが、物質を構成する最小の単位というわけではありません。クォークと呼ばれる素粒子3個(uクォーク1個、dクォーク2個)が互いに(グルーオンやクォーク−反クォーク対を介して)相互作用しながら10
-15m程度の範囲で結合した状態であり、中性子の塊を押し潰すと、構成要素だったクォークがグチャグチャに入り混じった状態になるはずです。中性子星は大部分が中性子の集まりと言えますが、中心付近の密度は原子核密度よりも高くなっており(10
18kg/m
3以上)、そこでは中性子が潰れてクォークがバラバラになっていると推測されています。また、通常の中性子星よりも低温で高密度な天体が発見されており、星全体がクォーク物質でできている可能性もあります。
構成している物質が何であれ、天体が一定の状態を保っているとき、重力と圧力は安定な釣り合いを実現しています。逆に言えば、この釣り合いが成り立たなくなったときに、重力崩壊のようなカタストロフィが発生します。釣り合い条件を計算するには、物質の種類に応じた状態方程式を立てる必要があり、一般的な性質を論じるのは難しいのですが、構成要素が高温の自由粒子のように振舞う場合には、天体の質量がある限界値(限界質量)を越えると、重力と圧力が釣り合いを保てなくなることが示されます。オッペンハイマーとヴォルコフが1939年に行った計算では、天体が自由中性子のみから構成されているとの仮定の下で、太陽質量の0.7倍を越えると安定な釣り合いが存在しないという結果が導かれました。その後、天体内部の物質状態に関して条件を変更し、さまざまなケースでの限界質量が求められています。圧縮された物質が、物理学者の常識を越える奇妙な振舞いを示さない限り、常に限界質量が存在すると考えてよさそうです。
限界質量以上の質量を持つ天体は、収縮したときの圧力の増加よりも重力の増加の方が大きくなるため、ひとたび収縮を始めると、止め処なく潰れていきます。物質の状態方程式が質的に変化しないと仮定し、一般相対論の方程式(アインシュタイン方程式)と連立させると、この重力崩壊によって物質は有限の時間内に完全に潰れてしまい、あたかも空間に開いた穴のように、物理法則の破綻する“特異点”が残されるという結論が出てきます。しかし、この結論は、おそらく正しくないでしょう。中性子が潰れてクォーク物質となり、さらにクォークも潰れて(現在の物理学では解明できていない)内部構造があらわになり……と進んでいく過程のどこかで、アインシュタイン方程式が成り立たなくなり、全く新しい物理現象が見られるようになるはずです。ただし、この問題に関しては、多くの物理学者が真剣に取り組んでいるものの、まだ明確な答えは得られていません。
【Q&A目次に戻る】

光が入るだけで出てこない瞳孔が黒く見えるのと同じように、可視光線を吸収する網膜も黒く見える──ということはありません。網膜上の光受容体は感度が高く、入射光の一部を吸収するだけで機能するので、網膜自体は、血液の色が透けて赤く見えます。
網膜に存在する視細胞には、一定範囲の波長の光を吸収して立体構造を変えるという特性を持つ光受容タンパク質が存在しています。例えば、色の識別を行う錐体細胞には、アミノ酸配列がわずかに異なる3種類のタンパク質(ヨードプシン)があり、それぞれ青・緑・赤の光を吸収します。これらのタンパク質が光を吸収し構造変化を起こすことが引き金となって、一連の生化学反応が生じ、最終的に視神経の興奮となって脳にシグナルが伝達されるのです。
水晶体で光線が屈折したり、網膜上の視細胞で光が吸収されたりしても、外部から見る限りあまり目立たないので、透明人間は“ほぼ透明”(眼球がうっすらと浮かんでいるだけ)でいられるはずです。しかし、瞳孔以外から網膜に入射する光を遮る方法がないため、やはり透明人間は目が見えないでしょう。
【Q&A目次に戻る】

現在の日本では、大学受験など将来に備えて高校生のときに文系・理系にコース分けされますが、多くの学生が、自分の適性を正しく把握できておらず、将来に悔いを残すことも少なくありません。高校で進路を決める際に重視されるのが数学の成績であり、数学が苦手な人は文系、得意な人は理系と割り振られる傾向にあります。しかし、文系であっても、経済学では確率微分方程式のような高等数学が用いられますし、生物学のようにあまり数式を用いない理系科目もあります。数学の得手不得手は、必ずしも文系・理系の適性を決定するわけではありません。
私の考えでは、文系と理系を隔てる最も大きな差異は、世界中に緊密に張り巡らされたロジックのネットワークを実感できるかどうかだと思います。理系で扱う対象は、通常、異なる地平からのアプローチが可能であり、複数の学問の間でデータの交換が行われています。例えば、ある動物が摂取した食物がどのように代謝されるかを考える場合、動物行動学から量子化学に至るさまざまな研究方法があり、特定の分子構造が環境への適応度を左右する因子として棲み分け理論に援用されたりします。このように、複数の学問の相互乗り入れが可能になっているのは、自然のあらゆる現象が、孤立して自存することなく、法則によって互いに深く関連しているからです。理系の学者は、学問的方法論を駆使して、さまざまな方向から法則というロジックの網目を辿っていくことにより、自然の謎を解き明かそうとしているのです。
これに対して、文系の学問では、学問の相互乗り入れはあまりないように見受けられます。もちろん、マクロ経済学の研究に、経済行為の担い手である投資家や消費者に関する心理学的な分析が盛り込まれるといったケースもあるでしょうが、一般に、ある研究対象に関して1つのジャンルが成立していると言えそうです。文系の対象も自然現象の一部なので、根底にはロジックのネットワークがあるはずですが、人間が介在することによって法則性が見えにくくなっているため、どうしても(景気動向のような)対象の性質を抽象的に表す概念を用いざるを得ません。こうして、ジャンルごとに独自の学問的概念が多用されるようになり、ますます、学問間の交流は困難になっていきます。
理系的な発想の1つに、「わからなくなったときには先に進め」というのがあります。実際、勉強している途中で難しくてわかりにくい箇所に出会ったときには、そこでいつまでも悩んでいないで、先のページに進む方が、結果的に早く理解できることが少なくありません。これは、ロジックのネットワークをある方向から辿って行き詰まったとしても、常に別の方向からのアプローチが可能であり、先のページにその説明が記されていることがあるためです。方程式を見ただけではわからないことも、具体的な応用例で示されれば腑に落ちるというものです。このほか、「空白はロジックで埋められる」というのもあります。私自身、論文を読む際には、前半の1/3程度にしか目を通さない場合が多く、各段落の最初の文章だけを飛び飛びに読んでいくこともあります。データの種類と方法論さえわかっていれば、内容が予想できるからです。一般的に言って、理系の人間は理詰めでものを考えますが、1つの信念に従って直線的に思考するのではなく、さまざまな方向から理詰めのアプローチを試みる特性があるようです。
おそらく、文系の人間には、「ロジックで空白を埋める」という発想は皆無でしょう。ロジックの重要性は認めるにしても、一歩一歩着実に学説を組み上げていく際に用いるものであって、多面的・多層的にロジックを使い回すことはないはずです。ロジックで埋められない部分は、全体を見渡す総合的な視座から説明を加えていくのが、文系的なやり方と言えるでしょう。
こうした意見は、私が理系人間だけにかなり偏っているかもしれませんが、一つの見方として受け取ってください
(もっとも、私は、高校のときに担任をはじめ何人かの教師から文系進学を強く勧められた“なんちゃって理系人間”ですが…)。
【Q&A目次に戻る】

熱力学の理論が完成される19世紀中庸以前には、温度計を利用した経験的な温度概念が利用されていました。しかし、このやり方では、熱膨張率が(絶対)温度に依存して変化するので、温度計に封入する物質の種類によって、温度の定義が異なることになってしまいます(気体温度計の場合は、理想気体からのずれがあると、絶対的な温度が定義できません)。物質の種類によらない「絶対温度」を定義するためには、カルノーによる熱機関の理論が必要です。
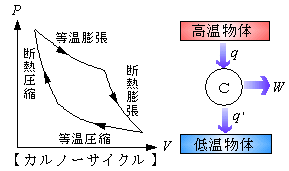
カルノーは、熱機関が動作するためには、高温の炉だけではなく低温の冷却器が必要であること、すなわち、高温物体から低温物体への熱の流れによって仕事が行われることを、正しく認識した最初の科学者でした。この考えに基づいて、彼が理論的に証明したのが、いわゆる「カルノーの定理」です。この定理は、「熱は高温物体から低温物体へと流れる」という(一見自明な)前提の下で、「熱機関の熱効率は可逆的なサイクルのときに最大になる」ことを主張するもので、熱力学が経験科学から理論科学へと発展する第一歩となりました(ただし、カルノーは熱量の保存則を仮定するなどいくつかの点で誤っており、後に、クラウジウスによって修正されます)。
気体を作業物質とする理想機関は、次の一連のプロセスを経て最初の状態に戻る「カルノー・サイクル」によって実現されます。
- 気体を高温の炉と接触させて、準静的に等温膨張させる。この過程で、熱量qを吸収する。
- 気体を熱源から切り離して、準静的に断熱膨張させる。
- 気体を低温の冷却器と接触させて、準静的に等温圧縮させる。この過程で、熱量q'を放出する。
- 気体を熱源から切り離して、準静的に断熱圧縮させる。
この一連の過程を通じて、気体は、膨張するときには外部に対して仕事をし、圧縮されるときには外部から仕事をされますが、これらを併せた1サイクルでの正味の仕事をWとします(熱力学第1法則によれば、 W=q-q' になります)。熱効率ηは、吸収した熱に対する仕事量、すなわち、η=W/q で定義されます。
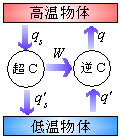
カルノー・サイクルで熱効率が最大になることは、次のようにして証明されます。カルノー・サイクルでは、全ての過程が準静的に行われているので、各過程を完全に逆転させた逆カルノー・サイクルも、実現可能です。仮に、カルノー・サイクルよりも効率が高く、qよりも少ない熱量q
sを高温の炉から吸収して仕事Wを行う熱機関(超カルノー・サイクル)が存在したとします。この熱機関によって逆カルノー・サイクルを動かすことを考えましょう。1サイクルの動作を終えるまでに、正味 q-q
sの熱量が冷却器から炉に流れていますが、2つの熱機関は最初の状態に戻っており、外部との間に仕事のやりとりも行われていません。従って、他に何の変化がないにもかかわらず、熱が低温物体から高温物体に流れたことになり、前提と矛盾します。作業物質が何であるかによらず、可逆なサイクルが理論的に最大の熱効率を与えるという結論になります。
「熱が低温物体から高温物体にひとりでに流れることはない」という性質は、クラウジウスによって、「熱も仕事も無から生じない」という原理(熱力学第1法則)と同程度に重要な原理(熱力学第2法則)として、熱力学理論の根幹に据えられました。クラウジウスは、後にエントロピーという量を導入し、第2法則を「不可逆変化ではエントロピーが増大する」という形で数学的に定式化しています。
現在の高校物理の知識を使うと、理想気体を作業物質とするカルノー・サイクルの熱効率を計算することができます。計算過程は省略しますが、高温物体の温度をT、低温物体の温度をT-ΔTとすると、熱効率として、
ΔW/q = ΔT/T
が得られます(ΔTが無限小になる場合を考慮して、仕事量をΔWと表しました)。ところが、この熱効率は、作業物質が理想気体であるか否かにかかわらず、可逆的なサイクルでは常に同じ値になるはずです。従って、「理想的な熱機関が熱量qを吸収して行う仕事」を使えば、作業物質の物性に依存する経験温度ではなく、絶対的な温度が定義されます(温度差が無限小の場合、上の式の右辺は d(lnT) になるので、簡単に積分できます)。こうした絶対温度の定義は、1848年にケルヴィン卿によって示されました。この定義は、統計力学によって温度概念が抜本的に変更されるまで、熱力学で重要な役割を果たします。
【参考文献】山本義隆著『熱学思想の史的展開』(現代数学社) 名著です!
【Q&A目次に戻る】

波とは、波動方程式に従って振動が伝播していく現象です。通常の波動方程式は、時間を反転させても式の形が変わらないため、関数f(t) が方程式の解になっているならば、f(-t) も同じく解になります。例えば、x軸のプラスの向きに進む正弦波:
A sin (kx-ωt)
が方程式を満たしているならば、マイナスの向きに進む
A sin (kx+ωt)
も、やはり方程式を満たす解関数となります。この2つの波は、互いに時間を反転したプロセスになっているので、見ようによっては、一方が未来に進む(遅延)波、他方が過去に進む(先進)波とも言えます。しかし、そうした解釈は、物理的に見てあまり意味がありません。
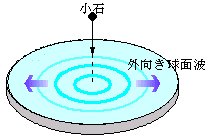
先進波と遅延波を積極的に区別しなければならないのは、波と物体が相互作用しているとき、系のセットアップによって一方の解だけが実現されるようなケースです。例えば、水面に小さな石を落としたときに生じる波を考えてみましょう。このとき、石が落ちた地点から球面状に外向きに拡がっていく波が生じますが、波動方程式の性質から、これを時間反転した内向きに収縮してくる波も、また方程式を満たすはずです。しかし、現実に内向きの球面波が生じることはありません。「水面の1点に小さな石が落ちる」という原因によって生まれる波は、因果律によって、常に原因よりも時間的に遅れて伝播していくからです。内向き球面波が生じるのは、巨大な円柱状の波動発生装置を用意し、同じ位相の内向きの波を人為的に作り出すようなきわめて特殊な場合に限られます。
このように、互いに時間反転の関係にある2つの解のうち、「原因よりも時間的に遅れた解(遅延波)」だけを採用し、もう一方の解(先進波)は捨てなければならないという事例は、波と物体の相互作用を扱うさまざまな分野で見られます。良く知られているのが、加速された電荷による電磁放射のケースで、ある地点で観測される電磁波は、光速で伝播するのに要した時間だけ遡った時刻に放射された遅延波になっています。
ここで注意したいのは、先進波を捨てて遅延波だけを採用するのは、“過去に戻る波など存在しない”からではなく、遅延波を使う方が実用的だからです。われわれが物理学を応用して計算しなければならない現象の多くは、過去の方が単純な設定になっており、この設定を「原因」と見なして未来の状態を求めようとすると、遅延波が必要になるのです。上で述べた「石を落としたときの外向き球面波」の場合でも、「石の落下」を出発点として計算を始めたために、遅延波だけを使うことになったのです。逆に、「波が遠方でどのような状態になったか」が完全に観測されており、これを計算の出発点とする場合は、「遠方の状態」を微分方程式を解く際の境界条件として、先進解を求めなければなりません。ただし、遠方で観測される状態と合致するような先進波は、あくまで外向きの球面波であり、過去・未来いずれを出発点にするにせよ、内向き球面波が現実的な解になることはありません。
場合によっては、遅延波・先進波を一緒くたにして計算することもあります。例えば、素粒子同士の相互作用では、まず粒子Aが電磁波(光子)を放射し、その後に粒子Bに吸収される過程と、逆に、Bが電磁波を放射してAに吸収される過程とを、区別することができません。どちらが先に放射したかわかるならば、それを出発点として遅延波を使って計算すれば良いのですが、時間の先後関係がはっきりしないので、便宜的に遅延波と先進波を併せた関数(伝播関数)を使い、粒子Aと粒子Bの間を遅延波とも先進波とも特定されない電磁波が伝播したものとして計算しています。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
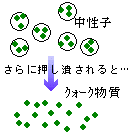 中性子は原子核を構成する粒子の1つですが、物質を構成する最小の単位というわけではありません。クォークと呼ばれる素粒子3個(uクォーク1個、dクォーク2個)が互いに(グルーオンやクォーク−反クォーク対を介して)相互作用しながら10-15m程度の範囲で結合した状態であり、中性子の塊を押し潰すと、構成要素だったクォークがグチャグチャに入り混じった状態になるはずです。中性子星は大部分が中性子の集まりと言えますが、中心付近の密度は原子核密度よりも高くなっており(1018kg/m3以上)、そこでは中性子が潰れてクォークがバラバラになっていると推測されています。また、通常の中性子星よりも低温で高密度な天体が発見されており、星全体がクォーク物質でできている可能性もあります。
中性子は原子核を構成する粒子の1つですが、物質を構成する最小の単位というわけではありません。クォークと呼ばれる素粒子3個(uクォーク1個、dクォーク2個)が互いに(グルーオンやクォーク−反クォーク対を介して)相互作用しながら10-15m程度の範囲で結合した状態であり、中性子の塊を押し潰すと、構成要素だったクォークがグチャグチャに入り混じった状態になるはずです。中性子星は大部分が中性子の集まりと言えますが、中心付近の密度は原子核密度よりも高くなっており(1018kg/m3以上)、そこでは中性子が潰れてクォークがバラバラになっていると推測されています。また、通常の中性子星よりも低温で高密度な天体が発見されており、星全体がクォーク物質でできている可能性もあります。
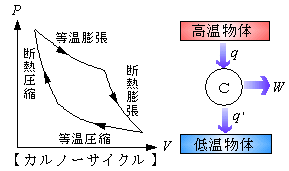 カルノーは、熱機関が動作するためには、高温の炉だけではなく低温の冷却器が必要であること、すなわち、高温物体から低温物体への熱の流れによって仕事が行われることを、正しく認識した最初の科学者でした。この考えに基づいて、彼が理論的に証明したのが、いわゆる「カルノーの定理」です。この定理は、「熱は高温物体から低温物体へと流れる」という(一見自明な)前提の下で、「熱機関の熱効率は可逆的なサイクルのときに最大になる」ことを主張するもので、熱力学が経験科学から理論科学へと発展する第一歩となりました(ただし、カルノーは熱量の保存則を仮定するなどいくつかの点で誤っており、後に、クラウジウスによって修正されます)。
カルノーは、熱機関が動作するためには、高温の炉だけではなく低温の冷却器が必要であること、すなわち、高温物体から低温物体への熱の流れによって仕事が行われることを、正しく認識した最初の科学者でした。この考えに基づいて、彼が理論的に証明したのが、いわゆる「カルノーの定理」です。この定理は、「熱は高温物体から低温物体へと流れる」という(一見自明な)前提の下で、「熱機関の熱効率は可逆的なサイクルのときに最大になる」ことを主張するもので、熱力学が経験科学から理論科学へと発展する第一歩となりました(ただし、カルノーは熱量の保存則を仮定するなどいくつかの点で誤っており、後に、クラウジウスによって修正されます)。
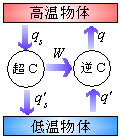 カルノー・サイクルで熱効率が最大になることは、次のようにして証明されます。カルノー・サイクルでは、全ての過程が準静的に行われているので、各過程を完全に逆転させた逆カルノー・サイクルも、実現可能です。仮に、カルノー・サイクルよりも効率が高く、qよりも少ない熱量qsを高温の炉から吸収して仕事Wを行う熱機関(超カルノー・サイクル)が存在したとします。この熱機関によって逆カルノー・サイクルを動かすことを考えましょう。1サイクルの動作を終えるまでに、正味 q-qsの熱量が冷却器から炉に流れていますが、2つの熱機関は最初の状態に戻っており、外部との間に仕事のやりとりも行われていません。従って、他に何の変化がないにもかかわらず、熱が低温物体から高温物体に流れたことになり、前提と矛盾します。作業物質が何であるかによらず、可逆なサイクルが理論的に最大の熱効率を与えるという結論になります。
カルノー・サイクルで熱効率が最大になることは、次のようにして証明されます。カルノー・サイクルでは、全ての過程が準静的に行われているので、各過程を完全に逆転させた逆カルノー・サイクルも、実現可能です。仮に、カルノー・サイクルよりも効率が高く、qよりも少ない熱量qsを高温の炉から吸収して仕事Wを行う熱機関(超カルノー・サイクル)が存在したとします。この熱機関によって逆カルノー・サイクルを動かすことを考えましょう。1サイクルの動作を終えるまでに、正味 q-qsの熱量が冷却器から炉に流れていますが、2つの熱機関は最初の状態に戻っており、外部との間に仕事のやりとりも行われていません。従って、他に何の変化がないにもかかわらず、熱が低温物体から高温物体に流れたことになり、前提と矛盾します。作業物質が何であるかによらず、可逆なサイクルが理論的に最大の熱効率を与えるという結論になります。
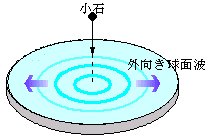 先進波と遅延波を積極的に区別しなければならないのは、波と物体が相互作用しているとき、系のセットアップによって一方の解だけが実現されるようなケースです。例えば、水面に小さな石を落としたときに生じる波を考えてみましょう。このとき、石が落ちた地点から球面状に外向きに拡がっていく波が生じますが、波動方程式の性質から、これを時間反転した内向きに収縮してくる波も、また方程式を満たすはずです。しかし、現実に内向きの球面波が生じることはありません。「水面の1点に小さな石が落ちる」という原因によって生まれる波は、因果律によって、常に原因よりも時間的に遅れて伝播していくからです。内向き球面波が生じるのは、巨大な円柱状の波動発生装置を用意し、同じ位相の内向きの波を人為的に作り出すようなきわめて特殊な場合に限られます。
先進波と遅延波を積極的に区別しなければならないのは、波と物体が相互作用しているとき、系のセットアップによって一方の解だけが実現されるようなケースです。例えば、水面に小さな石を落としたときに生じる波を考えてみましょう。このとき、石が落ちた地点から球面状に外向きに拡がっていく波が生じますが、波動方程式の性質から、これを時間反転した内向きに収縮してくる波も、また方程式を満たすはずです。しかし、現実に内向きの球面波が生じることはありません。「水面の1点に小さな石が落ちる」という原因によって生まれる波は、因果律によって、常に原因よりも時間的に遅れて伝播していくからです。内向き球面波が生じるのは、巨大な円柱状の波動発生装置を用意し、同じ位相の内向きの波を人為的に作り出すようなきわめて特殊な場合に限られます。