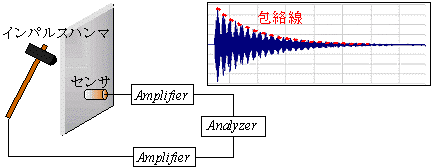古典的な命題論理学において、質問文にあるような反射律・対称律・推移律を満たす論理演算子は「同値⇔」になります。代数学ならば、「3で割ったときの余りが等しくなる関係」というように、トリヴィアルでない同値関係を定義し、互いに同値関係にある元の集合として(「3で割り切れる自然数」のような)クラスを定義することができます。しかし、命題論理を扱う場合、命題の「意味」は真偽値によってしか表されないため、
P⇔Q
が恒真になる2つの命題PとQは、「同じ意味の命題」ということになり、日常言語に翻訳したときに、これを使って面白い推論を行うのは無理でしょう。おそらく、質問者が関心を持っているのは、「命題論理学における三段論法などの形式的な推論が、なぜ論理的だと考えられるか」という点だと思われますので、以下では、この問題について解答することにします。
例を元にして考えましょう。仮言的三段論法:
((P⇒Q)∧(Q⇒R))⇒(P⇒R)
「「PならばQ」かつ「QならばR」」 ならば「PならばR」
は、古典論理学の範囲では常に真になりますが、日常的な思考において、こうした形式の推論が「論理的に正しい」と考えられるためには、いくつかの条件が必要になります。何よりも、命題が(ある程度の)普遍性を持っていなければいけません。例えば、
「P(x); xはソクラテスである」
「Q(x); xは人間である」
「R(x); xは死ぬ」
などの命題を使って、「ソクラテスは人間である」かつ「人間は死ぬ」ゆえに「ソクラテスは死ぬ」という三段論法を構築した場合、「人間である」とか「死ぬ(ものである)」といった述語が、主語(述語論理における代入項)を一般的なクラスに分類するものであるからこそ、発展的な推論として意味を持つのです。しかし、胎児や脳死体、高度な文化を持った類人猿や脳以外は全て機械で作られたサイボーグなど、「人間」に分類して良いかどうか微妙なケースがいろいろとあるにもかかわらず、境界事例を無視してクラスに分類することが論理的なのでしょうか。もちろん、論理学においては、「人間」や「死」の意味を問うことはせず、「漬け物桶」や「ティンブクツー」といった言葉で置き換えてもかまわないはずですが、それでも、「分類可能性」は、形式的推論が有効であるための暗黙の前提として含意されているはずです。実際、「ゴミ屋敷を掃除して出てきたゴミは12.3トンだった」といったあまり普遍的でない命題は、「うひゃー」という感嘆詞を引き出すばかりで、(シャーロック・ホームズならいざ知らず)論理学的な推論にはなじみません。
こうした「一般的なクラスへの分類」は、世界の状態を記述する上で必然的に要請される作業ではなく、人間が行う「判断」の基本的な形式に沿ったものであると考えられます。そもそも地球上の生物が進化の過程で知的能力を獲得していったのは、餌の増減や捕食者の来襲を予測していち早く行動を起こせる個体の方が、生存確率が高くなるからです。知的生物が中枢神経系で感覚器官から入力されたデータを解析するのは、例えば、危険性を素早く察知し「向きを変えて逃げ出す」という行動にスムーズに移るための作業であって、「世界の本質を探ろう」などという高尚な目的を持ってのことではありません。データ解析に際しては、生存のために有用ではない情報はあっさり捨象し、「危険性の有無」などの重要なポイントに限定してデータを処理することになります。
知的生物に備わっている神経回路網では、「神経興奮の収束」というプロセスによって、こうしたデータ処理を実行しています。発生初期の神経回路は、ランダムなシナプス接続を持っており、神経興奮のパターンは安定しません。しかし、成長過程での学習を通じて不必要な接続が淘汰され、個体として自立的に活動する頃には、状況に依存する複雑なデータが入力されても、神経興奮が、最終的にいくつかの定まったパターンのどれかに落ち着くように編成されます。ここで、定型的な神経興奮のパターンは、限定されたポイントに関する状況判断に対応すると考えられます。人間の場合は、パターンがきわめて多様になって、常に安定した状態に落ち着くわけではありません(だからこそ、常に新しい発想に基づいて思考することが可能なのです)。しかし、「複雑な状況を(危険かそうでないかといった)一般的なクラスに分類する」という知的判断の基礎が、神経回路網というハードウェアに依存していることは、否定できません。
論理学とは、人間が行っている知的作業のエッセンスを抽出したものであり、肉体から切り離された“血も涙もない”学問のようでありながら、実は、神経回路の動作と密接に結びついているのです。同一命題に関して反射律が満たされる、すなわち、
「P⇔Pは常に真」
であることは、深く考えるまでもなく当たり前のことに思えるかもしれませんが、神経興奮のパターンが安定しなければ、「離散的なクラスへの分類」が確定されず、「Pが成立するならば…」と考えているうちに命題の意味が変動することもあり得るので、エイリアンの論理学においても成り立っているとは言い切れないのです。人間である以上、「クラスへの分類」を伴わない論理学について推測するのはかなり難しいことですが、例えば、命題が一定の記述ではなく出力を持つ機能として定義されており、そこに含まれる連続パラメータによって機能も連続的に変動するといった事態が考えられます(と言っても、私自身、具体的にどういう論理学になるのか、想像もつきませんが…)。
【Q&A目次に戻る】

ランバート・ベールの法則とは、希薄な溶液(または気体)を透過させたときの光の吸収に関する法則です。純溶媒を透過した光の強度をI
0、これに溶質を加えて濃度cの溶液にしたときの透過光の強度をIとすると、
log (I
0/I) = εcd
という関係が成り立つというものです。ただし、dは光が透過する溶液層の厚さ、εは物質と波長だけによって決まる吸光係数です(化学では対数として常用対数を使うことが多いのですが、ここでは、計算の便宜のため、自然対数を使います)。
ランバート・ベールの法則で重要なのは、右辺に cd という積が現れるという点です。この値は、光が透過する部分に含まれる単位面積あたりの分子数に比例しており、分子数が同じならば、濃度を下げて厚みを増しても、その逆でも、吸収される光の量は同じになることを意味しています。これは、溶質分子が独立に一定の割合で光を吸収していくと考えると理解できます。
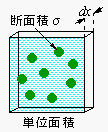
各分子が光を吸収する割合は、吸収断面積σ(光の波長に依存します)という概念を利用するとわかりやすくなります。光がこの断面積の内側に入ると吸収され、外側なら素通りしていくという考え方です。いま、底面が単位面積、高さが dx の角柱に光が入射する場合を考えると、その内部に含まれる分子数は Ndx (N:単位体積あたりの分子数)であり、これらの分子が光を吸収する総面積は、σNdx となります。角柱の底面に入射された光は、dx の層を透過する間に σNdx の割合で吸収されることになるので、入射光の強度を I とすると、光強度の変化は、
dI = -IσNdx
あるいは、c=Nm (m:溶質分子質量)を使って、
dI = -Iσcdx/m
となります。σ/mをεと置いて積分すると、ランバート・ベールの法則を得ます。
【Q&A目次に戻る】

減衰比を測定するには、強制振動させて機械インピーダンスを測定するやり方など、試験体の特性に応じていくつかの方法がありますが、あまり急激に減衰しない試験体ならば、インパルスハンマで叩いて振幅の時間変化を調べる方法が、最も簡便でしょう。
振動が減衰していくときの振幅の包絡線は、減衰比をζ、固有振動の周期をTとすると、
const×exp(-2πζt/T)
で表されます。Tを導入したためにζは無次元量になっていますが、[s
-1]の単位を持つ減衰定数 K=2πζ/T が使われることもあります。実際に減衰比を求めるには、センサ(非接触加速度計など)の出力を対数アンプを通すことによって指数関数的な減衰を直線で表示し、1秒あたりの減衰量D を測定するのが簡単です。このとき、減衰比は、
ζ = DT/2π
で求められます。ただし、加振直後にはさまざま振動モードが励起されていて指数関数的な減衰にはならず、また、振幅が一定値に近づく領域でもノイズが大きくなるので、中間領域で減衰比を求める必要があります。どの領域でも直線で近似できないときには、複数の振動モードが関与しており、減衰比は一定値になりません。
きわめてゆっくり減衰する場合は、ある振動の振幅A
1と次の振幅A
2の比を使えば、
2πζ = ln (A
1/A
2)
という関係式から、減衰比が得られます。
実際の測定では、振動板のセッティング(釣り下げるのか支持台に取り付けるのか)や加振位置によって結果がばらつきますので、精度を上げるには、誤差を補正する必要があります。
【Q&A目次に戻る】

反周期境界条件は、フェルミオン場を「経路積分」によって量子化する際に利用されます。
フェルミオンの波動関数は、粒子を交換すると符号が逆になりますが、この性質は、フェルミオン場に関する演算子が、通常の量子力学で現れる交換関係:
[A, B] = AB - BA = …
ではなく、反交換関係:
{A, B} = AB + BA = …
を満たすことと数学的に等価です。フェルミオン場ψ(t,x)に関しては、
{ψ
a(t,
x), ψ
†b(t,
y)} = δ(
x-y)δ
ab
という反交換関係が成り立ちます。このような関係を満たす場の演算子を扱うには、かなり難解な数学的テクニックが必要となります。特に、経路積分を行う場合は、反交換関係を満たす代数を構築しなければなりません。こうした代数はグラスマン代数と呼ばれており、(「2×3=3×2」のような)積の交換関係の代わりに、
ab = -ba
という反交換関係が成り立ちます。これより、
a
2 = -a
2 = 0
とか
f(a) = f(0) + f'(0)a
といった直観に反するような関係式が導かれます。
フェルミオン場の経路積分は、グラスマン代数を使って定義されます。典型的な積分は、
∫ΠψΠψ
† exp (-∫dτ∫d
x L(ψ,ψ
†))
という形をしています(ψなどは各時空点で定義されたグラスマン数になっています)。経路積分は、収束を良くするために、通常、時間tを τ=it に変換していますが、反周期境界条件は、この“虚数時間”の積分に関して要請されます。すなわち、虚数時間の積分領域を0〜βとすると、積分変数ψに、
ψ(0,
x) = -ψ(β,
x)
という条件が課せられます。こうした条件がなぜ要請されるかは専門的なので省略しますが、グラスマン代数の下で積分を正しく定義するために必要になるとだけ言っておきましょう。
反周期境界条件は、経路積分で場の量子論を定式化するに使わるものであり、大学レベルの量子力学の計算でお目にかかることは、まずありません。
【Q&A目次に戻る】

人間の認識は、生まれつき備わっている知覚能力に大きく左右されています。例えば、人間が外界を認識する際に積極的に利用する視覚情報は、伝播速度がきわめて速く直進性の高い可視光線によって運ばれているので、幾何学的なビジョンをもたらすことになります。その結果、外界の認識においては、(光線が遮られないような)“空虚な空間”の存在が前提となり、「その中に物体が存在する」という世界像が描かれることになります。しかし、全ての知的生物が同じイメージを抱いているとは限りませんし、そもそも、これが自然の“似姿”であるという保証もありません。
動物の中には、外界について主たる情報を視覚以外の感覚器官から得ているものが、少なくありません。例えば、イヌの場合、「何時間前に別の牝イヌが通った地点」といった匂いに基づく情報が、行動方針を決定する際に優先されます。イヌの心を想像するのは難しいのですが、嗅覚野の発達具合から考えると、人間のように、まず幾何学的な空間をイメージし、そこに嗅覚情報を“重ね描き”しているのではなく、外界のイメージ自体が、時間方向への拡がりを持って表象されていると推測されます。また、微生物の中には、温度や圧力、特定物質の濃度、磁場や微弱電流など、アナログ的な情報に基づいて運動性を決定しているものもあります(磁場は渡り鳥なども利用しています)。
ここで、人間がイメージしている描像こそが正当であり、他の生物は能力が劣っているために不完全なイメージしか描けないと、傲慢な誤解をしないことが重要です。実際、目に見えている「この瞬間の世界」だけがリアルだとする刹那的な認識よりも、イヌが感じている時間的に拡がったビジョンの方が、相対性理論に適っていますし、多くの人が風の揺らめきやかすかな匂いに対して示す無頓着さは、人間が外界に関する物理的情報を微生物ほどにも利用していないことを意味します。もちろん、微生物に人間のような認識能力があるとは考えられませんが、この広い宇宙のどこかに、アナログ的な情報を認識の基盤にしている知的生物がいる可能性は否定できません。例えば、スタニスワフ・レムのSF小説『ソラリスの陽のもとに』に登場する“知性を持った海”は、おそらく「空間の中に1個の物体が存在する」という形式の認識を持ち得ないでしょう。
彼が抱くであろう連続的に変動する世界のイメージは、場の理論に通じるものがあると言えるかもしれません。
ただし、量子論的な粒子/波動の二重性を統合できる先験的な認識能力を持つ知的生物がいると想像するのは、ちょっと無理があります。粒子/波動二重性──あるいは、その背後にある場の量子論的な揺らぎ──は、せいぜい高分子のレベルまでで見られる現象であり、生体組織以上のスケールで表面化することは、まずありません。生物の生き残り戦略に直接の関わりがなく、これを理解できるような認識能力を進化させる淘汰圧が働かないのです。いかなる知的生物であっても、量子効果を直観的に把握することはできず、人間と同様に、既存のカテゴリーを相補的に組み合わせて何とか理解することになるでしょう。
【Q&A目次に戻る】

人間は、所詮、偶然が重なってサルから進化することになった動物であり、動物と人間を峻別する原理的な何かがあるわけではありません。二足歩行ならティラノサウルスでもしますし、対象を概念化する能力はイヌにもあります。人間に匹敵する高度な言語能力を持つ動物は見つかっていませんが、鳴き声によるシグナルの伝達くらいはウシでもできます。チンパンジーともなれば、単なるシグナルではない単文を構成する能力を示します。かつては、「道具を作る動物」は人間だけだと言われていましたが、その“常識”も、動物行動の観察を通じて覆されつつあります。
自然界で動物が道具を作る例として最も有名なのは、チンパンジーが蟻塚から好物のアリを捕まえる際に、小枝の葉をむしり取って“アリ釣り”に利用するケースです。これは、葉が付いたままでは蟻塚の穴に差し込みにくいことを理解した上で、意図的に道具を製作する行為です。おそらく、当初は偶然に発見した技能でしょうが、類人猿には文化を伝承する能力があるので、群れの中で定着していったと思われます(サルにおける文化の伝承としては、ニホンザルのグループで、イモを水で洗ってから食べるという行動が広まっていったケースがよく知られています)。
人間と共同生活をしている類人猿では、さらに驚くべき状況が見られます。NHKスペシャルで紹介されたボノボ(ピグミーチンパンジー)は、2つの石を打ち付けて打製石器もどきを作っていました。NHKのやらせでなければ、人間の祖先であるアウストラロピテクス並の能力があるようにも思えます。
質問にあるカラスの例は、2002年にオックスフォード大の研究グループがオス・メス2羽のニューカレドニアカラスを使って実験したものです(Science 297(2002)981)。このグループは、当初、真っ直ぐな針金と曲がった針金数種類をあらかじめ用意しておき、これを使ってカラスが鉛直の筒の中に置かれた餌入り容器(フック付き)を引き上げられるかどうかを調べていましたが、実験中にたまたま曲がった針金がなくなったとき、真っ直ぐなものを曲げて筒から餌を引き上げるのが観察されました。そこで、改めて真っ直ぐな針金(直径0.8mm、長さ90mm)だけを筒の上に置いたところ、メスの方が針金を曲げて餌を引き上げることに9回成功したというものです(オスは針金を曲げられず、メスが引き上げた餌を横取りしたとか…)。針金を曲げるには、そばにあった粘着テープか足で一端を固定し、他端をくちばしで引っ張ったとのこと。各トライアルでは、まず真っ直ぐな状態で引き上げられるか試し、その後に針金を曲げて再挑戦したそうで、試行を開始してから餌を得るのに2分と掛からなかったと報告されています。この針金曲げがどこまで結果を予測した意図的なものかは、はっきりしません。穿った見方をすれば、曲がった針金で餌を得ることに成功したという体験と、針金をいじっているうちに曲がったという学習の記憶が連合され、一連の行動パターンを形成したとも考えられます。しかし、外部から行動を観察した範囲では、目的を持って道具を製作しているように見えます。
動物による道具製作に関しては、管理された実験にせよ自然界での観察にせよ、報告例があまりに少ないため、いまだ明確な結論が出せる段階ではありません。しかし、報告された少数の事例を見る限り、「道具を作るのは人間だけだ」というのは、浅はかな自惚れだったようです(「“道具を作る道具”を作るのは人間だけだ」という説もありますが…)。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
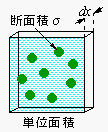 各分子が光を吸収する割合は、吸収断面積σ(光の波長に依存します)という概念を利用するとわかりやすくなります。光がこの断面積の内側に入ると吸収され、外側なら素通りしていくという考え方です。いま、底面が単位面積、高さが dx の角柱に光が入射する場合を考えると、その内部に含まれる分子数は Ndx (N:単位体積あたりの分子数)であり、これらの分子が光を吸収する総面積は、σNdx となります。角柱の底面に入射された光は、dx の層を透過する間に σNdx の割合で吸収されることになるので、入射光の強度を I とすると、光強度の変化は、
各分子が光を吸収する割合は、吸収断面積σ(光の波長に依存します)という概念を利用するとわかりやすくなります。光がこの断面積の内側に入ると吸収され、外側なら素通りしていくという考え方です。いま、底面が単位面積、高さが dx の角柱に光が入射する場合を考えると、その内部に含まれる分子数は Ndx (N:単位体積あたりの分子数)であり、これらの分子が光を吸収する総面積は、σNdx となります。角柱の底面に入射された光は、dx の層を透過する間に σNdx の割合で吸収されることになるので、入射光の強度を I とすると、光強度の変化は、