
コルモゴロフ・エントロピーとは、確率過程に情報エントロピーのアイデアを適用したもので、あまり一般的ではありませんが、カオス理論などで用いられることがあります。
クラウジウスによる熱力学的なエントロピーのアイデアは、ボルツマンによって統計力学的に基礎付けが与えられました。力学系の状態を表す軌道空間を微小部分に分割したとき、各部分の分布関数をP
jとすると、エントロピーは、
H = -Σ P
jlog P
j (ボルツマン定数k=1とする)
となります(Boltzmann,1872; Gibbs,1902)。
一方、ボルツマンの議論を情報理論に拡張したのがシャノンによる情報エントロピーで、ある状態jが実現される確率をp
jとすると、
H = -Σp
jlog p
j
という形で与えられます(Shannon,1948)。2種類のエントロピーは、形式的には同じ式で表されており、系の変化が確率的に記述されるような物理的システムでは両者は一致することが知られています。しかし、情報エントロピーは、物理的なプロセスだけでなく、不良品の発生や電話の呼び出し回数など統計的なイベントなら何にでも適用できるものであり、また、条件付きエントロピーのように統計力学には存在しない応用もあるので、通常は別個の概念として扱われています。
近代確率論の創始者として知られるコルモゴロフは、1950年代に、確率過程に関する情報エントロピーを公理論的に定式化することにより、これを物理的なプロセスに直接適用する道筋を明確に示しました。コルモゴロフが採用した方法論は、、
(1)ある確率法則に従って逐次的に生起する一連の事象(確率過程)に関して、情報エントロピーを定義する
(2)その際に、「サイコロ振り」のような具体的なイメージは捨象し、あるシステムが取り得るあらゆる状態の集合である抽象的な状態空間Xを導入し、X内部での変換を考える
というものです。試行回数や状態数が有限のケースでは、「サイコロの目が1,2,3の順に出る」といった特定の過程が起きる確率をp
jと置くことにより、シャノンの定義をそのまま使うことができます。しかし、これでは、一般的な確率過程に拡張することができません。そこで、抽象的な確率論の手法を使って、連続極限を取ることが可能な論法を用いたわけです。このとき、事象の生起確率は状態空間の確率測度μとして読み替えられ、ある事象と次の事象の関係は、「何回目の試行か」というイメージを伴わない保測写像f(測度が保存される写像)によって表されます。こうした抽象的な枠組みを用いることにより、知識の欠如レベルとして扱われてきた情報エントロピーが、自律的な法則に従う力学系の状態量として扱えるようになったわけです。
3体問題の例からも明らかなように、大半の物理的プロセスは、系の振舞いを解析的に記述することが困難であり、状態変化を直接的に表す個々の軌道ではなく、軌道空間における軌道の分布によってしか記述できません。コルモゴロフの定式化は、こうした統計的な状態変化を表現するのに、実に好都合と言えます。物理的な力学系に適用する場合、保測写像fは、「ある時刻の状態から一定時間経過した状態への写像」を意味することになり、連続極限を取れば、時間変化の演算子と見なすことができます。
コルモゴロフ・エントロピーの具体的な表式はかなり複雑ですが、ボルツマンやシャノンによる定義がベースになっています。一般に、Xの分割となる部分集合族
C の元をC
iとすると、確率測度μを用いたエントロピーは、
H(C) = -Σμ(C
i)log μ(C
i)
と定義されます。コルモゴロフの議論は、この定義を拡張し、
Cに次々に保測写像fを作用させて得られる集合族
C, f(
C), f
2(
C), f
3(
C), …
を併せたもののエントロピーを考えることによって、次々に生起する一連の事象のエントロピーを与えようとするものです。この際、全ての可能な分割を行ったときの上限値を保測写像fのエントロピーと定義すれば、状態空間Xの分割の仕方によらない値が得られます(煩雑になるので式は省略します)。物理的プロセスに適用した場合、このエントロピーは、長時間が経過する間に軌道がどれほど複雑な(=予測不能な)振舞いをするかを表す指標となります。例えば、単振動のように単純な周期解のみの場合は、エントロピーはゼロになり、複雑さが増すにつれて値が大きくなります。近年のカオス理論では、このエントロピーとリヤプーノフ指数の間に単純な関係が成り立つことが示されています(詳しい解説は、大学院レベルのカオス理論の教科書にあります)。
【Q&A目次に戻る】

地球をはじめとする多くの天体は、その周囲に磁石と同様の双極子磁場を持っていますが、こうした磁場は、天体内部に電流が流れることによって生じていると考えられています。言ってしまえば、地球は巨大な電磁石なのです。ジュール損失に打ち勝って電流を流し続けるには一種の発電機(ダイナモ)が必要であり、地球の外核がそうした発電機になっていることをほぼ解明したのが、1940年代にブラードらによって提唱された「ダイナモ理論」です。
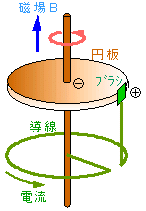
ダイナモ理論は、電磁流体力学の高度な応用としてかなり難解なものなので、ここでは、ブラードが用いた簡単なモデルを使って、そのエッセンスだけを説明することにします。図のように、磁場Bが存在している領域で電気伝導性を持つ円板が回転すると、ファラデーの法則に従って、円板の軸と円周の間に電位差が発生します。軸と円周をつなぐ図のような回路が存在すると、電流が流れて(右ネジの法則によって)元の磁場Bと同じ向きに誘導磁場が形成されます。円板を回転させる外力がないと、回路内部にジュール熱が発生してエネルギーが失われ、円板は止まってしまいますが、ある値以上の力で円板を回している場合は、元の磁場と誘導磁場を合成した磁場がだんだんと大きくなり、それに伴って誘導起電力や電流も増大して、最終的には、かなり強い磁場が形成されることになります。
天体内部で生じているプロセスも、おおよそはこれと似たものです。地球の場合、中心部の内核は固体ですが、深度2900〜5200kmの外核部分は、主成分が鉄の液体になっています。これが、電気伝導性を持つ円板に相当します。さらに、放射性元素の崩壊によって内核で生み出さる熱が外核に伝えられ、対流を引き起こしていますが、地球が自転しているために、コリオリ力(回転する座標系で運動方向に垂直に加わる見かけの力)が作用して運動の向きが変わり、西から東へと進む帯状の流れを形成しています。これが円板の回転に相当する運動で、放射性元素の崩壊熱が、ジュール損失に抗して運動を維持するエネルギー源となっています。
円板モデルと異なって、実際の地核には、ブラシも導線もありません。にもかかわらず、磁場が成長するのは、単一の電磁流体において、最初の弱い磁場B
0内部での伝導性流体の運動によって誘導電流に伴う誘導磁場B
1が誘起され、このB
1内部での運動が磁場B
2を、B
2内部での運動が磁場B
3を……と続くフィードバック・ループが、ポジティブな方向に作用するためです。非線形な電磁流体力学の方程式を解いて実際に正のフィードバックが生じることを示すのは相当に難しい(し、さまざまな条件が整っていなければ実現されない)のですが、地球内部では、こうした複雑なプロセスによって、偶発的な弱い磁場の“種”が成長して、強い地磁気が生成されると考えられています。
地磁気が生成・維持されるプロセスは、必ずしも安定していません。地質学的なタイムスケールで見ると、地磁気は、何度か反転したことが知られています。地磁気のダイナミックな変化はカオス的であり、これをダイナモ理論で説明する試みは、現在なお、完成途上にあります。
【Q&A目次に戻る】

地球以外の生物にとってもタンパク質は欠かせないものなのか、即答するのは困難ですが、これが生命活動の本質に関わる特性──すなわち、1次元的な情報をコードすることが可能であると同時に、3次元的な構造を通じて複雑な機能を実現できるという性質──を備えた稀な物質であることは確かです。
まず、タンパク質は、アミノ酸配列という形で1次元的な情報をコードすることができます。生物学の常識に従えば、生物は遺伝によって次世代に情報を伝えていく必要があるため、結晶のような単純な繰り返し構造ではなく、構成要素の配列が入れ替えられる可変性がなければなりません。また、分子中にコードされた情報を他の分子に効率的に転写するためには、分子の基本構造が1次元の鎖状であることが望ましいと考えられます。ペプチド結合によってアミノ酸が鎖状につながっているタンパク質は、核酸などとともに、情報をコードする上で理想的な高分子だと言えます。
さらに、タンパク質の特徴として、1次元鎖が折り畳まれた特異な3次構造を取ることが上げられます。こうした構造は、非線形なアロステリック効果を通じて複雑な生命現象を実現するために欠かせないものです。
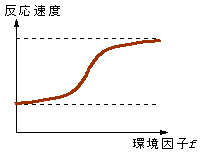
アロステリック効果とは、環境因子f(特定の基質の濃度など)に応じて分子の立体構造が大きく変化し、その結果として、fに対してプロットした反応速度がスイッチのオン/オフに相当するS字型曲線になるような現象です。分子量の大きなタンパク質の場合、折り畳んだときのエネルギー準位が環境因子のわずかな変動に応じて上下し、それに伴って基底状態が入れ替わって反応部位が表面に現れたり覆い隠されたりするため、反応性のオン/オフが生じることになります。こうした非線形効果が、線形応答を基本とする単純な物理的システムとは異なる生命現象の特殊性を支えていると言えます。
タンパク質は、上の2つの性質を併せ持つことから、地球上の生物にとっては不可欠の物質になっています。おそらく、この宇宙に生息する大半の生命体が、何らかの形でタンパク質を利用していると考えても良いでしょう。ただし、あらゆる生物がそうだと言えるかどうかは疑問です。地球上には水という特殊な溶媒が大量に存在するため、全ての生物が水を体内で利用していますが、水の少ない天体には、他の溶媒に頼っている生き物がいるはずです。その場合、タンパク質のペプチド結合やアミノ酸残基の相互作用が生命維持にとって必ずしも適当な強度ではなく、別の(ペプチド結合以外の結合がメインになるような)高分子が利用される可能性があります。また、遺伝による情報の継承を行わず、1個体がさまざまな変容を遂げながら何億年も生き続けているケースも考えられます。こうした生命体においては、高分子の1次元鎖に情報をコードする必要がないため、シリコン結晶内部で形成された不純物の立体構造が生命現象の基礎になるといったことがあるかもしれません。
【Q&A目次に戻る】

物理学では、(量子重力理論や格子理論などの特殊な例外を別にすると)時間を実数tで表します。従って、“現在”の時刻をTと表すと、t>Tは未だ来ぬ未来、t<Tは過ぎ去った過去であり、“現在”とは、t=Tとなる持続時間無限小の瞬間にすぎないことになります。しかし、こうした時間的拡がりのない瞬間にどのような物理的な意味があるのか、そもそも実在すると考えて良いのか、明らかではありません。
心理的な“現在”は、物理学における時間とは異なり、ある拡がりを持っています。これは、ごく短い時間(数百ミリ秒程度)に継起的に加えられた知覚刺激が、個々の刺激ごとではなく、1つのまとまり(パターン)として脳で情報処理されるためだと考えられます。物理的には別の時刻に生じた事象であっても、心理的に1つのまとまりとして認知されるならば、それらは、同じ“心理的現在”の中にあると言って良いでしょう。例えば、数百ミリ秒間隔のパルス状の音列が数秒間以下継続する場合、人間は、それを個々の音の並びとしてではなく、1つのリズムとして認知します。“心理的現在”とは、リズムのように、「時間的に拡がりながらもまとまり感のある」事象によって構成されたものです。
質問にある視覚の場合、数百ミリ秒から数秒の間に継起的に提示された光刺激がひとまとまりのパターンとして認知される点は聴覚と同じですが、短い時間の弁別能は聴覚よりも悪く、継続時間が百数十ミリ秒以下の光刺激は、長さのない“瞬間的な”光パルスに感じられ、十数ミリ秒以下の時間幅で起きた複数の事象は、全て同一時刻の出来事に見えるようです。ただし、視覚的イメージは、網膜に充分な数の光子が到達し一定数以上の光受容器が励起されると生じるので、光刺激の持続時間τがどんなに短くても、τと光量Iの積がある閾値を超えれば、「物が見える」ことになります。さらに、光が消えた後も視覚像は150〜200ミリ秒ほど保持されるため、きわめて短い時間での変化を捉えるのは困難です。映画は1秒間に24コマの静止画像が提示されますが、前のコマの残像が見えている間に次のコマが現れるので、明滅はほとんど意識されずに連続的な変化として把握されます(ただし、24コマはスムーズに見えるかどうかのギリギリのところで、状況によってはチラつきが感じられます)。猛スピードで動く小さな物体を見る場合、ある位置からやってくる光子の総数が閾値以上になる(=物体が明るく輝いている)と視覚像は生じますが、時間的な弁別能が低いため、物体の動きそのものは認知できず、ゆっくりと消えていく軌跡の残像だけが見えるはずです。
【Q&A目次に戻る】

重力の起源は、質量ではなくエネルギー(と運動量)です。重力場の振舞いを定めるアインシュタイン方程式は、
G
μν = κT
μν
という形をしており、右辺が重力場とその微分の組み合わせであるアインシュタインテンソル、左辺がエネルギー運動量テンソルになります。この方程式は、静電場の方程式:
divE = 4πρ (ガウス単位系)
と同じように、左辺のソース(電場の場合は電荷、重力場の場合はエネルギー・運動量)によって右辺の場が生じると解釈されます。この解釈は、重力子を扱う量子論においても妥当すると考えられます(ただし、重力の量子論は、いまだ建設途上ですが…)。
ヒッグス粒子の場は、宇宙空間全体に瀰漫するように広がっています。電子やクォークなどの素粒子は、このヒッグス場と相互作用するため、空間中を自由に運動することができず、慣性を獲得します。しかし、ここから直ちに重力場が派生するわけではありません。質量と重力場が結びつくのは、次の2つの性質があるためです。
- 質量mを持つ素粒子とその反粒子を対生成するためには、2mc2以上のエネルギーを与えなければなりません(それ以下のエネルギーでは、すぐに対消滅してしまいます)。このため、質量mの素粒子は、存在するだけでmc2以上の巨大なエネルギーを持っていることになり、重力場の主たるソースとなるのです。
- 質量のない粒子が常に光速で運動するのに対して、質量を獲得した物質粒子は、運動エネルギーの多寡に応じて光速以下の遅い速度で運動するようになります。特に、運動エネルギーの小さいものは、互いに重力を振り切ることができずに、次第に凝集し天体を形成します。質量のない粒子が宇宙全体に薄く広がるのに対して、質量を持つ物質粒子は天体近傍に束縛され、惑星系・恒星系・銀河系など重力場に支配された特徴的な天体構造を生み出します。
このように、天体が関与する重力場は素粒子が質量を持つことによってもたらされたものですから、ヒッグス場の存在が決定的な役割を果たしていると言っても良いでしょう。
【Q&A目次に戻る】

今や「抗酸化」という言葉は、健康関連グッズの宣伝に頻出するキーワードとなった感があります。しかし、中には、科学的な観点からすると首を傾げざるを得ないような宣伝文句も見受けられます。
抗酸化物質(antioxidant)の効能が注目され始めたのは、1950年代にフリーラジカル(反応性の強い化学種で単にラジカルとも言う)と老化の関係が指摘されてからです。活動中の細胞内では、エネルギー源となるATP分子をミトコンドリアで合成する際に、副産物として活性酸素(種)(reactive oxygen species; スーパーオキシドラジカル
.O
2-などの化学的活性に富んだ酸素種)が放出されています。この活性酸素は、酸化によってミトコンドリアなどの細胞内器官を傷つける作用があります。多くの傷は酵素によって修復されますが、修復できなかった傷が次第に蓄積されると、細胞の機能が維持できなくなり、それとともに生体の老化が進行します。生体内では、スーパーオキシドラジカルを通常の分子に変化させる酵素SOD(
Super
Oxide
Dismutase)の働き(抗酸化作用)によって活性酸素による害が抑制されているものの、加齢とともにSODの産生量が減少し、老化やそれに伴う疾患(ガン・心臓病・白内障など)が表面化してきます。学者の中には、SOD様作用を持つ抗酸化物質を摂取すれば、SODの減少を補って老化を防止できるという説を唱える人もいます。確かに、ビタミンCやEなどの抗酸化物質を含む緑黄色野菜を多食するグループでは、ガンや心臓病などの罹患率が低くなることが、疫学調査によって示されています。ただし、この結果が抗酸化物質によるものと判明したわけではありません。サプリメントの形で抗酸化物質を経口摂取しても寿命延長効果はほとんどないというデータもあり、その効能に関しては、現在なお研究中の段階です。
一方、ゴム・石鹸・油脂・食品などの酸化劣化を防ぐ目的で、抗酸化物質が添加されることもあります。この場合は、(英語では同じ antioxidant であっても)「酸化防止剤」と呼ぶのが一般的です。酸化劣化は、通常、(必ずしも活性酸素種ではない)フリーラジカルによって引き起こされる一連の反応として生じるので、そうしたラジカルを“中和”したり分解したりする物質が有効な酸化防止剤となります。食品用以外の酸化防止剤には有毒なものも多く、直接的に人間の健康を増進する効果はありません。
このように、抗酸化物質にはさまざまなタイプがあり、使い方によっては有効性を示すことがあるものの、フリーラジカルによる酸化の害をおしなべて防ぐような万能薬はあり得ません。一般論として言えば、「抗酸化」をキャッチコピーとして過大な効果を謳っている商品──特に、健康面でのメリットを強調するもの──は、疑ってかかった方が良いでしょう。
質問にある「抗酸化溶液」に関しては、科学的データが不足しているので、ここでは結論を出せません。一般論に基づいて、各自が判断して下さい。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
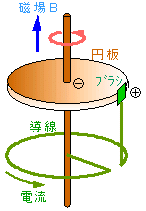 ダイナモ理論は、電磁流体力学の高度な応用としてかなり難解なものなので、ここでは、ブラードが用いた簡単なモデルを使って、そのエッセンスだけを説明することにします。図のように、磁場Bが存在している領域で電気伝導性を持つ円板が回転すると、ファラデーの法則に従って、円板の軸と円周の間に電位差が発生します。軸と円周をつなぐ図のような回路が存在すると、電流が流れて(右ネジの法則によって)元の磁場Bと同じ向きに誘導磁場が形成されます。円板を回転させる外力がないと、回路内部にジュール熱が発生してエネルギーが失われ、円板は止まってしまいますが、ある値以上の力で円板を回している場合は、元の磁場と誘導磁場を合成した磁場がだんだんと大きくなり、それに伴って誘導起電力や電流も増大して、最終的には、かなり強い磁場が形成されることになります。
ダイナモ理論は、電磁流体力学の高度な応用としてかなり難解なものなので、ここでは、ブラードが用いた簡単なモデルを使って、そのエッセンスだけを説明することにします。図のように、磁場Bが存在している領域で電気伝導性を持つ円板が回転すると、ファラデーの法則に従って、円板の軸と円周の間に電位差が発生します。軸と円周をつなぐ図のような回路が存在すると、電流が流れて(右ネジの法則によって)元の磁場Bと同じ向きに誘導磁場が形成されます。円板を回転させる外力がないと、回路内部にジュール熱が発生してエネルギーが失われ、円板は止まってしまいますが、ある値以上の力で円板を回している場合は、元の磁場と誘導磁場を合成した磁場がだんだんと大きくなり、それに伴って誘導起電力や電流も増大して、最終的には、かなり強い磁場が形成されることになります。
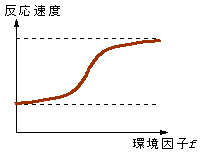 アロステリック効果とは、環境因子f(特定の基質の濃度など)に応じて分子の立体構造が大きく変化し、その結果として、fに対してプロットした反応速度がスイッチのオン/オフに相当するS字型曲線になるような現象です。分子量の大きなタンパク質の場合、折り畳んだときのエネルギー準位が環境因子のわずかな変動に応じて上下し、それに伴って基底状態が入れ替わって反応部位が表面に現れたり覆い隠されたりするため、反応性のオン/オフが生じることになります。こうした非線形効果が、線形応答を基本とする単純な物理的システムとは異なる生命現象の特殊性を支えていると言えます。
アロステリック効果とは、環境因子f(特定の基質の濃度など)に応じて分子の立体構造が大きく変化し、その結果として、fに対してプロットした反応速度がスイッチのオン/オフに相当するS字型曲線になるような現象です。分子量の大きなタンパク質の場合、折り畳んだときのエネルギー準位が環境因子のわずかな変動に応じて上下し、それに伴って基底状態が入れ替わって反応部位が表面に現れたり覆い隠されたりするため、反応性のオン/オフが生じることになります。こうした非線形効果が、線形応答を基本とする単純な物理的システムとは異なる生命現象の特殊性を支えていると言えます。