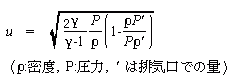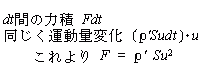「技術論概説」−「
軍事研究の重荷に喘ぐアメリカ
」の中で、
化学レーザーを利用する場合、大気での散乱によって著しく減衰するため、出力レベルを少なくとも現在の20倍にしなければならないと言われる。しかも、レーザーはコヒーレントな電磁波を発生するものなので、ただ大型化すれば良いという訳でもない。
と記述されていますが、2005年に米空軍が配備予定の U.S.A.F Ballistic Missile Interceptor Boeing AL-1A (http://www.f5.dion.ne.jp/~mirage/hypams01/al-1.html) などのレーザーを利用した迎撃システムが実用化に至ったのは、どのような理由によるのでしょうか?【その他】

「技術論概説」のベースになった講義ノートは、1990年代前半にSDI(戦略防衛構想)に対する批判として執筆されたものであり、それ以降の世界情勢の変化と技術的進展によって、状況はかなり異なったものになっています。アメリカは、ソ連と弾道弾迎撃ミサイル制限条約に調印した1972年以来、長らくミサイル防衛システムの配備を行っていませんでしたが、ソ連崩壊後、一部のテロ国家からの攻撃やロシアが保有するミサイルの偶発的な発射が懸念されるようになり、1996年から新たなミサイル防衛システムの開発に着手しました。1999年には、当時のクリントン大統領が米本土ミサイル防衛法に署名しています。
現在、アメリカで構想されているミサイル防衛システムでは、主に、飛来する弾頭を迎撃ミサイルによって撃ち落とすことが計画されており、大型航空機が搭載する空中発射レーザー(ABL)によってミサイルを破壊するシステムは、それを補完するものと考えられます。
SDIにおいてレーザーによるミサイル迎撃が困難だと考えられた理由は、発射直後の大陸間弾道ミサイル(ICBM)を遠方から攻撃しようとしていたからです。ICBMは、打ち上げ後十数分で高速の弾道軌道に入り、狙い撃ちすることがきわめて難しくなるため、まだ速度が遅いブースト段階で攻撃しなければなりません。SDIでは、広大なソ連領土のどこからミサイルが発射されても迎撃できるように、核爆発をエネルギー源とする高出力X線レーザー装置などを衛星軌道上に配備しておき、早期警戒衛星に搭載した赤外線感知システムでロケット噴射を確認すると、直ちに超長距離からミサイルをピンポイント攻撃することが目標とされていました。これが技術的に見て非現実的な計画であることは、今も変わりありません。
米空軍による配備が予定されているABL(配備計画は遅れ気味のようです)は、レーザー発生装置を搭載した大型航空機を敵領土に接近させ、たかだか数百kmの距離から、低速の戦域ミサイル(スカッドなど)やブースト段階の長距離ミサイル(テポドンなど)を撃ち落とそうというもので、SDIのX線レーザーなどと較べると、かなり実現性の高いものです。こうした兵器が実用化段階に達した背景には、レーザーの大出力化、コンピュータやセンサの高性能化、ビーム制御ソフト(大気による散乱を補償する)の開発などの技術的進展があったと推測されます。
ただし、軍事技術に関しては、プレス発表される内容を鵜呑みにしない方が良いでしょう。開発担当企業は多額の予算を獲得するために、軍の広報は相手国にプレッシャを加えるなどの戦略的な目的で、実際の威力よりも誇大に宣伝することがあるからです。湾岸戦争の際にも、当初は、イラクからのミサイル攻撃をパトリオットで防衛したと言われていましたが、実際には、スカッド・ミサイル44発に対して迎撃を試み、ほぼ全てで失敗したことが判明しています。
【Q&A目次に戻る】

われわれが「形」というとき、何を指しているかを考えてみてください。懸濁溶液の中でブラウン運動をしている粒子の軌跡は、きわめて複雑な図形になっているかもしれませんが、通常の「形」の概念からは逸脱していると思われます(それに、目で見ることもできません)。日常的な範囲で「形」を語るときには、多くの場合、境界を持つ物体を念頭に置いていると言って良いでしょう。とすれば、「形」の多様性には、自ずと限界が生まれてきます。
物体が結晶から作られている場合、結晶表面では内部よりも余分な表面エネルギーが必要になるため、原子は自由エネルギーを小さくしようと移動します。実際、気相中で成長している結晶を電子顕微鏡で観察すると、任意の格子点に原子が付着していくのではなく、表面がなだらかな階段状になることが確認できます。細胞のように表面が膜構造になっているときには、通常、表面張力の効果で球に近いものになります(細胞は細胞骨格や膜タンパクの影響で変形しています)。表面から突起が成長するようなケースでは、表面エネルギーの増加を補償するような何らかのメカニズムが働いており、自由に突起が出てくるわけではありません。このように、物理的な境界面を持つ物体の形は、かなり限られたものになります。
雲のように、明確な境界が存在しない対象もあります。しかし、この場合も、あるスケールで平均した温度や湿度の分布を見ると、揺らぎがならされて、水滴の成長が可能な比較的なめらかな境界を持つ領域を“雲の内部”として画定できます。これが、遠くから見たときの雲の「形」に相当します。より小さなスケールで見ると揺らぎがあらわになってきますが、そうなると、雲の形そのものを捉えることができなくなります(山登りの際に雲の中に入ったことのある人は、実感としてわかるでしょう)。
人間の認知能力にも限界があります。人間が直観的に捉えることができるのは、曲率があまり大きくない曲線や比較的短い線分など、限られた範囲の図形にすぎません。視覚を通じて物を見る際には、数少ない認知のテンプレート(鋳型)と照合しながら形を把握するので、きわめて複雑な形状を持つ対象は、「ゴチャゴチャした良くわからないもの」としてしか認知されないのです。数学的に構成された“あらゆる幾何学図形の集まり”は無限集合になりますが、その全てを人間が認知できるわけではありません。
【Q&A目次に戻る】

物体が人間の目に見えるのは、表面の各点からやってきた光が網膜に到達するからです。これを映像として再現するためには、同じような形で光線が目に入射されなければなりません。何もない空中から光を送り出すのは、技術的にはほとんど不可能に近いことです。
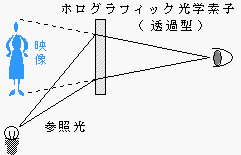
多少なりともこれに近い技術としては、ホログラフィック光学素子を使って立体映像を作り出すというものがあります(右図)。ただし、目と映像の間に光学素子を置くことが必要です。SF映画の古典『禁断の惑星』には、透明な半球状の装置の内側に立体映像を映し出すシーンがありますが、これなら近未来の技術で実現可能でしょう。
空想的なもので良いならば、何もない空間に立体映像を作り出す技術を思いつかないわけではありません。例えば、細い光束をある点で交差させるとそこだけ散乱光が強くなることを利用すれば、無数の光束を素早く動かすことによって交点で映像を描けるかもしれません。超音波による密度変化で空気の屈折率を変え、参照光をうまく曲げて像を結ばせるというのはどうでしょうか。毒性のない揮発性の微小結晶を吹き出して光を反射させるのは、乱暴だと言われそうです。現在の技術水準では夢物語であっても未来に実現されることもあるので、とにもかくにも、いろいろとアイデアを出し合うことから始めるべきでしょう。
【Q&A目次に戻る】

熱力学第2法則は、閉じた物理系でのみ成立するものです。例えば、温度T
1の物体AとT
2の物体B(T
1>T
2)を接触させると、AからBに熱が移動しますが、微小熱量dQが移動したとき、AではエントロピーはdQ/T
1だけ減少しています。一方、BではdQ/T
2だけ増大しており、AとBを併せた系での全エントロピーは(温度の不等式を使えばわかるように)増大しているので、第2法則とは矛盾していません。地球は閉鎖系ではないので、地上でエントロピーが減少する過程が進行することも可能なのです。
隕石による物質の流入や火山の噴火などのわずかな例外を別にすれば、地球表面は、外部環境との間で電磁波のみをやり取りしていると考えられます。エントロピー収支を見ると、太陽から短波長光(主に可視光線で有効温度が高い)を受け取り、これを長波長光(赤外線)に変換して低温の宇宙空間に放出しているので、地表システムだけに限れば、エントロピーが減少する余地は充分にあるのです。光合成について考えてみましょう。光合成における化学反応は、
6CO
2(気体) + 6H
2O(液体) → C
6H
12O
6 + 6CO
2(気体)
と表されます。このとき、ブドウ糖(C
6H
12O
6)1モルに固定されるエネルギーは約700kcalですが、もちろん、二酸化炭素と水を容器に閉じこめて、このエネルギーに相当する熱量を加えても、ブドウ糖が生成されるわけではありません。実際の反応では、50N
A(N
A:アボガドロ数)個以上の光子が吸収され、そのエネルギーの過半が液体の水分子を気化するのに使われています。水蒸気は水よりもエントロピーが大きく、ここに大量のエントロピーが捨てられたことによって、ブドウ糖分子にエネルギーを固定するというエントロピー減少反応が、熱力学第2法則と矛盾することなく実現されたのです。こうした生化学反応が積み重ねられた結果が、生物の発生や進化、さらに人類による文明の形成なのです。
地表でのエントロピーを可能にする太陽光線は、元をただせば、ビッグバンの際に宇宙を満たしていた水素(やヘリウム)が、重力の作用で凝集して核融合を開始したことに由来しています。こうした凝集過程は、宇宙開闢当初に“エントロピー溜め”であるブラックホールが多数あると、そこに物質が飲み込まれてしまって実現不可能になります。地球上で生命が発生したのは、言うなれば、この宇宙が、ブラックホールがほとんどなくエントロピーのきわめて小さい状態から始まったからです。宇宙史のスケールで見ると、人類の文明など、エントロピーが急増する最初期のほんの一瞬(数千億年?)でのみ可能なささやかなエピソードにすぎないのです。
【Q&A目次に戻る】

「数学的真理は普遍性を持つ」とは数学者が口にしたがる文句ですが、「普遍性(universality)」は、所詮「宇宙(universe)」を超えて妥当するものではありません。
三平方の定理(ピタゴラスの定理)のような幾何学的命題の正否は、宇宙がどのような幾何学的法則に従っているかに依存します。われわれが生きている「この」宇宙は、全体としてはきわめて平坦に近い状態にあるものの、ブラックホールのような強い重力源の近くで測量を行うと、ユークリッド幾何学が成り立たない(=時空が歪んだ)世界になっていることがわかります。もっとも、ブラックホールの近傍には文明は発生できないでしょうから、この宇宙に存在している知的生命の多くは、ピタゴラスの定理を真理として受け入れているのかもしれません。しかし、少なくとも「この」宇宙で厳密に成り立っている定理とは言えないのです。
数学者は、こう反論するかもしれません。
「なるほど、宇宙空間で測量を行うと、ピタゴラスの定理は実際に成り立っていないのだろう。だが、ユークリッド空間というイデアの世界では、理論構成の必然として定理が成立するはずであり、それこそが普遍性の意味するところだ」と。
この議論は正しそうに見えますが、物理学的に可能な世界の多様性を過小評価したものです。幾何学を考えるときには、“拡がり”を持つ空間や、その内部にある点や線などを、何らかの形で思い描いているはずです。ところが、物理学の議論に現れる世界には、そもそも拡がりを想定することのできないものがあります。例えば、フェルミオンの運動を支配する関数空間は、反可換数で記述される世界であり、“拡がり”という概念がありません。また、真空が常に不安定になるような量子場では、真空を“何もない空間”として扱うことは不可能です。こうした世界に知的生命が発生するとは考えにくいのですが、もしそこに生きる知性があったとすると、人間ならば子供にもわかる「空間の中の線」というイメージを獲得することは、不可能でしょう。人間が幾何学を構築できたのは、「ほとんど何もない空間の中の所々に物体がある」という特性を持つ「この」宇宙に生きているからなのです。
以上の議論は、あくまで私個人の考えであり、異なる主張をする人もいるでしょう。それはそれで面白いことであり、そうした主張にも耳を傾けていただきたいと思います。
【Q&A目次に戻る】

ペットボトルロケットで起きている現象を理論的に解析するのは、高校物理のレベルを超える問題になります。むしろ、まず単純化したモデルで解析を進め、その上で実験とのズレがどこから生じたかを考える方が、建設的な議論になると思います。
はじめに、ボトル内部でのメタノールの燃焼を考えます。ロケット実験をするときにペットボトルに注入するメタノールは0.5〜1ミリリットル程度であり、メタノールの燃焼熱は(状態によって異なりますが)700[kJ/mol]余りですから、爆発(衝撃波を伴う瞬間的な燃焼;爆轟)によって全てが一気に反応したとすると、確かにボトル内は数千度に上昇するはずです。しかし、実際には、ボトル内のメタノールは気相と液相が混じった状態になっており、 爆発というよりは、引火による火炎伝播に近いものになるはずです。燃焼速度がそれほど速くないため、燃焼途中で燃料を含む気体の一部は穴から吹き出してしまいます。こうした現象は現実的な解析が難しく、どのくらいのメタノールが反応するか、気体の圧力がどこまで上昇するかは、にわかに答えられません(燃焼工学の教科書はありますが、理論的に解析できるのは、一様な管内での燃焼のような簡単なケースに限られます)。そこで、問題を単純化して燃焼段階と噴射段階を分離し、まずメタノールの何パーセントかが瞬間的に反応して高温状態となり、その後に、穴から気体が噴出してペットボトルが飛び始めると仮定して計算してみたらどうでしょうか。
気体が噴出する際の排気速度の計算をきちんと行うには、圧縮性流体の方程式を立てなければなりません。一般に、排気口から排出される気体の排気速度uは、ベルヌーイの定理を使って、
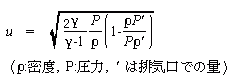
と表されます(γは比熱比)。これと断熱変化の式・状態方程式・質量保存則を連立させれば、排気速度の時間変化を求めるのに必要な式が揃います(厳密なことを言えば、排気口付近での流速が音速近くになる場合には、別の考察が必要になります)。さらに、ロケット噴射による推力Fは、排気口の断面積をSとすると、
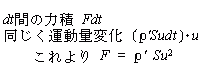
となり、排気速度や密度の変化から求めることができます。
ただし、上の計算を遂行するには、高等数学とコンピュータの助けが必要です。ここでは思い切り単純化して、ボトル内の気体が平衡状態を保ったまま真空中に放出されると仮定することにしましょう。この仮定の下では、断熱膨張ではなく自由膨張になるので、気体の温度は変化せず、排気速度も気体分子平均速度の定数倍(1/4弱)という一定値になります。質量保存則:
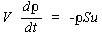
を使えば時間とともに指数関数的に減少する密度の式が得られるので、ロケットの推力も直ちに求められます。ロケットを鉛直方向に打ち上げる場合(※メタノールが飛び散って危険なことがあります)は、この推力と重力の差を時間積分すれば、空気抵抗を無視するという条件下で、最終速度などを求めることができます。このとき、燃焼直後のボトル内の温度が初期条件を決定するので、メタノールの燃焼率を唯一の未知数としてペットボトルロケットの運動が与えられることになります。
もちろん、この近似はあまりに粗いので、実験データとはかなりのズレがあるはずです。この計算を0次近似として、実際とはどこが違うかを推測してみるのも、勉強になるでしょう。
【Q&A目次に戻る】

太陽の年齢を恒星進化論などから直接導くことは、まだ成功していません。地球の岩石における同位体比から地球が約46億年前にできたことが判明しており、さらに、初期太陽系が形成されてから微惑星が凝集して惑星になるまで数千万年しかかからないという理論的な計算結果があるので、太陽の年齢も46〜47億年だろうと推定されているだけです。ただし、この推定値は他の観測データと整合しているので、信頼して良いでしょう。
恒星進化論をもとに太陽の寿命や年齢を推定するためには、まず、
(1)他の恒星に関する観測データ
(2)恒星進化に関する物理学的な理論
の2つを組み合わせて恒星進化の一般論を作り、それに
(3)太陽に関する観測データ
を当てはめるという手順になります。
恒星に関する最も基本的なデータは、光度と温度を両軸とするヘルツシュプルング=ラッセル図(HR図)にまとめられます。天体が形成されるガス雲の化学組成はだいたい同じなので、各恒星がHR図のどこに位置するかは、質量と年齢という2つのパラメータで決まるはずです。そこで、質量をパラメータとする物理学的な恒星のモデルを作り、その進化過程が観測されたHR図のパターンと一致するように改良することによって、信頼できる恒星進化論を構築していきます。
恒星の進化は3つの段階に分類されます。
- 原始星 : ガス雲が収縮して天体を形成、急激な重力エネルギーの放出に伴って明るく輝いた後、複雑な過程を経て準平衡状態に到達する。力学的不安定性に起因するダイナミックな変化を示すため理論化が難しく、完全には解明されていない。この期間は全寿命の1%程度であり、通常は星の年齢に含まれない。
- 主系列星 : 準平衡状態を保ったまま、内部で水素の熱核融合が進行している状態。核反応式・状態方程式・光の発生吸収の式などを連立させて、質量と放出エネルギーの関係や光度の時間変化などの計算を行う。ただし、理論的な計算と観測データとは完全には一致せず、初期条件となる化学組成を変えてみるなど、部分的な手直しが必要。太陽と同じ質量の恒星は、主系列星として110億年を過ごすと推定される。
- 巨星化以降 : 熱核融合を起こしていた水素燃料がなくなると、星は主系列を離れて巨星へと進化していく。この過程は、理論的なモデルによって説明することができる。ヘリウムの燃焼が始まるといったん安定するが、すぐに燃料を消耗して急激に変化し、軽い星は白色矮星に、重い星は超新星爆発を起こして中性子星やブラックホールになる。太陽の場合、巨星化・赤色巨星の段階で13億年を過ごした後、1億年余を掛けて白色矮星に進化していく。
このような恒星進化論を太陽に当てはめる場合、他の恒星では得られない力学的パラメータなどの観測データと整合するかをチェックする必要があります。具体的には、主系列に達した段階を初期状態として、そこから47億年にわたる変化を恒星進化論を使って計算し、これが現在の状態と一致するかを見なければいけません。今のところ、初期の化学組成が未定パラメータとなっており、これを許容できる範囲で調節することによって、理論的に求めた半径や明るさが観測値と一致することが確認されています。ただし、太陽内部における核反応の状態を調べる手段となる太陽ニュートリノに関しては、観測された個数が理論的な予測よりもかなり少なくなっており、これをどのように解釈すべきか、いまだに議論が続いています(太陽内部の核反応は理論通りであり、地球に飛来するまでの間にニュートリノが変化するという説が有力です)。
より詳しくは、恒星進化(Stellar Evolution)について解説した教科書を参照してください。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
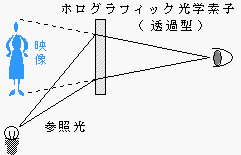 多少なりともこれに近い技術としては、ホログラフィック光学素子を使って立体映像を作り出すというものがあります(右図)。ただし、目と映像の間に光学素子を置くことが必要です。SF映画の古典『禁断の惑星』には、透明な半球状の装置の内側に立体映像を映し出すシーンがありますが、これなら近未来の技術で実現可能でしょう。
多少なりともこれに近い技術としては、ホログラフィック光学素子を使って立体映像を作り出すというものがあります(右図)。ただし、目と映像の間に光学素子を置くことが必要です。SF映画の古典『禁断の惑星』には、透明な半球状の装置の内側に立体映像を映し出すシーンがありますが、これなら近未来の技術で実現可能でしょう。