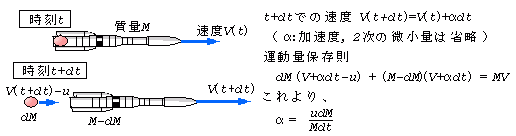ダーウィン以来の正統的な進化論によれば、生物の進化は、
変異と
選択という基本的なメカニズムによって引き起こされると考えられています。ただし、全ての進化論者が同意するのはここまでで、どのような要因が進化の方向を決定するのか、個々の種はいかなるプロセスを経て特定の表現型に到達するのか──といった点については、ごくわずかな例外を除いて、議論が決着を見ていません。「変異は主に紫外線などの外的要因に起因するのか、内的要因があるのか」「変異の多くは生存にとって不利か、あるいは中立か」「高等動物で外来遺伝子が大きな役割を果たすことがあるか」「進化の主流は漸進的か断続的か」「隔離された小集団の重要性はどの程度か、群淘汰は進化にとって本質的な役割を果たすか」「淘汰の単位は遺伝子、個体、種のいずれか」などの論点を巡って、多くの論客が議論を戦わせています。生物界はきわめて複雑な過程を経て膨大な多様性を獲得しており、ある生物種の示す性質が特定の学説を支持する実例なのか、偶然に生じた例外的ケースなのか、判断がつかないのです。もちろん、あらゆる現象を演繹的に説明できる学説などありません。
質問にある「キリンの長い首」は、進化は「小さな変化が長い年月にわたって積み重なって起きる」というダーウィンのオリジナルな学説では説明できない事例として知られています。首の長い現在のキリンの原型は200万年前の化石に見いだされていますが、第三紀中新世(1400〜2000万年前)にいた首の短い祖先とを結ぶ中間的な種は、発見されていません。おそらく、地質学的なスケールと比較してごく短い期間に小集団内部で変化が進行したと推測されます。さらに、この変化が自然淘汰を通じて選択されたというのも不合理です。仮に、ほんの少し首の長い個体が生まれたとしても、それだけでは高い木の葉っぱを食べられるわけでもなく、逆に脳貧血を起こしやすくなるため、生存上の利点はあまりないはずです。首の長い個体が優先的に子孫を増やしたとは考えられません。
キリンの場合、頸椎の個数は他の哺乳類と同じく7個であり、個々の椎骨が長くなることによって首の長さが増大しています(ちなみに、ジュラ紀に棲息していたクビナガリュウでは、頸椎の個数が40個もあり、キリンとは異なるプロセスを経て首が長くなったことを示しています)。推測するに、首を長くする変化の背後にあるのは、頸椎の骨形成を制御する遺伝子の変異に起因する頸椎の伸長傾向であり、これが、頸椎伸長に伴う生存上の不利益を打ち消す(主に血圧をコントロールするための)一連の遺伝的変化をプールしていた小集団で発現、急速に首が伸び始めたものの、際限のない伸長を止める身体的および環境的な淘汰圧が加わって、体高5mほどで安定したのでしょう。もっとも、こうした遺伝的変異がどのようにして生じたかは、全くわかっていません。近い将来、キリンの仲間である首の短いオカピ(キリン科の現存動物はキリン属キリンとオカピ属オカピだけです)とキリンのゲノム比較を通じて、遺伝的変異に関する具体的な知見が得られるはずですが、現時点では、多くが謎として残されています。
なお、サラブレッドのケースは、足が速くなる遺伝子セットを持つ個体を人為的に選択していった結果であり、犬や家畜と同様に、自然界ではあまり見られないほど大きな変化が短期間で実現されています。
【Q&A目次に戻る】

微小物体の温度を測定しようとする場合、通常の液体温度計などは使えません。対象と接触させるだけで、相手の温度を変化させてしまうからです。対象の温度を変えない温度計としては、次のようなものがあります。
- 放射温度計 : 対象に接触させずに放射電磁波のスペクトルを測定し、温度とスペクトルの関係を与える放射公式に当てはめて温度を求める温度計。顕微鏡と組み合わせて微小物体からの赤外線を計測することにより、10μm程度の物体の温度が測定できます。
- ナノ温度計 : 温度計自体が充分に小さく、接触させても対象の温度を変化させない温度計。実作されたものとしては、2002年に物質材料研究機構が開発した「カーボンナノ温度計」があります(Nature 415(2002)599)。これは、直径85nmのカーボンナノチューブに液体の金属ガリウムを注入したもので、ガリウム柱の長さが温度変化に対してほぼ線形に変化することを利用して、50〜1000℃程度の範囲で温度計測を行うことができます。具体的な応用はこれからですが、半導体回路の特定部分など1μm以下の対象の温度を測れると予想されます。
今後も、ナノテクノロジーが進展するにつれて、より小さい対象の温度を測定する技術が開発されてくるでしょう。ただし、文字通りのナノスケール(10億分の1メートル程度)では、統計的な量として定義される“温度”の物理的意味が曖昧になり、個々の分子のエネルギーのような非統計的な量の測定の方が重要になります。
【Q&A目次に戻る】

形式的には、n階微分をD
nという作用素と考え、関数D
nf をnについて解析接続すれば、微分の回数nが複素数に拡張されたものになります。例えば、t
mのn階微分は、次のように表されます:
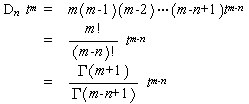
ただし、Γはガンマ関数で、整数の階乗を拡張した関数です。ここで、最終的な表式がnの連続関数に解析接続できるので、nが自然数以外の値νに拡張されたときの微分作用素を定義したことになっています。同様にして、指数関数など初等関数に対する微分作用素 D
νも
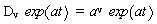
のように定義できます。
微分作用素は一般に線形なので、初等関数の多項式として表される関数の微分は、項別微分によって与えられます。しかるに、有限区間で無限回微分可能な任意関数は、初等関数だけを使った一様収束する級数によって表されるので、項別微分を使ってν階の微分を定義できることになります。積分は、微分の逆として定義されます。
このように、性質の良い関数ならば、任意の複素数νに対するν階微分を考えることが可能ですが、私の知る限り、応用はあまり効かないようです。物理数学の分野では、やはり演算回数が整数の微分・積分しか意味を持たないでしょう。
【Q&A目次に戻る】

調理する過程で食品を加熱するのは、主に、(1)食品に付着している微生物を殺す、(2)生体高分子を変性させて消化・吸収を容易にする──ためです(タンパク質がアミノ酸に分解されて美味しさが増すという副次的な効果もあります)。加圧調理は、圧力の物理的な作用によって、これと同様の効果を実現するものです。
高い圧力は、細胞構造を破壊することによって微生物に致死的な影響を与えます。具体的には、3000〜6000気圧で大半の細菌・カビ・酵母菌が死滅することが確認されています。また、生体高分子の構造が変化して化学反応度が変わるために、多くのウィルスも失活します。微生物の中には、ボツリヌス菌の耐熱性胞子のように、かなりの高温まで耐えられるものもあるので、加圧殺菌の方が加熱より効果的なケースもあります。
圧力による分子構造の変化は、熱に比べてかなり限定的なものです。10000気圧以下では、生体高分子の共有結合は破壊されず1次構造は変化しませんが、2次以上の(立体的な)構造が崩壊するため、化学的な反応性が変わります。例えば、自然状態では疎水基に守られて消化酵素で分解されないタンパク質も、圧力による構造変化で内側の部分が露出して消化しやすくなります。また、圧力に応じて酵素の働きが増減するので、加工段階で酵素反応の制御に利用されることもあります。
加圧調理は、加熱の場合と異なって食品の化学成分を変化させないので、栄養素の破壊や風味の変化が防げるというメリットがあり、ジャムの製造など一部の食品で実用化されています。ただし、殺菌に使うためには静水圧で数千気圧を加えなければならず、加熱に比べて技術的な難しさが伴い、必ずしも一般的な調理法にはなっていません。
(【参考文献】『食品加工の新技術』(木村・亀和田監修、CMC))
【Q&A目次に戻る】

物質を構成する基本粒子(物質粒子; 標準的な理論では大きさのない点粒子と考えられる)は、大きく分けて、グルーオンを介して強い相互作用を行うクォーク族と、行わないレプトン族に分類されます。クォーク族とレプトン族は、いずれも、(「uクォークとdクォーク」、「電子ニュートリノと電子」のように)電磁弱相互作用の二重項に相当する対を形成しており、さらに、こうした対が3つの“世代”(generation; 物理的な起源は不明)を形作っています。これを表にまとめると、次のようになります。
物質粒子の種類
| 第1世代 | 第2世代 | 第3世代 |
|---|
| クォーク族 |
u | c | t |
| d | s | b |
| レプトン族 |
νe | νμ | ντ |
| e | μ | τ |
ニュートリノはレプトン族に属する電気的に中性のフェルミ粒子(スピン1/2)で、-e(e:電気素量)の電荷を持つ荷電レプトンと対をなしています。「電子ニュートリノ(ν
e)」「ミューニュートリノ(ν
μ)」「タウニュートリノ(ν
τ)」とは、それぞれ電子(e)、ミュー粒子(μ)、タウ粒子(τ)と対をなすニュートリノです。例えば、ミューニュートリノが陽子や中性子に衝突すると、弱い相互作用によってミュー粒子が飛び出してきますが、電子やタウ粒子が飛び出すことはありません。
3つのニュートリノは、いずれも電気的に中性で、物質とは弱い相互作用を通じてのみ反応します(物質粒子と言われますが、固体などの構成要素にはなりません)。素粒子の標準理論では、ニュートリノの質量はゼロだと仮定されていますが、現在では、1998年に行われたスーパーカミオカンデ(岐阜県神岡に建造された素粒子観測装置カミオカンデの後継機)での観測結果などをもとに、きわめて小さな質量を持つことが確実視されています。まだ個々のニュートリノ質量の値は確定していませんが、スーパーカミオカンデのデータによると、最も重いと予想されるタウニュートリノで、
0.03〜0.1 eV (1 eV = 1.8×10
-36 kg)
程度になります。ニュートリノ以外では最も軽い物質粒子と考えられている電子の質量が51万eVですから、いかにニュートリノの質量が小さいかがわかります(この値では、宇宙論の分野で謎の質量源とされているダークマターにはなれません)。質量がきわめて小さいので、大半のニュートリノは、光速に近い速度で運動しています。これは、アインシュタインによるエネルギーと質量の関係式:
E = mc
2/(1-v
2/c
2)
1/2
より明らかでしょう。低エネルギーのニュートリノはゆっくり運動するはずですが、ニュートリノの場合、他の物質との反応のしやすさがエネルギーに比例するという法則があるため、エネルギーの小さいニュートリノは現実問題として観測できません。
ニュートリノは、弱い相互作用を含む素粒子反応によって生成されます。例えば、重い元素ほど原子核における中性子の比率が高いので、恒星内部で核融合反応が進行する際には、中性子数の帳尻を合わせるために、陽子の電子捕獲による中性子生成が行われます。このケースでの素過程は、
uクォーク + 電子 → dクォーク + 電子ニュートリノ
であり、生成された電子ニュートリノは、質量が小さいために重力で補足できず、宇宙空間に放出されます。この反応で太陽から放出される「太陽ニュートリノ」はエネルギーが小さいため、厳密な測定はかなり難しいようですが、これまでの観測を通じて、太陽ニュートリノの個数が理論値より大幅に少ないことが(ほぼ)判明しています。多くの物理学者は、この謎も、ニュートリノに質量があると仮定すれば解決できると考えています
(*)。
(*)正確に言えば、電子ニュートリノが空間を飛んでいる間にミューニュートリノに変化する「ニュートリノ振動」という現象が起きると仮定する。ニュートリノ振動が起きるためには、ニュートリノに質量がなければならない。
大質量の恒星が進化の最終段階で起こす超新星爆発の際にも、さまざまな核反応によって大量のニュートリノが生成されます。ニュートリノは重力で補足されたり他の物質に遮られることがないため、遠方の超新星から地球まで飛来することが可能です。1987年、大マゼラン星雲に現れた超新星1987A爆発の際に放出されたニュートリノは、カミオカンデで検出され、ニュートリノ天文学の幕開けとなりました。
人為的にニュートリノを作るにはいくつかの方法がありますが、最も簡単なのは、既存の原子炉内部に溜まっている核分裂生成物(死の灰)のβ崩壊を利用するものです(原子炉ニュートリノ)。β崩壊とは、次の素過程によって中性子が陽子に変化するものです。
dクォーク → uクォーク + 電子 + 反電子ニュートリノ
現在、カムランド(スーパーカミオカンデの近くに建造された観測装置)で、敦賀や美浜の原発から飛来する反電子ニュートリノの測定が行われています。
【Q&A目次に戻る】

南米のオリノコ川やアマゾン川に棲息するデンキウナギは、シビレエイやデンキナマズなどとともに強電気魚と呼ばれ、体の後部にある電気器官を使ってパルス状の電圧を発生し、獲物を捕獲するのに利用しています。
デンキウナギが持つ電気器官は、電気板ないし電函と呼ばれる多核の発電細胞が積み重なったものです。生物の細胞膜には、特定のイオンを能動的に通過させるイオンチャネルが存在しており、膜をはさんで数十mVの電位差を生み出すことができます。強電気魚の発電細胞の場合、静止時には細胞の内外で-85mVの電位差が生じていますが、細胞全体で見ると電位差はありません。
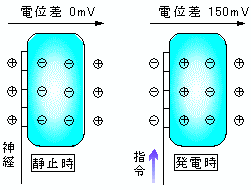
しかし、細胞の片側の膜にシナプス結合している神経から指令が伝えられると、そちら側だけイオンチャネルの状態が変化してプラスのナトリウムイオンが流入、+65mVの活動電位が生じ、全体で150mVの電位差になります(右図)。デンキウナギの場合、発電細胞が4000〜5000個も直列に並んでいるため、全体で600〜800V程度の電圧(頭側がプラス)を発生させることができます。
デンキウナギの電気器官は、心臓などの重要器官のない体の後部に位置し、絶縁性の高い結合組織で覆われているため、自分自身にダメージを与えることはありません。電流は、電気器官の中軸を通り、両端の抵抗の小さい体側部分から体外に流れ出します。
【Q&A目次に戻る】

気化爆弾とは、落下中に液体燃料(燃焼剤)を空気中に放出し、適当な混合比になったところで点火して大爆発を起こさせる爆弾です。TNT火薬を用いた爆弾に比べて数倍の爆発力があると言われ、衝撃波と熱で多数の人間を一瞬のうちに殺傷することができます。
通常の弾頭に大量の燃料を詰め込んでも、そのエネルギーを全て爆発力に変えることは困難です。燃料の密度や形状によって反応の仕方にばらつきが生じ、早く進行した一部の反応によって他の燃料が吹き飛ばされてしまうからです。しかし、燃料を気化させて最適な条件が整ったところで点火すると、拡がった燃料が一斉に化学反応を起こすため、瞬間的に高温・高圧状態を実現することができます(粉塵状態の固体燃料をばらまいて点火しても、同様の効果が得られます)。この結果、きわめて強力な(圧力が高く持続時間の長い)衝撃波が発生、爆心地ではクレーターが形成されて地下壕も破壊され、衝撃は数キロ先まで届くそうです。また、広範囲にわたって1000度以上の高温状態を作りだし、遮蔽物に隠れている人も容赦なく焼き殺します。気化爆弾の殺傷力は、この衝撃波と熱によるものです(一部の資料に「無酸素状態を作り出して生物を窒息させる」とありますが、高温になると上昇気流が生じて周辺の空気が流入するので、酸欠によって窒息することはないと思います)。
【Q&A目次に戻る】

数億光年以遠の天体の場合、距離を直接測定することは不可能であり、スペクトルの赤方偏移の値(ドップラー効果による波長の伸びの割合)をもとに計算されます。ただし、この計算は、宇宙全体がどのように膨張しているかを記述するモデルに依存しており、膨張は加速しているか、ハッブル定数としてはどの値を使っているか──などによって答えが変わってきます。例えば、「100億年前に発せられた光」が観測されたとしても、光源から地球までの間の空間が膨張しているのですから、単純に「100億年前に100億光年彼方にあった」とは言えないのであり、いつどこにあったかは、モデルごとに違った結果となります。
特に、地球から見て膨張速度が光速度となる“宇宙の地平線”近くの天体になると、単純な直観は通用しません。実際、地平線のすぐそばでは地球から見たときの光速がきわめて遅くなり、光がゆっくりと進むので、「距離=時間×c」という関係式は成り立たなくなります(同様の現象は、ブラックホールの周囲にある“事象の地平線”付近でも見られます)。このため、赤方偏移の値が6以上になる遠方の天体に関しては、発表された天文学的なデータが何を意味しているのか、論文をきちんと読んで把握しなければなりません。少し前に、ハワイ大学の研究チームが「153億年前の銀河を発見した」という報告がありましたが、この数値は加速膨張モデルに基づいて光が発せられた時期を推定したものであり、その時点での天体は153億光年よりずっと地球に近く、また、光速に近いスピードで遠ざかっているので、現時点では、153億光年より遠い所にあるはずです。具体的な距離を求めるには、一般相対論を用いた計算が必要になります。
【Q&A目次に戻る】

物体が等加速度運動をする場合、運動エネルギーは速度の2乗に比例して増加するので、等加速度を維持するためには、供給すべきエネルギーもどんどんと増やしていかなければなりません。しかし、これをロケットに当てはめると、確かに奇妙な感じがします。常に一定の強さで噴射をしているのですから、増加する運動エネルギーは一定のはずです。しかし、加速度の変化は加速度計を使って測定可能なので、ロケットの速度に応じて加速度が変わるとすると、“絶対速度”を検出できることになってしまいます。
このパラドクスを解くカギは、ロケットが質量を放出して、その反動で加速しているという点にあります。常に一定の割合で質量を後方に噴射しているロケットを考えます。時刻tにおけるロケットの質量をM(t)、速度をV(t)とします。放出される質量の(放出直後における)相対速度をu(=一定)とすると、運動量保存則より、次のようにしてロケットの加速度が求められます。
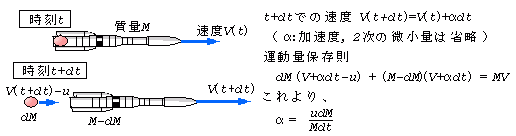
これより、dM/dt(=単位時間に放出される質量)が一定で、考えている間のMの変化が無視できる場合、加速度は一定値になることがわかります。
一定の相対速度でコンスタントに質量を放出しているのですから、化学燃料の燃焼によって運動エネルギーに転換する化学エネルギーは一定のはずです。それなのに、なぜロケットが等加速度運動できるかというと、放出される質量の運動エネルギー変化が、ロケットの速度によって異なるからです。単位時間に増加する全運動エネルギーは、一定の値(Mαu/2)ですが、これは、ロケット本体と後ろに残される質量を併せた物体に関する値です。放出される質量だけに着目すると、Vがuより大きい場合は、放出前よりも運動エネルギーが減少しており、その分だけ、ロケットの運動エネルギーに加算されることになります。高速になるほどロケット本体は大きな運動エネルギーを獲得します。こうして、燃料から発生する運動エネルギーが一定であるにもかかわらず、等加速度運動を持続することができるのです。
実は、この現象は、ニュートン力学の本質に関わっています。運動方程式は、速度に一定の値を加えても同じように成り立つので、ニュートン力学では、絶対静止や絶対速度という概念を定義することができません。これを、“ガリレオの相対性原理”と言います。周囲に天体が全くない状況下でロケットを噴射させたとき、加速度計を使って真空に対する絶対速度が検出されたとすると、ニュートン力学そのものが破綻したことになってしまうのです。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
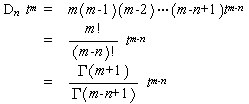
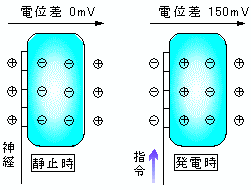 しかし、細胞の片側の膜にシナプス結合している神経から指令が伝えられると、そちら側だけイオンチャネルの状態が変化してプラスのナトリウムイオンが流入、+65mVの活動電位が生じ、全体で150mVの電位差になります(右図)。デンキウナギの場合、発電細胞が4000〜5000個も直列に並んでいるため、全体で600〜800V程度の電圧(頭側がプラス)を発生させることができます。
しかし、細胞の片側の膜にシナプス結合している神経から指令が伝えられると、そちら側だけイオンチャネルの状態が変化してプラスのナトリウムイオンが流入、+65mVの活動電位が生じ、全体で150mVの電位差になります(右図)。デンキウナギの場合、発電細胞が4000〜5000個も直列に並んでいるため、全体で600〜800V程度の電圧(頭側がプラス)を発生させることができます。