
原子(あるいは分子)に紫外線やX線を照射したときに電子が光子を吸収して飛び出すという光電効果は、現在では、原子構造を解明する手段となる「光電子分光法」に応用されています。孤立原子や物質表面の原子の場合、原子から飛び出してくる光電子は、他の原子と相互作用することがないので、そのエネルギーE は、照射される紫外線・X線の振動数をνとすると、
E = hν - I
となります。ただし、I は、電子が原子に束縛されているときの結合エネルギーです。
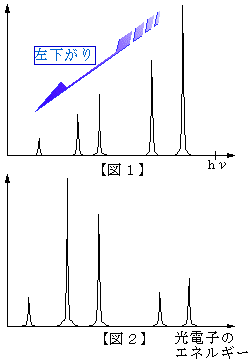
X線の波長は、原子と同程度(軟X線で数オングストローム以上)なので、イメージとしては、原子全体を揺さぶるような相互作用となり、結合エネルギーの小さい外側の電子ほど弾き出されやすいように思えるかもしれません。そうだとすると、横軸に光電子のエネルギー、縦軸に電子のカウント数を取ってプロットした場合、図1のようになるはずです。しかし、実際には、「結合エネルギーがhν以下」という条件を満たすならば、内殻の電子もかなりの割合で飛び出していきます。さまざまな原子(あるいは分子)に対する光電子分光実験のデータを見ると、図2のようなグラフの方が一般的です。
この現象は、エネルギーと運動量の保存則を使って定性的に説明できます。光電子の運動量をpとし、非相対論の近似が使える(p≪mc)とします(軟X線〜紫外線の範囲では妥当します)。c=1 という単位系を用いると、光子ではエネルギーと運動量が同じ値(hν)になるのに対して、質量を持つ粒子では、運動量pよりもエネルギー(p
2/2m)がきわめて小さいというアンバランスさがあるため、エネルギー・運動量の保存則を破らずに自由粒子が光子を吸収することはできません。ところが、光電効果の場合は、少し事情が異なります。静止している原子に1光子が吸収されて光電子と反跳イオンになるとすると、エネルギー保存則は、
hν − I = p
2/2m + P
2/2M
となります(P,Mはイオンの運動量と質量;ただし、相当に粗っぽい近似です)。この式からわかるように、運動量保存則によってpまたはPがhν/cと同じオーダーだったとしても、hν〜Iならば、(右辺がhνよりきわめて小さいにもかかわらず)エネルギー保存則を満たすことができます。従って、非相対論近似が成り立つ範囲では、結合エネルギーがhνに近い内殻電子だけが光電子として飛び出すことができるのです。
この傾向は、hνが大きくなって光電子が相対論的なエネルギーを持つようになっても継続します。金属原子を用いた実験では、hν〜mc
2程度の硬X線による光電効果において、光電子の約80%が最低束縛状態から弾き出されたものです。
もう少しきちんと計算するには、量子力学の摂動論を援用する必要があります。光電効果の遷移確率Wは、
W ∝ |<Ψ
f|
e・p|Ψ
i>|
2δ(E
f−E
i−hν)
で与えられます。ただし、
eは入射光子の偏光の向き、
pは電子の運動量演算子です。外殻電子と内殻電子の遷移確率の差異は、この計算において、主に、エネルギー・運動量保存則によって制限される積分領域の大きさの違いとして現れます。近年、こうした計算は、いくつかの原子・分子に関してコンピュータを使って数値的に遂行されており、実験結果とかなり一致することが判明しています。
【Q&A目次に戻る】

トルマリン(電気石)とは、化学組成
WX
3B
3Al
3(AlSi
2O
9)
3(O,OH,F)
4
(W=Na,Ca X=Al,Fe
III,Li,Mg)
を持つ六方晶系異極像鉱物の総称です(『岩波理化学辞典』より)。最近、「マイナスイオンを発生する健康グッズ」としてトルマリンがブームになっているようですが、いくつか誤解があるようですので、ここで指摘しておきます。
トルマリンが圧電性・焦電性を持っており、加圧・加熱すると表面に電荷が現れることは、19世紀以来知られています。この性質を利用して、圧力センサー・温度センサーとしても利用されています。ただし、放射性物質のように内部にエネルギー源があるわけではないので、持続的にマイナスイオンを作り出す効果はありません(加圧した状態で両極を接続すると微弱電流が流れますが、これは、仕事の形でエネルギーを供給したためです)。エネルギーの供給がなければ、電気分極を生じているとは言っても、静電気によって空気中の埃を吸着する程度です。また、トルマリンを使った健康グッズのカタログの中には、遠赤外線を放射すると謳っているものもありますが、トルマリン自体が熱を発生することはなく、他の鉱物と同様の熱放射(温度に応じた赤外線の放射)以外の何かがあるとは考えられません。
【Q&A目次に戻る】

温度は、巨視的物理系の内部エネルギーが各自由度にどのように割り振られるかを定める指標です。例えば、温度Tの理想気体の場合、ある分子がエネルギーE
nを持つ確率は、exp(-E
n/T) に比例することが知られています。有限自由度の物理系に限りなくエネルギーを与えられるとすれば、各自由度に対して際限なく大きなエネルギーを割り当てなければならないので、温度も無限に上昇することになります(高温プラズマなどでは、粒子の運動エネルギーは、相対論的な値:
mc
2/(1-(v/c)
2))
1/2
になり、粒子の平均速度が光速に近づくと、エネルギーも温度も無限大に発散します)。
ただし、実際に物理系をバラバラにせずにエネルギーを供給し続けるのは、かなり困難です。巨大星における重力閉じ込めでも、せいぜい数十億度までしか上昇させられません。宇宙において温度が限りなく上昇するのは、ビッグバンの瞬間へと時間を遡っていく場合だけでしょう。このとき、実際にどこまで温度が上がるのか(あるいは温度という物理量がどこまで意味を持ち続けるか)については、あまりよくわかっていません。
物質の状態は、超高温になるにつれて大きく変化します。大統一理論によると、素粒子が慣性質量を持っているのは、空間の至る所に凝縮しているヒッグス粒子が他の素粒子を動きにくくしたためだとされますが、10
32度以上になると、凝縮していたヒッグス粒子が“蒸発”してしまうため、全ての素粒子は質量がゼロになって光速で飛び回るようになります。こうした状態に対しては、相対論的な効果を取り入れた熱力学を適用しなければなりません。
【Q&A目次に戻る】

量子力学は、しばしば古典的な世界観を根底から覆したと主張されますが、正確に言えば、ニュートンの力学やマックスウェルの電磁気学などの古典物理学的な世界観をひっくり返したのであって、必ずしも、われわれの日常的な世界観と直接的に違背するというわけではないのです。
例えば、量子力学の対象は、不確定性関係によって、正確な位置と運動量を同時に持ち得ないことが要請されており、位置と運動量の正確な値に基づいて運動を記述するニュートン力学の対象とは本質的に異なっています。しかし、われわれの日常的な認識は、物体が正確な位置や運動量を持っていないと、基礎がぐらつくようなものでしょうか。たとえ1000万分の1ミリでも不確定性があると世界の描像が整合的でなくなるというのは、全世界を統一的な方法論で記述しようとする(主に科学の)分野に限った話であって、日常的認識においては、把握しきれない不確定さがあることを、むしろ当然と感じているのではないかと思われます。
量子力学的な非因果性についても、同様なことが言えるでしょう。20世紀初頭までの古典物理学は、「初期条件が与えられると、それ以降の時間変化が全て確定する」という因果律を理論の基礎に据えていますが、量子力学は、どのような変化が起きるかを完全に予知することは原理的に不可能だという非因果性を主張します。これは、ニュートン的な世界観を信奉する者にとっては一大事ですが、日常的な生活世界では、逆に、「宇宙開闢の瞬間にきょうの夕食に何を食べるかまでが決まっている」という古典力学の方が、不気味に感じられるはずです。
そもそも、私たちの日常的な世界観は、日々の生活を送るのに必要な範囲でしか整備されていないのであって、世界の本質を解明しようとして細部に至るまでの厳格さを要求するものではありません。固体がなぜ潰れずに一定の大きさを保っていられるか、金属を熱するとなぜ低温では赤く高温では白く輝くのか、はるか彼方にある星の光をなぜ人間の眼は捉えることができるのか──量子力学の登場によって初めて解かれたこれらの謎は、科学者にとっては重大な懸案だったものの、一般市民にとっては、端から謎とは言えないでしょう。近代科学は、こうした“杜撰な”世界知を数学の力で厳密な理論体系に置き換えようとしたものですが、その際、日常的には想定されていないようなさまざまな仮定を、科学の中に持ち込んでしまいました。「ある質点の位置は連続性を持つ実数体の1点で与えられる」とか「物理法則は(因果律の元になる)コーシー条件を満たすような微分方程式のセットで記述される」といった古典物理学の要請は、日常的な世界観からはるかに隔たった極端な仮定であり、これが量子力学と矛盾するとしても、われわれの生活には何の影響もないわけです。
【Q&A目次に戻る】

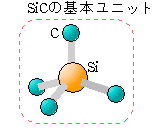
SiC(シリコンカーバイド、炭化ケイ素)には、170種類以上とも言われる数多くの多形(ポリタイプ)が存在することが知られています。どの結晶でも、基本構造となるのは、あるシリコン原子は4個の炭素原子に、ある炭素原子は4個のシリコン原子に取り囲まれるという四面体のユニットです。このユニットは、孤立炭素原子の2s2p軌道、あるいは、孤立シリコン原子の3s3p軌道が結晶中で混じり合ってsp
3混成軌道を形成したことによって作られるもので、最近接原子との原子間隔がほぼ1.89Aに固定された堅い共有結合で結ばれています。SiCに見られる結晶の多形は、この四面体ユニットをどのように積み上げていくかに応じて生じています。
結晶構造は、炭素とシリコンの二重層が積み重なった形になっていますが、この層に垂直な方向から見て、ある層と次の層の原子が反転した配列になっているのが3C-SiCあるいはβ-SiCと呼ばれるダイヤモンド構造の立方晶で、同じ配列になっているのが2H-SiCという六方晶です。このほかにも、二重層の重なり方によって、さまざまな結晶構造のタイプがあり、これらは2H-SiCと併せてα-SiCと総称されています。
SiCの各タイプは自由エネルギーの極小値に対応する準安定な構造になっていますが、タイプ間での自由エネルギーの差は小さく、温度や圧力が変わると最も安定な構造も異なったものになります。例えば、シリコン粉末と黒鉛を混ぜて加熱した場合、1400℃以下では2H-SiCが生成されやすいのですが、高温になるにつれて、3C(1500〜1800℃),4H(2000℃付近),6H(2000℃以上)などが生じやすくなります。
【参考文献】宗宮重行編『炭化珪素セラミックス』(内田老鶴圃、1988)
【Q&A目次に戻る】

エンタングル(ド)状態(もつれ合った状態; entangled state)とは、相互作用している2つ(以上)の量子系A,Bを併せた全体の波動関数が、個々の系の固有状態を表す波動関数の積で展開されることを意味します:
Σc
n ψ
n(A) φ
n(B)
AとBの間の相互作用が強いと、
ΣC
n Ψ
n(A+B)
というように各系の固有状態からずれた波動関数でしか展開できないので、エンタングル状態が実現されるのは、2つの系の相互作用が何らかの形でスイッチオフされる場合に限られます。こうしたケースに相当するものとして最初に提唱されたのが、1935年にアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼンが考案した2粒子ペアの状態でした。ただし、このペアでは相互作用が完全にスイッチオフされておらず、エンタングル状態の議論としては、やや不備があります。その後、アインシュタインによって、はじめに相互作用していた系が2つに分かれて空間的に遠く隔たるという形で再定式化されたのに従い、現在では、空間的に分離された2つの系がエンタングル状態を構成するとき、これをEPRペアと呼んでいます。EPRペアは、一般に、異なる基底による二重展開:
Σc
n ψ
n(A) φ
n(B) = Σd
j f
j(A) g
j(B)
が可能であり、そのことを利用して、量子テレポーテーションやセキュアな量子通信を実現できると考えられています。
EPRペア以外のエンタングル状態としては、空間的には充分に分離されていないものの、相互作用が小さく、全体の波動関数が個々の固有状態の積で表されるケースがあり、量子コンピュータに利用される量子ドットの状態が、その具体例になっています。リソグラフィの手法で半導体基板上に100ナノメートルほどの間隔で整然と並ぶ小さな窪みを作り、そこに10ナノメートル程度の金属や半導体の微小な球を形成すると、個々の球の電子状態は、孤立系と同様の鋭い関数で表されるはずです。こうした球を量子ドットと呼び、1つの量子ドットの状態──例えば、スピンアップとスピンダウンの状態──を|1>と|0>と表すことにすると、多数の量子ドットの固有状態は、
|0>|1>|0>|1>|1>|1>...
のような各固有状態の積で表されるはずです。従って、量子ドット以外の状態関数を完全にファクターアウトできれば、これは一種のエンタングル状態になっているわけです。量子コンピュータは、ある固有状態から別の固有状態への遷移を1つの演算として実現するものです。
【Q&A目次に戻る】

現在、自動車の動力源や携帯機器用電源として開発が急がれている燃料電池は、パーフルオロスルホン酸系ポリマ製の高分子固体電解質膜や、ナノテクノロジを駆使して加工した電極を使用する最先端技術の固まりですが、1839年にウィリアム・グローブが考案した燃料電池の原型は、
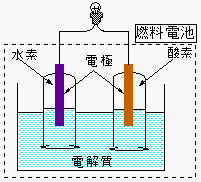
右図のような実験室で手作りできる素朴なもの──実際に行われた実験では、この燃料電池を4台直列につなぎ、水の電気分解を行う装置に接続したそうです──であり、同じものを家庭で制作することも不可能ではありません。
グローブの燃料電池は、電解質(イオンを通すが電子を通さない物質)として希硫酸を、電極として白金を用いるものでしたが、水素のイオン化が起きるアノード(電池としてはマイナス極)の面積が小さく、あまりパワーは出ませんでした。その後、電極として白金黒(白金の微粒子から成り黒く見える物質)を用いるなどして反応面積を大きくし、出力を増大していったという経緯があります。また、アノードに白金やパラジウムなどの触媒作用を持つ素材を使うと、電極反応が促進されることもわかっています。燃料電池を自作する場合にも、電極素材の選択が鍵になると思われます。
私自身は燃料電池を作ったという経験がないので、インターネットで「燃料電池+教材」ないし「燃料電池+自作」で検索してみたところ、多くの自作例が見いだされました。それによると、アノードの素材としては、次のようなものが使われていました(カソードは炭素棒やステンレス金網で充分なようです)。
- 炭素棒またはステンレス金網(出力は小さい)
- 目の細かいステンレス/ニッケル金網にパラジウムメッキを施したもの
- 白金箔を塩ビ板に糊付けしたもの
- 備長炭
塩化パラジウム粉末や白金箔は実験教材などの専門店で購入することができますが、かなり高価なので、家庭で自作するのには不向きかもしれません(塩化パラジウムを使って金網にメッキするのも一苦労でしょう)。備長炭を電極に用いたという報告は1例だけでしたが、小型モータが10分以上動いたとあり、これが本当ならば燃料電池の自作に最適と思われます。
なお、電解質としては、簡単に入手できることもあって、希薄な水酸化ナトリウム溶液(苛性ソーダ)が多く用いられています(変な化学反応を起こさないものならば、これ以外の溶液も使えるはずです)。また、電極反応の元になる水素や酸素は、ボンベから直接供給することもできますが、まず電極間に電池を接続して水の電気分解で水素・酸素を作り出し、その後にモータなどに接続を変えるという方法もあります。
【Q&A目次に戻る】

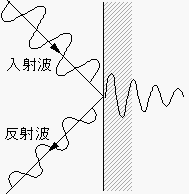
電磁気学の教科書などでは、右のような図に基づいて、入射波と反射波のエネルギーの差が物質に吸収されるエネルギーになることを説明していると思います。こうした理想的なケースでは、照射された電磁波のうち、反射波以外は全て物質内部に進入し、そこで全て熱エネルギーに変換されてしまいます。しかし、現実には、物質の幅は有限なので、充分に減衰されないうちに端に達して、電磁波のまま透過していく透過波の項を考えなければなりません。さらに、物質に当たらずに素通りしてしまう電磁波もあります。
誘電体に振動数νの電磁波が進入したときのエネルギー損失P は、複素誘電率
ε=ε′+iε″
を使うと、
P = 2πν<E
2>ε″
で与えられます(ただし、<E
2>は、電界強度の2乗の時間平均で、透磁率の虚数部分に起因する磁気的損失は無視しました)。物質によるエネルギー損失の違いはε″の差に起因しているので、ε″を損失係数と呼ぶことがあります。物質に進入した電磁波は、dx進む間にPdxのエネルギーを失います。Pはエネルギー密度に比例しているので、表面からの進入距離に対してエネルギー密度は指数関数的に減少することがわかります。特に、エネルギー密度が半減する電力半減深度は、電磁波が物質を透過するかどうかの目安になります。
電子レンジで使われる2450MHzのマイクロ波は、水分子の電気的モーメントを効果的に回転させるため、常温の水で損失係数が特に大きく、電力半減深度が小さくなっています。いくつかの物質での半減深度を、表で示しましょう:
| 半減深度 |
| 空気 | 実質的に∞ |
| 氷・磁器 | 数メートル |
| 紙・塩ビ・木材 | 50cm程度 |
| 水 | 1〜4cm(温度により異なる) |
| 食塩水 | 0.3〜1cm |
電磁波を照射する物質の厚さがこの値以下だと、(反射波を別にして)照射エネルギーの過半が物質を加熱せずに透過してしまいます。
ただし、電子レンジの場合は、透過波も無駄にしないように、庫内が金属の内壁で覆われており、壁に反射されたマイクロ波が繰り返し食品を通過するようになっています。このため、照射した電磁波のエネルギーのうち加熱に使われる割合は(反射損失などがあるため100%ではないものの)かなり高いとされます(具体的な値は、食品の種類・形状によって異なります)。
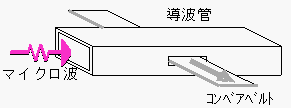
導波管などを使って物質を加熱するケース(右図)では、反射や透過などによる損失が相当に大きくなります。標的を加熱せずに通り抜けてしまった電磁波は、外部に漏出して他の物質を加熱しないように、終端に置かれた水などに吸収させなければなりません。この分のエネルギーは全く無駄になるので、導波管内の電界分布を調整するなどして、加熱効率を高める工夫が必要です。
【Q&A目次に戻る】

指紋の詳細パターンは、胎児段階での偶発的要素が作用して決定されるものなので、一卵性双生児(あるいはクローン)といえども同一ではありませんが、蹄状紋・渦状紋などの大まかなパターンに関しては、遺伝的な要素が強く働いており、その出現頻度は民族によってほぼ決まっています。例えば、蹄状紋は、白人に多く黄色人に少ないというデータがあります。
指紋の頻度に関するデータは、犯罪捜査に役立つことから、主に警察によって収集されており、アカデミックな文献で公表されることはあまりないようです。少し古いデータになりますが、岡田鎮著『指紋』(令文社、1958)には、大場茂馬が市ヶ谷監獄の全囚人を対象として行った調査の結果として、次のような数値が上げられていました(指先欠損などのケースがあるので、総和は100%にならない):
| 弓状紋 | 1.81% |
| 蹄状紋(甲種(*)) | 3.84% |
| 蹄状紋(乙種) | 48.92% |
| 渦状紋 | 45.16% |
(*)隆線が拇指側から拇指側へ流れるもの。逆が乙種。
犯罪性向のある人に偏っている可能性もありますが、日本人の指紋の頻度をほぼ正確に表していると思われます。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
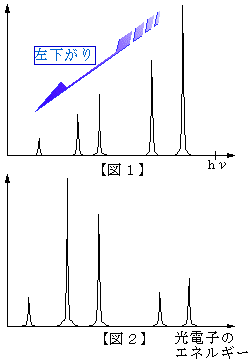 X線の波長は、原子と同程度(軟X線で数オングストローム以上)なので、イメージとしては、原子全体を揺さぶるような相互作用となり、結合エネルギーの小さい外側の電子ほど弾き出されやすいように思えるかもしれません。そうだとすると、横軸に光電子のエネルギー、縦軸に電子のカウント数を取ってプロットした場合、図1のようになるはずです。しかし、実際には、「結合エネルギーがhν以下」という条件を満たすならば、内殻の電子もかなりの割合で飛び出していきます。さまざまな原子(あるいは分子)に対する光電子分光実験のデータを見ると、図2のようなグラフの方が一般的です。
X線の波長は、原子と同程度(軟X線で数オングストローム以上)なので、イメージとしては、原子全体を揺さぶるような相互作用となり、結合エネルギーの小さい外側の電子ほど弾き出されやすいように思えるかもしれません。そうだとすると、横軸に光電子のエネルギー、縦軸に電子のカウント数を取ってプロットした場合、図1のようになるはずです。しかし、実際には、「結合エネルギーがhν以下」という条件を満たすならば、内殻の電子もかなりの割合で飛び出していきます。さまざまな原子(あるいは分子)に対する光電子分光実験のデータを見ると、図2のようなグラフの方が一般的です。
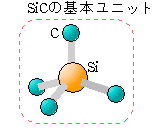 SiC(シリコンカーバイド、炭化ケイ素)には、170種類以上とも言われる数多くの多形(ポリタイプ)が存在することが知られています。どの結晶でも、基本構造となるのは、あるシリコン原子は4個の炭素原子に、ある炭素原子は4個のシリコン原子に取り囲まれるという四面体のユニットです。このユニットは、孤立炭素原子の2s2p軌道、あるいは、孤立シリコン原子の3s3p軌道が結晶中で混じり合ってsp3混成軌道を形成したことによって作られるもので、最近接原子との原子間隔がほぼ1.89Aに固定された堅い共有結合で結ばれています。SiCに見られる結晶の多形は、この四面体ユニットをどのように積み上げていくかに応じて生じています。
SiC(シリコンカーバイド、炭化ケイ素)には、170種類以上とも言われる数多くの多形(ポリタイプ)が存在することが知られています。どの結晶でも、基本構造となるのは、あるシリコン原子は4個の炭素原子に、ある炭素原子は4個のシリコン原子に取り囲まれるという四面体のユニットです。このユニットは、孤立炭素原子の2s2p軌道、あるいは、孤立シリコン原子の3s3p軌道が結晶中で混じり合ってsp3混成軌道を形成したことによって作られるもので、最近接原子との原子間隔がほぼ1.89Aに固定された堅い共有結合で結ばれています。SiCに見られる結晶の多形は、この四面体ユニットをどのように積み上げていくかに応じて生じています。
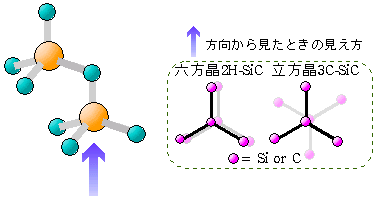
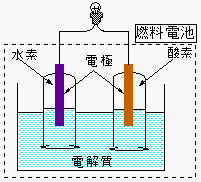 右図のような実験室で手作りできる素朴なもの──実際に行われた実験では、この燃料電池を4台直列につなぎ、水の電気分解を行う装置に接続したそうです──であり、同じものを家庭で制作することも不可能ではありません。
右図のような実験室で手作りできる素朴なもの──実際に行われた実験では、この燃料電池を4台直列につなぎ、水の電気分解を行う装置に接続したそうです──であり、同じものを家庭で制作することも不可能ではありません。
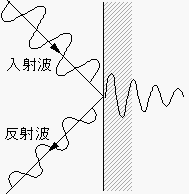 電磁気学の教科書などでは、右のような図に基づいて、入射波と反射波のエネルギーの差が物質に吸収されるエネルギーになることを説明していると思います。こうした理想的なケースでは、照射された電磁波のうち、反射波以外は全て物質内部に進入し、そこで全て熱エネルギーに変換されてしまいます。しかし、現実には、物質の幅は有限なので、充分に減衰されないうちに端に達して、電磁波のまま透過していく透過波の項を考えなければなりません。さらに、物質に当たらずに素通りしてしまう電磁波もあります。
電磁気学の教科書などでは、右のような図に基づいて、入射波と反射波のエネルギーの差が物質に吸収されるエネルギーになることを説明していると思います。こうした理想的なケースでは、照射された電磁波のうち、反射波以外は全て物質内部に進入し、そこで全て熱エネルギーに変換されてしまいます。しかし、現実には、物質の幅は有限なので、充分に減衰されないうちに端に達して、電磁波のまま透過していく透過波の項を考えなければなりません。さらに、物質に当たらずに素通りしてしまう電磁波もあります。
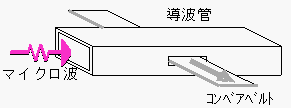 導波管などを使って物質を加熱するケース(右図)では、反射や透過などによる損失が相当に大きくなります。標的を加熱せずに通り抜けてしまった電磁波は、外部に漏出して他の物質を加熱しないように、終端に置かれた水などに吸収させなければなりません。この分のエネルギーは全く無駄になるので、導波管内の電界分布を調整するなどして、加熱効率を高める工夫が必要です。
導波管などを使って物質を加熱するケース(右図)では、反射や透過などによる損失が相当に大きくなります。標的を加熱せずに通り抜けてしまった電磁波は、外部に漏出して他の物質を加熱しないように、終端に置かれた水などに吸収させなければなりません。この分のエネルギーは全く無駄になるので、導波管内の電界分布を調整するなどして、加熱効率を高める工夫が必要です。