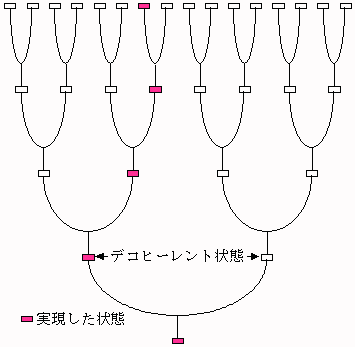「猫を殺す実験」とは、量子力学の建設者の一人であるシュレディンガーが、『量子力学の現状』(1935)と題した論文の中で論じた有名な思考実験で、これをどのように解釈するかは、量子力学の根幹に関わる重要な問題だと考えられています。
はじめに、量子力学について、簡単に説明しておきます。
量子力学では、対象とする物理的なシステムの状態は、状態関数(波動関数とも言う)Ψで表されます。この関数には、(微視的な原子の結合状態から巨視的な物体の運動まで含めて)物理学的に観測可能なすべての状態に関する情報を含めることができると考えられています。ある時刻 t
0の状態がΨ
0であるシステムが、別の時刻 tにどのような状態になっているかは、量子力学の基礎方程式であるシュレディンガー方程式を使って、完全に計算されます。
問題は、こうして計算された時刻 tの状態Ψが、一般に、
「物理的に区別できる」状態の重ね合わせになっているという点です。例えば、放射性原子核が、はじめにΨ
0という状態にあったとして、1時間後の状態を計算すると、放射性崩壊を起こしている状態Ψ
1と起こしていない状態Ψ
2の和になっているのです。式で書くと、
Ψ
0→c
1Ψ
1+c
2Ψ
2
となります(“+”は、関数同士の和を表しますが、詳しいことは省きます)。Ψ
1とΨ
2という2つの状態の(関数論に基づく数学的な意味での)“重み”は、それぞれ
|c
1|
2 と |c
2|
2 で与えられます。
こうした状況を具体的にイメージする手がかりとして、シュレディンガーは、次のような思考実験の行いました。箱の中に、生きた猫と青酸ガスの入ったビンを入れておきます。別に、適当な放射性原子核を用意し、これが放射性崩壊を起こしたかどうかはガイガー計数管で測定できるようにします。さて、ガイガー計数管が放射性崩壊を感知した場合には、一連の装置が作動して、ハンマーで青酸ガス入りのビンを割るようにしておいたとき、一定時間の後に猫はどのような状態になるか、というのがシュレディンガーの出した問いです。特に、放射性原子核が崩壊している状態と崩壊していない状態の重みが等しいケースでは、猫が死んでいる状態と生きている状態の重みも等しくなるはずです(下図)。このとき、箱の中の猫は、いったい生きているのか死んでいるのか、どちらなのでしょう?
「シュレディンガーの猫」の生死に関しては、大きく分けて、2つの解釈があります。
- 猫の状態は、実際に生きている状態と死んでいる状態の和であり、生きていると同時に死んでいる。
- 猫の状態は、生きているか死んでいるかのどちらかである。シュレディンガー方程式から求められた“重み”は、それぞれの状態が実現される確率を表している。
前者のいささか「超越的な」解釈は、1957年のエヴァレットの論文に始まるもので、猫が生きている世界と死んでいる世界が、同じ時空間内部に併存するというSF的な「多世界解釈」です。この考え方は、ド・ウィットやウィーラーといった“大物”物理学者に支持されたこともあって、一時期はかなり関心を集めました。しかし、事が猫の生死にとどまらず、「第二次大戦でヒトラーが勝利した世界」や「ナポレオンが子供の頃に事故死した世界」など、さまざまなパラレル・ワールドを認めなければならないことから、あまりに非現実的だとして、最近は人気がありません。
後者の「確率解釈」は、量子力学の正統的な理解(「コペンハーゲン解釈」と呼ばれる)だとされていますが、これについても、学者間で次のような観点の違いが見られます。
- 猫が、時間と共にどのような状態の変化を経て、最終的に生または死に到ったかについては、量子力学の枠内では記述できない。
- 猫の時間的な状態変化を記述することは、ある程度まで可能である。
レーザーや半導体などの振舞いを計算するために量子力学を利用する多くの物理学者は、1の立場をとっています。科学の様々な分野で驚異的な成功を収めている量子力学といえども、所詮は科学の「道具」にすぎない。量子力学にできることは、ある状態から別の状態へ変化する確率がいくらになるかを示すことだけであり、世界が時間と共に変化していく過程を記述するのは、原理的に不可能だというのです。
一方、2の解釈は、ノイマンによる量子力学の古典的な解釈(1932年の『量子力学の数学的基礎』という教科書による)に端を発しています。簡単に言うと、次のようなものです。
- 人間のような意識を持った観測者が猫を観測すると、それまでは“生”状態と“死”状態の和だった猫の状態が、生か死のいずれか一方に瞬間的に変化する。
実は、ノイマンは、あくまで数学的に状態変化の式を記しているのですが、シュレディンガーは、こうした解釈が奇妙だということを示すために、猫を使った実験を持ち出したのです。人間が箱を開けて猫がどうなっているかを見るまで、猫は生きていると同時に死んでいたと考えるのは、いかにもキテレツです。それに、猫だって意識を持っているのではないでしょうか。でも、猫の代わりに、昆虫やミジンコやバクテリアを使ったら、どうなるのでしょう?
意識を持った存在者が、量子力学的な状態変化と密接な関係を持っているという解釈は、最近でも、ペンローズ/ハメロフなどによって主張されていますが、必ずしも賛同者は多くありません。
2の解釈をもう少し現実的なものにする試みは、1960年代から今日に至るまで、先鋭な物理学者および科学に関心のある哲学者によって、続けられています。
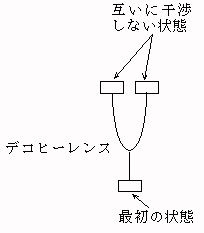
特に関心を呼んでいるのが、「デコヒーレンス」と呼ばれる過程です。これは、数多くの構成要素から成り立っている物質の状態が、自然に「互いに干渉しない(デコヒーレントな)」状態に分岐していく過程です(図)。「互いに干渉しない」というのはわかりにくいかもしれませんが、物理的に異なった状態を意味しており、「多世界解釈」における別世界に相当するものと考えれば良いと思います。デコヒーレンスが起きた後の状態だけを問題としている限り、物理的に異なる状態が併存する世界とか、観測による突然の状態変化といった訳の分からないものを仮定しなくても済むのです。例えば、放射性原子核の状態変化については、崩壊を起こしている状態とそうでない状態はデコヒーレントであり、いつまでも、その和を考える必要はありません(もっとも、「いつ」崩壊が起きたかを記述しようとすると、かなり厄介な問題が生じますが)。
こうした解釈は、グリフィス(1984)とオムネス(1985)によって独立に定式化されました。彼らの理論によれば、デコヒーレントな状態の時系列によって、世界の歴史を記述することは可能になるはずです。シュレディンガーの猫も、人間が観測する前に、生きているか死んでいるかが決まっていることになります(下図)。
ただし、グリフィス/オムネスの理論には、いくつかの問題点があります。中でも「致命的」ではないかと思われるのが、数学的な厳密さに欠けている点です。この理論が正当だと認められるには、デコヒーレンスが完全で、分岐した状態が「互いに全く干渉しない」ことが必要です。ところが、実際に証明できたのは、きわめて簡単なモデル的システムで「互いにほとんど干渉しない」状態に分岐するということだけです。わずかに残った「干渉する部分」−−死んだ猫にほんの少し混じっている生きた猫の要素?−−が、遠い将来、巡り巡って何らかの影響を及ぼすことは、あり得ないとは言えないのです。
現時点では、「シュレディンガーの猫」の問題は、物理学的に完璧と言える形で解決されたわけではありません。しかし、多くの物理学者が真剣にこの問題を議論しており、21世紀の初頭には、誰もが納得できる形で解決されるのではないかと思っています。

放射線とは、電離作用を示すような大きなエネルギーを持った粒子の流れのことで、広義の解釈ではX線や宇宙線なども含まれますが、原子力発電や核廃棄物などの問題とリンクさせて論じる場合は、放射性物質から放射されるものを指します。ここでは、後者の意味に限定して、α粒子(=ヘリウム原子核)、β粒子(=電子ないし陽電子)、γ粒子(=高エネルギー光子)の流束を放射線と呼ぶことにします。
放射線が生体に照射されると、生体物質と相互作用して、通り道にある原子から電子をはじき出して、次々にイオン化していきます。イオン化の割合や生体に侵入する深さは、放射線の種類やエネルギーによって異なっています。例えば、プルトニウムやラジウムから放射されるα粒子は、数十ミクロン程度(細胞数個分)までしか侵入しませんが、1ミクロンあたりで見ると、同じエネルギーの電子よりも、はるかに多くの原子をイオン化します。物質内で、放射線を構成する個々の粒子は、急速にエネルギーを失って無害になりますが、放射線が作り出したイオン(H
+やOH
−など)はきわめて反応性が強く、細胞を傷害します。特に、染色体に対する影響が大きく、染色体の損傷(欠失や転座など)によってガンを誘発することが知られています。仮に、α線を放射する物質が気管支の上皮細胞に付着したとすると、α粒子が通る度に周辺の数個の細胞で反応性の強いイオンが発生して染色体を傷つけるため、肺ガンの危険性が確実に高まります。
放射性物質は、有害な高エネルギー粒子を持続的に放出しています。一定時間に放出される粒子数は、次第に減少する(半減期と呼ばれる期間が経過すると半分になる)ものの、個々の粒子が持っているエネルギーは変わらないので、ガン誘発の危険性が去るわけではありません。
ただし、生体に対する放射線の影響を論じる場合には、常に定量的な評価を心がけるようにしなければなりません。「体内被曝と体外被曝はどちらが有害なのか」「半減期の短い核種の方が長いものより生物学的危険が大きいのでは」−−といった問題は、定量的な分析を行わなければ、即答できないものです。ここではあまり詳しい議論はしませんが、興味のある人は、できるだけ数値をもとに論じる専門書を繙くようにしていただきたいと思います。

てんかん(Epilepsy)とは、脳神経系の特定部位に繰り返し過剰な興奮が起こり、その影響が周囲の神経細胞に波及して、意識の低下や手足の痙攣、感覚異常などの発作を起こす病気の総称です。てんかん発作自体は、聖書に記述されていることからもわかるように紀元前から知られていますが、その正体はなかなか明らかにされず、「悪魔に取り憑かれた状態」として迷信的な恐怖の対象とされてきました。しかし、19世紀後半に大脳皮質の異常が原因だと突き止められ、さらに20世紀に入り、てんかんに特有の脳波(発作波)が観測されるにいたって、その病理が漸く解明されつつあります。
てんかんは単一の疾患ではなく、さまざまな原因によって引き起こされ、障害部位に応じて多様な症状を呈する「症候群」です。潜在的なケースも含めると、てんかんの患者は、地域や民族によらず、小児で1-2%、成人では0.5-1%程度になると推測されており、決して珍しい病気ではありません。
原因
てんかんは、次のような要因によって中枢神経の一部が傷害を受け、神経興奮がうまく制御できなくなることによって発症します。
- 脳を傷害するような頭部外傷
- 特定の薬物の大量摂取による中毒
- 脳血流停止による酸素欠乏
- 脳出血や脳腫瘍など神経細胞を損傷する病気
個々の患者ごとに見ると、原因が特定できない“特発性”てんかんも、かなりの割合に上っています。ただし、てんかんが感染することはなく、遺伝する可能性もほとんどありません。
症状
てんかん発作にはさまざまなタイプがあり、その頻度やパターンは患者ごとに大きく異なります。ただし、治療薬の進歩によって、かつて見られたような“大発作”(この名称は最近はあまり使われません)は抑制できるようになっています。
てんかん発作は、大きく
部分発作と
全般発作の2つに分類されます。
部分発作は、限局された脳神経細胞の過剰な興奮から始まるもので、その部位の機能が障害されるだけで意識が保たれる場合を、
単純部分発作と呼びます。このケースでは、異常が生じる部位によってさまざまな症状が現れ、身体の一部のけいれん、錯視や錯覚、理由のない恐怖感や不快感といった運動・感覚・感情の異常が起こります。こうした症状に加えて意識水準の低下が生じる発作は、
複雑部分発作と呼ばれ、多くは側頭部に異常があります。このケースでは、意図的に行っているかのような自動症(例えばボタンの掛け外しのような)が見られることもあります。
一方、脳の異常がもっと深い所にあり、過剰な興奮が脳全体で同調して起きるように見えるものは、全般発作に分類されます。全般発作には、点頭発作、欠神発作、ミオクロニー発作、強直発作、脱力発作などが含まれます(詳細は省略します)。
この2つのタイプの発作を区別することが、治療の上で非常に重要になってきます。
治療
てんかんの原因が神経組織の器質的障害にある場合、根本的な治療は困難ですが、大半のケースで、抗てんかん薬を用いた内科的治療で発作を抑えることによって、支障なく日常生活が送れるようになります。また、小児期に発症するてんかんの中には、成長するにつれて発作がなくなるケースも多く見られます。このほか、発作の原因となる脳の一部を外科手術で切除することによって、発作が永続的に起こらなくなることもあります。いずれにせよ、できるだけ早い時期に専門医による適切な治療を受けることが大切です。
このコーナーでは、あまり専門的な内容には踏み込めないので、詳しくは、
(社)日本てんかん協会や
長崎てんかんグループのホームページなどをご覧ください。

確かに、化学便覧などに、猛毒のシアン化水素には「アーモンドのような特有の匂いがある」と書かれているのを見ると、どうやって調べたのか不思議な気がします。
色彩や音色は、基本的には電磁波や音波の物理的パラメータで決定されているため、物理的な測定器を使えば、目や耳で知覚したときにどのように感じられるかが予測できます。これに対して、味覚や嗅覚は、呈味成分や有香成分が舌や鼻の化学的受容体を(必ずしも明らかではない仕方で)刺激することに起因するものであり、分子構造と味や匂いの関係は、ある程度の相関性は見いだされているものの、まだ未解明と言って良い状況です。例えば、シアン化水素(HCN)のような小さな分子が、なぜアーモンド様の匂いを感じさせるのかは、良くわかっていません。こうしたことから、ある化学物質がどのような味や匂いを持っているかは、実際に人間が味わったり嗅いだりして試験するのが一般的です。
また、人間の味覚や嗅覚は、最も鋭敏な化学センサーよりもはるかに“高性能”で、機械では識別できないようなわずかな違いも感じ取れる能力を持っているので、食品や香料などをチェックするときにも、最終的には、人間の力を借りることになります。
匂いに関して、もう少し具体的に説明しましょう。匂いの標準照合法と呼ばれる手法は、複数(数十人程度)の被験者に、試験物質の標準物質の匂いを嗅ぎ比べさせて、その類似度を点数で付けさせるというものです。例えば、どちらも「アーモンド香」がすると言われるベンズアルデヒドとシアン化水素を標準照合法(各要素8点満点)で比較すると、下の表のように、全く異なったスコアになることがわかります(『匂い : その分子構造 』( E.アムーア著、恒星社厚生閣)より)。
|
エーテル |
樟脳 |
麝香 |
花香 |
ハッカ |
刺激臭 |
腐敗臭 |
| ベンズアルデヒド |
1.3 |
1.7 |
1.1 |
2.7 |
2.1 |
0.1 |
0.1 |
| シアン化水素 |
0.6 |
0.6 |
0.2 |
0.4 |
0.4 |
2.6 |
2.4 |
こうしたデータを見ても、匂いが単純な化学的性状には還元できないことがわかると思います。
ところで、有毒物質に関しては、当然のことながら、人間による試験はかなり制約を受けます。毒性の閾値(それ以上になると身体に悪影響が現れる値)がはっきりしている物質に関しては、危険性のない濃度で試験することができます。匂いの評価では吸い込まなくても鼻腔内に注入するだけで十分であり、また、人間の鼻がきわめて低濃度でも識別できる鋭敏なセンサーであることから、ごく微量の毒物を使った実験が可能になるのです。上のシアン化水素のデータは、こうした試験で得られたものです。
しかし、サリンのようにきわめて毒性の強い物質に関しては、被験者を使って実験することは現実問題として不可能でしょう。「無味無臭」という性質は、事故や事件に遭遇してサリンに中毒した人の証言に基づくものだと思われます。

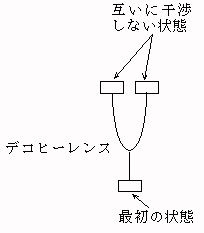 特に関心を呼んでいるのが、「デコヒーレンス」と呼ばれる過程です。これは、数多くの構成要素から成り立っている物質の状態が、自然に「互いに干渉しない(デコヒーレントな)」状態に分岐していく過程です(図)。「互いに干渉しない」というのはわかりにくいかもしれませんが、物理的に異なった状態を意味しており、「多世界解釈」における別世界に相当するものと考えれば良いと思います。デコヒーレンスが起きた後の状態だけを問題としている限り、物理的に異なる状態が併存する世界とか、観測による突然の状態変化といった訳の分からないものを仮定しなくても済むのです。例えば、放射性原子核の状態変化については、崩壊を起こしている状態とそうでない状態はデコヒーレントであり、いつまでも、その和を考える必要はありません(もっとも、「いつ」崩壊が起きたかを記述しようとすると、かなり厄介な問題が生じますが)。
特に関心を呼んでいるのが、「デコヒーレンス」と呼ばれる過程です。これは、数多くの構成要素から成り立っている物質の状態が、自然に「互いに干渉しない(デコヒーレントな)」状態に分岐していく過程です(図)。「互いに干渉しない」というのはわかりにくいかもしれませんが、物理的に異なった状態を意味しており、「多世界解釈」における別世界に相当するものと考えれば良いと思います。デコヒーレンスが起きた後の状態だけを問題としている限り、物理的に異なる状態が併存する世界とか、観測による突然の状態変化といった訳の分からないものを仮定しなくても済むのです。例えば、放射性原子核の状態変化については、崩壊を起こしている状態とそうでない状態はデコヒーレントであり、いつまでも、その和を考える必要はありません(もっとも、「いつ」崩壊が起きたかを記述しようとすると、かなり厄介な問題が生じますが)。