
近年、量子力学を使って脳の機能を明らかにしようという試みに、何人かの科学者がチャレンジしています。最も有名なのは、細胞骨格となる微小管で生じる波動関数の収縮が意識と関係しているとするペンローズとハメロフの主張ですが、一般相対論に関する優れた業績(特異点定理の発見など)で知られるペンローズの名声を持ってしても、多くの科学者の賛同を得るには至っていません。また、物理学者の梅沢博臣とリチアルディも、場の量子論のフォーマリズムを用いて、神経細胞と環境との相互作用による集団運動の励起を考察していますが、モデルが具体性を欠いてわかりにくい上に、「非一様で高温の脳内部では、熱雑音に乱されて量子論的な集団運動は生じないはずだ」という批判に答えられないと思われます。
量子脳力学(
Quantum
Brain
Dynamics; QBD)とは、梅沢らの業績に触発されて、保江邦夫と治部眞理が展開している理論です。保江らは、微小管の近くに存在する水分子の磁気モーメントに注目し、これらが一斉に向きを揃えることが、梅沢の提案した集団運動に該当すると考えました。さらに、磁気モーメントのこうした振舞い──いわゆる“自発的対称性の破れ”に相当します──のために、これと相互作用する電磁場が、空間を伝播するふつうの光とは異なって、特定の場所に局在するエバネッセント光になることを示しました。
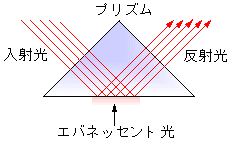
ちなみに、エバネッセント(evanescent)光とは、通常は、全反射する界面の外側にしみ出している電磁場を指し、近接場光学顕微鏡などで利用されるものです(右図)。このエバネッセント光は、神経細胞に比べて巨大な拡がり
(正確に言えばコヒーレント長)を持っており、記憶が脳内部に拡がって貯蔵されているように見えることと関係しているとされます。また、この光の発生/消滅が意識の起源であるというのが、彼らの主張です。……………と言うと、何やらもっともらしい理論に聞こえますが、私には、あまり信憑性が感じられません。水分子は周囲にあるさまざまな分子と激しく相互作用しており、広い範囲にわたって磁気モーメントが配向するとは考えにくいからです。簡単なモデルを使ったために、たまたま自発的対称性の破れが起きたように見えるだけであって、分子間相互作用を正しく評価すると、巨視的なコヒーレンスを持つエバネッセント光など消えてしまうでしょう。「光と意識が結びつく」というフレーズに幻惑されてか、新時代を告げる画期的理論として量子脳力学を持ち上げる評者もいますが、私は、数多い泡沫理論の1つとして黙殺することをお勧めします。
【Q&A目次に戻る】

“万有引力”である重力によって引き寄せあう物質が自重で潰れてしまわないのは、(陽子間相互作用で比較して)重力より10
36倍も強い電気的な力が同種の荷電粒子間で斥力になっており、互いに引き合う粒子だけを集めることができないからです。物質の構成要素として原子核と電子を考えることにすると、原子核同士/電子同士は互いに強く反発しあうので、原子核だけ/電子だけを1箇所に集めることはできません。原子核の隙間に電子が入り込み、プラスの電荷をシールドすることによって、重力と電気力がうまく釣り合った物質構造を作ることができるのです。もし、電気的な相互作用の引力・斥力が反対になると、軽い電子が原子核の存在する領域から弾き出され、原子核同士/電子同士が強い引力で凝集して、あっという間にあらゆる物質が潰れてしまうでしょう。
もっとも、同符号が反発し逆符号が引き合うという性質は、電磁気相互作用がベクトル型である(ベクトルポテンシャルA
μを介して力を及ぼしあう)ことの帰結であり、これを逆にするには、場の理論を根幹から作り替える必要があります。このため、どのような現象が起きるかを理論的に予測することは、かなり困難だと言わざるを得ません。
【Q&A目次に戻る】

蒸留とは、液体の混合物を揮発性の違いに基づいて分離する方法で、蒸留法によって精製された水を、一般に蒸留水と呼びます。蒸留法では主に電解質が除去され、通常の化学実験などに使用するには充分な純度になりますが、微量の不純物は取り除かれずに残ります。
実験室で蒸留水を得るには、銅・スズ・ステンレスなどの金属製の蒸留器が使用されますが、銅・亜鉛・鉄などが溶出して不純物となるので、より純度の高い水を得るには、石英製蒸留器が用いられます。ただし、この場合も、アルカリ成分がわずかに溶出します。また、水が薄膜状になってガラス壁面を這い上がるクリーピングや、気泡が破裂してできる飛沫が蒸気とともに運ばれる飛沫同伴などの現象によっても、蒸留水の汚染が生じます。化学実験用の市販の装置を用いた場合、電解質の濃度を示す指標である電気抵抗率(大きい方が純度が高い)は、次のようになります。
| 金属製蒸留器 |
0.1〜0.5 MΩcm |
| 石英製蒸留器(1回蒸留) |
0.5 MΩcm |
| 石英製蒸留器(3回蒸留) |
2 MΩcm |
この方法では、最高純度の蒸留水でも、炭酸カルシウム換算で約0.3 ppmの電解質を含むことになります。また、二酸化炭素を吸収するため、pHは約5.7 になります。
なお、近年では、クリーピングや飛沫同伴による汚染を防ぐ蒸留法や装置が考案されており、これよりも純度の高い蒸留水が得られるようになっています。
(【参考文献】『新実験化学講座 1 基本操作』(井口洋夫ほか編,丸善)
一方、精製水とは、通常は、日本薬局方に定められた水質基準に適合する水を指します。それによると、精製水とは、常水(水道水)を蒸留・イオン交換・超濾過(逆浸透法/限界濾過)のいずれか、あるいはこれらを組み合わせた方法で処理した水で、抵抗率・生菌数・TOCなどに関する純度試験に合格することが要求されます。精製水をさらに高純度化したものに、高圧蒸気滅菌法で滅菌した滅菌精製水と、蒸留ないし超濾過で処理した注射用水ががあります。日本薬局方による注射用水の管理目標値は、次のようになっています(一部)。
| 抵抗率(MΩcm)25℃ | >5 |
| 微粒子(個/ml) >10μm | <0.1 |
| >25μm | <0.01 |
| 生菌(個/ml) | <0.01 |
| TOC(μg/l) | <100 |
なお、半導体製造の際に利用される超純水は、精製水よりもさらに高純度であり、抵抗率は 18MΩcm 以上であることが要求されます。
【Q&A目次に戻る】
 昔から引っかかっていた疑問があり、お聞きしたいのでお便りします。ここに1本の硬い棒があります。
昔から引っかかっていた疑問があり、お聞きしたいのでお便りします。ここに1本の硬い棒があります。
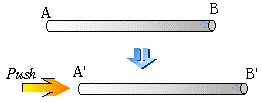
左端をA、右端をBとします。この棒の左端を右に押します。棒は右に移動し、移動した左端をA'、右端をB'とします。さて、A点がA'点に到達する時刻と、B点がB'点に到達する時刻は同時刻なのでしょうか? もし同時刻であるならば50光年の長さの棒を用意し、たとえばB点にスイッチを置いてA点から棒を押したり引いたりすれば、「超光速通信」が可能ということになりますよね? 直感的な質問で恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。【古典物理】

この通りのことが起きると「相対論は間違っていた」と言えるのですが、現実には、こうした超光速通信は不可能だと考えられています。その理由は、物質を構成する原子の相互作用が相対論に従っているからです。
金属棒のケースで説明しましょう。このとき、棒が固体になっているのは、プラスの金属イオンとマイナスの自由電子との間の電磁気的な相互作用によって、金属結晶が形作られているためです。簡単のために、古典的なマクスウェル方程式を使うことにします(量子論的な効果を取り入れても結果は同じです)。点電荷が周囲に作るポテンシャルとして、よくクーロン・ポテンシャル

(q:電荷, r:電荷からの距離)
が利用されますが、これは、電場の時間的変化を無視するという近似の下で成り立つ公式であり、時間微分を含んだマクスウェル方程式を正しく解
(いて境界条件を適切に置)くと、リエナール・ヴィーヒェルトのポテンシャル
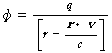
(
r:電荷から観測点までの動径ベクトル,
v:電荷の速度ベクトル,c:光速)
が得られます。ただし、右辺分母の[ ]内は、観測点の時刻をtとすると、
t' + r(t')/c = t
を満たすような時刻t'──すなわち、その瞬間に電荷から放射された光がちょうど観測点に届くような時刻──の量を表します。つまり、電荷が運動しているときのポテンシャルの変化は、一瞬のうちに遠方まで伝えられるのではなく、たかだか光速でしか伝播しないのです。ですから、金属棒の左端の原子層に力を加えて動かしても、電磁場の変化を介してその影響が次の原子層に伝わるには光が伝わるのに必要な分だけタイムラグがあることになります。それ以降の原子層でも同じように影響が遅れて伝播していくので、結局、超光速通信を実現することはできないのです。相互作用の伝播速度が光速を越えないという特徴は、こんにち知られている全ての理論で成り立っており、(現在の物理学の知見の範囲内では)「決して変形しない剛体は存在しない」と結論することができます。
ついでに言えば、50光年の長さの金属棒は、質量がとてつもなく巨大になり、左端を押せども引けども、棒全体を動かすことはできないでしょう。
【Q&A目次に戻る】

天体から物質がジェット状に噴出する現象の背後には、天体の周囲に形成された降着円盤(accretion disk)があります。重力の作用で天体付近に集まってきた分子雲は、自分自身の重力で凝縮しようとする一方で、角運動量が保存されて全体として回転するため、次第に天体を中心とする薄い円盤状になります。外部からの物質の流入がなくなると、円盤内でさらに凝集が進んで天体を周回する惑星/衛星群が形成されますが、銀河中心核や巨大質量星と連星系をなす白色矮星のように、常に円盤上に物質が降り注いでいるケースでは、中心天体に落ち込む物質量と円盤に降着する物質量が釣り合って、定常状態になります。このとき、物質の流入に伴って莫大な重力エネルギーが解放され、強力な電磁波や物質粒子が放出されたり、矮新星爆発(重力エネルギーの急激な解放による爆発)が起きたりします。
多くの銀河の中心部にはブラックホールが存在していると考えられています。
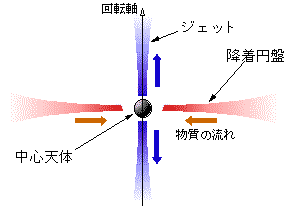
このブラックホールの周囲には、銀河から定常的に質量が降り注ぐ降着円盤が形成されており、円盤からラセン軌道を描いて物質がブラックホールに流入する一方で、その過程で解放される重力エネルギーによって、中心軸方向に高エネルギー放射が行われることがあります(右図)。特に、"radio loud" に分類される活動銀河核の一種では、中心部から対称的に物質粒子(主に電子と陽電子)の流れであるジェットが吹き出しており、大きなもので10
22メートルまで遠方に伸びています。
一方、巨大分子雲の中で形成されつつある原始星の周囲にも、しばしば降着円盤が存在しています。活動的な天体では、周辺の分子雲から流入する物質(水素・ヘリウムなど)の一部が、磁気的な力によってドライブされ、円盤に垂直な方向にジェット状に吹き出しています(双極分子流)。このジェットと分子雲が相互作用して輝いて見えるのが、ハービックハロー天体(HH天体)です。
なお、砂時計星雲(惑星状星雲MyCn18)やSN1987A(1987年に大マゼラン雲で観測された超新星)の周囲に見える模様は、晩年に不安定になった中心天体から断続的に放出されたガスやダストが、周囲の分子雲との相互作用や磁場によるドライブを通じて固有の密度分布を形成したところに、高エネルギー電磁波が当たって高密度部分が明るく輝いているもので、2次元面に投影しているために単純なリング状に見えていますが、3次元的には複雑な構造をしているようです。
【Q&A目次に戻る】

この質問に答える前に、まず質量とは何かをはっきりさせておく必要があります。ニュートン力学では、真空の中を自由に飛び回る質点が存在すると考えられていたので、この質点の慣性をもとに質量を定義することができました。しかし、陽子や中性子内部のクォークは、グルーオン(糊粒子)によってがんじがらめに縛り付けられており、自由粒子の慣性として質量を定義することは困難です(陽子や中性子はちょうど繭玉のようなもので、外側の方がグルーオンの場でグルグル巻きにされ、内奥ではクォークが比較的自由に運動していると考えてください)。また、たとえ外部に飛び出せたとしても、素粒子にとっての真空は何もない“虚空”ではなく、スカラー場が凝縮していたり仮想粒子のペアが生成・消滅していたりするので、これらと相互作用をしながら進んでいかなければなりません。電子質量 0.51MeVとかミューオン質量 105.66MeVという値は、真空中を相互作用しながら運動する効果を“くり込んだ”慣性質量(=エネルギー/c
2)です。クォークの場合、陽子や中性子の奥深くに高エネルギー電子を打ち込んだときの反応から、真空に対する慣性質量は、uクォークで2〜8MeV、dクォークで5〜15MeVと推定されています(陽子と中性子の質量の違いは、主としてこの差に起因します)。もっとも、この値には、グルーオンとの相互作用の効果が含まれていないため、核子内部のクォークの振舞いを議論するときには、その効果を加えた構成クォーク質量(constituent quark mass)という概念が使われることがあります。これが、陽子や中性子の質量の1/3程度の大きさになるもので、質問にあるクォークの質量に対応すると考えられます。
構成クォーク質量は、グルーオンの相互作用の含め方に曖昧さがあり、厳密に定義することができません。もちろん、質量の相加法則は成り立たず、各クォークの質量の和が陽子や中性子の質量になるわけではありません。専門家でも、大ざっぱに300MeV程度と考えています。また、2つのクォークが結合してできた中間子の中で、π中間子の質量が異常に小さい(π
0:134.98MeV、π
±:139.57MeV)ことは、π問題として1960年代に議論されましたが、現在では、「カイラル対称性の破れ」という特殊な機構によってクォークが堅く(結合エネルギーが低くなるように)結びついたためだと説明されています。u-dクォークから構成されるもう1つの中間子であるηの質量は547.45MeVとなっており、構成クォーク質量が300MeV程度であることと矛盾していません。
【Q&A目次に戻る】

量子力学における観測問題は、1冊の書物でも語りきれないほど多岐にわたる議論がありますので、ここでは、要点だけをごく掻い摘んで記すにとどめます。
量子力学的な観測結果に客観性がないと主張されるのは、いくつかの理由があります。1927年にハイゼンベルグが不確定性関係を見出した当初は、ミクロな量子系を観測しようとすると、観測操作によってどうしても系の状態を擾乱してしまい、人間の手が加わらない“生の”状態を測定するのは不可能だという点が、古典理論とは異なる特徴として強調されていました。確かに、量子力学の最大の特徴である波動的な可干渉性は、観測による擾乱のために簡単に壊れてしまい、観測する前の状態を“客観的に”調べることはしばしば困難になります(例えば、光子による二重スリットの実験で、光子がどちらのスリットを通過したかを測定するケースなど)。しかし、こうした「観測による擾乱」は、実験方法を工夫することによって取り除ける場合もあります。1930年にアインシュタインは、エネルギー固有状態にある系から光子が放出されたとき、放出した系の方のエネルギーを測定することによって、観測による光子状態の擾乱なしに光子のエネルギーを確定できると主張しました。
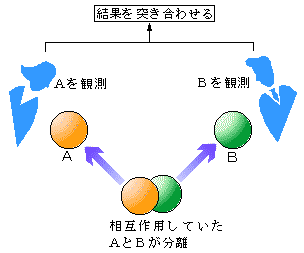
このアイデアは、現在ではさらに洗練され、初めに相互作用していた系が2つに分離して十分に遠ざかった後、それぞれを観測するという形で実際に試されています(右図)。分離した2つの系のうちAを測定すればBを擾乱することなくその状態が予測できるし、逆もまた可能です。それでは、同時に測定を行って結果を突き合わせたらどうなるのか。これまで、何とかして理論の“裏をかこう”とさまざまな工夫を凝らした実験が行われましたが、分離系それぞれを測定した結果の「相関」は、常に量子力学の予想通りになっていました。つまり、量子力学は何が観測されるかを(ある意味では客観的に)規定している理論であり、2人の観測者が相反する観測結果を得るということは起こり得ないのです。
量子力学が客観的でないと言われるもう1つの理由は、この理論が、波動関数という確率振幅を表す量で記述されている点です。確率とは、現象の統計的性質に基づいて人間が割り当てる量なので、系の物理的状態そのものを直接的に表している訳ではないと考えられます。“正統的な”コペンハーゲン解釈では、波動関数はあくまで状態が変化していく可能性を表現している確率振幅にすぎず、測定によって系の状態が確定した場合は、波動関数の時間的変化を与えるシュレディンガー方程式から離れて、境界条件を新たに取り直すべきだとされています(この「境界条件の再設定」が、俗に言う「波動関数の収縮」です)。基本方程式を無視してもかまわないというのはいかにも乱暴なやり方ですが、波動関数はどのみち現象記述のために考案された“単なる”確率振幅なので、断続的に変化させても不都合はないという考えなのでしょう。
こうした正統的解釈に対して、エヴェレットの論文から出発して多くの物理学者が練り上げていった「デコヒーレント理論」が近年注目を集めています(ここでは、質問者に倣ってエヴェレット解釈と呼びます)。この解釈では、波動関数は常にシュレディンガー方程式に従っていると見なされます。観測によって区別されるはずのさまざまな可能性は、すべて1つの波動関数で記述されており、「互いに干渉しあわない」という形で実質的に分離され(つつ並存す)ることになります。ただし、多くの可能な状態が並存すると言っても、現実に無数の世界が存在するというのではなく、あくまで1つの関数であらゆる可能性が記述されると見なすべきでしょう。エヴァレット解釈はきわめてエレガントで物理学的にもスマートですが、本当に干渉しあわない状態に分離されるか証明されていない、測定装置を含めた全システムを対象としなければならず実用的でない──などの理由で、量子力学を道具として使う大半の研究者には受容されていません。
なお、エヴァレットの議論を極端に押し進めて、並存する可能な状態が現実に存在している(と考えても良い)とする「多世界解釈」も提唱されています。これは、ドウィットなど一部の先鋭な物理学者が主張しているものですが、あまりに突飛なので、(面白がって論文を書く人はいても)本気で信じている物理学者はほとんどいないと思います。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
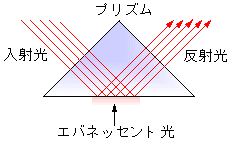 ちなみに、エバネッセント(evanescent)光とは、通常は、全反射する界面の外側にしみ出している電磁場を指し、近接場光学顕微鏡などで利用されるものです(右図)。このエバネッセント光は、神経細胞に比べて巨大な拡がり(正確に言えばコヒーレント長)を持っており、記憶が脳内部に拡がって貯蔵されているように見えることと関係しているとされます。また、この光の発生/消滅が意識の起源であるというのが、彼らの主張です。……………と言うと、何やらもっともらしい理論に聞こえますが、私には、あまり信憑性が感じられません。水分子は周囲にあるさまざまな分子と激しく相互作用しており、広い範囲にわたって磁気モーメントが配向するとは考えにくいからです。簡単なモデルを使ったために、たまたま自発的対称性の破れが起きたように見えるだけであって、分子間相互作用を正しく評価すると、巨視的なコヒーレンスを持つエバネッセント光など消えてしまうでしょう。「光と意識が結びつく」というフレーズに幻惑されてか、新時代を告げる画期的理論として量子脳力学を持ち上げる評者もいますが、私は、数多い泡沫理論の1つとして黙殺することをお勧めします。
ちなみに、エバネッセント(evanescent)光とは、通常は、全反射する界面の外側にしみ出している電磁場を指し、近接場光学顕微鏡などで利用されるものです(右図)。このエバネッセント光は、神経細胞に比べて巨大な拡がり(正確に言えばコヒーレント長)を持っており、記憶が脳内部に拡がって貯蔵されているように見えることと関係しているとされます。また、この光の発生/消滅が意識の起源であるというのが、彼らの主張です。……………と言うと、何やらもっともらしい理論に聞こえますが、私には、あまり信憑性が感じられません。水分子は周囲にあるさまざまな分子と激しく相互作用しており、広い範囲にわたって磁気モーメントが配向するとは考えにくいからです。簡単なモデルを使ったために、たまたま自発的対称性の破れが起きたように見えるだけであって、分子間相互作用を正しく評価すると、巨視的なコヒーレンスを持つエバネッセント光など消えてしまうでしょう。「光と意識が結びつく」というフレーズに幻惑されてか、新時代を告げる画期的理論として量子脳力学を持ち上げる評者もいますが、私は、数多い泡沫理論の1つとして黙殺することをお勧めします。
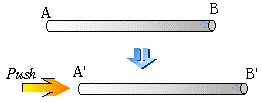 左端をA、右端をBとします。この棒の左端を右に押します。棒は右に移動し、移動した左端をA'、右端をB'とします。さて、A点がA'点に到達する時刻と、B点がB'点に到達する時刻は同時刻なのでしょうか? もし同時刻であるならば50光年の長さの棒を用意し、たとえばB点にスイッチを置いてA点から棒を押したり引いたりすれば、「超光速通信」が可能ということになりますよね? 直感的な質問で恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。【古典物理】
左端をA、右端をBとします。この棒の左端を右に押します。棒は右に移動し、移動した左端をA'、右端をB'とします。さて、A点がA'点に到達する時刻と、B点がB'点に到達する時刻は同時刻なのでしょうか? もし同時刻であるならば50光年の長さの棒を用意し、たとえばB点にスイッチを置いてA点から棒を押したり引いたりすれば、「超光速通信」が可能ということになりますよね? 直感的な質問で恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。【古典物理】
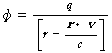
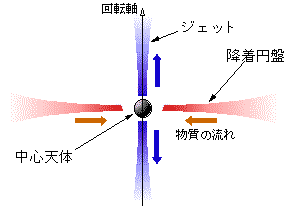 このブラックホールの周囲には、銀河から定常的に質量が降り注ぐ降着円盤が形成されており、円盤からラセン軌道を描いて物質がブラックホールに流入する一方で、その過程で解放される重力エネルギーによって、中心軸方向に高エネルギー放射が行われることがあります(右図)。特に、"radio loud" に分類される活動銀河核の一種では、中心部から対称的に物質粒子(主に電子と陽電子)の流れであるジェットが吹き出しており、大きなもので1022メートルまで遠方に伸びています。
このブラックホールの周囲には、銀河から定常的に質量が降り注ぐ降着円盤が形成されており、円盤からラセン軌道を描いて物質がブラックホールに流入する一方で、その過程で解放される重力エネルギーによって、中心軸方向に高エネルギー放射が行われることがあります(右図)。特に、"radio loud" に分類される活動銀河核の一種では、中心部から対称的に物質粒子(主に電子と陽電子)の流れであるジェットが吹き出しており、大きなもので1022メートルまで遠方に伸びています。
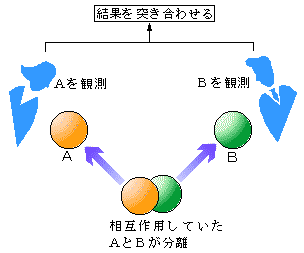 このアイデアは、現在ではさらに洗練され、初めに相互作用していた系が2つに分離して十分に遠ざかった後、それぞれを観測するという形で実際に試されています(右図)。分離した2つの系のうちAを測定すればBを擾乱することなくその状態が予測できるし、逆もまた可能です。それでは、同時に測定を行って結果を突き合わせたらどうなるのか。これまで、何とかして理論の“裏をかこう”とさまざまな工夫を凝らした実験が行われましたが、分離系それぞれを測定した結果の「相関」は、常に量子力学の予想通りになっていました。つまり、量子力学は何が観測されるかを(ある意味では客観的に)規定している理論であり、2人の観測者が相反する観測結果を得るということは起こり得ないのです。
このアイデアは、現在ではさらに洗練され、初めに相互作用していた系が2つに分離して十分に遠ざかった後、それぞれを観測するという形で実際に試されています(右図)。分離した2つの系のうちAを測定すればBを擾乱することなくその状態が予測できるし、逆もまた可能です。それでは、同時に測定を行って結果を突き合わせたらどうなるのか。これまで、何とかして理論の“裏をかこう”とさまざまな工夫を凝らした実験が行われましたが、分離系それぞれを測定した結果の「相関」は、常に量子力学の予想通りになっていました。つまり、量子力学は何が観測されるかを(ある意味では客観的に)規定している理論であり、2人の観測者が相反する観測結果を得るということは起こり得ないのです。