
光電子や熱電子の放出によって起電力が生じることは早くから知られており、簡単な構造で効率的に電気エネルギーを作り出す発電装置に応用できると期待されてきました。例えば、真空中で温度差を持った金属を接近させると、熱電子放出の違いのために金属間に電位差が生じます。こうした現象をうまく利用すれば、恒星からの放出エネルギーを用いた宇宙空間での発電、あるいは、核分裂の熱エネルギーによる直接発電が可能になるかもしれません。
ただし、電気エネルギーを取り出せるような起電力を生み出すためには、電流を流して非平衡状態を実現しなければなりません。金属の表面付近の電子は、近似的に井戸型ポテンシャルの内部に束縛されており、有限温度では、フェルミ準位より大きなエネルギーを持つ少数の電子が存在しています。中でも、「フェルミ準位+仕事関数」以上のエネルギーを持つ電子は、熱電子として金属の外に飛び出すことができます。温度を上げると熱電子放出される割合が増加しますが、飛び出した電子を取り除かないでいると、空間電荷が溜まって再び金属に戻ってくる電子も増加し、最終的には、金属周辺に(温度によって決まる)「電子雰囲気」が形成されて平衡状態に達します。このとき、金属は確かに正に帯電してはいますが、遠方から見ると空間電荷にシールドされており、電気的には中性に近くなります。これでは電気エネルギーが取り出せないので、発電を行うためには、正イオンを生成して空間電荷を中和する一方、金属に電子を供給しなければなりません。
X線などの短波長の電磁波による光電効果の場合は、大きなエネルギーを持った電子が飛び出す非平衡現象なので、金属は直ちに帯電します。試料の物性を測定する光電子分光に際しては、X線照射を続けると試料表面が正に帯電して測定が困難になってしまうので、電子銃を使って試料に電子を供給しています。
なお、遠心力は、加速度が10
20G程度にならなければ電気的な力と拮抗できませんが、これほどの巨大な遠心力になると金属の結晶構造が破壊されてしまうので、遠心力で電子だけを飛び出させることは不可能です。
【Q&A目次に戻る】

BeeSpiという装置は初めて聞きましたが、ミニ四駆やチョロQの速度測定用にハドソン社が開発した製品だそうですね。コの字状の本体の内側に赤外線センサーが2つあり、その間を通過する時間から時速を計算するもので、中学・高校での物理実験のために利用している先生も増えているとか。
金属球の落下を利用した重力加速度の測定には、さまざまな誤差が伴います。誤差の原因を推定するためには、実験を繰り返して、測定値がどのようにばらついているかを見る必要があります。測定値が9.8のまわりにランダムに分布している場合は、測定の際の偶発的なエラーが起因していると思われます。例えば、初速度が正確にゼロにならずに計測のたびにブレがあると、当然、結果はばらつきます。
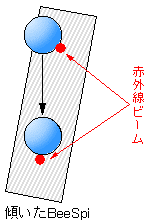
また、金属球のどの部分が BeeSpi内部の赤外線センサーに引っかかるかも、影響を与えます。BeeSpiが傾いていると、金属球の落下開始点がわずかに左右にずれるだけで、速度の測定に誤差が生じてきます(右図;この現象は、水平方向の初速がある場合にも起きる)。この種の誤差は完全になくすことが難しいので、測定回数を(できれば数十回まで)増やして平均を取らなければなりません。
測定値が9.8とは異なる値にそろっている場合は、系統的な誤差が考えられます。装置全体の傾き、BeeSpiの不良、空気抵抗の影響などがあり得ます。原因を究明するには、実験装置を調整・交換したり、落下距離を変化させたりして、誤差の現れ方がどのように変わるかを調べる必要があります。ただし、簡単な実験装置を用いた場合、数%の誤差が生じるのは、やむを得ないでしょう。むしろ、17〜18世紀の科学者たちが、簡単な装置を使って物理法則を正しく導き出したことに敬意を表すべきです(もっとも、クーロンのように、正しい測定結果が得られないまま、データを捏造してクーロンの法則を“立証”した人もいたようですが)。
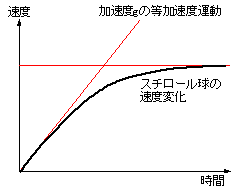
なお、スチロール球の場合は、速度に比例する空気抵抗が大きく寄与して一定の距離だけ落下した後に等速運動になるため、終端速度から求めた加速度は、落下距離が短いほどgに近く、長くなるにつれてゼロに漸近していきます。
【Q&A目次に戻る】

中性子過剰原子核と中性子星では、中性子を束縛している力が異なるためです。
通常の原子核では、陽子や中性子がπ中間子を媒介とする“核力”によって結合しています。この核力は、大雑把に言うと、陽子同士・中性子同士よりも陽子と中性子の間で強く働きます。このため、陽子と中性子の数がほぼ等しい原子核ほど緊密に結合して安定であり、陽子や中性子が過剰になっている原子核は、ベータ崩壊(β
+/β
-)や電子捕獲によって、より安定な(質量の小さい)状態に遷移してしまいます(実際には、陽子の電荷によるクーロン相互作用があるため、中性子がやや多い方が安定になる)。陽子や中性子の割合がさらに高くなると、核力によって束縛状態を作ることは不可能になり、ベータ崩壊を起こすよりも前に(10
-20秒以下で)バラバラになってしまいます。ある陽子数に対して核力で束縛できる中性子の限界が中性子ドリップラインであり、軽い原子核に対しては、次のようになっています。
ドリップライン付近の原子核では、中性子の結合エネルギーはきわめて小さく、一部の中性子は、他の核子に比べて外側に大きく拡がったハローを形成していることが知られています。
中性子星は、質量が太陽と同程度でありながら、中心付近の密度が標準的な原子核密度の数倍にも達しており、それ自体が巨大な“原子核”になぞらえられる天体です(ただし、表面付近の密度は原子核よりも小さく、あちこちにクラスターが存在する非一様な構造になっています)。質量の80%以上を中性子が占めており、原子核のドリップラインを外挿すると、当然、その外側に位置するはずです。とは言っても、もちろん、物理法則に反するものではありません。核力によって中性子が束縛されている通常の原子核とは異なり、中性子星では、巨大な重力が物質を高密度にしているからです。進化の最後の段階で冷えて潰れ始めた天体の内部では、通常は原子核から遠く離れた所にあるはずの軌道電子が原子核近傍に押し込まれることになります。こうなると、電子が高密度状態のままでいるよりも、核内部の陽子が電子を捕獲して中性子に変わった方がエネルギー的に有利であるため、中性子の割合がどんどん高くなっていき、それとともに原子核同士の電気的な反発力も弱まって、最終的には、中性子が大半となった核物質が融合して、中性子物質となるわけです。
なお、現在では、RIビームと呼ばれる特殊なビームを利用することによって、10
-21秒程度のほんの一瞬だけ、
5H(陽子1個、中性子4個)や
10He(陽子2個、中性子8個)のように、中性子の割合が80%と中性子星なみの原子核を作ることが可能になっています。こうした原子核をもとに、中性子星の内部状態を地上で実現しようという試みも始まっています。
【Q&A目次に戻る】

質問にある反応は、「陽子崩壊に対するモノポールの触媒作用 (monopole catalysis of proton decay) 」として知られているもので、1981年にルバコフが考察しました。
ここで謂うモノポールとは、トフーフトとポリヤコフが1974年に大統一理論(
Grand
Unified
Theorie
s; GUTs) の1つの帰結として存在を予測したもので、もともとのディラックのモノポールに比べて理論的に無理がなく、大統一理論が正しければ現実に存在するはずだと考えられています。このモノポールは、質量が陽子の1京倍はあり、反モノポールと対消滅しない限り他の粒子に崩壊することはありません。
大統一理論によれば、さまざまのクォークやレプトン(およびその反粒子)は、実は、同じ粒子の異なる状態だとされます。ビッグバン直後の高温状態では、クォークとレプトンの区別はなく全て同じように相互作用をしていたはずですが、宇宙が膨張して温度が下がるにつれて、ちょうど強磁性体が冷えて自発磁化を示すように、クォークとレプトンを区別する状態へと場が変化(相転移)していきました。このとき、強磁性体が異なる向きに磁化したいくつかの磁区に分かれるように、宇宙の相転移でも、場所によってクォークとレプトンの区別の仕方が異なるはずですが、ほとんどの場合、この差は、ゲージ不変性と呼ばれる性質によってうち消されてしまいます。しかし、場合によっては、ゲージ不変性を使っても解消できない差が生じることがあります。これが“位相欠陥”と呼ばれる特殊な領域で、トフーフト=ポリヤコフのモノポールも、その一種と見なせます(下図;
この図は概略的なもので正確ではありません)。
モノポールが陽子や中性子に接近すると、強い磁場(1/r
2の距離依存性を持つ)によってクォークを引き寄せます。ところが、モノポールの中心は、クォークとレプトンを特定の仕方で区別することができない相転移前の状態になっており、ここに引き込まれたクォークは、もはやレプトンと区別できなくなってしまいます。このため、クォークとしてモノポールと接触した粒子が、飛び出したときにはレプトンに変わっているということも起こり得るのです。ただし、電荷が保存するように、クォーク1個がレプトンと2個の反クォークに変化することになります。具体的には、次のような反応が起こります:
p + M → e
+ + π
0 + M
(M : monopole)
この反応では、モノポール自体は変化することなく、陽子や中性子を通常よりも(おそらく1兆倍以上も)高い確率で崩壊させていきます。この意味で、モノポールは化学反応における触媒になぞらえられます。また、どんな物質でも、モノポールと接触させると陽子・中性子が崩壊して莫大なエネルギーを放出する可能性があるので、新たなエネルギー源として利用できると想像するSF作家もいます。ただし、残念ながら、モノポールが存在する証拠は、今のところいっさい見つかっていません。
【Q&A目次に戻る】

人類は、有史以前からたびたび飢餓状態に晒されてきたため、栄養不足に対応するためのさまざまな機構が身体に備わっています。特に、脳のエネルギー源となるのは血液中のブドウ糖だけであり、極端な低血糖に陥ると意識を喪失する危険があるため、何とかして血糖値を上げようとする生体反応が生じます。初めのうちは、肝臓や筋肉に蓄えられているグリコーゲンが利用されますが、このまま糖質の補給がない状態が続くと、さらに筋肉のタンパク質が分解されアミノ酸として血中に溶け出し、これがブドウ糖に作り替えられるようになります。このため、長期間にわたって糖質の摂取が抑制されたり、激しいトレーニングの後に糖質を補給しないでいると、次第に筋肉がやせ細ってしまいます。
こうした筋肉の分解は、いくつかのカタボリック(異化)ホルモンによって制御されています。代表的なカタボリックホルモンに、コルチゾルという副腎皮質ホルモンあります。コルチゾルは、ダイエットや激しい運動などさまざまなストレスが引き金となって分泌されるストレスホルモンの一種で、視床下部からの司令によって副腎皮質で作られます。そこから血液で筋組織に運ばれたコルチゾルは、筋繊維にあるホルモン受容体と結合することによって、筋肉の代謝(同化・異化)に関わる酵素を作る一連の生化学反応を引き起こします。この酵素の機能によって、筋タンパク質の分解(異化)が促進されるのです。
興味深いことに、コルチゾルは内臓脂肪(特に腹の周囲の脂肪)を増やす効果もあるようです。脂肪組織は体を保護する緩衝材としての役割があるので、生体防御反応としては正常なのでしょうが、下手なダイエットをすると脂肪が減らずに筋肉だけが痩せていくという困った結果をもたらすことになりかねません。
【Q&A目次に戻る】

光は秒速30万kmで進むので、単純に計算すると、1.28秒で月面に到達するはずですが、実際に懐中電灯を照らしても、月にいる人が観測できるほどの光は届きません。理由の1つは、地球の大気中を進む間に、光の大半が散乱されてしまうからです。暗闇で懐中電灯を照らすと光の道筋がぼんやりと見えますが、これは、気体中の塵などによって横方向に逸らされた光が目に達するためで、通過する空気の層が厚くなるほど、透過する光の量は少なくなっていきます。また、懐中電灯からの光が拡がる効果も無視できません。仮に、頂角10°の円錐状に拡がるとすると、月軌道付近では、光の拡がりは月直径の20倍程度になり、それに応じて光量も少なくなってしまいます。ごく一部は月まで到達しているはずですが、ある懐中電灯から発した光だと識別することは、かなり難しいと思います。
レーザーのように指向性の強い(拡がらずに直進する)光ならば、多少の散乱はあっても、月面まで到達させることが可能です。実際、月面にはアポロ計画の際に設置された反射板があり、地球から照射したレーザービームの反射を捉えることによって、月までの距離をセンチメートル単位で測定することができます。
【Q&A目次に戻る】

水素原子のエネルギー準位を正しく計算するためには、本来は、陽子によるクーロン場内部での電子の振舞いを記述するシュレディンガー方程式:
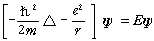
を解く必要があります(△はラプラシアン)。基底状態のエネルギーは、波動関数が球対称になるという条件を付けて動径方向の式を考えれば、比較的容易に求められます
(詳しいことは、量子力学の教科書に書いてあります)。しかし、このやり方は、物理学を勉強したことのない人には難しすぎるでしょうから、厳密性を犠牲にして、もう少し簡単な計算を紹介しておきます。
量子力学によれば、電子は粒子と波の二重性を兼ね備えており、運動学的に運動量p を持つ電子は、波長λが、
λ = h/p
というド・ブロイの関係式を満たす波としても振舞うことが知られています。
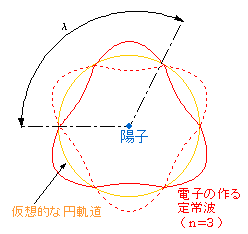
特に、束縛状態にある電子は、どこかに進んでいくことのない波──定常波を形作ります。陽子のクーロン場に捉えられている電子の場合、仮に陽子の周りを回る半径r円軌道上にn波長分の波があるとすると、
2πr = nλ
という関係式が成り立ちます。さらに、遠心力とクーロン力が釣り合うという円運動の運動方程式:
mv
2/r = e
2/r
2
も成立すると仮定すると、λ,r,v について解くことができ、運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの和:
E = p
2/2m - e
2/r …(1)
の値として、
E = 2π
2me
4/n
2h
2
が得られます。多くの(必ずしも正当化できない)仮定を含んでいるにもかかわらず、この式は、水素原子のエネルギー準位を正しく与えており、基底状態のエネルギーは、n=1 の場合に相当します。
基底状態のエネルギー準位は、不確定性関係
ΔqΔp 〜 h/2π
を使って概算することもできます。古典力学では電子はクーロン場の中心にまで落ち込んで原子が潰れてしまいますが、量子力学では、不確定性関係があるため、電子が中心に局在しようとすると運動エネルギーが大きくなってしまい、原子が潰れることはありません。このとき、中心付近での電子の拡がりをr
0 とすると、運動量の不確定性は h/2πr
0 程度になります。したがって、(1)式で与えられる全エネルギーは、
E = h
2/8π
2r
02 - e
2/r
02
となります。この値は、
r
0 = h
2/4π
2me
2
のとき最小になり、そのときのエネルギーは、
E = - 2π
2me
4/h
2
となって、基底状態のエネルギーの値と一致します。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
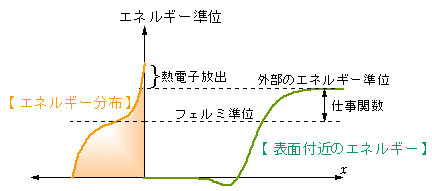
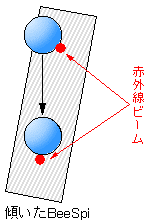 また、金属球のどの部分が BeeSpi内部の赤外線センサーに引っかかるかも、影響を与えます。BeeSpiが傾いていると、金属球の落下開始点がわずかに左右にずれるだけで、速度の測定に誤差が生じてきます(右図;この現象は、水平方向の初速がある場合にも起きる)。この種の誤差は完全になくすことが難しいので、測定回数を(できれば数十回まで)増やして平均を取らなければなりません。
また、金属球のどの部分が BeeSpi内部の赤外線センサーに引っかかるかも、影響を与えます。BeeSpiが傾いていると、金属球の落下開始点がわずかに左右にずれるだけで、速度の測定に誤差が生じてきます(右図;この現象は、水平方向の初速がある場合にも起きる)。この種の誤差は完全になくすことが難しいので、測定回数を(できれば数十回まで)増やして平均を取らなければなりません。
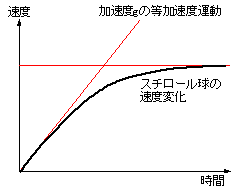 なお、スチロール球の場合は、速度に比例する空気抵抗が大きく寄与して一定の距離だけ落下した後に等速運動になるため、終端速度から求めた加速度は、落下距離が短いほどgに近く、長くなるにつれてゼロに漸近していきます。
なお、スチロール球の場合は、速度に比例する空気抵抗が大きく寄与して一定の距離だけ落下した後に等速運動になるため、終端速度から求めた加速度は、落下距離が短いほどgに近く、長くなるにつれてゼロに漸近していきます。
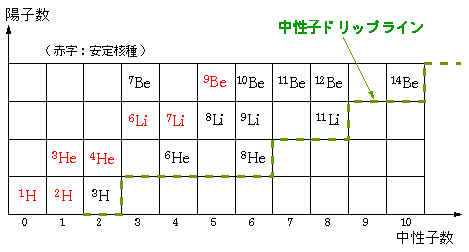
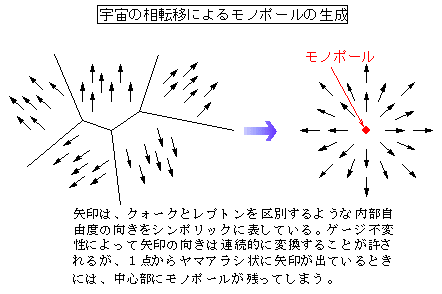
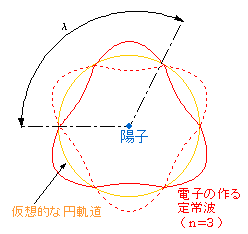 特に、束縛状態にある電子は、どこかに進んでいくことのない波──定常波を形作ります。陽子のクーロン場に捉えられている電子の場合、仮に陽子の周りを回る半径r円軌道上にn波長分の波があるとすると、
特に、束縛状態にある電子は、どこかに進んでいくことのない波──定常波を形作ります。陽子のクーロン場に捉えられている電子の場合、仮に陽子の周りを回る半径r円軌道上にn波長分の波があるとすると、