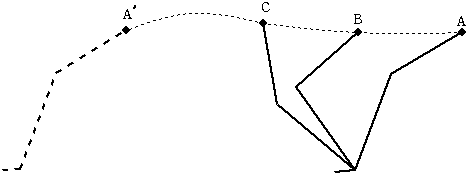格子欠陥や不純物による散乱、結晶粒子の界面での反射などを別にすれば、紫外線領域(波長 400〜数ナノメートル)の電磁波の透過率を決めるのは、主に結晶内部の電子の挙動です。
金属結晶の場合は、自由電子近似を用いると、紫外線が透過するかどうかの違いが直観的にわかりやすくなります。単色電磁波による電場Eの作用で、電子(質量m、電荷-e)が単振動していると仮定しましょう。電子の変位をxとし、運動方程式
md
2x/dt
2=-eE
において、xもEも exp(-iωt) の時間依存性を持つとすると、
-mω
2x = -eE
となり、電子密度をnとすると、単位体積あたりの双極子モーメントPは、
P = -nex = -ne
2E/mω
2
で与えられます。誘電率εは、
εE = E + 4πP
という関係を満たすので、
ε = 1 - ω
p2/ω
2
となります。ただし、
ω
p2 = 4πne
2/m
で定義されるω
pは、プラズマ振動数と呼ばれます。この式より明らかなように、ωがプラズマ振動数以下になると誘電率が負になり、マクスウェル方程式で電磁場が exp(ikx-iωt) の因子を持つと仮定したときの分散関係
k
2 = εμω
2/c
(μ:透磁率、金属ではμ〜1)
において、波数kが虚数になります。これは、媒質内部で電磁場が exp(-|kx|) の形で減衰することを意味し、電磁波が媒質に進入できないことを表します。逆に、ωがプラズマ振動数以上になると、上の分散関係を満たす波数k で媒質を透過することになります。リチウムの結晶の場合、プラズマ振動数に対応する波長は155ナノメートルであり、これより短い波長を持つ紫外線にとって、リチウムは“透明な”媒質となります。
誘電体に関しては、原子に束縛された電子を調和振動子として取り扱うローレンツ模型を使って同様の計算をすることができますが、量子論的な補正をしなければ、定量的に満足のいく結果は得られません。仮に、調和振動子の共鳴振動数をω
0とし、電子が“感じる”局所的な電場を E
L と置くと、運動方程式は、
md
2x/dt
2 + mω
02x =-eE
L
となり、誘電率の計算に、
ε-1 〜 4πne
2/m(ω
02-ω
2)
という項が現れます(局所的電場を求める際の補正も必要ですが、ここでは省略しました)。これより、ω〜ω
0 付近でεが大きく変化して、透過率が急激に変わることが予想されますが、その正確な振舞いは、量子論的な取り扱いをしなければわかりません。ローレンツ模型を使った近似が許されるのはωの大きな領域で、そこでは、ω
0を無視して金属と同様に議論することができます。
【Q&A目次に戻る】

1964年にゲルマンらによって考案されたクォーク仮説は、当時発見されていた全てのバリオンとメソン(中間子)を、u,d,sという3種類の基本粒子から成る複合粒子だと見なすものでした。さらに、ニュートリノν,電子e,ミューオンμという3つのレプトンとの間に、u←→ν,d←→e,s←→μという対応関係があることが指摘されます。こうしたことから、自然界では、3種類の基本粒子が1セットになって物質を構成しているのではないかというアイデアが生まれました。数学的には、(u,d,s)および(ν,e,μ)が特殊ユニタリ群SU(3)のトリプレット(三重項)表現になっているという主張です。
正確に言えば、トリプレット表現のアイデアが先に提唱され、これを元にクォーク仮説が作られています。
その後、ニュートリノにはν
eとν
μの2種類があることが判明、eとμが質量以外はそっくりな性質を持っていることから、(ν
e,e)と(ν
μ,μ)という2つのダブレット(二重項)を考えた方がシンメトリックだと見なされるようになります。これに対応して、クォークにもいまだ発見されていないcクォークが存在し、(u,d)(c,s)という組を考えるべきだという仮説が提唱されます。これが有名なワインバーグ−サラム−グラショウ模型(1968)で、ダブレットを構成する2つの粒子は、WやZ粒子によって媒介される弱い相互作用によって、(c→s,e→ν
eのように)互いに変換されます。2つのダブレット間にはもともと相互作用はありません(クォークに関しては、量子力学的な混合があって、sがuやdに変わることがあります)。cクォークを含むメソンは、1974年に発見されました。
2つのダブレットだけでは、実験で示される全ての現象を説明できないことを明らかにしたのが、1973年の小林−益川の理論です。彼らは、実験データと合致させるためには、クォークが少なくとも6個なければならないことを数学的に証明しました。
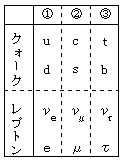
ワインバーグ−サラム−グラショウ模型と調和させ、クォークとレプトンの間のシンメトリーを保つには、クォーク/レプトンごとにダブレットが少なくとも3つは必要になります(右図)。その後、Z粒子を大量に作る加速器実験によって、この宇宙にダブレットはたかだか3つしかないことが確定されました。3番目のダブレットに含まれる粒子(bおよびtクォークとτ粒子)は、1998年までに全て発見されています。
クォークとレプトンの各3つのダブレットは、それぞれ独立のものであり、各ダブレット間に何らかの相互作用があるのか、なぜ3つのダブレットだけが存在するのか、全くわかっていません。便宜的に「世代(generation)」という呼び方で区別していますが、これらを生み出す(generate)原理がわかっている訳ではありません。同じ世代に属するクォークとレプトンのダブレットを1つにまとめる大統一理論は提唱されているものの、理論を実証するデータはほとんど無く、各世代間の関係を明らかにする理論に至っては、信頼性のあるものは1つもないと言って良い状況です。
【Q&A目次に戻る】

ボーズ・アインシュタイン凝縮は、統計的にしか記述できないはずの多数の粒子集団が、極低温状態で同一の量子力学的状態になって協調的な振舞いを示すようになることを意味します(したがって、原子1個について考えることはできません)。「約2000個のルビジウム原子」の凝縮は、絶対温度1000万分の1度にまで冷却することによってようやく実現されました。
多数の原子から成る理想気体を考えてみましょう。通常の温度領域では、個々の原子は異なる運動量を持って飛び回っており、運動量の違いによって原子を識別することができます。このとき、原子集団の統計的な振舞いは、気体原子はビリヤード玉のようなものだと考える古典的な理論と似たものになります。ところが、この気体を冷却していくと、各原子の運動エネルギーはどんどん小さくなり、ついには、ほぼ全ての原子が、並進運動量を持たない最低エネルギー状態に落ち込みます。古典論では、たとえ動かなくても原子を互いに区別することは可能ですが、量子論では、同じ状態の原子を区別することは、原理的に不可能です。こうして、全ての原子が単一の波動関数に従って同じように(協調的に)振舞うことになり、古典論の範囲では説明の付かない奇妙な現象が見られるようになります。
ボーズ・アインシュタイン凝縮の最も有名な例は、超流動ヘリウムです。液体ヘリウムを絶対温度2.2度以下に冷却すると、全ての原子が同じように動こうとするため、原子間の摩擦として生じる粘性が消失します。このため、容器の中に入れようとしても、するすると容器壁を上って外に流れ出してしまいます。また、超流動ヘリウムを回転させようとすると、全ての原子が同じ角運動量を持つため、ヘリウム全体の角運動量も量子化されて飛び飛びの値しか取れなくなります。
ルビジウムなどの原子を集めて作った凝縮体で角運動量が離散的になることは、1999年にレーザーで凝縮体を回転させる実験を通じて確かめられました(凝縮体内部に渦が発生している写真が撮影されています)。粘性については実験が難しいので確認がとれていませんが、おそらくその値はきわめて小さく、内部に発生した波は減衰せずに存続し続けると予想されます。
【Q&A目次に戻る】

光線が二重スリットを通り抜けて背後の感光板上に干渉パターンを作っているとき、1個1個の光子がどちらのスリットを通り抜けたかを完全には決定できないという(実験的にも検証された)事実は、量子論の不思議さを際だたせるものとして、解説書などでよく取り上げられています。しかし、この実験は、かえって量子論的な過程の本質を見誤らせる問題点を孕んでいます。その点から説明していきましょう。
量子論には、古典論とは著しく異なる2つの特徴があります。第1は、初期条件を与えても、その後の時間発展を一意的に決定できないという「非因果性」です。このため、量子系の振舞いを規定するシュレディンガー方程式の解は、状態変化を確率的に表す確率振幅でしかなく、観測を通じて状態が確定された場合は、新たに境界条件を付け加える必要があります(これが波動関数の“収縮”と呼ばれるものです)。第2は、粒子描像に基づく軌道の概念が適用できず、波動描像に基づく方法論を援用する必要があるという「粒子・波動二重性」です。電子のような粒子的な対象が、電子線回折などの波動的振舞いを示すのは、この性質の現れです。
本来、「非因果性」と「粒子・波動二重性」とは、峻別される特徴のはずです。理論的な計算において、前者は、始状態iから終状態fに至る遷移確率T
ifの中に、後者は、T
ifに寄与する積分項の中に、それぞれ姿を現します。電子−陽子散乱を例に取りましょう。この場合、エネルギーがある値を超えると、散乱後に電子と陽子が互いに飛び去っていく弾性散乱以外にも、陽子が壊れて多数のπ中間子などが発生する非弾性散乱が起きるようになり、始状態を決めただけでは、終状態がどうなるかは決定できません。各終状態に対して生起確率だけが与えられるというのが、非因果性の物理的な意味です。さらに、終状態を特定して遷移確率を計算する際に、いくつかの項が干渉するという波動特有の振舞いが見られます。
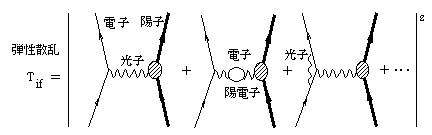
弾性散乱の場合、最も単純な1光子交換に加えて、右のファインマン図で表されるさまざまな高次項が現れますが、各項が遷移確率に加法的に寄与するのではなく、絶対値の2乗を取るために、異なる項の積が消えずに残ります。つまり、散乱過程の途中に現れる光子や電子などは、軌道が確定している古典的な粒子ではなく、互いに干渉しあう波動的な性質を示しているという訳です。
二重スリット実験の場合でも、光子の到達場所が確率的にしか定められないという「非因果性」と、異なる中間状態の干渉が生じるという「粒子・波動二重性」を分けて考える必要があるはずです。ところが、実験のセットアップがあまりに単純で、簡単なシュレディンガー方程式を解くだけで直ちに遷移確率が求められるため、どうしても、この2つの性質を一緒くたにして議論してしまいがちです(実際、多くの解説書がそういう取り扱いをしています)。その結果、「始状態が与えられただけでは終状態が確定できない」という本来の非因果的な主張だけでなく、中間状態に見られる波動的な性質に関しても、「確定的なことは何も言えない」という不可知論的なステイトメントが、あたかも量子論の基本的命題であるかのように述べられることになります。
こうした誤解の背景には、「観測されないものについては状態を定義できない」という量子力学黎明期にハイゼンベルグが広めた哲学的な世界観があると思われます。ハイゼンベルグが執筆した啓蒙的な書物は、量子論的世界観の斬新さを一般の人々に伝える上で歴史的な役割を果たしたものですが、いささか勇み足的な発言も多く、無批判に受け入れることはできません。実際、金属の超伝導に関しては、電子状態そのものを観測しなくても、マイスナー効果を確認するだけで、クーパー対の形成に関して確定的な言明をすることが可能ですし、無機錯体の色の変化を見さえすれば、配位子場による3d軌道の分裂が起きたと断定できます。中間状態が観測されていないからといって、そこで何が起きているか語れない訳ではありません。
二重スリット実験で中間状態を確定するには、散乱問題で遷移確率を求める場合と同様に、始状態と終状態を選んだ上で量子力学的な計算を行なうことが必要です(厳密に言えば、もう少し制約を付けなければいけませんが、専門的になるのでここでは省略します)。このとき、干渉が生じるような条件が満たされているならば、中間状態が「スリットの一方を通過した」と確定されることはなく、それぞれのスリットを通過している状態の重ね合わせという形で記述されます。この中間状態は、あくまで理論的に記述されるだけなので、通常「現象(phenomenon)」とは呼ばれません。「量子過程(quantum process)」という言い回しが好まれるようです。しかし、現実と結びつかない便宜的な記述ではなく、物理的な過程を適切に記述していると信じられています。「干渉」や「回折」そのものは直接観測できませんが、「干渉を起こさない量子過程」を仮定した理論は(不自然な条件設定を行わない限り)観測された干渉縞の存在を説明できませんから、(それを否定した理論が反証されるという意味で)間接的に「反証可能」であると見なせます。
【Q&A目次に戻る】

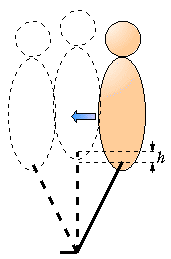
当たり前のことですが、単純に足を鉛直方向に振り下ろしても、上に飛び上がる力しか作用しません。水平歩行の運動量を得るには、移動中に関節を巧みに折り曲げることが必要になります。
足に膝関節がないとすると、人間が2足歩行するためには、足首を中心とした円周に沿って重心を持ち上げるような運動をしなければならず、図のhだけ上体を持ち上げるためのエネルギーmgh(m:上体の質量、g:重力加速度)を供給する必要があります。これでは効率が悪く、スピードが出ません。
疾走する場合、人間は、無意識のうちに関節を曲げて、上下動を最小限に抑えるようにします。このときの関節の曲げ方と上体(黒丸で表す)の移動は、下図のようになります(実際には、足首から先の動きも重要ですが、ここでは省略します)。図のAからBでは、上体はほぼ水平(わずかに沈み込む)に移動しているので、足の筋肉を使ってエネルギーを供給しなくても、慣性によって前に移動していきます。重心が接地点の前方に位置するBからCにかけて、関節を伸ばすように筋肉を働かせると、地面を後方に蹴る形になるので、重心を前方に押し出す作用が働いて水平方向の運動エネルギーが得られます。これが、摩擦や空気の抵抗に抗して前方に進み続けるパワーの元になります。さらに、CからA′では体が地面から離れて放物運動を行いますが、この間に、もう一方の足を前に出し、A′で着地してから同じような運動を繰り返します。4足歩行では足の出し方に複数のパターンが見られるようになりますが、エネルギーの供給法は基本的に同じです。
上下動はエネルギーの無駄遣いになるので、ピョンピョンと跳びながら移動する動物以外は、「足の振り下ろし」にはあまりエネルギーを使わないようにしています。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
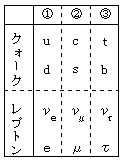 ワインバーグ−サラム−グラショウ模型と調和させ、クォークとレプトンの間のシンメトリーを保つには、クォーク/レプトンごとにダブレットが少なくとも3つは必要になります(右図)。その後、Z粒子を大量に作る加速器実験によって、この宇宙にダブレットはたかだか3つしかないことが確定されました。3番目のダブレットに含まれる粒子(bおよびtクォークとτ粒子)は、1998年までに全て発見されています。
ワインバーグ−サラム−グラショウ模型と調和させ、クォークとレプトンの間のシンメトリーを保つには、クォーク/レプトンごとにダブレットが少なくとも3つは必要になります(右図)。その後、Z粒子を大量に作る加速器実験によって、この宇宙にダブレットはたかだか3つしかないことが確定されました。3番目のダブレットに含まれる粒子(bおよびtクォークとτ粒子)は、1998年までに全て発見されています。
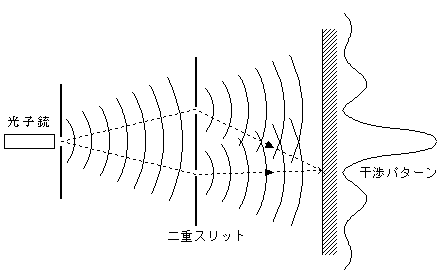
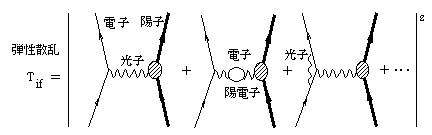 弾性散乱の場合、最も単純な1光子交換に加えて、右のファインマン図で表されるさまざまな高次項が現れますが、各項が遷移確率に加法的に寄与するのではなく、絶対値の2乗を取るために、異なる項の積が消えずに残ります。つまり、散乱過程の途中に現れる光子や電子などは、軌道が確定している古典的な粒子ではなく、互いに干渉しあう波動的な性質を示しているという訳です。
弾性散乱の場合、最も単純な1光子交換に加えて、右のファインマン図で表されるさまざまな高次項が現れますが、各項が遷移確率に加法的に寄与するのではなく、絶対値の2乗を取るために、異なる項の積が消えずに残ります。つまり、散乱過程の途中に現れる光子や電子などは、軌道が確定している古典的な粒子ではなく、互いに干渉しあう波動的な性質を示しているという訳です。
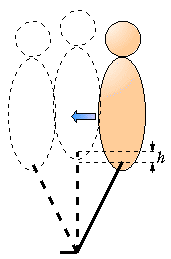 当たり前のことですが、単純に足を鉛直方向に振り下ろしても、上に飛び上がる力しか作用しません。水平歩行の運動量を得るには、移動中に関節を巧みに折り曲げることが必要になります。
当たり前のことですが、単純に足を鉛直方向に振り下ろしても、上に飛び上がる力しか作用しません。水平歩行の運動量を得るには、移動中に関節を巧みに折り曲げることが必要になります。