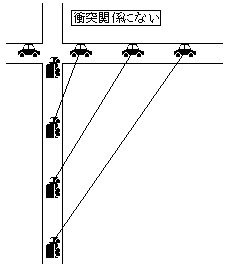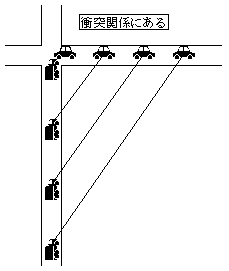超弦(ひも)理論(super string theory;最近では単に弦理論ということが多い)は、1980年代に、ただ1つの方程式であらゆる物理現象を記述する「万物の理論(TOE;theory of everything)として期待されたものですが、最近は、理論的にやや行き詰まっているようです。
超弦理論が登場する前、素粒子物理学界は、実験面での成功に酔いしれる反面、理論面での欠陥に対する不満が高まりつつありました。
成功は、主として、1970年代半ばまでに完成された「標準理論」によるものです。この理論によると、物質の構成要素には、クォーク族(陽子や中性子を構成する)とレプトン族(電子、ニュートリノなどから成る)の2種類があり、これらの間の相互作用を媒介するものとして、グルーオン、弱ボソン、光子の3種類のゲージボソンが存在します。大型加速器を使った実験データは、ことごとく標準理論の正当性を立証するものでした。ここに到って素粒子物理学は初めて、高い精度を持って理論が実験結果を予測できる精密科学としての地位を獲得したのです。
しかし、「標準理論」は、理論家を満足させないいくつかの欠陥を抱えていました。第一の欠陥は、素粒子の種類が(数え方によっては)3ダース以上に上り、「究極の理論」とは考えにくい点です。ちょうど、19世紀末に元素の種類が膨大なものになり、より根源的な(原子核)理論が必要とされたのと似ています。こうした状況を打開するために、(大統一理論や複合模型理論など)新しい理論がいくつも提案されましたが、素粒子の種類を減らすという点では必ずしも成功を収めませんでした。もう1つの欠陥は、「発散の困難」と呼ばれる問題で、相互作用を行う素粒子の間の距離を無限に小さくして計算すると、いろいろな物理量が無限大になってしまうというものです。この点に関しては、朝永振一郎らの「くりこみ理論」によって、遠距離での予測に影響を及ばさないような計算テクニックが開発されていますが、ミクロの極限では理論が破綻をきたすという点で、理論の根幹にかかわる大問題と言えます。さらに、20世紀の理論物理学において量子力学と双璧をなす一般相対論(重力理論)が取り入れられておらず、これを取り込もうとすると「発散の困難」がくりこみ理論でも始末できないほど厄介なものになってしまうという問題もあります。
超弦理論は、これらの欠陥を一気に解決する驚くべき理論として注目を浴びてきました。歴史的には、1970年代に展開された2つの理論−−南部陽一郎らによる中間子をひも状の素粒子として扱う弦理論と、シャークらによる「力」と「物質」を統一する超対称性理論−−が合体してできあがった理論で、1984年のグリーンとシュワルツによる論文が、現代的な超弦理論の出発点とされています。この理論によれば、(力と物質をあわせた)万物の構成要素は、大きさが10
-35m程度の1種類の「ひも」であり、これが、いろいろな形に捩れたり巻き付いたりしたものが、クォークやゲージボソンなどの多種類の素粒子に対応するというのです。また、「発散の困難」は、素粒子を点状のものと考えたことに起因するもので、大きさを持ったひもを扱うときには、こうした困難は(ある条件の下で)回避されます。さらに、超弦理論によれば、時間や空間は、弦がその内側に持っている「内部自由度」から派生的に生み出されるものであり、時空の性質としての一般相対性や重力法則も、弦の振舞いに起源を持つことになります。実際、あるタイプの超弦理論からアインシュタインの重力理論が導かれることが、すでに示されています。
もっとも、このように記すと、超弦理論が「万物の理論」として成功しているかのように誤解されるかもしれませんが、現実はそれほど甘くありません。まず、超弦理論は数学的にあまりに難しく、上に述べたような好ましい性質が理論的にきちんと導かれた訳ではないのです(その難しさは、理論の枠組みを作り上げるための研究をしていたウィッテンが、数学のノーベル賞と言われるフィールズ賞を受賞したことからもわかると思います)。また、超弦理論にはさまざまなタイプがあり、どれが現実を記述する理論か決められません。検討されたタイプは、いずれも内部自由度が大きすぎて、標準理論に見られる数ダースの素粒子表をピッタリ埋められるような巻き付きのパターンを与えることができないでいます。アインシュタインの重力理論を導いたとはいっても、その「種」となる共変性はあらかじめ理論の前提として仕込まれていたのですから、大した成果とは言えないかもしれません。何よりも、「ひもの振動」を記述するきわめて数学的な理論が、この世界のあらゆる現象を説明するという発想それ自体に、居心地の悪さを感じてしまいます。故ファインマンやグラショウ、ホーキングといった現代物理学の碩学たちが、超弦理論に対して疑いの眼差しを向けているのも、頷けます。
科学とは、常にtrial and errorの繰り返しであり、膨大な研究の果てにほんの僅かの成功した理論が生き残っていくのですが、超弦理論という壮大なtrialが最後にどのような形で終わるのか、専門家ならずとも興味のわくところです。

かつては『魔法の弾丸』と言われた抗生物質も、過剰な使用や治療途中での使用中止などの不適切な使用法がたたって、いまや耐性菌の逆襲を受けています。かつては肺炎や梅毒など多くの感染症を克服することができたペニシリンはもとより、クロラムフェニコールやテトラサイクリン、メチシリンなど、人類が開発したさまざまな抗生物質も、その有効性が徐々に失われてきています。
そうした中で、1960年代に開発されたバンコマイシンは、アミノ酸に結合して菌の細胞壁合成を阻害する機能に優れ、史上最強の抗生物質と謳われてきました(ただし、副作用もかなりありますが)。欧米で30年以上にわたって使用されてきたにもかかわらず、耐性菌がほとんど生じなかったことからも、その優秀さがうかがえると思います。
ところが、1980年代に、それまで多用されてきたメチシリンが効かないMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)による院内感染が広まったため、MRSAに著効のあったバンコマイシン使用量が急速に増え、その結果として、短時日のうちにバンコマイシンの耐性菌が現れてしまいました。このほか、家畜の病気予防や腸での吸収効率増進のために餌にバンコマイシンと似た構造を持つ抗生物質を混ぜていたことも、耐性菌出現を促したと考えられています。
まず、1986年にフランスでVRE(バンコマイシン耐性腸球菌)が確認されました。その後、VREの報告例が欧米で相次ぎ、89年に0.3%だった出現頻度が、93年には7.9%に跳ね上がっています。VREは、日本でも見いだされており、98年春には、ガン手術を受けた60代の男性が感染して死亡したことが報告されています。ただし、VREの病原性は弱く、健康な人が感染してもほとんど影響はありません。
VRE以上に恐れられているのが、院内感染で問題になる黄色ブドウ球菌です。
バンコマイシンの効かないMU50(バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌)が、
1996年に平松啓一・順天堂大教授によって国内の病院で検出され、その後、
アメリカでも発見されています。細菌間では、種類が異なっても遺伝情報
を伝達する「水平遺伝」が可能なため、VREから黄色ブドウ球菌へと耐性が
伝わった可能性もあります。
事態を重視した厚生省が、1997年の11月から12月にかけて、全国278施設で調
査を行っています。患者から発見された6625株のMRSA(メチシリン耐性黄色ブ
ドウ球菌)について検査したところ、3.7%に当たる248株がバンコマイシンが
効きにくい性質を持っていることが判明しました。病院数では、調査対象の4
割に当たる113施設で検出されています。
黄色ブドウ球菌の中でMRSAが占める割合は、1986年で約25%だったのが90年に
は50%を越えており、抗生物質が使われ続けると急速に増加する傾向があるた
め、現在のようにバンコマイシンが多用されている状況では、MU50も急増する
可能性が高いと考えられます。
ただし、MRSAによる院内感染が1993年頃に大きな社会問題になって以降、病院
側でも対策委員会を設置して、手指の消毒などを徹底しているため、MU50の院
内感染が死亡事故につながったケースはないようです。MU50が治療にどの程度
の悪影響を与えているかは、現時点でははっきりしていません。
このように見てくると、抗生物質には未来がないようにも思えますが、必ずし
も悲観的になる必要はありません。耐性菌は、抗生物質に抵抗するために通常
の細菌にはない機能(抗生物質を分解する酵素の産生など)を備えており、こ
れが生育上の負担となっています。耐性菌がはびこっているのは、抗生物質が
コンスタントに使用されている状況下で、他の細菌よりも環境適応度が高くな
っているからに他なりません。したがって、抗生物質の使用を適切にコントロ
ールし、微生物環境に安易に放出することをなくせば、耐性菌であることのメ
リットはなくなり、他の細菌との生存競争に敗れていつかは消滅するはずです。
要は、抗生物質の適切な使用を医者も患者も心がけることです。

北海道などのの見通しの良い平原にある交差点で、互いの車がよく見えているはずなのに衝突事故が起きることがあります。従来は、単にドライバーの不注意として片づけられてきましたが、実は、人間の視覚特性が大きくかかわっていることがわかってきました。
図からわかるように、2台の車が一定の速さで動いている場合、相手の車が「動いて見える」(車の方位が刻々と変化する)ならば交差点での衝突は起こりませんが、常に同じ方位に見えているときには、両者は「衝突関係にある」ことになります。こうした状況は、飛行機のパイロットや船舶を操る船長にはよく知られていることですが、自動車の場合には、たとえ衝突関係にあるときにも、周囲の建物に対して相対的に移動しているため相手は「動いて見える」はずなので、あまり問題にされませんでした。しかし、建物がない開けた平原では、衝突関係にある相手の車は、背景の山並みなどに溶け込んでしまい、動きがほとんど捉えられなくなります。こうして、動いていなかったはずの車と出会い頭に衝突するという結果になるのです。
さらに、自動車の運転では、前方の道路上に注意を集中するので、交差する道路を走っている車は視野の周辺部で捉えられることになりますが、これも重要なポイントです。こうした「周辺視」の場合、対象物が視野の中で動かないと、中心部で見ているときよりも、「見えた」という認知につながりにくいことが、認知心理学の実験によって確かめられています。こうして、相手の車が完全に見えていたはずなのに、「見れども見えず」という状態になってしまうのです。