
永久磁石を2つに切断しても切り口がそれぞれN極とS極になって、N極ないしS極だけのモノポール(磁気単極子)は存在しない──というのが、20世紀初頭までの電磁気学の常識でした。この常識に挑戦したのが、イギリス人物理学者ディラックで、彼は、ディラック・ストリングと呼ばれる奇妙な存在を認めれば、マクスウェル方程式の中にモノポールの項を導入できることを示しました。こうすれば、電磁気の方程式群は双対変換という電気と磁気を入れ替える変換操作に対して対称的になり、数学的にきわめてシンメトリックになります。ただし、ディラック・ストリングはいささか非現実的な代物であるため、多くの物理学者はモノポールの存在に対して懐疑的でした。
事情が変わったのは1970年代の終わり頃で、トフーフトとポリヤコフという2人の学者が、素粒子の大統一理論(Grand Unified Theory)を適用すれば、ストリングのないモノポールが存在できることを示し、にわかにこの奇妙な粒子に対する関心が高まりました。特に、1982年に、著名な実験物理学者キャブレラが、長期にわたって実験している間に1個のモノポールが装置を横断したことを示すデータを得たと発表して、大きなニュースになりました。しかし、キャブレラに“幸運”は2度と訪れず、他の研究者の追試もうまくいかなかったため、このデータは今では黙殺されています。このほか、月の岩石中にモノポールが閉じこめられていないか、ニュートリノを利用した実験で尻尾を捕まえられないか、ビッグバンのときにできたものがいまだに宇宙を漂っていないか──とモノポール探索の試みがたびたび繰り返されました(日本では、1980年代後半に KAMIOKANDE という施設で研究が行われました)が、いずれも成功していません。今なお探索を続けている実験物理学者もいますが、そもそもモノポールなど存在しないか、あるいは、あったとしてもごくわずかだと考える学者が増え、以前の熱狂はすでに冷めてしまったようです。
ただし、モノポールが実際に発見されれば、中性子や中間子の発見に匹敵する物理学史上の大事件として、確実にノーベル賞の対象となります。モノポールは安定な粒子なので、見つかったモノポールは大切に保管され、大統一理論の検証や電磁現象の基礎的性質のチェックに利用されることでしょう
(実験中になくしでもしたら、それはもう大騒ぎです)。
【Q&A目次に戻る】

電気ブランコとは、導線で金属棒を磁界内に吊り下げて、電流を流して運動させる実験装置で、中学の理科でフレミングの法則などを勉強する際に、良く利用されます。右図のように長さL の金属棒に流れる電流i とU字型磁石が作る磁界B が直交する場合は、フレミングの法則より、図の右向きにiBL という大きさの力が加わります。このとき、ブランコの振れの角度φは、磁界からの力iBL、重力mg、糸の張力Tが釣り合うという条件より、
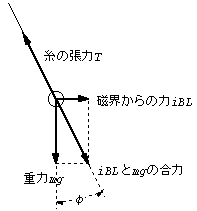
tanφ = iBL/mg
で与えられます。実際には、U字型磁石の内部で磁界に粗密の差がありますが、その場合は、金属棒の各点に加わる力を積分して、棒全体の釣り合いの式を立てることになります(棒の軸方向に磁界が変化しなければ、上の式のままでかまいません)。ブランコでなくて坂道で金属棒を転がしたときは、「φ=一定」となるので、B が上式を満たす値になる地点があれば、そこで釣り合います。また、電流の向きが反対の場合には、磁界からの力が逆向きになるのでブランコは反対側に振れます。
…というのが、通常の教科書に書いてある説明ですが、これでは満足できないという人もいると思います。例えば、磁界からの力は、金属棒に直交するのでニュートンの運動方程式によれば仕事をしないはずなのに、なぜブランコが振れて重力のポテンシャルエネルギーが増加したのか、疑問に感じる人もいるでしょう。こうした疑問に答えるためには、金属棒内部での荷電粒子の微視的な運動を考察する必要があります。
金属中の電子は、通常は高速でデタラメな熱運動をしていますが、これに外部電源を接続して一定方向に電場を印可すると、秒速数メートルの割合で(電場と逆向きに)移動し始めます。これが、電流が流れている状態です。ここに、さらに外部から磁界H を加えると、1個1個の電子に、速度v と微視的磁界h(〜H) の外積に比例するローレンツ力
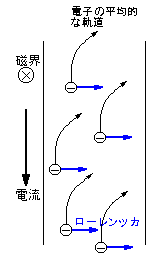
f = ev・h
が加わります(ローレンツ力の正体はアインシュタインの相対性理論によって明らかにされますが、ここでは、これ以上は詳しく説明しません)。この力によって電子の軌道が曲げられ、金属棒内部で電子の分布が変化して電場が生じます。この電場が結晶を構成する金属イオンに作用したものが、「磁界から電流に加わる力」に相当します。さらに、この力によって金属棒が運動を始めると、ファラデーの電気誘導の法則に従って、金属棒内部に起電力が発生します(起電力が発生する理由も、相対性理論によって説明されます)。金属棒に供給されるエネルギーは、「磁界から電流に加わる力」がした仕事としてではなく、外部電源の電圧によって、この起電力に抗して電子を移動させることでもたらされたものです。電気ブランコの場合、外部電源が供給したエネルギーが、重力のポテンシャルエネルギーに変化したため、ブランコの位置が以前よりも高くなったのです。
【Q&A目次に戻る】

特定の実験装置に量子力学の法則を当てはめると、あたかも遠隔相互作用が行われているかのような現象が予想されることは、1935年にアインシュタイン−ポドルスキー−ローゼンの連名の論文で指摘されました。3人の頭文字をとってEPR効果と呼ばれるこの現象を、アインシュタインは「一種のテレパシー」と表現し、このように“物理的にあり得ない”現象を導き出す量子力学は誤った理論だと結論しましたが、1950年代になって予想された通りの現象が実験的に観測され、現在では、量子力学に従うこの世界の現実の性質として受け入れられています。
多くの物理学者は、EPR効果を「相互作用(interaction)」ではなく「相関(correlation)」と解釈しています。これは、EPR効果を使っても、空間的に離れた地点に一瞬のうちに作用を及ぼすことが不可能だからです。
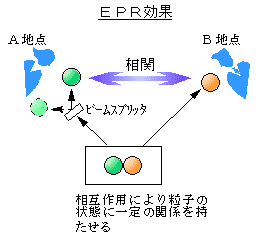
典型的なEPR効果とは、次のような実験で観測されます(右図)。
- はじめに、ある地点で2つの粒子(多くの場合、光子が使われます)を相互作用させて、両者が一定の量子論的な関係を持つようにします。
- 次に、2つの粒子を(光子ならば光ファイバーなどを使って)空間的に引き離し、互いに相互作用を及ぼしあわなくなった2地点A,Bで、各粒子の適当な物理量に関して測定を行います。
- このような実験を繰り返し行うと、測定結果の組(a,b)が多数得られ、統計的な相関分布が求められます。
量子力学の場合、相関分布は、どの物理量を測定するかによって変わってきます。例えば、A地点でカイラリティχを、B地点で特定方向のスピンsを測定したときのデータ(χ
a,s
b)と、A,B両地点でスピンを測定したときのデータ(s
a,s
b)は、それぞれ特有の分布を示します。そこで、A地点でχとsのどちらを測定するかを粒子が到達する直前に(ビームスプリッタなどで)切り替えたら、どうなるでしょうか。驚くべきことに──と物理学者たちは考えました──このような切り替えを行っても、A地点でカイラリティを測定したときのデータだけを集めると、初めからカイラリティを測定しようと準備していた場合と同じ結果になり、スピンを測定したときのデータだけを集めても、同様になったのでした。これは、まるで、A地点で何を測定するかがB地点の粒子に一瞬のうちに伝わったかのようです。さらに、B地点の方で時間的に先に測定した場合でも同じ結果になるので、A地点で何が行われるかを“予知”しているようにも見えます。EPR効果とは、こうした不思議な相関の存在を指しています。
EPR効果が「なぜ」生じるかについては、(ごく一部の例外を除いて)ほとんど研究が行われていません。多くの物理学者は「量子力学とはこういうものだ」と解釈しており、新たな理論を導入する必要性を感じていないからです。
EPR効果を利用して一種のテレポーテーションが可能であるというアイデアは、1993年にIBMのベネットら6人の研究グループによって提出されました。ただし、誤解のないように言っておくと、ここでいうテレポーテーションとは、ある物体を別の地点へ一瞬のうちに移送するようなものではありません。
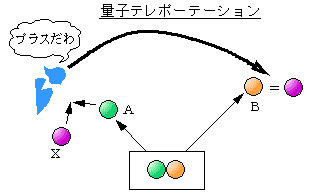
実際にテレポートさせられるのは、光子や原子などの粒子の状態です(右図)。ある測定を行うと一定の結果が得られるような状態を取っている粒子Xを考えましょう。ここで、粒子対A,Bを用意し、AとXを相互作用させながら測定した結果がプラスになったならば、BがXと同じ状態にあることがわかるように、A,Bを相関させておきます。さて、AとBが充分に引き離されたところで、AとXを相互作用させて測定を行ったとしましょう。このとき、測定結果がプラスと出れば、その瞬間(光よりも速く)BがXと同じ状態であることがわかります。一方、Aと相互作用させたことにより、Xの状態は変化してしまいます。ベネットらは、この過程を「Xの状態がBにテレポートした」と表現したのです。この実験は、すでに1997年に実施されており、光子の偏光状態に関する量子テレポーテーションが確認されました。この技術を改良すれば、ある実験室に置かれたサンプルの分子状態を別の地点にコピーするのに使えるかもしれません。
残念ながら、量子テレポーテーションを利用しても、物質の瞬間移動ができないだけでなく、光速以上のスピードで通信することすら不可能です。実際、遠く離れた地点でBの状態を測定したとしても、それがXのもともとの状態と同じかどうかは、Aで行われた測定結果がプラスであることを(従来の通信技術を使って)教えてもらうまではわからないのです。なお、ザイリンガーなど一部の物理学者は、物質転送がさも実現できそうな文章を書いていますが、私には、彼らが本気であるとは思えません(物理学者は、ジョークが好きなのです)。
物理学者たちが量子テレポーテーションに興味を示すのは、それが量子力学の根本的な性質と深くかかわっているせいでもありますが、同時に、これを使ってきわめてセキュリティの高い暗号を作ることができるからです(このほか、量子コンピュータへの応用もあります)。EPR効果をもたらす粒子対の相関はきわめて脆弱で、外部からわずかでも作用を加えるとすぐに壊れてしまいます。記号列を量子テレポーテーションを利用して伝えているときに、何らかの方法で外部からこのやりとりに介入すると相関が壊れてデータ送信に異常が生じるため、“盗聴”されたことが確実に判明します。現在用いられている暗号は次世代コンピュータを使えば短時間で解読できてしまうことが知られており、物理法則によって盗聴が原理的に不可能になる量子暗号は、将来的に国家機密などの通信に役立てられると期待されています。
【Q&A目次に戻る】

セファイド型変光星の変光周期と絶対光度の間に一定の関係があることは、1912年にマゼラン星雲の観測を行っていたリービットによって報告されました。それ以来現在に至るまで、比較的近傍のセファイドの観測を通じて、周期−光度関係を正確なものにする試みが続けられています。さらに、この関係を遠方のセファイドに当てはめて、観測された周期から絶対光度を割り出せば、見かけの光度と比較することによって距離を決定することができます。最近では、NGC4603銀河に含まれるセファイドをハッブル望遠鏡で測定することにより、地球から1億800万光年の距離にあることが判明しました。
セファイドの変光メカニズムは、天体物理学によってかなりの程度まで解明されています。セファイドは脈動変光星とも呼ばれており、重力とガス圧のバランスが崩れて星全体がまるで脈打つように膨らんだり縮んだりすることによって、光度が変化しているのです。その過程をごくかいつまんで説明すると、次のようになります。
セファイドは、主に水素とヘリウムから成るガスでできています。中心部で発生した光は、このガス層を通り抜けて宇宙に放出されますが、その途中で一部の光子が電子をはじき出してイオン化します(あるいは、1価のヘリウムイオンを2価に変化させます)。この状態変化によってガスの透明度が低下し、通り抜けられなくなった光子が吸収されてガスを加熱するようになります。こうして高温になったガスは、膨張するとともに明るく輝き始めます。しかし、膨張を続けるうちに温度が低下し、イオンが再び電子と合体すると、内部からの光はまたガスを素通りするようになります。こうなると急速にガスは冷却され、重力がガス圧に打ち勝って収縮に転じます。通常のセファイドは、数日から数ヶ月の周期で、このサイクルを繰り返します。
星全体が膨らんだり縮んだりすることから、セファイドの変光周期は、天体の大きさと密接な関係があり、ちょうど長い弦がゆっくり振動して低い音を出すように、大きなセファイドほど周期が長くなります。きちんとガス体の状態方程式を立て、エネルギー輸送についてのいくつかの仮定を置いて計算すると、周期が天体の平均密度の平方根に反比例するという関係式が得られます。また、セファイドの光度は、ガスの熱放射に関する法則からだいたいの値が導けますが、これも、基本的には天体が大きいほど明るくなります。このようにして、周期と光度の間に正の相関が存在することが示されます。
ただし、こうした理論計算には限界があります。例えば、実際のセファイドには、金属成分の多いI型と少ないII型があり、I型の方がII型より1.5等級ほど明るいことが知られていますが、こうした定量的な関係を天体物理学を使って導くのは困難です。このため、天体距離の較正に利用する周期−光度関係は、観測データをベースにしています。現在、周期−光度関係を確定的なものとするため、地球に近い(と言っても300光年以上離れていますが)数十個のセファイドの年周視差を測定して厳密な距離を求める計画が進められています。
セファイドの変光が他の変光星と異なって星全体の膨張・収縮によって生じていることは、これまでドップラー効果によって間接的に確かめられていました。膨張するときには光源が観測者に向かってくるので波長が短くなってスペクトルが青方偏移を示し、収縮期にはその逆になるというものです。ところが、1999年にカリフォルニア工科大学の観測チームが、セファイドが大きくなったり小さくなったりするさまを直接観測することに成功し、多くの天文学者を驚かせました。全天中で最も明るいセファイドの1つである Zeta Geminorum をターゲットとしたこの試みでは、110メートルの2台の干渉計を用いて、1100光年の彼方にあってわずか0.0000004度の視角しかないこの天体が、さらにその10分の1だけ大きさを変化させていることを捉えました。こうした努力を通じて、かつて謎の天体と言われたセファイドも、次第にその姿を明らかにしているのです。
【Q&A目次に戻る】

ワームホールとは、一般相対論の特殊な解として想定されているもので、現実に存在するものなのか、全くわかっていません。理論的に可能な例として最初に考案されたのは、ブラックホールの周囲の空間の状態を表すシュヴァルツシルトの解を、途中で“別の宇宙”のシュヴァルツシルト解と接続してしまうというものです。これは、外から見るとブラックホールのように見える領域が実は別の空間とつながりを持っていることを意味しています。2つの空間をつなぐ部分は、当初、アインシュタイン−ローゼン橋と呼ばれました。
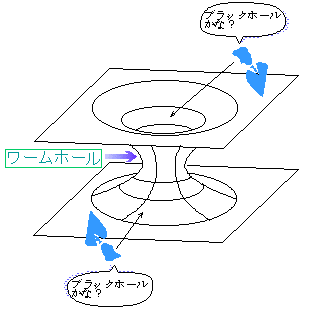
さらに、同じ宇宙の中で、空間のある部分と別の部分をつなぐような特殊解も理論的には可能であることがわかり、ホイーラーらによってワームホール(虫食い穴)として一般化されます。
ワームホールは、空間の懸け離れた2点を結ぶものではあっても、残念ながら、両端がブラックホールになっているため、これを通り抜けて“ワープする”という訳にはいきません(ブラックホールからは何物も脱出できないので)。おまけに、内部には巨大な重力が発生しているので、その潮汐力によって、いかなる物質もバラバラに引き裂かれてしまいます。また、一般相対論の方程式をそのまま適用すると、自分自身の重力で一瞬のうちに潰れてしまうことが、ホイーラーによって明らかにされました。このため、この宇宙のどこかに大きなワームホールが実在する可能性はほとんどないと考えられています。ただし、1980年代にソーンらが「負のエネルギー」が存在すればワームホールが潰れないように支えられることを示してから、一部の先鋭な(SF好きな?)物理学者は、ワームホールを利用してワープドライブやタイムトラベルが可能になると主張しています。惑星科学者であるカール・セーガンが『コンタクト』という小説(後に映画化された)を執筆したとき、ソーンは、ヒロインが宇宙の彼方に旅行するもっともらしい方法として、セーガンにこのアイデアを教えたそうです。
「負のエネルギー」という摩訶不思議なものがない限り、大きなワームホールが実際にあるとは考えられませんが、きわめて小さなマイクロ・ワームホールなら至る所に存在している可能性があります。これは、量子効果によって、古典論の範囲では存在できないものでも仮想粒子のような形で現れたり消えたりすることがあり得るためで、大きさが10
-30メートル以下のワームホールが何らかの物理的効果を時空に及ぼしているのではないか、研究が続けられています。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
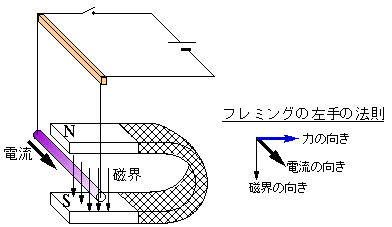
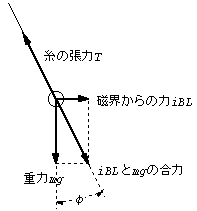 tanφ = iBL/mg
tanφ = iBL/mg
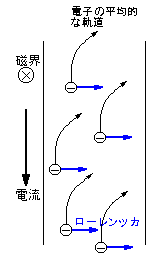 f = ev・h
f = ev・h
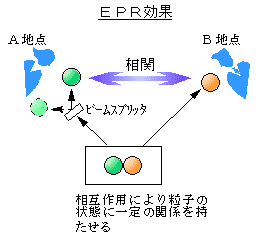 典型的なEPR効果とは、次のような実験で観測されます(右図)。
典型的なEPR効果とは、次のような実験で観測されます(右図)。
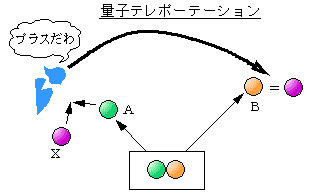 実際にテレポートさせられるのは、光子や原子などの粒子の状態です(右図)。ある測定を行うと一定の結果が得られるような状態を取っている粒子Xを考えましょう。ここで、粒子対A,Bを用意し、AとXを相互作用させながら測定した結果がプラスになったならば、BがXと同じ状態にあることがわかるように、A,Bを相関させておきます。さて、AとBが充分に引き離されたところで、AとXを相互作用させて測定を行ったとしましょう。このとき、測定結果がプラスと出れば、その瞬間(光よりも速く)BがXと同じ状態であることがわかります。一方、Aと相互作用させたことにより、Xの状態は変化してしまいます。ベネットらは、この過程を「Xの状態がBにテレポートした」と表現したのです。この実験は、すでに1997年に実施されており、光子の偏光状態に関する量子テレポーテーションが確認されました。この技術を改良すれば、ある実験室に置かれたサンプルの分子状態を別の地点にコピーするのに使えるかもしれません。
実際にテレポートさせられるのは、光子や原子などの粒子の状態です(右図)。ある測定を行うと一定の結果が得られるような状態を取っている粒子Xを考えましょう。ここで、粒子対A,Bを用意し、AとXを相互作用させながら測定した結果がプラスになったならば、BがXと同じ状態にあることがわかるように、A,Bを相関させておきます。さて、AとBが充分に引き離されたところで、AとXを相互作用させて測定を行ったとしましょう。このとき、測定結果がプラスと出れば、その瞬間(光よりも速く)BがXと同じ状態であることがわかります。一方、Aと相互作用させたことにより、Xの状態は変化してしまいます。ベネットらは、この過程を「Xの状態がBにテレポートした」と表現したのです。この実験は、すでに1997年に実施されており、光子の偏光状態に関する量子テレポーテーションが確認されました。この技術を改良すれば、ある実験室に置かれたサンプルの分子状態を別の地点にコピーするのに使えるかもしれません。
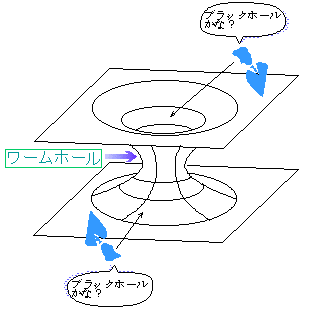 さらに、同じ宇宙の中で、空間のある部分と別の部分をつなぐような特殊解も理論的には可能であることがわかり、ホイーラーらによってワームホール(虫食い穴)として一般化されます。
さらに、同じ宇宙の中で、空間のある部分と別の部分をつなぐような特殊解も理論的には可能であることがわかり、ホイーラーらによってワームホール(虫食い穴)として一般化されます。