
宇宙の膨張を科学者たちが確信しているのは、観測データと理論的予測の見事な一致があるからです。どちらか一方だけでは、信頼できる根拠になりません。
しばしば、宇宙が膨張していることは、1929年にアメリカの天文学者ハッブルによって“発見”されたと言われています。しかし、これは、正確な表現ではありません。ハッブルが見いだしたのは、「遠方の銀河系から発せられた光の波長λが、太陽からの距離に比例する形で引き伸ばされてている」という(いわゆる“赤方偏移”の)データでした。こうした偏移が生じる原因としては、次のようなものが検討されました:
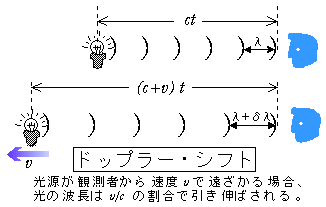
- 各銀河が距離に比例する速さで太陽から遠ざかっているため、ドップラー・シフト δλ=λv/c が生じた(右図)。
- 宇宙空間を伝わる過程で光が距離に比例してエネルギーを失い、アインシュタインの関係式 E=hc/λ に従って波長が伸びた。
- 遠方では時間の流れが遅くなり振動数が小さくなる(=波長が伸びる)というドジッターが示唆した一般相対論の効果が現れた。
宇宙観測のデータだけでは、こうした理論の中のどれが正当か、なかなか決定できません。ところが、1930年にイギリスの物理学者エディントンが、アインシュタインの一般相対論には空間が風船のように膨張していくという解が存在し、こうした膨張宇宙の1点から周囲を観察すると、他の銀河が自分からの距離に比例する速さで遠ざかっていくように見えることを示しました。これにより、ハッブルが発見した赤方偏移は、宇宙の膨張によって生じたドップラー・シフトであると解釈するのが最も合理的だと考えられるようになったのです。
現在では、数百万光年から十億光年程度の距離にある銀河に関して、距離と赤方偏移の比例関係が良く成り立っていることが判明しています。また、一般相対論に関しても、パルサーの周期の変化などをもとに、信頼性の高い理論であると考えられています。それだけに、観測と理論を結びつける「膨張宇宙」という解釈は、ほぼ確実なものだと言えるのです。
なお、一般相対論の膨張宇宙の解は、あくまで空間(=物質が存在するスペース)が拡がるというものであって、物理定数や天体の質量などは変化しません。太陽系における惑星の公転半径は、ニュートン定数・太陽質量・太陽に対する惑星の相対速度を与えれば決定するものなので、宇宙空間が膨張しても太陽系の大きさが変わることはありません。
【Q&A目次に戻る】

日本の携帯電話ビジネスは、世界的に移動体通信が普及し始めた1990年代前半に(NTTの見込み違いもあって)大きく出遅れ、普及率においても機器の販売シェアにおいても北欧や東アジア諸国の後塵を拝してきました。しかし、iモードの登場とともに、国内の携帯電話は、単なる「持ち運び可能な電話機」からインターネットに接続可能なモバイル端末「ケータイ」へと変貌を遂げ、今や日本発の「情報コンビニ」技術として世界に拡がろうとしています。
次世代携帯電話の方向性を示すキーワードは、「ネットワーク化」です。通話主体の携帯電話ビジネスは、国内外で2005年頃に頭打ちになると予想されており、代わって、デジタル家電やカーナビなどと連携した「ケータイ・ネットワーク」が重要になってきます。携帯電話の基本機能(ソフトウェアによるベースバンド処理)は、数年以内に、1cm角程度の1チップで実現されるようになると予想されています。そうなれば、ゲーム機やカーナビなどのデジタル機器にこのチップを組み込み、どこにいてもネットワークを利用できる環境が整えられます。例えば、カーナビに近くのレストランの情報を取り込んだり、そこから予約を入れることも可能になります。また、ICカードの利用によってセキュリティが確保されれば、ケータイを財布代わりに使う「モバイル・コマース」も盛んになるでしょう。
しばしば日本的ビジネスの典型と言われるのが、いわゆるコンビニエンス・ストアです。日常品を一通り揃えた小規模店舗というだけならアメリカが発祥の地ですが、回転率の高い商品を全国一律で用意し、POSシステムを駆使して常に欠品の出ないようにする商売のスタイルは、完全に日本独自です。この「いつでもどこでも同じような便利さを享受できる」という特長は、iモードにも通じるものであり、日本の情報通信産業がこれから進んでいくであろう道を示唆します。すなわち、少額決済や生活情報の送受信など、分散情報処理が絡んでくるような作業は、ケータイ1台あれば誰でも簡単にこなすことができる──というのが日本的「情報コンビニ」の未来形であり、高度な技術が人間生活をサポートする好例になると考えられます。
【Q&A目次に戻る】

ミトコンドリアは、エネルギーの元になるATPを細胞に供給するという基本的な役割を果たしていますが、その個数は一定ではなく、細胞の種類や生理的活性に応じて異なっています。特に、エネルギーを大量に消費する筋原線維の付近では、ミトコンドリアの個数が頻繁に変化してエネルギー供給の円滑化を図っていることが判明しています。
良く知られているように、ATPはアクチン−ミオシン系などにエネルギーを与えてADPに変化します。ここで、再びADPからATPを作るプロセスには、(1)グリコーゲン(またはグルコース)をピルビン酸に変換する際に無酸素的に生成する過程(解糖系)と、(2)ミトコンドリア内膜での酸化的リン酸化反応によって生成する過程(酸化系)とがあります(他にもありますが省略します)。このうち前者は、主に短時間に大きな負荷が加わる場合に利用されます。スプリントトレーニングなどを通じてこの種の負荷が繰り返し加わると、ADP濃度の上昇が引き金となって解糖系の酵素活性が高まり、グリコーゲンの分解能力が強化されます。これに対して、ある程度以上の負荷を持続的に加え続ける持久的トレーニングを行うと、解糖系よりも多くのATPを供給できる酸化系の強化が進みます。酸化系の能力を高める変化としては、毛細血管数の増加や脂肪酸化の割合の増大(グリコーゲンを利用するより疲労しにくい)などが見られますが、それとともに、ミトコンドリアの増殖も活発に行われます。
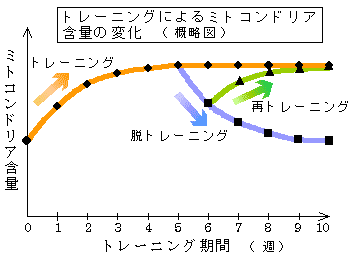
筋組織のミトコンドリア含量は、トレーニング開始後まもなく増大し始め、4〜5週間でトレーニング強度に応じたある定常状態に達します。ただし、トレーニングを中止すると、1週間で増加した分の半分が失われ、さらに数週間で再び元のレベルにまで減少してしまいます。また、最大酸素摂取量の50%以上のトレーニング強度でなければミトコンドリア数に顕著な変化は見られず、小さな負荷で長時間トレーニングするだけではあまり効果がないようです。
ミトコンドリアの数が増大すると、ADPをATPに変換する能力が向上するため、運動によってATP消費が高まっても筋肉内のADP濃度の上昇が抑えられ、疲労を生じにくくします(当たり前のようですが、持久的トレーニングで向上した能力は、持久力を増すのに貢献するわけです)。この効果は、酸素消費量が中程度の運動で最もはっきり現れ、高強度運動にはそれほどプラスになりません。
ここで述べたようなトレーニングとミトコンドリア数の関係については、多くの運動生理学の教科書(例えば、勝田茂編著『運動生理学20講(第2版)』(朝倉書店,1999)p24-)に概説されています。より詳しく調べるには、そこに掲載されている専門文献を参照すると良いでしょう。
【Q&A目次に戻る】

本当です。実際の船が作る波はかなり複雑ですが、理論的には、船のスピードによらず頂角39°のV字の領域に収まることが知られています。
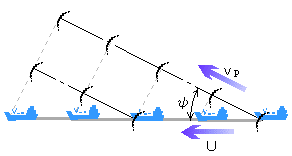
話を簡単にするために、大きさの無視できる船が、水面上を一定の速度Uで動いている場合を考えます。船の位置が波を引き起こす沸き出し点だとすると、ここから出た波(ホイヘンスの要素波)は、ある位相速度v
pで四方に広がっていきます。船の進行方向に対してψの角度をなして放射された波が干渉によって打ち消されず定常的に伝播していく条件は、右図からわかるように、
U cosψ=v
p
となります。v
pが定数の場合には、この式で角度ψが決定されてしまいます。しかし、重力による水の表面波(重力波)の位相速度は、波長λとともに
v
p=(gλ)
1/2
(g:重力加速度)
のように変化するので、船の進行方向には比較的波長が長く位相速度の速い波が、それと直交する方向には波長がきわめて小さく位相速度の遅い波が伝播していきます。
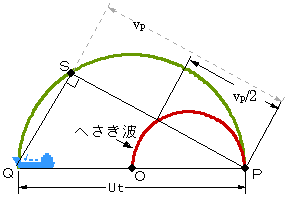
船が位置Pにあるときに発射されたこうした波は、t秒後には、その時点の船の位置をQとして、PQを斜辺とする直角三角形の頂点の位置に達しています。これらを連ねると、PQを直径とする半径 Ut/2 の円周になります。ただし、エネルギーを伝える波の本体はここではなく、群速度v
g で遅れてやってくる部分になります。重力波の場合、
v
g=v
p/2
となることが知られているので、波のこの部分(へさき波と言われることもあります)は、PQの中点をOとすると、POを直径とする半径 Ut/4 の円周上に位置します。

へさき波も時間とともに拡がっていきますが、(右のアニメーションで示されるように)船から見ると、最大でも進行方向となす角度φが、
sinφ=1/3
の範囲に限られます。
arcsin(1/3)=19.5°
なので、へさき波は、船のスピードによらず頂角39°のV字の内側に収まってしまいます。
なお、こうした波の振舞いを研究したのは、19世紀の大物理学者ケルヴィン卿です。彼は、へさき波の同位相面の満たす式が、パラメータξを使って次のように表されることを求めました。
x = a cosξ(1-(cos
2ξ)/2)
y = a(sinξcos
2ξ)/2
この式で定義される“ケルヴィン波”は、下のグラフのように表され、確かにV字型の範囲に収まる波紋に対応していることがわかります
(グラフを描くに当たっては、Yasu氏のフリーソフト "BearGraph" を使用しました)。
【Q&A目次に戻る】

プリオン(prion)とは、クロイツフェルト・ヤコブ病や狂牛病などの中枢神経変成疾患を引き起こす感染性病原体で、通常の細菌やウィルスと異なり、DNAやRNAのような核酸を含まずに純粋なタンパク質だけでできているという著しい特徴があります。プリオンによる病気は、海綿状脳症とも呼ばれ、脳が穴だらけになって確実に死に至るものです。特に有名なのは、1986年にイギリスの研究者が発見した牛の海綿状脳症──いわゆる“狂牛病”で、これに罹った動物は、筋肉の協調性を失って立っていられなくなり、また、知覚過敏を示して興奮しやすくなります。1970年代の終わり頃からイギリスを中心に狂牛病が発生した原因は、栄養補給用に牛の餌に入れられた羊肉にプリオン病の一種であるスクレイピーに感染したヒツジのものが混入していたため、病原体が牛に感染したものと判明しました。さらに、狂牛病の牛の肉を食べた人間にもプリオン病が発症したという報告もあり、プリオンが種の壁を越えて多くの生物に感染することがわかってきました。
通常の感染症は、宿主に侵入した病原体が、核酸の遺伝情報を利用した自己増殖によってその数を増やすと、はじめて発症します。したがって、核酸を含まないプリオンがいかにして伝染性の疾患を引き起こすのか、当初は全くの謎でした(と言うより、多くの研究者が、タンパク質が病原体であるという仮説を疑っていました)。しかし、プリオン病の動物の脳から単離したタンパク質を他の動物に注入すると同じ病気に罹るという実験を通じて、タンパク質が脳内部で“増殖”して病気を引き起こすことが疑い得ない事実となったのです。
プリオンが脳に作用するメカニズムは、1990年代に入って集中的に研究され、基本的な仕組みはわかってきましたが、まだ解明すべき点が数多く残されています。
もともと脳内部には、病気を起こさないプリオン・タンパク質 PrP(Prion Protein) が存在しています( PrP の生体内での機能は必ずしも明らかでなく、ネズミを使った実験によると、なくても生存には困らないようです)。
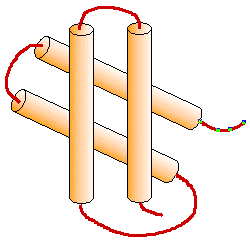
正常な動物の PrP は、細胞型PrP と呼ばれるコンフォーメーションをとっており、右の模式図の円筒形で表した部分がαヘリックスというラセン構造になっています。ところが、病気を引き起こす感染型PrP は、アミノ酸配列は細胞型と同一であるものの、手前の2つのαヘリックスがβシートという折り重なった構造に変化しています。驚くべきことに、2つのタイプの PrP が接触すると、(未知のタンパク質との相互作用を通じて)細胞型PrP が感染型PrP に変化することが判明しました。このため、外部から感染型PrP が侵入してくると、これと接触した細胞型PrP が感染型に変わることから始まって、ちょうど吸血鬼に咬まれた人間が吸血鬼に変身して別の人間を襲うように、ネズミ算式に感染型PrP の数が増えていきます。
増加した感染型PrP が、どのような作用を通じて神経細胞を傷害するかについても、必ずしも充分に解明されていません。ただ、細胞型PrP がプロテアーゼと呼ばれるタンパク質分解酵素によって簡単に分解されるのに対して、感染型PrP はなかなか分解されないという特徴が知られています。一つの仮説は、分解できない感染型PrP がリソゾームという細胞内器官に蓄積されていき、最終的にはリソゾームが壊れることが原因となって細胞が傷害を受けるというものです。この細胞が死ぬと、感染型PrP が放出されて再び周囲の細胞を攻撃することになり、最終的に脳細胞の多くが失われてしまいます。興味深いことに、感染型PrP の断片が脳に集まると沈着物が形成されるのですが、これが、アルツハイマー病患者の脳に見られる老人斑と類似しているのです。アルツハイマー病も原因は解明されていませんが、中枢神経細胞を傷害する仕方に何らかの共通項があるのかもしれません。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
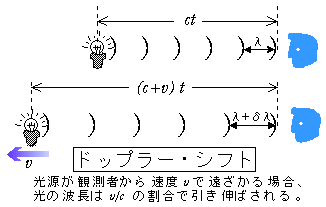
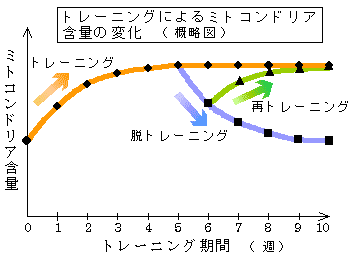 筋組織のミトコンドリア含量は、トレーニング開始後まもなく増大し始め、4〜5週間でトレーニング強度に応じたある定常状態に達します。ただし、トレーニングを中止すると、1週間で増加した分の半分が失われ、さらに数週間で再び元のレベルにまで減少してしまいます。また、最大酸素摂取量の50%以上のトレーニング強度でなければミトコンドリア数に顕著な変化は見られず、小さな負荷で長時間トレーニングするだけではあまり効果がないようです。
筋組織のミトコンドリア含量は、トレーニング開始後まもなく増大し始め、4〜5週間でトレーニング強度に応じたある定常状態に達します。ただし、トレーニングを中止すると、1週間で増加した分の半分が失われ、さらに数週間で再び元のレベルにまで減少してしまいます。また、最大酸素摂取量の50%以上のトレーニング強度でなければミトコンドリア数に顕著な変化は見られず、小さな負荷で長時間トレーニングするだけではあまり効果がないようです。
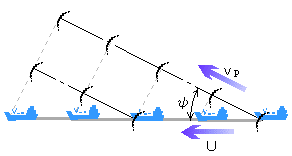 話を簡単にするために、大きさの無視できる船が、水面上を一定の速度Uで動いている場合を考えます。船の位置が波を引き起こす沸き出し点だとすると、ここから出た波(ホイヘンスの要素波)は、ある位相速度vpで四方に広がっていきます。船の進行方向に対してψの角度をなして放射された波が干渉によって打ち消されず定常的に伝播していく条件は、右図からわかるように、
話を簡単にするために、大きさの無視できる船が、水面上を一定の速度Uで動いている場合を考えます。船の位置が波を引き起こす沸き出し点だとすると、ここから出た波(ホイヘンスの要素波)は、ある位相速度vpで四方に広がっていきます。船の進行方向に対してψの角度をなして放射された波が干渉によって打ち消されず定常的に伝播していく条件は、右図からわかるように、
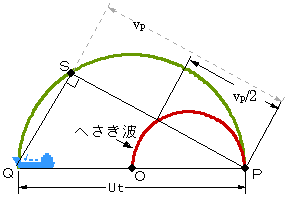 船が位置Pにあるときに発射されたこうした波は、t秒後には、その時点の船の位置をQとして、PQを斜辺とする直角三角形の頂点の位置に達しています。これらを連ねると、PQを直径とする半径 Ut/2 の円周になります。ただし、エネルギーを伝える波の本体はここではなく、群速度vg で遅れてやってくる部分になります。重力波の場合、
船が位置Pにあるときに発射されたこうした波は、t秒後には、その時点の船の位置をQとして、PQを斜辺とする直角三角形の頂点の位置に達しています。これらを連ねると、PQを直径とする半径 Ut/2 の円周になります。ただし、エネルギーを伝える波の本体はここではなく、群速度vg で遅れてやってくる部分になります。重力波の場合、
 へさき波も時間とともに拡がっていきますが、(右のアニメーションで示されるように)船から見ると、最大でも進行方向となす角度φが、
へさき波も時間とともに拡がっていきますが、(右のアニメーションで示されるように)船から見ると、最大でも進行方向となす角度φが、
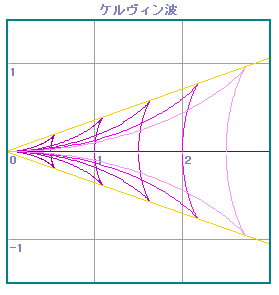
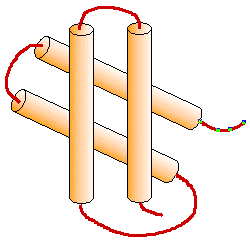 正常な動物の PrP は、細胞型PrP と呼ばれるコンフォーメーションをとっており、右の模式図の円筒形で表した部分がαヘリックスというラセン構造になっています。ところが、病気を引き起こす感染型PrP は、アミノ酸配列は細胞型と同一であるものの、手前の2つのαヘリックスがβシートという折り重なった構造に変化しています。驚くべきことに、2つのタイプの PrP が接触すると、(未知のタンパク質との相互作用を通じて)細胞型PrP が感染型PrP に変化することが判明しました。このため、外部から感染型PrP が侵入してくると、これと接触した細胞型PrP が感染型に変わることから始まって、ちょうど吸血鬼に咬まれた人間が吸血鬼に変身して別の人間を襲うように、ネズミ算式に感染型PrP の数が増えていきます。
正常な動物の PrP は、細胞型PrP と呼ばれるコンフォーメーションをとっており、右の模式図の円筒形で表した部分がαヘリックスというラセン構造になっています。ところが、病気を引き起こす感染型PrP は、アミノ酸配列は細胞型と同一であるものの、手前の2つのαヘリックスがβシートという折り重なった構造に変化しています。驚くべきことに、2つのタイプの PrP が接触すると、(未知のタンパク質との相互作用を通じて)細胞型PrP が感染型PrP に変化することが判明しました。このため、外部から感染型PrP が侵入してくると、これと接触した細胞型PrP が感染型に変わることから始まって、ちょうど吸血鬼に咬まれた人間が吸血鬼に変身して別の人間を襲うように、ネズミ算式に感染型PrP の数が増えていきます。