
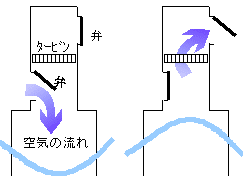
波力発電とは、波浪のエネルギーを利用して発電するシステムで、海面の上下運動を利用して空気の流れを起こし、空気タービンを回す方法がよく知られています(概略図を右に示します)。日本の海岸に打ち寄せる波の全エネルギーは10
7〜10
8kW程度なので、これを全て利用できるならばエネルギー問題も一気に解決するはずです。実際、オイルショックが世界経済を揺るがした1970年代には、イギリスを中心に百万kW規模の波力発電が研究されたこともありました。しかし、大規模な波力発電施設は、建設費・保守費がかさむ割に出力が小さく、気象による変動が大きいため、現在では、あまり有望視されていません。
日本では、1977年から出力125kWの発電機8台を装備した実験船「海明」で実験が開始されています。当初は発電効率が低く実用にはほど遠かったものの、1985年には約50円/kWhとディーゼル発電と同レベルの効率を達成しています。また、防波堤の前面に固定式のものを設置して、発電と消波を同時に行う研究も進められています。
波力発電は、小規模分散型に向いており、具体的には次の用途が考えられています。
- 灯台・灯標用の電源
- 他に発電施設を作れない離島での発電
- 防波堤における消波を兼ねた発電
- 海洋構造物における補助電源
すでに実用化されているものに航路標識用ブイがあります。多くは出力30〜60Wの小型のものですが、出力1kWの高出力波力ブイも開発されています。
【Q&A目次に戻る】

温度は、基本的な物理量でありながら、厳密な定義や精密測定が難しいものです。通常は、液体の熱膨張を利用した液体温度計を使って測定していますが、管の太さが不均等であったり液体を溜める球の部分が変形したりして、あまり精密ではありません。アルコール(エタノール)温度計は、ふつう0℃と-78.5℃(炭酸ガスの昇華点)を基準とし、-100℃から78℃の範囲で体積が温度に線形に依存すると仮定して目盛りを付けています。より低温ではペンタンが用いられることもありますが、これもせいぜい-180℃程度までしか使えません。
温度を理論的に定式化する試みは、18〜19世紀に気体の熱力学的な振舞いをもとに進められました。フランスの化学者ゲイ=リュサックは、1801年に、酸素・水素・窒素・亜酸化窒素・アンモニア・塩酸・亜硫酸・炭酸を使った実験で、一定の圧力の下での気体の熱膨張率が気体の種類によらずに等しいことを見いだしました(基準となる温度の測定には液体温度計を用いています)。同様の実験は、その後、多くの学者(特にフランスの化学者ルニューによるもの(1847)が信頼性が高い)によって行われ、測定可能な範囲では、高い精度で次の関係式が成り立っていることが確認されました:
v=α(t+273)
(v:モル体積、α:熱膨張率)
ここで、tは各気体に共通する温度の尺度で、液体温度計によって測定された摂氏温度(水の融点を0°、沸点を100°とする温度)と一致します。1848年にイギリスの物理学者ケルヴィン卿は、全ての熱現象に共通する「絶対的な」温度目盛りを導入することの重要性を訴え、上の関係式を利用した気体温度計が物質の種類によらない絶対温度を与えると主張しました。さらに、論文の注で、気体の体積が-273℃でゼロになることを指摘し、この温度は到達不可能であると述べています。これが「絶対零度」というアイデアの嚆矢となります。絶対温度T[K]と摂氏温度t[℃]は、
T=t+273
という関係式で結ばれています。
現在では、統計力学の手法を用いて絶対温度を定義しています。詳しい説明は省略しますが、(熱力学第3法則によって定義される)エントロピーをエネルギーで微分した量の逆数が絶対温度となります。
熱現象全般を統計力学の手法で解析するのは困難ですが、いくつかのケースでは、測定可能な量と絶対温度の間に簡単な関係式が成立することが理論的に示されるため、それを利用した温度測定法が開発されています。例えば、高温物体から熱放射される光の輝度は、プランクの放射公式によって与えられるので、ある波長の光の輝度を測定することにより、物体の温度が求められます。この原理を利用した光高温計は、高温領域(700〜数千℃)での標準温度計となっています。また、白金の電気抵抗は、広い範囲で温度に線形に依存するので、-183〜630℃の範囲で国際実用温度目盛りを決定するのに利用されています。実用上は、14K〜1600℃程度の範囲で問題なく使えます。
極低温での温度測定には、いくつかの方法が開発されています。
- 圧力温度計 : 気体の圧力変化を利用した温度計。特に、ヘリウムの飽和蒸気圧をプルドン管(渦巻き状の金属管で作られた圧力計)を利用して測定する蒸気圧温度計は、0.25〜3.33Kの範囲で標準的に用いられています。
- 抵抗温度計 : 金属や半導体の電気抵抗の温度依存性を利用した温度計。ゲルマニウムに微量の不純物を添加して温度の低下とともに急激に抵抗が増大するようにしたものは、0.2〜20Kでよく利用されます。炭素抵抗体は市販のものが簡単に入手できますが、抵抗値が変化しやすいのできちんと校正しておかなければなりません。
- 磁化率温度測定法 : 0.2K以下では蒸気圧温度計が利用できないので、相互インダクタンスによって磁化率を測定し、磁化率と温度の関係を与えるキュリーの法則を使って温度を決定しています(ただし、キュリーの法則からのずれを適切に補正する必要があります)。この方法で、0.002〜1Kの温度が計れます。
- その他 : 熱雑音や核整列を利用した温度測定法もあります。
【Q&A目次に戻る】

一般に、「発明(invention)」とは、それ以前にはなかった有用な道具・機械・システムなどを、高度な技術を用いて新たに作り出すことであり、「発見(discovery)」とは、それまで知られていなかった事実や理論を見つけ出すことだと考えられています。前者が技術的な創作として人間によって初めて作り出されたのに対して、後者は、もともと自然界に存在していたものを新たに科学的知見に加えることだというのが一般的な見方でしょう。ただし、両者は必ずしも截然と区別される訳ではありません。例えば、堆肥を撒くと作物の生育が良くなるという現象の発見と、施肥によって収量を増大させるという農耕技術の発明は、実際には不可分な一連の過程として行われたと推測されます。
自然界の法則に関しては、それまで知られていなかった普遍的性質を科学者が新たに記述した場合、「発見」と呼ぶのが妥当ではないかと思われます。もっとも、19世紀までに見つかった比較的単純な法則(「落体の法則」とか「ベルヌイの法則」など)は、いかにも「発見」と呼ぶのが相応しいものですが、20世紀以降に作られた高度に数学的な理論については、発明とも発見とも言い難いような例がいくつもあります。例えば、朝永−ファインマン−シュヴィンガーによる「くりこみ理論」は、摂動論を使って場の量子論の計算を遂行するための数学的な技巧で、自然界の性質をそのまま反映した理論とは言えないのですが、これを電磁気理論に適用したときに見いだされる「くりこみ理論で計算ができる(=くりこみ可能である)」という性質は、電磁現象がミクロの極限でもマクロ世界と似たような振舞いを示すことを示しており、物理的に重要な意味があります。したがって、ノーベル賞をもらった3人の学者は、くりこみ理論を「発明」し、電磁現象のくりこみ可能性を「発見」したと言っても良いかもしれません。しかし、そうした煩わしい用語法を徹底している科学史家や科学ジャーナリストはあまりいないようです(特に「発明」という語には工学系の匂いがするので科学者には嫌われます)。自然現象の特質を直接的に表しているような単純な法則の場合は「発見」という語が使われることが多く、数学的・理論的に難解な法則(「オンサーガーの相反定理」や「ゴールドストンの定理」など)のときは「導く(introduce)」とか「定式化する(formulate)」といった言葉を適当に選んでいるのが現状です。
数学の定理の場合、「発見」という言い方をするのが慣例です。しかし、ここでも、高度で複雑なものに関しては曖昧さが生じる余地があります。有限なリソースを用いて業務を遂行する際に、これをどのように割り振っていけば生産性が最も高くなるかという問題は、線形計画法の1部門となっていますが、最適解を得るのはかなり難しいとされています。1988年にAT&Tのカーマーカーは、ある手法を用いればこの計算が簡単になることを「発見」しましたが、これは「新しくて役に立つ(new and useful)」技術なので特許法で定めた「発明」の要件に該当するとして特許出願を行い、日本やアメリカで特許を取得しています(厳密に言えば、特許はカーマーカーの手法で計算を行うコンピュータに対して与えられています)。新しい特質を持つ数学的テクニックを開発した場合、どこまでが発見でどこからが発明かは現実には区別しようがないのですが、数学は普遍的な思考の形式だと信じる多くの数学者は、敢えて全てを「発見」だと見なしているようです。
【Q&A目次に戻る】

1905年にアインシュタインが提唱した光子(フォトン)仮説によれば、光の振動数ν・波長λとフォトン1個のエネルギーEの間には、
E=hν=hc/λ (h:プランク定数、c:光速度)
という関係があるとされています。この式は、コンプトン散乱や光電効果の実験結果を見事に説明するので、しばしば自然界における基本的な関係式と見なされ、高校の教科書にも記載されているほどです。
しかし、考えてみると、これはずいぶん奇妙な式です。光子はエネルギーが集中している点状の粒子としてイメージされることが多いのですが、その点粒子が持つエネルギーと、波長という“拡がりを表す量”がなぜ結びつくのかは、そう簡単には納得できないでしょう。TV送信波ともなると波長は1メートル程度にもなるので、きわめて微弱で(上の関係式によれば)たかだか数個の光子しかないはずの電波の場合、どこに光子があるか考え始めるとわからなくなります。
実は、アインシュタインの関係式は、光(電磁波)に関する基礎的な理論の特殊な応用例と考えるべきものなのです。荷電した物体との相互作用によって生じる電磁波は、一般的に電磁場の集団運動として表されますが、いくつかの特殊なプロセスでは、1光子状態によって近似的に記述することが可能になります。
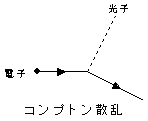
これは、あたかも1個の光子だけが反応に関わっていると見なすもので、コンプトン散乱や光電効果のようなケースでは良い近似となります。1光子状態のエネルギーは、集団運動の記述に現れる振動数や波長を使うと、アインシュタインの関係式によって表されます。アインシュタインの関係式が適用できるのは、こうした稀なプロセスに限られており、光に関するあらゆる現象で、E=hνというエネルギーを持つ光子が飛び交っていると解釈できる訳ではないことに注意してください。
【Q&A目次に戻る】

科学の分野で「ビッグバン」と言えば、宇宙の始まりにあったと推定される大爆発を指しています。
宇宙の物質がどのようにして生成されたかについて、1940年代の後半から、αβγ理論と定常宇宙論という2つの理論が対立していました。前者は、1946年にロシア出身の物理学者ジョージ・ガモフが提唱し、1948年にアルファ−ベーテ−ガモフの連名の論文(αβγ理論という名称は3人の名前をもじったもので、この名称を使いたいために、ガモフは一緒に研究をしたわけでもないベーテを共著者に引きずり込んだそうです)で改良された理論で、宇宙の始まりには大爆発があり、その高温・高圧状態の中で核融合が進んで多くの物質が合成されたと主張しています。これに対して、後者は、SFを著したこともある異能物理学者フレッド・ホイルが、ボンディとゴールドとともに作り上げたもので、宇宙空間にある物質は、真空の状態が変化して何もない空間から湧き出すようにして生じるとされていました。
それぞれの理論の提唱者は、さまざまな面から互いに相手を批判していました。あるときホイルがαβγ理論を揶揄するつもりで、「連中は宇宙がバーンという大爆発(big "bang")でできたなどとバカなことを言っている」と口にしたところ、洒落のわかるガモフ陣営の学者がこの言い回しを面白がって使うようになり、いつのまにか理論の名称として定着していったのです。(αβγ理論改め)ビッグバン理論と定常宇宙論の対立は1960年代まで続きますが、1964-65年にベル研究所のペンジアスとウィルソンが宇宙の背景放射という“大爆発の名残り”を発見したことによって、前者の正当性が強く支持されました。現在ではさらに多くの改良が加えられて、宇宙論の定説となっています。
宇宙がビッグバンという大爆発で始まり、いまだに宇宙全体が膨張を続けているという壮大なアイデアは、20世紀的な宇宙創造の物語として一般の人々にも広く伝えられています。こんにちでは、新たな宇宙を作り出した大爆発になぞらえて、従来の枠組みを根底から作り替えるような大改革を「ビッグバン」と呼ぶこともあります。例えば、1986年にイギリスで実施された売買手数料の自由化・取引所会員権の開放などを柱とする証券制度の改革や、2001年をめどに日本で進められている金融分野での規制撤廃が、「ビッグバン」と表現されています。
【Q&A目次に戻る】

「生物(あるいは生命)とは何か」という問いは、多くの科学者や哲学者によって古くから繰り返し考察されてきましたが、現在なお、全ての学者を納得させるような普遍的な定義は案出されていませんし、おそらく、これからも、生物と無生物の境界画定を巡る議論が延々と続けられることになるでしょう。この問題は、結論を出すことよりも、議論を続けることに学問的な意義があるように思われます。
教科書的な定義としては、「生物とは、代謝による自己維持能力を備え、外界からの刺激に対して反応し、生殖を行って自己増殖することのできる物理的システムである」というのが、最も適当なものでしょう。しかし、現実には、この定義ではカバーしきれない実例がいくつもあります。
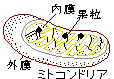
例えば、細胞内でエネルギー産生を行っているミトコンドリアは、独自の遺伝子を持つ自己増殖的システムであり、上の定義と照らしても生物と呼んでおかしくないのですが、通常は、細胞内器官の1つとして位置づけられています。もともとは、多細胞生物の祖先と共生していた微生物だったものが、次第に自立的な器官が退化して非生物化し、いつしか細胞内器官の1つになったと考えられています(でも、いつから生物でなくなったのでしょう?)。
共生進化は、しばしば生物の機能のいくつかを退化させ、上の定義にある全ての要件を満たしていない“生物もどき”を生み出します。究極的には、寄生生物の遺伝子が宿主の染色体に組み込まれてしまい、特定の状況で宿主が産生する機能体にまで変化することもあり、外見上はどう見ても1個の生物でありながら、自己増殖できない個体が存在するようなケースも現れます(昆虫の寄生生物で実例が報告されています)。それならばと生物の定義から自己増殖能力を削除すると、今度は、範囲が広がりすぎて、逆に混乱が生じてしまいます。例えば、動物の体内には、アメーバのように変形しながら血管の中を動き回り、バクテリアなどを見つけると細胞内に取り込んで分解してしまうマクロファージが存在しています。これは、造血細胞で作られる血球の1種なので、通常は生物とは見なされませんが、下手に定義を広げると、マクロファージも生物だと言わざるを得なくなるでしょう。もっとも、「個々の細胞は生物ではない」という主張は、必ずしも自明ではないのですが。
物理学者が好んで口にする生物の特性は、「代謝によって低エントロピー状態を維持する」という点です。光合成を行う植物は、水と二酸化炭素を元に(エントロピーが1モルあたり70.5R低い)ブドウ糖を合成しており、こうして得られた低エントロピー物質を利用して、システムの機能維持や拡張(成長)を自律的に実行しています。従属栄養生物の場合は、光合成に起源を持つ低エントロピー物質を摂取し、これを排泄物に変換することによって、システムのエントロピーを低い状態に維持しています。こうしたシステムは、現時点ではいわゆる“生物”しか存在していないので、「代謝による自己の(低エントロピー状態の)維持」は、生物を無生物から峻別する決定的な特性となっています。
この特性は、人造物と生物を区別する明確な基準にもなっています。現在すでに、センサーによって外界からの刺激を感知してこれに反応したり、ガソリンなどの燃料を代謝して活動するようなロボットは作成されています。ですが、こうしたロボットの場合、代謝によってシステムに供給されるエネルギーは、メカニカルな運動や電気的処理を行うために消費されており、システムの低エントロピー状態を維持・拡張するために代謝を利用している生物とは、明らかに異なっています。実際、ロボットは、部品が損耗すれば自己修復することなく機能を停止してしまいます。
しかし、遺伝子工学の進展は、人造物と生物のこのような区別を曖昧にしていくことでしょう。現在のバイオリアクターは、大腸菌などのバクテリアに合成したい物質の遺伝子を組み込むことによって実現していますが、近い将来、機能の維持に必要な遺伝子だけを使って、生合成を行うための「生物的部品」が化学的に作り出されると予想されます。こうした部品は、代謝によってエントロピーを下げているので生物と言えるかもしれませんが、そうだとすると、人間の手が生命を生み出したことになります。さらに、実験室やバイオ工場で、遺伝子が部分的に改変された個体ないし生体の一部が作り出されるようになると、どれが生物でどれが無生物か、もはや識別が困難な状況が訪れるかもしれません。こうした事態に備えて、われわれは、いま一度、「生物とは何か」を自問してみるべきでしょう。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
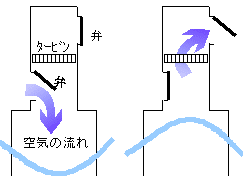 波力発電とは、波浪のエネルギーを利用して発電するシステムで、海面の上下運動を利用して空気の流れを起こし、空気タービンを回す方法がよく知られています(概略図を右に示します)。日本の海岸に打ち寄せる波の全エネルギーは107〜108kW程度なので、これを全て利用できるならばエネルギー問題も一気に解決するはずです。実際、オイルショックが世界経済を揺るがした1970年代には、イギリスを中心に百万kW規模の波力発電が研究されたこともありました。しかし、大規模な波力発電施設は、建設費・保守費がかさむ割に出力が小さく、気象による変動が大きいため、現在では、あまり有望視されていません。
波力発電とは、波浪のエネルギーを利用して発電するシステムで、海面の上下運動を利用して空気の流れを起こし、空気タービンを回す方法がよく知られています(概略図を右に示します)。日本の海岸に打ち寄せる波の全エネルギーは107〜108kW程度なので、これを全て利用できるならばエネルギー問題も一気に解決するはずです。実際、オイルショックが世界経済を揺るがした1970年代には、イギリスを中心に百万kW規模の波力発電が研究されたこともありました。しかし、大規模な波力発電施設は、建設費・保守費がかさむ割に出力が小さく、気象による変動が大きいため、現在では、あまり有望視されていません。
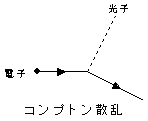 これは、あたかも1個の光子だけが反応に関わっていると見なすもので、コンプトン散乱や光電効果のようなケースでは良い近似となります。1光子状態のエネルギーは、集団運動の記述に現れる振動数や波長を使うと、アインシュタインの関係式によって表されます。アインシュタインの関係式が適用できるのは、こうした稀なプロセスに限られており、光に関するあらゆる現象で、E=hνというエネルギーを持つ光子が飛び交っていると解釈できる訳ではないことに注意してください。
これは、あたかも1個の光子だけが反応に関わっていると見なすもので、コンプトン散乱や光電効果のようなケースでは良い近似となります。1光子状態のエネルギーは、集団運動の記述に現れる振動数や波長を使うと、アインシュタインの関係式によって表されます。アインシュタインの関係式が適用できるのは、こうした稀なプロセスに限られており、光に関するあらゆる現象で、E=hνというエネルギーを持つ光子が飛び交っていると解釈できる訳ではないことに注意してください。
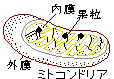 例えば、細胞内でエネルギー産生を行っているミトコンドリアは、独自の遺伝子を持つ自己増殖的システムであり、上の定義と照らしても生物と呼んでおかしくないのですが、通常は、細胞内器官の1つとして位置づけられています。もともとは、多細胞生物の祖先と共生していた微生物だったものが、次第に自立的な器官が退化して非生物化し、いつしか細胞内器官の1つになったと考えられています(でも、いつから生物でなくなったのでしょう?)。
例えば、細胞内でエネルギー産生を行っているミトコンドリアは、独自の遺伝子を持つ自己増殖的システムであり、上の定義と照らしても生物と呼んでおかしくないのですが、通常は、細胞内器官の1つとして位置づけられています。もともとは、多細胞生物の祖先と共生していた微生物だったものが、次第に自立的な器官が退化して非生物化し、いつしか細胞内器官の1つになったと考えられています(でも、いつから生物でなくなったのでしょう?)。