
媒質中を伝播する角振動数ωの単色光は、マクスウェル方程式をフーリエ変換した式で記述されます。電気誘導
D・磁気誘導
Bがそれぞれ電場
E・磁場
Hと線形関係にあると仮定すると、
Eと
Hのフーリエ成分が満たす式は、それぞれ次のようになります。
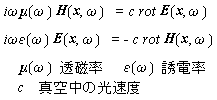
ここで、光が平面波であって
Eと
Hが
exp(iknx) に比例する( ただし、
nは実単位ベクトル、
kは複素係数)ならば、
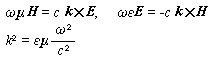
という関係式が得られます(この関係式は必ずしも一般的ではありませんが、多くの媒質で近似的に成り立ちます)。一般に、複素屈折率は、
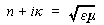
と定義されるので、
Eと
Hの空間座標に依存する部分は、
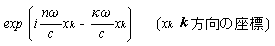
と表されます。指数の虚数部は正弦波としての伝播を表しており、その位相速度と波長が真空の時の1/nになるので、nが光学で言うところの屈折率に相当することがわかります。また、実数部は、波の強さが進入距離とともに減衰する割合を表しており、κは吸収係数と呼ばれます。金属の場合、透磁率は近似的に1であり、振動数が小さいときには、
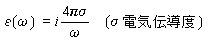
という関係があることが知られているので、この式が成り立つ範囲で、
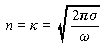
という関係式が成立します。
【Q&A目次に戻る】

中性子(neutron)は、陽子(proton)とともに原子核を構成する「核子」と呼ばれる粒子で、1932年にチャドウィックによって、質量が陽子とほぼ等しい中性の粒子であることが確認されました。
中性子の性質は、持っている運動エネルギーによって大きく異なります。ウランの核分裂やその他の核反応の際には、数千KeV(=1兆分の1ジュール程度)の中性子が放出されます。
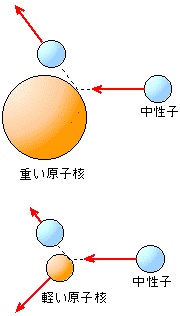
こうした“高速中性子”は、電荷を持たないためにイオン化のような電気的相互作用をほとんどせず、原子核との衝突が運動状態を変える主要なプロセスとなります。ぶつかる原子核の質量が大きいと、衝突しても向きを変えられるだけでエネルギーをあまり喪失せず、中性子はそのまま物質を突き抜けていきますが、水素のように原子核の質量が中性子と同程度の場合は、(ビリヤードの持ち玉が止まっている玉にぶつかったときと同様に)相手に大きなエネルギーを与えて自分は著しく減速されます(右図)。このため、水素を多量に含んだ物質中では、速い中性子は急激に運動エネルギーを失っていきます(下図)。
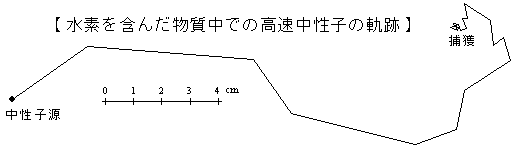
物質中で1KeV以下に減速された中性子を、低速中性子と呼びます。特に、周囲の分子温度と同じ程度のエネルギー(常温では0.000025KeV程度)になったものは熱中性子と呼ばれ、容易に物質に捕獲されます。熱中性子は、また、ウランやプルトニウムの原子核に吸収されて核分裂を引き起こします。核分裂の連鎖反応を実現するためには、分裂の際に放出される高速中性子を“減速材”によって熱中性子にしてやる必要があります。
高速中性子のビームが生物に照射されると、生体物質に多くの水素原子が含まれているために、体内で多くのエネルギーを放出します。放出エネルギーの一部は水酸基ラジカルのような反応性の高い遊離基を作って細胞を傷害します。また、原子核に捕獲されていない中性子は、平均寿命1000秒で電子線を放出して陽子(水素の原子核)に変わる放射能を持っています。
【Q&A目次に戻る】

ブラックホールは、一般相対論によってその存在が予言されている天体ですが、強い重力によって光すら脱出できないため、望遠鏡などで直接観測することはできません。周囲の星から物質が流れ込むときに発するX線のデータなどをもとに、その存在を推測しているだけです。例えば、天の川銀河の中心付近にある「射手座 A*」は、巨大な質量(太陽質量の260万倍)が狭い領域(4.6光日)に集中していることから、ブラックホール(または数個のブラックホールの集まり)であることがほぼ確実だとされていますが、一般相対論で言うところの(事象の地平を持つ)ブラックホールだと断定された訳ではありません。その一方で、ブラックホールではないかと思われる候補の数は、年を追って増え続けています。
ブラックホールには、その質量が恒星サイズのものと銀河サイズのものの2種類があります(両者の中間サイズのものも報告されていますが、ここでは省略します)。前者は、太陽の数倍から十数倍の質量を持っており、超新星爆発を経て生まれると考えられています。この天体は、単独では観測できませんが、X線連星を形成している場合は、放出されるX線のパターンをもとにブラックホールかどうかが推定できます。1994年にガンマ線天文衛星GROによって発見された「GRO J1655-40」は、1996年に起きたX線バーストのデータを分析した結果、ブラックホールである可能性がきわめて高いと言われています。逆に、「コンパス座 X1」は、発見以来ブラックホールではないかと思われていましたが、X線バーストの観測によって、実は中性子星であることが確認されました。1997年時点で、ブラックホール候補の天体は10個記載されています。
一方、銀河サイズの巨大ブラックホールは、銀河の中心部に形成され、最大規模のものは太陽の数千億倍もの質量を持つと推定されます。すでに、ハッブル望遠鏡による観測結果をもとに、近隣の20の銀河の中心核にブラックホールが存在する証拠が得られています。また、VLBA(Very Long Baseline Array)で約100個の近隣の銀河を観測したところ、うち30%がブラックホールからと推測される電磁波を放射していることが判明しました。こうしたデータに基づけば、多くの銀河系の中心部にブラックホールが存在していると考えられます。
特に、クエーサーやセイファートと呼ばれる活動的な(強い電波源となる)銀河は、全て内部に巨大ブラックホールを抱えていると信じられています(活発なクエーサーとセイファートは基本的に同じタイプの天体です)。これまで数千個も発見されているクエーサーの正体は完全には解明されていませんが、銀河同士が衝突して、一方の銀河から引き剥がされたガスや天体がもう一方の銀河の中心部にあるブラックホールに流れ込み、その際に強い電磁波を放出しているという説が有力です。こうした銀河が活動的でいられる期間は比較的短く(1億年以下)、次第に静穏な銀河に変わっていきます。ハッブル望遠鏡を使って5000万年彼方の「M87星雲」の中心核を観測したところ、クエーサーと共通するスペクトルが得られたことから、何人かの天文学者は、数十億年前はM87はクエーサーとして強力な電磁波を放出していたが、ブラックホールに供給される質量が減少して大人しくなったのだと推測しています。
【Q&A目次に戻る】

こんにち定説となっている標準理論によれば、物質を構成する素粒子の間に働く「力」には、強い相互作用・弱い相互作用・電磁相互作用・重力の4種類があるとされています。このうち、強い相互作用は、陽子と中性子を固く結びつけて原子核を作り上げるための力で、核分裂を利用する原子力発電所の内部ででもなければ、その効果が身近に及ぶことはまずありません。また、弱い相互作用となると、その名の通りきわめて微弱なもので、ある種の放射性崩壊を引き起こす以外は、人間とは無縁のものと言っても良いでしょう。したがって、われわれが日常的に体験する力は、物体に重量を与える重力を別にすれば、全て電磁相互作用に由来するということになります(遠心力などの「見かけの力」は、強いて分類すれば重力の範疇に入ります)。物体同士が接触して生じる抗力や摩擦力はもちろん、物体がある形状を維持するための結合力も、化学反応を引き起こすミクロな力も、元をただせば電磁相互作用の一種なのです。
電磁気の力と言うと、距離の2乗に反比例するというクーロンの法則のような単純なものを思い浮かべるかもしれません。しかし、これは真空中にポツンポツンと点在する点電荷に関する法則であって、現実の物質のように、膨大な数のイオンと電子が複雑に絡み合っている場合には、話はそう単純ではないのです。通常は、イオンと電子の電荷が釣り合って電気的にほぼ中性になっているため、物体を少し引き離せば、引力と斥力が相殺して全体として力を及ぼしあうことはありません。しかし、人間の目には接触して見えるほど近づけると、イオンの外側にある電子が電気的な力を受けて微妙に移動し、計算式では表せないような複雑な相互作用が生じます。その力をトータルしたものが、物体同士の抗力や摩擦力と呼ばれるものであり、物体の運動状態を調べることによって、初めてそのベクトルが求められるのです。
【Q&A目次に戻る】

光のエネルギーを利用して水と二酸化炭素から炭素化合物と酸素を作るという光合成は、地球上のあらゆる生命活動の基礎を成すものとして、古くから科学者の興味を引いてきました。現時点では、光合成に関与する生化学物質の1次構造や大まかなエネルギーの流れは明らかになっており、化学反応の基本的な枠組みは理解できたと言っても良いのですが、まだ、各物質の3次構造(立体構造)や電子状態の変化の詳細に関して未解明の領域がかなり残されています。この分野の研究は、単にアカデミックな観点から興味深いだけでなく、二酸化炭素固定のスピードアップや人工的な光合成の実現のために必要なものであり、多くの科学者が精力的に取り組んでいます。
光合成とは、葉緑体内部で起きる一連の酸化・還元反応の総称であり、光化学反応によってATPとNADPHを合成する光化学系(明反応系)と、ここで作られたATPとNADPHを用いて炭酸固定を行うカルビン回路(暗反応系)の2段階から成ります。このうちカルビン回路(*)は1957年に解明され、基本的なプロセスは早くから知られていましたが、光化学系での反応過程が明らかにされたのは、比較的近年のことです。
(*)6分子のリブロース-1,5-二リン酸から出発して、6分子の二酸化炭素を取り込み、18分子のATPと12分子のNADPHを消費して、1分子のグルコースを生成した後、6分子のリブロース-1,5-二リン酸に戻る反応回路。この過程で、リブロース-1,5-二リン酸カルボキシラーゼをはじめ、14種類の酵素が関与する。
光化学反応は、葉緑体内部にあるチラコイドと呼ばれる小胞の表面膜で進行する反応で、光化学系Iと光化学系IIという2つのシステムで実現されます(下図)。
光化学系IIでは、集光性クロロフィルa分子が光を吸収し、そのエネルギーを利用してチラコイド内腔の水分子を酸素と水素イオンに分解するとともに、そこから奪った電子をP680という分子(クロロフィルaがタンパク質と結合したもので680nmの光を吸収する)に受け渡して、これを高エネルギーの励起状態に遷移させます。その後、電子はP680に比べてエネルギー状態の低いプラストキノン(PQ)、チトクロム(Cyt)b/f複合体、プラストシアニン(PC)へと順次受け渡されてから、光化学系Iに入っていきます。電子がプラストキノンを経てチトクロムb/f複合体に渡されるときに放出されるエネルギーは、水素イオンをチラコイド内腔へ汲み出すのに使われます(同様の水素イオンポンプは、光化学系Iにもあります)。この水素イオンがATP合成酵素系を通ってチラコイドの外側にあるストロマに流れ込む過程で、リン酸化反応によってADPからATPが合成されます。
一方、光化学系IにあるP700(700nmの光を吸収)は、光のエネルギーで励起状態になった後、電子をフェレドキシン(Fd)に受け渡します。電子は、さらにFADを経て膜外部にあるNADP
+に移り、NADPリダクターゼの助けを借りてNADPHを生成します。
こうした光化学反応に関して、不明な点がまだいろいろあります。例えば、光化学系IIで水分子から酸素分子が生成される過程において、マンガン結合タンパク質がどのように反応に関与しているのか、あるいは、効率を最適化するために何らかの信号伝達系統があると予想されるが、具体的にいかなるシグナルが使われているかなどについて、今後の研究成果が待たれています。また、反応に関与する生化学物質の3次構造も、X線回折によってかなり判明してきていますが、中間段階の形状をはじめ、まだわかっていない部分が少なくありません。電子伝達系のエネルギー準位についても、モデルに基づく計算が難しく、まだ初歩的な段階にとどまっています。光合成というと小学校の教科書にも載っている既知のプロセスと思われるかもしれませんが、科学はまだまだ膨大な未知の分野を抱えているのです。
【Q&A目次に戻る】

この宇宙には、奇妙な非対称性が随所にみられますが、その一つが、ご質問にある「粒子と反粒子」のアンバランスです。自然界がシンメトリーを重んじるならば、「粒子」と「反粒子」が同じ数だけ存在しているはずです。しかし、実際には、地上に転がっている石ころから近隣の銀河に属する恒星に至るまで、観測される物体のほぼ全てが「粒子」から構成される「物質」であり、電荷などの量子数が粒子と反対の「反粒子」から成る「反物質」は、高エネルギー反応によって生じた宇宙線の中などに例外的に存在するだけです。こうしたアンバランスがなぜ存在するのかは、1928年にディラックが反粒子の理論を提唱して以来、長く謎とされてきましたが、1967年にソ連の反体制物理学者サハロフが発表した「CP非保存と宇宙における重粒子の非対称性」という論文によって、ようやくその基本的なメカニズムが明らかにされました。
サハロフの議論を説明する前に、「反粒子」について簡単に説明しておきましょう。反粒子は、粒子と衝突して対消滅してしまうために、「真空に開いた孔(空孔)」のようにイメージされることもありますが、現在の理論では、素粒子が持っている自由度と解釈するのが一般的です。例えば、クォーク(物質を構成する究極的な素粒子)を表現するψという記号は、実は4つの成分を持つスピノルと呼ばれる量であり、各成分が、スピンが右巻き/左巻きのクォーク/反クォークを表しています。安定した状態として長時間にわたって存在できるのは、そのうちの1つの成分が励起状態(excited state)にあるものです(厳密に言えばスピン成分はミックスされるのですが、その説明は難しくなるので省略します)。つまり、「反粒子」と言っても、別に「粒子」に対する「影の世界」のようなものではなく、素粒子を表す変数の1つの成分でしかありません。
物理法則は、何らかの対称性を持っています。例えば、マクスウェルの電磁気学は、座標
xを
-xに、磁場
Bを
-Bに置き換えても式の形が変わらないことから「空間反転に対して対称的」であり、鏡の中の世界でも、こちら側の世界と全く同じ電磁現象が生じることが示されます。
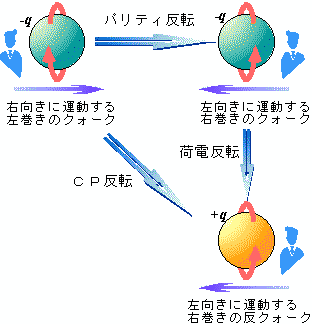
素粒子論の分野で特に重要なのが、パリティ(P)反転(空間およびスピンの反転)と荷電(C)反転(素粒子が持つ電荷の符号の反転)であり、クォークに関してはψの各成分の入れ替えに対応します。この2つを同時に荷電パリティ(CP)反転として行うと、「スピン右巻きのクォーク」が「スピン左巻きの反クォーク」になるといった具合に、粒子と反粒子が完全に入れ替わった世界になります(右図)。物理法則がCP反転に対して変わらないような理論は、CP対称性がある(CPが保存される)と呼ばれます。式の上では、CP反転は数値の複素共役を取る(虚数の
iを
-iに置き換える)ことに相当するので、相互作用の係数が複素数でなければ素粒子の理論はCP対称性を持つはずであり、多くの物理学者が長らくそう信じていましたが、1964年に現実の世界ではCP対称性が破れていることが実験的に確かめられました。粒子と反粒子とでは、相互作用の仕方にほんの少しだけ違いがあるというのです。
サハロフの理論は、CP対称性が破れており、さらに熱力学的な非平衡過程があれば、物質と反物質の不均衡が生じるということを一般的に主張したものですが、その具体的なプロセスを明らかにしたのが、1979年の吉村の業績です。大統一理論と呼ばれる理論によれば、宇宙が高温だったビッグバン直後には、X粒子と呼ばれるきわめて質量の大きい素粒子が存在していたことが示されます。X粒子は2個の反クォークかクォーク・反レプトン対に、その反粒子は2個のクォークか反クォーク・レプトン対に崩壊するのですが、CP対称性の破れの効果で、X粒子と反粒子の間で崩壊の分岐比に差が生じ、2個のクォークが作られる割合がわずかに高くなる可能性があります(この部分の記述は物理学的には厳密でありません)。

吉村は、こうした差があれば、ビッグバンから10
-36秒ほどの間にクォークが反クォークよりも割合にして100億分の1個だけ多くなり、100億個のクォーク・反クォークのペアが対消滅した後、余った1個のクォークが残って天体などの物質を構成するようになることを指摘しました。
サハロフ−吉村の理論は、観測される物質の量などに関してまだいくつかの問題が残されてはいますが、物質−反物質の不均衡が生じることになった基本的なシナリオとして、ほぼ定説と言って良い地位を獲得しています。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
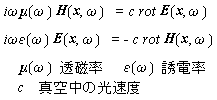
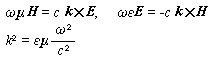
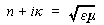
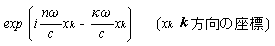
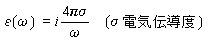
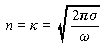
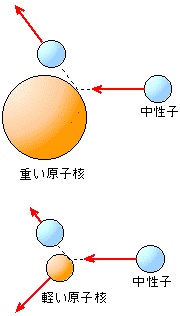 こうした“高速中性子”は、電荷を持たないためにイオン化のような電気的相互作用をほとんどせず、原子核との衝突が運動状態を変える主要なプロセスとなります。ぶつかる原子核の質量が大きいと、衝突しても向きを変えられるだけでエネルギーをあまり喪失せず、中性子はそのまま物質を突き抜けていきますが、水素のように原子核の質量が中性子と同程度の場合は、(ビリヤードの持ち玉が止まっている玉にぶつかったときと同様に)相手に大きなエネルギーを与えて自分は著しく減速されます(右図)。このため、水素を多量に含んだ物質中では、速い中性子は急激に運動エネルギーを失っていきます(下図)。
こうした“高速中性子”は、電荷を持たないためにイオン化のような電気的相互作用をほとんどせず、原子核との衝突が運動状態を変える主要なプロセスとなります。ぶつかる原子核の質量が大きいと、衝突しても向きを変えられるだけでエネルギーをあまり喪失せず、中性子はそのまま物質を突き抜けていきますが、水素のように原子核の質量が中性子と同程度の場合は、(ビリヤードの持ち玉が止まっている玉にぶつかったときと同様に)相手に大きなエネルギーを与えて自分は著しく減速されます(右図)。このため、水素を多量に含んだ物質中では、速い中性子は急激に運動エネルギーを失っていきます(下図)。
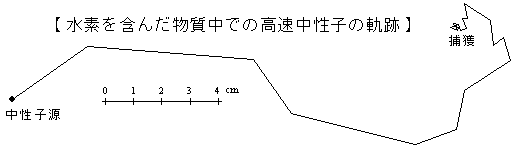
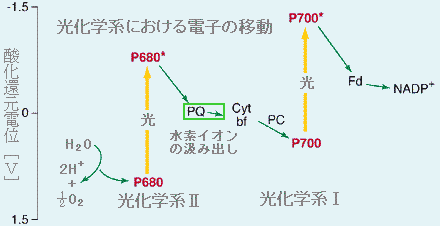
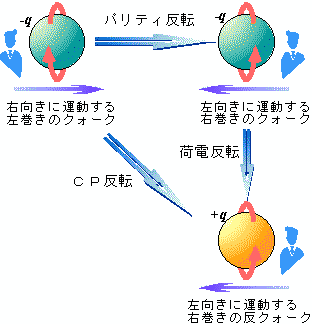 素粒子論の分野で特に重要なのが、パリティ(P)反転(空間およびスピンの反転)と荷電(C)反転(素粒子が持つ電荷の符号の反転)であり、クォークに関してはψの各成分の入れ替えに対応します。この2つを同時に荷電パリティ(CP)反転として行うと、「スピン右巻きのクォーク」が「スピン左巻きの反クォーク」になるといった具合に、粒子と反粒子が完全に入れ替わった世界になります(右図)。物理法則がCP反転に対して変わらないような理論は、CP対称性がある(CPが保存される)と呼ばれます。式の上では、CP反転は数値の複素共役を取る(虚数のiを-iに置き換える)ことに相当するので、相互作用の係数が複素数でなければ素粒子の理論はCP対称性を持つはずであり、多くの物理学者が長らくそう信じていましたが、1964年に現実の世界ではCP対称性が破れていることが実験的に確かめられました。粒子と反粒子とでは、相互作用の仕方にほんの少しだけ違いがあるというのです。
素粒子論の分野で特に重要なのが、パリティ(P)反転(空間およびスピンの反転)と荷電(C)反転(素粒子が持つ電荷の符号の反転)であり、クォークに関してはψの各成分の入れ替えに対応します。この2つを同時に荷電パリティ(CP)反転として行うと、「スピン右巻きのクォーク」が「スピン左巻きの反クォーク」になるといった具合に、粒子と反粒子が完全に入れ替わった世界になります(右図)。物理法則がCP反転に対して変わらないような理論は、CP対称性がある(CPが保存される)と呼ばれます。式の上では、CP反転は数値の複素共役を取る(虚数のiを-iに置き換える)ことに相当するので、相互作用の係数が複素数でなければ素粒子の理論はCP対称性を持つはずであり、多くの物理学者が長らくそう信じていましたが、1964年に現実の世界ではCP対称性が破れていることが実験的に確かめられました。粒子と反粒子とでは、相互作用の仕方にほんの少しだけ違いがあるというのです。
