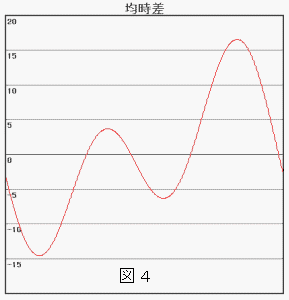現在観測される多くの天体の元になるガス雲は、約150億年前のビッグバン(宇宙の始まりとなる大爆発)から数十万年経った頃、空間に薄く広がっていた中性の原子が、互いに及ぼしあう重力によって凝集して形成されたものです。こうして空間のどこかに物質が集まり始めると、その質量に比例して重力が強くなるので、周りの物質がどんどんそこに引き寄せられ、次第に巨大な天体となっていきます。このとき、図1のように全ての物質が天体の中心に向かってまっすぐ集まっていけば、形成される天体が自転することはありません。しかし、引き寄せられる前には互いにすれ違うような速度を持っていると、回転速度を速めながらラセン軌道を描いて近づいていきます(図2)。こうした運動が生じるのは、空間に漂う物質のように外部から回転を妨げるような力が働かない場合は、「角運動量の保存則」が成り立つからです。周囲の物質を集めて少しずつ質量が大きくなっている天体がある場合、これに近づいていく小天体は、次第に強まる重力によってどんどん引き寄せられていきますが、このとき、角運動量(質量×軌道半径
2×角速度)が一定に保たれるので、近づくにつれて角速度が大きくなって回転が速くなるのです(この過程は、フィギュアスケートでスピンしている選手が、外側に伸ばしていた手足を身体に引き寄せると回転速度が速くなるのと同じです)。この結果、多くの天体(恒星・惑星など)や天体系(太陽系・銀河系など)が回転運動をすることになります。
ただし、各天体が現在持っている自転速度を獲得するまでには、上で説明したよりもはるかに複雑なプロセスがあったと考えられています。例えば、地球の場合は、太陽系が形成されて間もない45億年ほど前に火星と同程度の大きさの天体が衝突し、その衝撃で以前よりも急速に自転するようになったと考えられています。
【Q&A目次に戻る】

原子核の中で陽子(p)と中性子(n)をつなぎ止めている素粒子として1934年に湯川秀樹によって予言され、1947年にその存在が確認された中間子(π中間子)は、1964年にゲルマンが提唱し、現在では大多数の物理学者に支持されているクォーク理論においては、クォークと反クォークがグルーオンの作用で結合した複合粒子とされています。粒子と反粒子は、衝突すると一般に対消滅してしまうので、なぜ、10
-15m程度の狭い範囲にクォークと反クォークが共存していられるか、不思議に思えるかもしれません。
ここで考えなければならないは、中間子の中に存在するクォークと反クォークが対消滅したときに、いったい何になるかです。例えば、「n→p+π
-」あるいはその逆反応によって原子核の中で生まれたり消えたりしているπ
-中間子は、dクォークと反uクォークから成り立っており、-1の電荷(電気素量を単位とする)を持っているので、クォーク・反クォークの対消滅が起こっても、光子のような電荷のない粒子に変わることはできません。π
-中間子を(原子核の中ではなく)真空中に置くと、平均2.6×10
-8秒でミューオンと反ニュートリノに崩壊しますが、その途中でいったん質量の大きいZ
-粒子に変わらなければならないので、こうした反応は起こりにくくなり、結果的にかなり「長生き」の素粒子になります。このように、素粒子が何らかの反応によって変化するときには、エネルギー保存則や電荷の保存則をはじめ、数々の保存則を満たしていなければならないのです。
原子核の中では、さらに素粒子反応が制限されます。陽子と中性子はπ中間子を放出・吸収することによって互いに引き合い、ポテンシャル・エネルギーの低い状態になって結合しています。このとき、中間子が突然崩壊してしまうと、ミューオンやニュートリノが外に飛び出して以前よりもエネルギーが高い状態に変化することになるので、外からエネルギーが供給されない限りは起こり得ないのです。核反応などで原子核のエネルギーが高くなっている(励起状態になっている)ときには、そのエネルギーを利用して中間子が崩壊することも可能ですが、この場合は、いったん重いZ粒子に変わるような起きにくい反応よりも、ガンマ線やアルファ粒子を放出する過程の方がはるかに簡単に生じるので、原子核内部のπ中間子が崩壊することは、現実にはありません。
【Q&A目次に戻る】

19世紀までに確立される近代解析では、実数の演算に基づいて極限や連続を扱ってきましたが、いわゆる現代数学になると、抽象的な空間に適当な構造を与えることによって極限や連続の概念を定義し、これを元にそれまでの解析学と同様な理論を展開するのが一般的になっています。こうした抽象的な「位相空間(topological space)」──
ハウスドルフ空間は、異なる2点が決してくっついていないような位相空間で、2点間の距離が定義できる位相空間(距離空間)はハウスドルフ空間の一種です──を利用すると、ユークリッド空間のような具体的な空間が持つ特殊性に縛られずに、数学の手法を使って一般的な性質を調べることができます。例えば、フラクタルという概念は、純粋数学の研究対象にとどまらず、相転移など非線形な物理過程の解明、ひび割れ・放電・凝集などのパターン解析、素材の質感(テクスチャ)や土壌の間隙率の評価、コンピュータ・グラフィクスの作成など、さまざまな方面に応用できるもので、特定の空間を仮定しない方が扱いやすいのです。
位相空間とフラクタル次元の関係はかなり高度な数学の領域に属しますので、本格的な説明は数多く出版されている参考書に譲るとして、ここでは、フラクタル次元とはどういうものかを直感的に紹介するだけにしておきましょう。

フラクタルとは、数学者マンデルブロが1975年に提唱した概念で、簡単に言うと、拡大・縮小によって観測のスケールを変えても同じように見える図形のことです。右の図は有名なマンデルブロ図形の一部ですが、上の図の四角に囲まれた部分を拡大すると相似的な下の図になることを示しています
(宮根裕司氏のフラクタル描画ソフト “MandelPalette 1.1”で描いた絵を256色に減色しています)。こうした自己相似性を持つ図形の次元は、通常の線(1次元)や面(2次元)と同じように定義することはできません。実際、マンデルブロ図形の縁は、いくら拡大してもなめらかな曲線にはならずに複雑にゆらめいていて、1次元の線とも2次元の面ともつかないものになっているのです。
こうしたフラクタル図形の次元を定義するために案出されたのが、フラクタル次元という概念です。フラクタル次元の厳密な定義には数学のテクニックが必要になりますが、凝集パターンなど実験的に得られた図形のフラクタル次元を推測するには、ボックス・カウンティング(Box-counting)という簡単な方法が使われます。これは、図1に示すように曲線を1辺の長さLの正方形(3次元の場合は立方体)のボックスで覆い、曲線を含むボックスの個数N(L)を求めるというものです。ここで、1辺の長さを変化させたとき、
N(L) = C・L
-D (Cは定係数)
という関係式が(良い近似で)成り立つ場合、Dをフラクタル次元と定義します。図1では曲線を含むボックスは影を付けた14個ですが、1辺の長さを半分にした図2では27個になっているので、D=1と推測されます(実際には、もう少しサンプルを多く取らなければなりません)。
フラクタル次元が1より大きくなる曲線の最初の例は、ペアノが創案しヒルベルトが簡単な作り方を提示したペアノ曲線でしょう(下図)。これは、初めにコの字型の図形から出発し、正方形のボックスの中の部分を一定の方法で段階的に変形していくことによって得られる曲線で、1本の線で平面を完全に埋め尽くしてしまうものです。実際、ボックス・カウンティング法によれば、曲線が全てのボックスを通過しており、正方形の1辺を半分にすると曲線が通過しているボックスの数が4倍に増えることから、フラクタル次元が2になることがわかります。
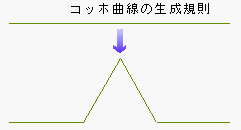
もう一つの有名な例がコッホ曲線と呼ばれるもので、右図のように線分を3等分し真ん中の部分を正三角形の2辺で置き換える操作を繰り返すことによって生成される曲線です。コッホ曲線のフラクタル次元は、1.26…になることが知られています。
【Q&A目次に戻る】

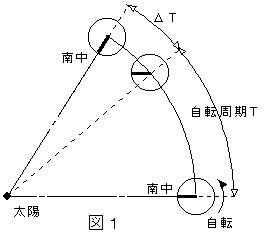
地球が太陽の周りを等速円運動しており、自転軸が公転面に対して垂直ならば、南中時刻は常に同じになるはずですが、実際には、公転速度の変化や地軸の傾きがあるので日々変化します。南中時刻の間隔は、地球の自転周期Tに地球が移動した分の補正ΔT(約4分)を加えたものであり
(図1)、地球の自転周期がほぼ一定であっても、ΔTの変化が生まれるからです。
公転速度の変化による影響から説明しましょう。
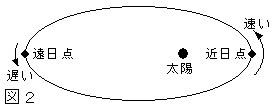
地球は円軌道ではなく太陽を焦点とする楕円軌道を描いていますが、ケプラーの第2法則(面積速度一定の法則)に従って、近日点付近では速く、遠日点付近では遅く動いています
(図2)。公転速度が速いとΔTが大きくなるので、見かけの太陽の動きに基づく時刻(視太陽時)は平均太陽時(恒星系の観測に基づく絶対的な時刻)から遅れていき、均時差=視太陽時−平均太陽時はマイナスの側に振れていきます。特に、公転速度が最大になる近日点では、均時差のグラフの傾きが最大になります。1次近似
(数%の誤差があります)では、この効果による均時差の変化は、
-Asin(φ−ω)
となります。ただし、φは太陽系に固定された座標での地球の経度、ωは近日点経度、Aは軌道要素によって決定される係数で、近似的には、1月1日の位置を経度の起点とするとω=0[rad]、A=7.7[分]となります。
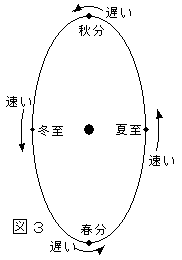
均時差をもたらすもう一つの原因は、軌道面に対して地軸が23.5°傾いていることです。地球から見たときの太陽の軌道(簡単のため真円とします)を地球の赤道面に投影すると、春分点−秋分点が長径になるような楕円になり、春分と秋分では見かけの公転速度が最も遅く、逆に夏至と冬至では最も速くなります
(図3)。従って、均時差のグラフの傾きは、春分と秋分でプラスの側に最大、夏至と冬至でマイナスの側に最大となります。これも1次近似で表すと、
+Bsin2(φ-Ω)
となり、軌道要素の値から春分点経度Ω=1.4[rad]、係数B=9.9[分]と与えられます。
上の2つを加えあわせると図4のようなグラフとなり、実測値と数%の誤差で一致します。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
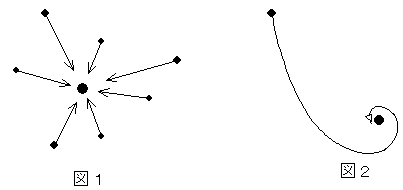
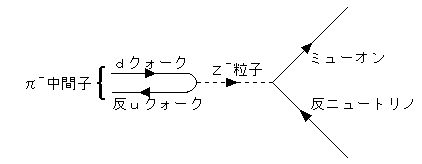
 フラクタルとは、数学者マンデルブロが1975年に提唱した概念で、簡単に言うと、拡大・縮小によって観測のスケールを変えても同じように見える図形のことです。右の図は有名なマンデルブロ図形の一部ですが、上の図の四角に囲まれた部分を拡大すると相似的な下の図になることを示しています(宮根裕司氏のフラクタル描画ソフト “MandelPalette 1.1”で描いた絵を256色に減色しています)。こうした自己相似性を持つ図形の次元は、通常の線(1次元)や面(2次元)と同じように定義することはできません。実際、マンデルブロ図形の縁は、いくら拡大してもなめらかな曲線にはならずに複雑にゆらめいていて、1次元の線とも2次元の面ともつかないものになっているのです。
フラクタルとは、数学者マンデルブロが1975年に提唱した概念で、簡単に言うと、拡大・縮小によって観測のスケールを変えても同じように見える図形のことです。右の図は有名なマンデルブロ図形の一部ですが、上の図の四角に囲まれた部分を拡大すると相似的な下の図になることを示しています(宮根裕司氏のフラクタル描画ソフト “MandelPalette 1.1”で描いた絵を256色に減色しています)。こうした自己相似性を持つ図形の次元は、通常の線(1次元)や面(2次元)と同じように定義することはできません。実際、マンデルブロ図形の縁は、いくら拡大してもなめらかな曲線にはならずに複雑にゆらめいていて、1次元の線とも2次元の面ともつかないものになっているのです。
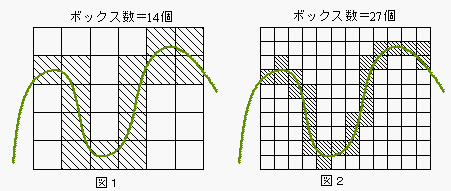
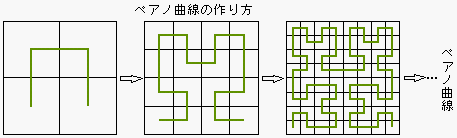
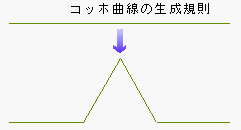 もう一つの有名な例がコッホ曲線と呼ばれるもので、右図のように線分を3等分し真ん中の部分を正三角形の2辺で置き換える操作を繰り返すことによって生成される曲線です。コッホ曲線のフラクタル次元は、1.26…になることが知られています。
もう一つの有名な例がコッホ曲線と呼ばれるもので、右図のように線分を3等分し真ん中の部分を正三角形の2辺で置き換える操作を繰り返すことによって生成される曲線です。コッホ曲線のフラクタル次元は、1.26…になることが知られています。
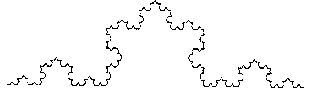
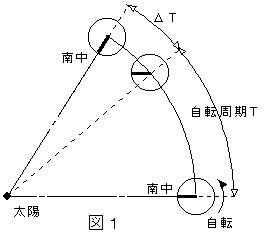 地球が太陽の周りを等速円運動しており、自転軸が公転面に対して垂直ならば、南中時刻は常に同じになるはずですが、実際には、公転速度の変化や地軸の傾きがあるので日々変化します。南中時刻の間隔は、地球の自転周期Tに地球が移動した分の補正ΔT(約4分)を加えたものであり(図1)、地球の自転周期がほぼ一定であっても、ΔTの変化が生まれるからです。
地球が太陽の周りを等速円運動しており、自転軸が公転面に対して垂直ならば、南中時刻は常に同じになるはずですが、実際には、公転速度の変化や地軸の傾きがあるので日々変化します。南中時刻の間隔は、地球の自転周期Tに地球が移動した分の補正ΔT(約4分)を加えたものであり(図1)、地球の自転周期がほぼ一定であっても、ΔTの変化が生まれるからです。
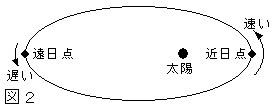 地球は円軌道ではなく太陽を焦点とする楕円軌道を描いていますが、ケプラーの第2法則(面積速度一定の法則)に従って、近日点付近では速く、遠日点付近では遅く動いています(図2)。公転速度が速いとΔTが大きくなるので、見かけの太陽の動きに基づく時刻(視太陽時)は平均太陽時(恒星系の観測に基づく絶対的な時刻)から遅れていき、均時差=視太陽時−平均太陽時はマイナスの側に振れていきます。特に、公転速度が最大になる近日点では、均時差のグラフの傾きが最大になります。1次近似(数%の誤差があります)では、この効果による均時差の変化は、
地球は円軌道ではなく太陽を焦点とする楕円軌道を描いていますが、ケプラーの第2法則(面積速度一定の法則)に従って、近日点付近では速く、遠日点付近では遅く動いています(図2)。公転速度が速いとΔTが大きくなるので、見かけの太陽の動きに基づく時刻(視太陽時)は平均太陽時(恒星系の観測に基づく絶対的な時刻)から遅れていき、均時差=視太陽時−平均太陽時はマイナスの側に振れていきます。特に、公転速度が最大になる近日点では、均時差のグラフの傾きが最大になります。1次近似(数%の誤差があります)では、この効果による均時差の変化は、
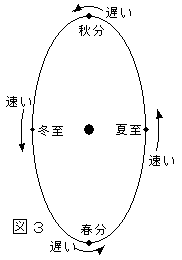 均時差をもたらすもう一つの原因は、軌道面に対して地軸が23.5°傾いていることです。地球から見たときの太陽の軌道(簡単のため真円とします)を地球の赤道面に投影すると、春分点−秋分点が長径になるような楕円になり、春分と秋分では見かけの公転速度が最も遅く、逆に夏至と冬至では最も速くなります(図3)。従って、均時差のグラフの傾きは、春分と秋分でプラスの側に最大、夏至と冬至でマイナスの側に最大となります。これも1次近似で表すと、
均時差をもたらすもう一つの原因は、軌道面に対して地軸が23.5°傾いていることです。地球から見たときの太陽の軌道(簡単のため真円とします)を地球の赤道面に投影すると、春分点−秋分点が長径になるような楕円になり、春分と秋分では見かけの公転速度が最も遅く、逆に夏至と冬至では最も速くなります(図3)。従って、均時差のグラフの傾きは、春分と秋分でプラスの側に最大、夏至と冬至でマイナスの側に最大となります。これも1次近似で表すと、