
複素数は、(0で割る以外の)全ての代数方程式が解を持つように導入されたものです。実数の範囲では、2乗してマイナスになるような数は存在せず、x
2=-1 という方程式は解を持たないので、虚数単位
i を導入して数の体系を拡張したわけですが、この方程式を、面積がマイナス1の正方形の1辺を求めるものと考えたのでは、何を意味しているのかわからなくなります。幾何学的なイメージから離れて、もっと抽象的な操作として数の演算を理解してください。
実数の掛け算で問題を難しくしているのは、符号です。実数は、数直線上の点と見なすことができ、正の実数に限れば、掛け合わせる2つの数の数直線上の位置を連続的に変化させると、積の位置も連続的に変わります。ところが、符号まで含めると、正か負かという離散的な量が計算に入り込み、負の数を掛けるときには、数直線上で0と逆の方向に移動しなければなりません。この離散性のために、同じ数を掛け合わせて負になるような数を定義することができなくなります。
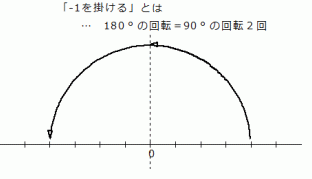
複素数とは、この問題を回避するために数直線を数平面に拡張したものだと考えると、わかりやすくなります。この場合、負の数を掛けることは、数直線上で0と逆の方向に移動するという離散的な操作ではなく、0を中心に角度θだけ回転するという連続的な操作で θ=180° と置いたことになります。同じ数を2度掛けて負にするとは、同じ角度だけ2度回転して180°の回転にすることなので、掛け合わせる数は θ=90° だけ回転させる数、すなわち、0を通り実軸に垂直な軸上の数を意味します。この垂直な軸が、いわゆる虚軸です。複素数とは、数平面上の1点で表される数であり、0からの距離(=絶対値)が
r、0から見て実軸となす角度(=偏角)がθの複素数は、
re
iθ と表されます。この数を別の複素数に掛けることは、絶対値を
r倍し、偏角にθを加える操作になります。
実数を複素数に拡張すると、代数方程式が必ず解を持つので便利ですが、それ以上に重要なのは、振動を表す式が簡単になることです。実数を使って調和振動を表す場合は三角関数を使わざるを得ず、加法定理などの面倒な公式を覚える必要があります。ところが、複素数ならば、絶対値が1の複素数 e
iθ を掛けるだけで0の回りの回転が表されることになり、数式がきわめて簡単になります。 e
iθ をθの関数として扱うと、微積分も容易に行えます。電磁気学で、交流や電磁波を扱う際に複素数を使うのは、この性質があるからです。
【Q&A目次に戻る】

力学的なエネルギーのやりとりは、仕事と呼ばれる物理量を通じて行われます。ところが、仕事は、力の運動方向成分に移動距離を掛けたものとして与えられるので、運動方向(=速度の向き)に対して垂直に働く力は仕事をしないことになります。コリオリの力は、まさに速度に垂直に働く力なので仕事はゼロであり、仕事の形でエネルギーをやりとりすることはできません。
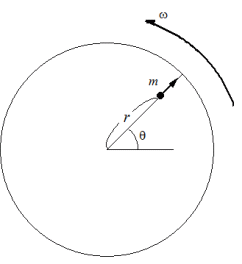
コリオリの力が仕事をしないことを示す簡単な例を紹介しましょう。中心軸の周りで滑らかに回転する円板があり、1匹の虫が、その上を中心軸から遠ざかる向きに歩いているものとします。円板の慣性能率を
I0(一定値)、角速度を ω 、虫の質量を
m、虫から中心軸までの距離を
rとします。このとき、円板と虫を併せたシステムの慣性能率
I、角運動量
L0(一定値)、回転による運動エネルギー
Kは、それぞれ、次式で与えられます。
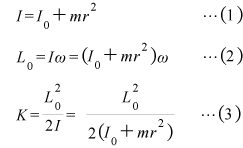
ここで、角運動量の保存則(これは運動方程式から導くべきものですが、ここでは、中心軸の周りに滑らかに回転していることから、常に成り立っているものと仮定します)を使って、角運動量
L0の時間微分がゼロになるという式を立て、(2)式を使って書き直すと、次のようになります(記号の上のドットは、時間微分を表します)。
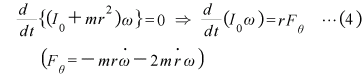 Fθ
Fθの第1項は角速度が変化することに伴う慣性力、第2項がコリオリの力を表しており、運動方向に対して垂直に働くこれらの力と拮抗させるために、虫は円板から
Fθと同じ大きさの摩擦力を受けます(この摩擦力は虫が踏ん張る際の静止摩擦なので、仕事はしません)。したがって、(4)式の右辺は、虫から円板に加わる摩擦力によるモーメントとなり、これが、円板の角運動量を変化させることを意味しています。コリオリの力は、円板の角速度を変化させるのに寄与しているわけです。しかし、このときの回転エネルギーの変化は、遠心力によってのみもたらされています。このことは、遠心力による仕事を計算すればわかります。中心軸からの距離が
r1から
r2まで移動したときの遠心力による仕事は、次式で与えられます。
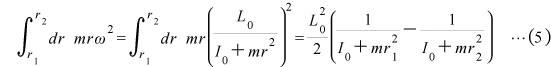
これと(3)式を比較すれば、遠心力による仕事と回転エネルギーの変化が一致することがわかります。
このように、運動方向に垂直なコリオリの力は、仕事をしません。しかし、他のエネルギーが形を変える際に、コリオリの力が寄与することはあり得ます。大学入試でよく出題される物理の問題に、磁場が加わった滑らかな斜面で導線を滑らせたときに発生する起電力を求めさせるというものがあります。起電力が発生するのは、導体内部の電子が磁場からローレンツ力を受けて移動するためですが、ローレンツ力はコリオリの力と同じく運動方向に対して垂直なので、仕事をしません。にもかかわらず、起電力という形で電気的なエネルギーが発生するのは、ローレンツ力を介して、重力のエネルギーが電気的なエネルギーに変換されたからです。これと同じようなことがコリオリの力でも起きれば、コリオリの力を介して発電することもあり得ます。
太陽からの放射エネルギーが大気を熱することで気流が生じますが、この気流がコリオリの力によって向きを曲げられ、渦巻き状になって台風を発生させることが知られています。台風のエネルギーは、あくまで太陽の放射エネルギーが変換されたもので、コリオリの力が仕事をしたわけではありませんが、コリオリの力を介してエネルギーが特定の領域に集中したとも言えるわけです。内部で雷(水滴の大きさによって帯電状態が異なるため、上昇気流で吹き上げられる際に荷電分離が生じることに起因する現象)が生じたならば、放射エネルギーがコリオリの力を介して電気的エネルギーに変換されたことになります(「発電する」と言うのは、ちょっと苦しいかもしれませんが)。
【Q&A目次に戻る】

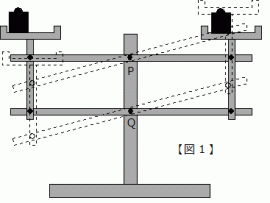
「Roberval の秤」は、17世紀にフランス人数学者ロベルヴァルが発明した秤で、図1のような構造をしています。鉛直な中心棒上に支点を持つ2本の横棒があり、その端に受け皿が載った縦棒が取り付けられています。図の黒丸は、滑らかな軸を表します。2本の横棒が完全に同型ならば、両側の縦棒は常に鉛直に保たれ、受け皿も水平になります。受け皿に同じ重さのおもりを載せると、秤は釣り合って静止するので、商品などを計量するのに使えます。
ここで面白いのは、受け皿のどの位置におもりを載せても、重さが同じならば釣り合って静止するという点です。これは、力のモーメントを考えると、少し不思議な気がします。図1では、左右のおもりがどちらも向かって左寄りに偏っていますが、それでも重量が同じならば、釣り合いが成り立ちます。棹秤が静止するためには、モーメントの釣り合いが成り立つように、それぞれの物体から棹に加わる力と中心軸までの距離の積が等しくなることが必要です。図2で言えば、 FL=fl でなければならず、重量が等しく F=f ならば、 L=l でないと秤は静止しません。これが、モーメントの釣り合いです。ところが、Roberval の秤では、おもりから中心軸までの距離が左右で異なっており、モーメントが釣り合っていないのに秤が静止するように思えるから奇妙です。
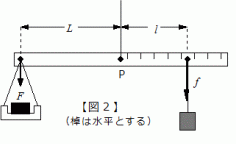
この謎は、力の加わり方をきちんと考えれば、解明することができます。中心からずれた場所におもりを載せたとき、受け皿を支える縦棒からの抗力は、受け皿に生じるモーメントを打ち消すように、場所によって異なったものになります(図3;縦棒の支えがない場所におもりを載せると、受け皿が接着されていない限り、ひっくり返ることを考えてください)。このため、受け皿から縦棒に加わる力(縦棒からの抗力の反作用)も、縦棒の中心軸に関して対称にならず、不均等になります。縦棒を支える軸受が滑らかな場合、軸受けから縦棒に加わる力は軸の表面に対して垂直になりますが、受け皿から縦棒に不均等に力が加わっているので、縦棒のモーメントを釣り合わせるために、この抗力は軸対称にはならず、結果的に横方向の力が発生します。この横方向の力は、横棒の支点PとQに伝わります。
ここで、支点Pの周りのモーメントを考えてみましょう。2つのおもりの位置が偏っているので、おもりだけを考えるとモーメントは釣り合っていません。しかし、支点Qにおいて横棒に水平方向の力が加わっているので、その効果をPの周りのモーメントに付け加えなければなりません。これを併せると、Pの周りのモーメントが釣り合っているはずです。
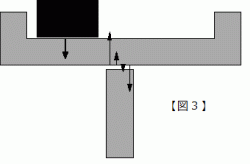
もっとも、実際にモーメントを計算して釣り合いを確かめるのは大変です。そこで役に立つのが、仮想仕事の原理です。考えている状態から仮想的に少し変位させたとき、外力が正の仕事をするならば、元の状態は釣り合っていない(安定平衡でない)という原理です。図2の棹秤で F=f の場合、左側のおもりを下げる方向に棹を水平からθだけ傾けたとすると、左のおもりは L sinθ 下がり、右のおもりは l sinθ 上がるので、 L=l でなければ重力は仕事をすることになり、釣り合っていないことがわかります。この原理を、Roberval の秤に適用してみましょう。秤の機構は対称なので、横棒を傾けたときの鉛直方向の移動距離は、左右とも等しくなります。したがって、受け皿に載せたおもりの重量が等しい場合には、水平状態から横棒を傾けても重力は仕事をしません(水平状態に限らず、どの状態から変位させても仕事量はゼロです)。このため、おもりの重量が等しければ、受け皿のどこに載せても、釣り合いが成り立って秤は静止するのです。
【Q&A目次に戻る】

主系列星内部では、水素の核融合によりヘリウムが作られていますが、このヘリウムは、水素より重いので恒星の中心部分に沈み込んだまま、どこにも行きません。
水素燃焼(恒星物理学では、核融合を“燃焼”と言います)の時期がしばらく続くと、核融合の燃料となる水素が不足してきます。恒星全体の質量が太陽の半分以下の場合は、そのまま核融合が停止して、ヘリウムを主成分とする白色矮星になります。質量が充分にある場合、水素の核融合がヘリウム中心核の表面部分で起きるようになるため、その熱で水素を主成分とする外層部が急激に膨張して巨星となる一方、中心核は自己重力で収縮していきます。
中心核が収縮する過程で温度が上がって臨界温度を超えると、3個のヘリウムが核融合を起こして炭素になるヘリウム燃焼段階に突入します。このとき、外層部が流出して恒星は質量を徐々に失っていきます。質量の小さな恒星は、そのままヘリウムを燃焼し尽くして炭素を主成分とする白色矮星になります。質量が充分にある場合は、主に炭素から成る中心核が収縮して温度が上がり、炭素が核融合を起こす炭素燃焼段階に入ります。この後も、質量の大小によって恒星の運命は異なり、軽い星は炭素燃焼段階の後に超新星爆発を起こしますが、重い星は、さらに、ネオン・酸素燃焼段階、ケイ素・マグネシウム燃焼段階と続き、中心には、“燃えかす”である鉄を主成分とする核が形成されます。鉄までくるとそれ以上の核融合は起きず、最終的には中心核が潰れて超新星爆発を起こし、後には中性子星やブラックホールが残ります。
【Q&A目次に戻る】

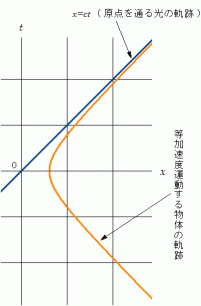
ブラックホールの性質などを記述する一般相対論では、座標系の選び方に任意性があるので、特定座標系における記述が物理的に何を意味しているかを正しく解釈する必要があります。事象の地平面付近を遠方の静止座標系から見ると、確かに時間が無限に引き延ばされているように見えますが、これは、ブラックホールに落下する物体の時間経過とは、全く異なっています。
ブラックホールにおける事象の地平面は、一方向(例えば、ブラックホールの中心から観測者に向かう方向)だけを考えると、等加速度運動する物体から見た地平面と良く似ています。等加速度運動する物体は次第に加速されて光速に近づくため、図の原点から発せられた光は、加速しながら逃げていく物体に追いつけません。同じように、図の x<ct の領域から出た光は決して物体に到達せず、この領域の情報は、物体とともに運動する観測者に伝わらなくなります。したがって、この観測者から見ると、x=ct という面が事象の地平面となります。ブラックホールの地平面も、これと同じように、観測者に情報が伝わる限界と考えれば、その物理的性質が理解しやすくなります。
等加速度運動する観測者から見ると、地平面は情報伝達の限界というはっきりした物理的意味を持っています。しかし、慣性運動している他の観測者にとって、地平面は存在しません。x>ct の領域から地平面の彼方に運動することに障害はなく、地平面を超える瞬間に何かが起きるということもありません。ブラックホールに落下する物体にとっても同じことです。シュワルツシルト面を通り抜けるときには何も起きず、有限の時間のうちに中心の特異点に到達します。
それでは、遠方で静止する観測者から見て地平面付近の時間が引き延ばされていることは、何を意味するのでしょうか? 簡単に言えば、地平面の少し外側から発せられた光の速度が遅くなったように見えるということです。物体がブラックホールに落ち込む直前に出した光は、いつまでも地平面付近から離れられず、「ブラックホールまでの距離/c」で求められる時間よりもかなり経ってから、観測者の所に到達します。ただし、物体がいつまでも地平面付近に漂って見えるというわけではありません。物体は何の障害もなく地平面を通り抜けていき、発せられる光量は急激に減少するので、遠方の観測者には、物体がスッと消えていくように見えるはずです。
【Q&A目次に戻る】

近年、先進国を中心にアトピー皮膚炎が増加していることはほぼ確実のようですが、これは、主に人工的な環境に要因があると思われます。
人間の身体は、過去数百万年の間に、環境に適合するように進化してきました。しかし、産業革命以降の環境の変化はあまりに急激であり、遺伝子の変化はこれに対応できていません。例えば、人間には、飢餓状態に耐えられるようなさまざまな遺伝子がありますが、飽食という以前にはほとんどなかった状況に備える遺伝子はほとんどなく、うまく対応できないまま糖尿病のような現代病を発症する結果になっています。
アトピー皮膚炎は、皮膚に炎症などが現れるアレルギー反応で、免疫機能の過剰反応と見なすことができます。免疫機能自体は、病原体を攻撃するために進化してきたものです。しかし、生活環境の急激な変化に対して旧来の遺伝子が適切に対応できないまま、免疫機能が不適切に発揮されると、現代的な病気として発症することがあります。アトピー性皮膚炎が増加した根本的な原因は、はっきりしていません。ダニや化学物質などのアレルゲンの増加が関係しているのかもしれません。例えば、家屋の密閉性が高まった結果、塵の中のチリダニが増加したとの報告もあります。しかし、これだけでは、アレルギー疾患の急激な増加(日本では、現在、人口の約40%がアレルギー疾患の罹患歴を持つとされる)は充分に説明できません。食事が関係している可能性もあります。欧米的な食事に多く含まれるリノール酸は、大豆・魚介類など日本食の食材に多いリノレン酸に比べて、アレルギー炎症を悪化させるという見方もあります。
最近注目されているのが、免疫系のバランスが崩れたという説です。衛生状態の改善や家族数の減少により細菌や寄生虫に感染する機会が減ったため、B細胞に抗体を作らせるヘルパーT細胞への刺激が少なくなり、Th1とTh2という2種類のヘルパーT細胞のバランスが崩れたというものです。実際、ツベルクリン反応が陽性で体内に結核菌を持つ児童は、そうでない児童に比べて、ヘルパーT細胞のバランスが良好だという報告もあります(結核菌を持つこと自体は好ましくありませんが)。
遺伝子が大きく変化するには数百世代が必要なので、われわれは、これからも旧来の遺伝子によって現代的な環境に対応していかなければなりません。その結果が糖尿病やアトピーなどの現代病だとすると、これは、現代人の宿痾なのでしょうか。
【Q&A目次に戻る】

シュヴァルツシルト半径のようなブラックホールに関連する量は、全てアインシュタイン方程式から理論的に導かれたものです。ブラックホールに関しては、現在なお、(ブラックホールに流入するガスからの放射のような)間接的な観測しか行われていません。
質点の周りにどのような重力場ができるかは、アインシュタイン方程式を解くことによって求められます。この計算を最初に行ったのは、ドイツの天文学者シュヴァルツシルトで、1916年のことです。彼の結果によれば、重力場は、時間を
t 、質点からの距離を
r とすると、次のような式で表されます。
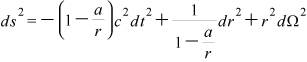
専門的になるので、式の意味が理解できなくてもかまいません。重要なのは、
r=a となるときに、右辺の
dt の係数がゼロ、
dr の 係数が無限大になることで、そのせいで、重力は奇妙な振舞いをします。例えば、
r<a の領域からは、あらゆる物が内側にしか進むことが出きず、光ですら外に出ることができません。また、
r=a よりほんの少し外側にいる場合、光速に近い速度でなければ脱出できないことがわかります。この
a がシュヴァルツシルト半径であり、
r=a となる球面は「事象の地平面」と呼ばれます。周囲に事象の地平面が形成される天体が、ブラックホールです。
ところで、誰がシュヴァルツシルト半径を発見したかについては、少し微妙な問題があります。現在では、巨大な質量を持つ天体が自分の重力でつぶれていくと、実際に事象の地平面が現れてブラックホールになると考えられています。しかし、アインシュタインが重力理論を構築した当時にあっては、事象の地平面のような奇妙な性質を持つ曲面が存在するとは信じられなかったようです。アインシュタイン方程式を解いたシュヴァルツシルト自身、
r=a の球面は現実的なものだと思いませんでした。そこで彼は、質点からの距離を表すのは
r ではなく、

という式で定義される
R だと考えました。この考え方によれば、
r=a は質点からの距離が
a となるような球面ではなく、質点が存在する
R=0 の原点だということになります。質点が置かれている地点以外では、
dt や
dr の係数がゼロや無限大になりません。シュヴァルツシルトは、さらに、一定の密度を持つ球体内部の重力場の計算も行いましたが、このときも、
r を用いて計算するのはまずいと考え、やはり、新たな変数を導入して特異性を回避しています。もっとも、この論文の末尾で、
r のままで計算すると、半径
a 以下の球体ではおかしなことが起きるように見えると指摘した上で、太陽の場合に
a は3kmになると記しています。これは、こんにち、太陽のシュヴァルツシルト半径として知られる値です。
質点からの距離が
a の地点に特異性があることに誰が最初に気づいたのか、私は調査し切れませんでしたが、英語版Wikipediaの記述によると、ドイツの数学者ヒルベルトのようです(彼の論文は読んでいません)。
【Q&A目次に戻る】

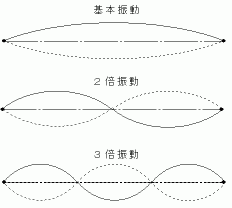
個数を数えられるからと言って、光子や電子が粒子だとは限りません。個数が数えられる波としてはソリトンが有名ですが、光子や電子はソリトンではなく、内部空間に形成された定在波だと考えられます。定在波とは、どこかに進んでいくことにない波で、両端が固定された弦を弾いたときに生じる波(右図)が、その典型的な例です。弦を弾いた直後はさまざまな波が重なって生じますが、時間が経つと波が安定し、半波長の波がいくつあるかを数えることが可能になります。素粒子とは、このような定在波が粒子のように振舞っているものです。
厳密なことを言うと、光子と電子では、個数の定義に少し差があります。フェルミオンと呼ばれるタイプの素粒子である電子の場合、生成・消滅の際には、常に電子と陽電子がペアになって現れたり消えたりするので、電子と陽電子の個数の差が一定になるという保存則があります。これに対して、光子には個数の保存則がないため、常に何個の光子があるか数えられるわけではありません。波長の長い電磁波では、光子の個数が確定できないケースが多くなります。一方、ガンマ線のように波長が短くなると、個数が定まった状態の寄与が支配的になるので、「光子が何個ある」と言えるようになります。1個ずつの光子を利用したとされる実験では、光子の個数が確定した状態の寄与が支配的になるように、エネルギー準位が確定した状態間の遷移を利用するなどの工夫がこらされています。
【Q&A目次に戻る】

素粒子に質量を与えるヒッグス機構に関しては、まだわかっていないことがたくさんあります。ヒッグス機構ではヒッグス場が凝縮すると仮定されますが、そもそもヒッグス場はなぜ凝縮するのかが、よくわかっていません。現在の理論では、凝縮するような相互作用を仮定して話を進めているだけです。あるいは、なぜグルーオンは質量を獲得せずW粒子だけが質量を得るのかも、わかりません。光子が質量を獲得しなかった理由も、不明としか言えないのが現状です。
ただし、光子が質量を持つと、宇宙で生命が発生できなくなるので、もし、物理定数の異なる宇宙が無数に誕生しているという多重宇宙の考え方が正しければ、「人間原理」の観点から解答できます。つまり、たくさん存在する中で、たまたま光子が質量を持たなかった宇宙にだけ人間が誕生し、「なぜ光子には質量がないのか」と悩んでいるということなのです。これは、「なぜ地球には水が大量にあるのか」と悩む地球人に対して、「水がなければ生命が発生しないから」というのが答えになるのと同じです。
生命の発生に光子が質量を持たないことが必要である理由を、簡単に説明しましょう。
グルーオンに媒介される核力は、非可換ゲージ相互作用という形式をしており、2粒子間の力は粒子を引き離すほど強くなるという特徴を持っています。このため、粒子はどこまでも遠ざかることができず、相互作用を中和するような塊を作る傾向があります。こうして、まず陽子や中性子のような核子が形成され、さらに、これらから漏れ出る相互作用によって原子核が作られます。
一方、光子に媒介される電磁気力は、遠方で弱くなる可換ゲージ相互作用であり、光子が質量を持っていなければ、長距離力として作用します。
ゲージ相互作用にはさまざまなタイプがあり、ある宇宙でどの相互作用が実現されるのか、その仕組みはまだわかっていません。しかし、仮に、統一的なゲージ相互作用があり、宇宙初期の相転移を通じて、いずれも質量を持たない非可換と可換の2つのタイプに分かれたとすると、前者は後者に比べてきわめて強い力となることが知られています。その結果、非可換ゲージ相互作用が固く結合した安定な原子核を作り出す一方で、可換ゲージ相互作用は、弱い長距離力となって緩く結合し簡単に化学変化を起こす原子や分子を形成します。こうして、「壊れにくい元素が化学反応を通じて千変万化する」という世界が実現されるのです。このような世界以外に生命が発生し人間が誕生するとは考えにくいので、われわれの住む宇宙で光子が質量を持っていないことは、たとえ仕組みはわからなくても、必然的なのです。
【Q&A目次に戻る】

「意識」について考えてみましょう。科学が「意識とは何か」という問いにいつか解答を与えられるかどうか、まだ、全く見通しは立っていません。今のところ、この問いに答えるための準備として、意識が持つさまざまな特徴をあぶり出そうとする段階に留まっています。
取りあえずは、意識の有無を判定する技術の向上が必要です。以前には、脳に重い損傷を受けた患者に意識があるかどうかを調べるのに、刺激に対してどのような行動を示すかを見ていましたが、これだけでは、意識はあるが体を動かせない、あるいは、意識はないのに偶然にも意識的と思える動きをした−−などのケースが区別できませんでした。ところが、最近では、fMRIなどによって動的な神経活動の検査が可能になり、意識判定の仕方が大きく変わってきました。例えば、植物状態だとされた患者でも、外部からの言語刺激に対して脳の特定部位が活性化される場合があるとわかり、植物状態でも意識があり得る(あるいは、植物状態という判定は間違いやすい)という見方が強まっています。現在のfMRIは空間的・時間的な解像度が低く、まだ、意識の有無を確定できるほどではありませんが、この技術は、今後、長足の進歩を遂げると考えられています。このほか、認知心理学的な実験手法も、意識の関与を判定する上で有用です。例えば、コンマ数秒の時間差をおいて2つの刺激を与えたとき、条件付けが実現されるには意識の関与が必要だとされています。この点に関してはまだ議論が残されていますが、fMRIが使えないケースでも、意識の有無を判定する材料として使えます。
もっとも、こうした技術がどんなに向上したとしても、意識の本質に迫ったとは言えないでしょう。意識が情報の統合と関係していることは明らかですが、統合を実現するハードウェアが意識の成立にどこまで関与しているのか、全くわからないからです。現在のコンピュータ技術をもとに意識を持つ機械を作るのは難しそうですが、では、データ駆動型マシンやバイオチップを用いたマシンならばどうか、遺伝子操作を利用して神経系を人工的に作り上げるとどうなるのか−−といった問いに対しては、推測以上の解答は難しいと思います。
ここで、私の推測を述べさせていただきます。私の考えは、ハードウェアが要素還元可能ならば、意識は成立しないというものです。ただし、要素還元可能なシステムとは、システムの動作を「各部分の状態」と「部分間の入出力」に分けて記述できるものです。物理学的な知見によると、要素還元可能でないのは、量子論的な効果を直接利用したシステムに限られます。脳は、神経興奮の過程で膜構造の安定化やイオン・チャネルの開閉に量子論的な効果を利用しているので、要素還元不能なシステムだと言えますが、半導体を利用したコンピュータは、情報を統合する過程に量子論的な効果が利用されていないので、たとえデータ駆動型であっても、要素還元は可能であり意識は生み出せないと思います。物理的な特性をもとに意識の成立を扱う論述は、いかがわしい似非科学との境界線上にあるため、いまだ科学として認知されておらず、私としてもどこまで将来性があるかわかりませんが、この方向で議論を洗練させていけば、「意識とは何か」という問いに科学的に答えることも夢でなくなるかもしれません。
【Q&A目次に戻る】

かつてPCBは、電気工業を発展させる上で欠かせない物質として大量に使われていました。1960年代に体内に蓄積されて慢性毒性を及ぼす可能性が指摘され、1972年に製造・輸入・新規使用が原則禁止になりましたが、それ以前に製造された5万トンに及ぶPCBの半分以上が、現在なお国内に存在しているはずです(違法に処理されたり行方不明になったものも多い)。2001年に制定されたPCB処理特別措置法では、2016年までにPCBを安全に処理することが事業者に義務づけられています。しかし、処理コストがあまりに高くつくため、多くの事業者が手を打てずに保管中というのが現状です。
PCB処理の難しさは、安全性とコストがトレードオフの関係にあることに由来します。例えば、政府系企業の JESCO は、当初、蛍光灯の安定器に含まれるPCBの処理費用を1kg当たり1,810円としていましたが、従来の方法では処理が不完全なのでプラズマ分解法(高温で分子がイオン化した気体を利用してPCBを分解する方法)に変更するとして、2010年に、1kg当たり29,400円に値上げしました(新聞報道より)。この金額は、多くの事業者にとっておいそれと支払えるものではありmせん。
安価な処理法には、高温焼却法があります。PCBが完全燃焼されないまま酸素と反応すると、毒性が遥かに強いダイオキシンに変わるおそれがあるため、現在、周辺住民の反対にあって焼却炉の建設が困難な状況が続いています。しかし、充分な高温状態を保つ温度管理と、熱によるPCB蒸散の防止ができれば、必ずしも危険だという訳ではありません。
コストは高いが安全な処理法としては、触媒を利用した化学反応によってPCBを無害化するというものがあります。PCBの毒性は、ベンゼン環に塩素原子が結合することで生じているので、この塩素を水素などに置換することができれば、毒性のない化学物質に変わります。こうした化学処理の基礎技術はすでに開発されており、現在では、コストを下げることが課題になっています。また、超臨界水(液体と気体の中間状態で反応性の高い水)など利用し、PCBを水・塩・二酸化炭素にまで分解してしまう完璧な処理法もあります。
PCBは、古いコンデンサーや蛍光灯ならふつうに含まれているので、さまざまな事業者が抱え込んでいます。その中には、費用負担能力の乏しい中小企業も少なくありません。また、保管期間があまりに長引くと、PCBの漏洩や不法投棄のリスクが高まります。このため、完璧でなくても、リスク評価の観点から充分に安全性が高く、一般的な事業者なら費用負担が可能な方法を採用するのが好ましいと考えます。化学処理のコストが低減できればそれに越したことはないのですが、高止まりして処理が進まない場合は、高温焼却法を再検討することも視野に入れるべきでしょう。
【Q&A目次に戻る】

現在、最も一般的なエネルギー供給のシステムは、都市部から離れた地点に火力や原子力などを利用する大規模発電所を建設し、そこから高圧送電線で電力の消費地へと電気を送る方式です。しかし、このやり方では、発電所で発生する大量の熱(エネルギー比率で60%以上)が利用されないまま廃熱として捨てられる上に、送電線の電気抵抗による熱も無駄になっています。超伝導体を使って送電の際のロスをなくすという構想もありますが、交流の場合には、熱の発生を完全に抑制することはできません。ただし、電気が都市部で利用するのに便利なエネルギー形態であることは間違いないので、無駄をできるだけなくしながら電気を利用する方法が望まれます。そこで提案されているのが、燃料をパイプラインなどで輸送し、燃料電池を用いて電気を消費する場所で発電する方式です。このような小規模分散型の発電ならば、遠隔地から送電することによるロスが低減できますし、発電する際の熱を、その地域で給湯や暖房に利用することも可能で、エネルギー効率を最大で70%以上に改善できるはずです。輸送する燃料としては、燃料電池でそのまま燃料として使える水素ガスが便利ですが、水素ガスは漏出しやすく爆発の危険も大きいので、メタンガスやエタノールの利用も考えられます。メタンガスならば、有機物を含むゴミからバクテリアを使って生産することも可能です。水素ガスを生産する方法としては、沿岸部や海上のメガフロートに太陽電池を敷き詰め、発生した電気で水を電気分解する方法があります(電気エネルギーを化学エネルギーに変換する際に無駄が生じるので、送電ロスと比較して有利かどうかを確認すべきでしょう)。
この方法以外にも、提案されているやり方がいくつかあります。例えば、衛星軌道上に巨大な太陽電池を設置し、マイクロ波(携帯電話などで利用される電磁波)を使ってエネルギーを送信する方法も考えられます。マイクロ波ならば、大気中での減衰があまりないので、かなり効率的にエネルギーを送ることができます。ただし、強力なマイクロ波は環境や健康に悪影響を与えるという懸念もあり、実用化には時間が掛かりそうです。
【Q&A目次に戻る】

相対論で否定されたアイデアは2つあります。1つは、光を伝えるのが物質的なエーテルだという考え方。もう1つは、時間と切り離された枠組みとしての空間(絶対空間)が存在するという考え方。この2つは密接に関連してはいますが、別のものと見なした方がわかりやすいでしょう。
ニュートン力学では、時間と空間は概念的に区別されていましたが、相対論では、両者を一体化した時空を考えることになります。一般相対論では、時空のダイナミックな変化が扱われますが、慣性座標系だけを考える特殊相対論では、リジッドなミンコフスキ時空だけを想定します。ミンコフスキ時空は、物理現象が生起する枠組みとして絶対的な地位を占めるので、特殊相対論は、絶対空間を否定して絶対時空を導入したと言っても良いでしょう。
エーテルは、もともとアリストテレス哲学で第5元素とされたもので、空間に対して運動すると考えられていました。このため、まず、公転する惑星が空間に充満するエーテルを引きずる可能性について検討され、天体の光学観測によってそれが否定されると、今度は、静止しているエーテル内部を惑星が素通りしていくという説が提唱されました。この場合、静止しているエーテルに対して地球上の観測者は運動しているので、エーテルの風が観測されるはずです。ところが、マイケルソン−モーレーの実験によって、エーテルの風が観測されないことからエーテル仮説がゆらぎ、ローレンツ−ポアンカレ−アインシュタインによる相対論へとつながっていきます。
相対論的な場の理論は、時空の各点で場の状態が与えられると言う形式をしているため、エーテル理論と似ていますが、場が空間に対して動かないという点で、決定的に異なっています。例えば、流体力学の基礎方程式であるナビエ−ストークスの方程式は、流体中の各点が持つ速度(流速)がどのように変化するかを表す式になっています。空間に対して流体が静止している場合でも、観測者が運動しているならば、流体の各部分は観測者に対して相対的な速度を持ち、全体として流速を持つ流体のナビエ−ストークス方程式に従います。ところが、場の理論になると、場の速度という概念は意味を持ちません。場の状態を、時刻tと位置xの関数として A(t,x) と表すことにすると、時刻tで位置xにいる観測者が観測する場は、観測者が運動していようといまいと A(t,x) であり、観測者に対する場の相対的な速度が観測されることはありません(場がスカラーでなくベクトルや高階のテンソルのときには、式の上で相対論的な変換が必要となる)。場は時空と一体になったものであり、時空内部に場が存在するというわけではありません。これが、場とエーテルの相違です。現在の理論では、同じ場所に電子や光子、クォークなどの場がいくつも重なって存在するので、単一の時空と複数の場という形で区別していますが、将来的には、全ての場が統一され、時空と場が同一視されるようになると期待されています。
ただし、19世紀の時点でもエーテルが原子から構成される物質とは異なるという認識があったことから、物理学者の中には、言葉の上で場とエーテルをあえて峻別しないという立場をとる人もいます。例えば、量子重力理論に先鞭を付けたことで知られるドウィットは、一般相対論における重力場のことを(新しい意味での)エーテルと呼んでいます。
【Q&A目次に戻る】

恒星内部で起きる元素合成が単純な熱核融合だけならば、安定核同士が融合して安定性の低い核になる反応が進むことはないので、鉄までの合成で反応は終わるはずです。しかし、元素合成は、こうした反応だけにとどまりません。太陽と同程度以上の質量を持つ恒星が赤色巨星へと進化する過程で、中心部の温度が数億度以上になってさまざまな熱核反応が起きるようになると、核反応の際に中性子が放出されるケースが増えてきます。例えば、炭素12同士の核融合でマグネシウム23が合成されるともに中性子が放出される次の核反応は、吸熱反応なので低温では起こりませんが、高温になると頻繁に生じるようになります。
12C +
12C →
12Mg + n - 2.6MeV
こうして放出された中性子が他の原子核に捕獲されると、ベータ崩壊を起こして原子番号の大きな原子に変わっていきます。恒星内部で中性子捕獲とベータ崩壊を繰り返すことにより重い元素が合成される過程は、「s過程」と呼ばれています(sは slow の頭文字で、すぐ後に述べる rapid の頭文字を取った「r過程」と対比される)。この過程でビスマス209まで合成されますが、それより重い元素は瞬間的に核崩壊を起こすので、ここでs過程は終了します。
宇宙空間に存在する鉄より重い元素の半分程度は、こうしたs過程で合成され、それ以外は、超新星爆発の際のr過程に由来すると推定されています。ただし、s過程とr過程の比率については、まだ未解明な点がいろいろとあります。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
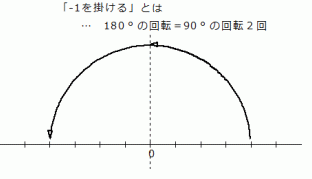 複素数とは、この問題を回避するために数直線を数平面に拡張したものだと考えると、わかりやすくなります。この場合、負の数を掛けることは、数直線上で0と逆の方向に移動するという離散的な操作ではなく、0を中心に角度θだけ回転するという連続的な操作で θ=180° と置いたことになります。同じ数を2度掛けて負にするとは、同じ角度だけ2度回転して180°の回転にすることなので、掛け合わせる数は θ=90° だけ回転させる数、すなわち、0を通り実軸に垂直な軸上の数を意味します。この垂直な軸が、いわゆる虚軸です。複素数とは、数平面上の1点で表される数であり、0からの距離(=絶対値)がr、0から見て実軸となす角度(=偏角)がθの複素数は、reiθ と表されます。この数を別の複素数に掛けることは、絶対値をr倍し、偏角にθを加える操作になります。
複素数とは、この問題を回避するために数直線を数平面に拡張したものだと考えると、わかりやすくなります。この場合、負の数を掛けることは、数直線上で0と逆の方向に移動するという離散的な操作ではなく、0を中心に角度θだけ回転するという連続的な操作で θ=180° と置いたことになります。同じ数を2度掛けて負にするとは、同じ角度だけ2度回転して180°の回転にすることなので、掛け合わせる数は θ=90° だけ回転させる数、すなわち、0を通り実軸に垂直な軸上の数を意味します。この垂直な軸が、いわゆる虚軸です。複素数とは、数平面上の1点で表される数であり、0からの距離(=絶対値)がr、0から見て実軸となす角度(=偏角)がθの複素数は、reiθ と表されます。この数を別の複素数に掛けることは、絶対値をr倍し、偏角にθを加える操作になります。
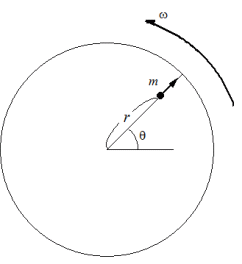 コリオリの力が仕事をしないことを示す簡単な例を紹介しましょう。中心軸の周りで滑らかに回転する円板があり、1匹の虫が、その上を中心軸から遠ざかる向きに歩いているものとします。円板の慣性能率をI0(一定値)、角速度を ω 、虫の質量をm、虫から中心軸までの距離をrとします。このとき、円板と虫を併せたシステムの慣性能率I、角運動量L0(一定値)、回転による運動エネルギーKは、それぞれ、次式で与えられます。
コリオリの力が仕事をしないことを示す簡単な例を紹介しましょう。中心軸の周りで滑らかに回転する円板があり、1匹の虫が、その上を中心軸から遠ざかる向きに歩いているものとします。円板の慣性能率をI0(一定値)、角速度を ω 、虫の質量をm、虫から中心軸までの距離をrとします。このとき、円板と虫を併せたシステムの慣性能率I、角運動量L0(一定値)、回転による運動エネルギーKは、それぞれ、次式で与えられます。
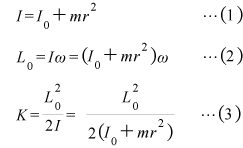
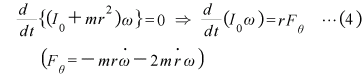
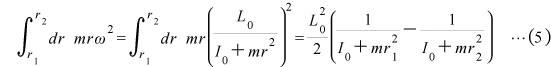
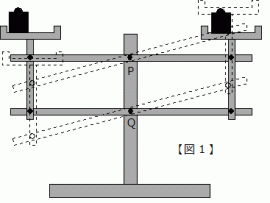 「Roberval の秤」は、17世紀にフランス人数学者ロベルヴァルが発明した秤で、図1のような構造をしています。鉛直な中心棒上に支点を持つ2本の横棒があり、その端に受け皿が載った縦棒が取り付けられています。図の黒丸は、滑らかな軸を表します。2本の横棒が完全に同型ならば、両側の縦棒は常に鉛直に保たれ、受け皿も水平になります。受け皿に同じ重さのおもりを載せると、秤は釣り合って静止するので、商品などを計量するのに使えます。
「Roberval の秤」は、17世紀にフランス人数学者ロベルヴァルが発明した秤で、図1のような構造をしています。鉛直な中心棒上に支点を持つ2本の横棒があり、その端に受け皿が載った縦棒が取り付けられています。図の黒丸は、滑らかな軸を表します。2本の横棒が完全に同型ならば、両側の縦棒は常に鉛直に保たれ、受け皿も水平になります。受け皿に同じ重さのおもりを載せると、秤は釣り合って静止するので、商品などを計量するのに使えます。
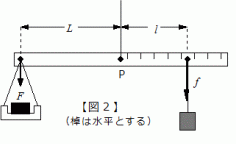 この謎は、力の加わり方をきちんと考えれば、解明することができます。中心からずれた場所におもりを載せたとき、受け皿を支える縦棒からの抗力は、受け皿に生じるモーメントを打ち消すように、場所によって異なったものになります(図3;縦棒の支えがない場所におもりを載せると、受け皿が接着されていない限り、ひっくり返ることを考えてください)。このため、受け皿から縦棒に加わる力(縦棒からの抗力の反作用)も、縦棒の中心軸に関して対称にならず、不均等になります。縦棒を支える軸受が滑らかな場合、軸受けから縦棒に加わる力は軸の表面に対して垂直になりますが、受け皿から縦棒に不均等に力が加わっているので、縦棒のモーメントを釣り合わせるために、この抗力は軸対称にはならず、結果的に横方向の力が発生します。この横方向の力は、横棒の支点PとQに伝わります。
この謎は、力の加わり方をきちんと考えれば、解明することができます。中心からずれた場所におもりを載せたとき、受け皿を支える縦棒からの抗力は、受け皿に生じるモーメントを打ち消すように、場所によって異なったものになります(図3;縦棒の支えがない場所におもりを載せると、受け皿が接着されていない限り、ひっくり返ることを考えてください)。このため、受け皿から縦棒に加わる力(縦棒からの抗力の反作用)も、縦棒の中心軸に関して対称にならず、不均等になります。縦棒を支える軸受が滑らかな場合、軸受けから縦棒に加わる力は軸の表面に対して垂直になりますが、受け皿から縦棒に不均等に力が加わっているので、縦棒のモーメントを釣り合わせるために、この抗力は軸対称にはならず、結果的に横方向の力が発生します。この横方向の力は、横棒の支点PとQに伝わります。
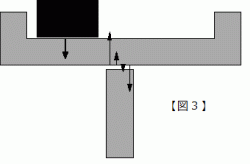 もっとも、実際にモーメントを計算して釣り合いを確かめるのは大変です。そこで役に立つのが、仮想仕事の原理です。考えている状態から仮想的に少し変位させたとき、外力が正の仕事をするならば、元の状態は釣り合っていない(安定平衡でない)という原理です。図2の棹秤で F=f の場合、左側のおもりを下げる方向に棹を水平からθだけ傾けたとすると、左のおもりは L sinθ 下がり、右のおもりは l sinθ 上がるので、 L=l でなければ重力は仕事をすることになり、釣り合っていないことがわかります。この原理を、Roberval の秤に適用してみましょう。秤の機構は対称なので、横棒を傾けたときの鉛直方向の移動距離は、左右とも等しくなります。したがって、受け皿に載せたおもりの重量が等しい場合には、水平状態から横棒を傾けても重力は仕事をしません(水平状態に限らず、どの状態から変位させても仕事量はゼロです)。このため、おもりの重量が等しければ、受け皿のどこに載せても、釣り合いが成り立って秤は静止するのです。
もっとも、実際にモーメントを計算して釣り合いを確かめるのは大変です。そこで役に立つのが、仮想仕事の原理です。考えている状態から仮想的に少し変位させたとき、外力が正の仕事をするならば、元の状態は釣り合っていない(安定平衡でない)という原理です。図2の棹秤で F=f の場合、左側のおもりを下げる方向に棹を水平からθだけ傾けたとすると、左のおもりは L sinθ 下がり、右のおもりは l sinθ 上がるので、 L=l でなければ重力は仕事をすることになり、釣り合っていないことがわかります。この原理を、Roberval の秤に適用してみましょう。秤の機構は対称なので、横棒を傾けたときの鉛直方向の移動距離は、左右とも等しくなります。したがって、受け皿に載せたおもりの重量が等しい場合には、水平状態から横棒を傾けても重力は仕事をしません(水平状態に限らず、どの状態から変位させても仕事量はゼロです)。このため、おもりの重量が等しければ、受け皿のどこに載せても、釣り合いが成り立って秤は静止するのです。
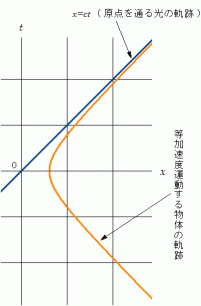 ブラックホールの性質などを記述する一般相対論では、座標系の選び方に任意性があるので、特定座標系における記述が物理的に何を意味しているかを正しく解釈する必要があります。事象の地平面付近を遠方の静止座標系から見ると、確かに時間が無限に引き延ばされているように見えますが、これは、ブラックホールに落下する物体の時間経過とは、全く異なっています。
ブラックホールの性質などを記述する一般相対論では、座標系の選び方に任意性があるので、特定座標系における記述が物理的に何を意味しているかを正しく解釈する必要があります。事象の地平面付近を遠方の静止座標系から見ると、確かに時間が無限に引き延ばされているように見えますが、これは、ブラックホールに落下する物体の時間経過とは、全く異なっています。
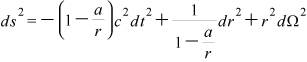
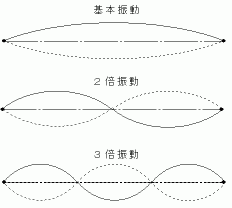 個数を数えられるからと言って、光子や電子が粒子だとは限りません。個数が数えられる波としてはソリトンが有名ですが、光子や電子はソリトンではなく、内部空間に形成された定在波だと考えられます。定在波とは、どこかに進んでいくことにない波で、両端が固定された弦を弾いたときに生じる波(右図)が、その典型的な例です。弦を弾いた直後はさまざまな波が重なって生じますが、時間が経つと波が安定し、半波長の波がいくつあるかを数えることが可能になります。素粒子とは、このような定在波が粒子のように振舞っているものです。
個数を数えられるからと言って、光子や電子が粒子だとは限りません。個数が数えられる波としてはソリトンが有名ですが、光子や電子はソリトンではなく、内部空間に形成された定在波だと考えられます。定在波とは、どこかに進んでいくことにない波で、両端が固定された弦を弾いたときに生じる波(右図)が、その典型的な例です。弦を弾いた直後はさまざまな波が重なって生じますが、時間が経つと波が安定し、半波長の波がいくつあるかを数えることが可能になります。素粒子とは、このような定在波が粒子のように振舞っているものです。