
「情報‐エネルギー変換」という言い回しはプレスリリースなどで使われましたが、正確な表現ではありません。実際に行ったのは、情報を利用することによって、熱エネルギーを電気エネルギーに変換するという過程です。
物理学の常識によれば、熱エネルギーを利用するためには、高温領域と低温領域を用意しなければなりません。高温側から低温側へと熱が自然に流れる際に、ちょうど流体の流れを使って水車や風車を回すのと同じように、熱エネルギーを仕事に変えることができます。火力発電や原子力発電では、燃焼や核分裂による熱エネルギーをこの方法で電気エネルギーに変換しています。「熱は高温側から低温側にしか流れない」という経験則を一般化したのが熱力学第2法則であり、「エントロピーは常に増大する」という形にまとめられます。
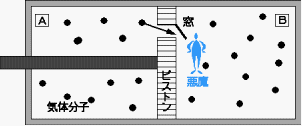
ところが、19世紀の物理学者マクスウェルは、次のような操作を行う仮想的な悪魔がいれば、高温・低温の領域がなくても熱エネルギーを仕事に変換できることを示しました。ピストンで隔てられたシリンダーの2つの領域AとBに等温・等圧の気体が封入されており、ピストンには悪魔が開閉操作をしている窓があるとします。悪魔は、気体分子が領域Aから領域Bに向かうときには窓を開けて分子を通過させ、逆向きのときには窓を閉めて通過させないようにしています(窓の開閉には、熱エネルギーよりも遥かに小さなエネルギーしか消費しないと仮定します)。すると、しだいに領域Bの圧力が領域Aよりも高くなるので、圧力差を利用してピストンを動かし、仕事の形でエネルギーを取り出すことができます。この過程は、高温・低温の領域がないにもかかわらず熱エネルギーを利用したことになるので、熱力学第2法則が破れたように見えます。熱力学第2法則を破る仮想的な悪魔は、「マクスウェルの悪魔」と呼ばれています。
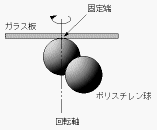
東大・中央大のグループが行ったのは、マクスウェルの悪魔を具現化する実験です。
2枚のガラス板の一方に1点で付着させた回転体(直径300nmのポリスチレン球を2個連結したもの)を取り付け、ガラス板の間隙に水を満たします。この回転体は水分子が衝突することで軸の周りを左右に回転しますが、回転角が何度になるかは顕微鏡を使って測定できます。何の操作も加えなければ、回転体は右に左にとランダムに回転するはずです。ここで、外部電極に電圧を加えることで、回転体を左回りに回転させるような電気的なポテンシャルを発生させます。このポテンシャルは図のように180°周期の振動関数に一定の勾配を持つグラフを重ね合わせた形をしており、スイッチ操作で位相を反転させることができます。このスイッチ操作が、マクスウェルの悪魔による窓の開閉に相当します。
このようなセットアップを用いると、回転体は、ポテンシャルの底となる位置を中心として、ブラウン運動に相当するランダムな回転をフラフラと行うことになります。その状況を継続的に観測しながら、たまたま右回りに大きく回転したときに、スイッチを切り替えてポテンシャルの位相を反転するようにします。すると、ポテンシャルの頂上近くまで回っていた回転体は、一転してポテンシャルの底近くに移り、その位置を中心としてフラフラと回転するようになります。この結果、回転体は、左回りに回転させようとする電場からの力に反して右に回ったことになり、電気的なエネルギーが増加しています。こうした操作を繰り返すことで、最終的には、回転体が右に回り続けて、大きな電気エネルギーを獲得するに至ります。増加した電気エネルギーは、水が持っていた熱エネルギーに由来するものです。こうのようにすれば、高温・低温の領域がないのに熱エネルギーが電気エネルギーに変えられた訳であり、スイッチ操作を行う機械的な装置がマクスウェルの悪魔に相当します。
この実験は、情報をエネルギーに変えたのではありません(したがって、情報と質量は関係ありません)。情報をもとに(ポテンシャルの切り替えという)マクロな操作を行うことで、ミクロの運動エネルギーである熱エネルギーをマクロな電気エネルギーに変換するものです。高温側から低温側に熱が流れるときにエントロピーは増大しますが、この実験では、温度差がないにもかかわらず水から熱エネルギーが流出しているので、エントロピーが減少し熱力学第2法則が破れたように見えます。これは、物理法則の破綻と言うよりは、温度と熱の流れだけに基づく定式化が不十分であることを意味すると考えるべきでしょう。実際、熱力学的な量と情報に関する量を併せて再定式化すれば、この実験でも熱力学第2法則が成り立っていることが示せます。
物理法則は対象の種類によらず統一された式になるべきなのに、このように異なる物理量を混ぜなければならないのは、ここで利用される実験装置が、熱平衡状態に近い統計的なシステムと、情報処理を行うプロセッサなどの機械的なシステムを組み合わせたものになっているからです。機械的なシステムも物質から構成されているので、全ての構成要素に関するシュレディンガー方程式を考えれば、統一的な物理法則に支配されているはずです。しかし、機械的なシステムの物理状態を完全に決定することは現実問題として不可能であり、実際には、(ポテンシャル切り替えスイッチのオン/オフのような)いくつかの離散量をもとにシステムの状態を表さなければなりません。このように、統計的システムとは異なる基準に基づいて粗視化された状態記述を使う以上、異種の物理量を混在させた法則にならざるを得ないのです。
【Q&A目次に戻る】

確かに、高性能の望遠鏡を使って天体表面の反射率などを詳しく調べることができれば植生の有無などもわかるはずですが、残念ながら、現在の技術ではそこまで性能を高めることは困難です。
すばる望遠鏡のホームページに掲げられた性能表によると、波長2.15μmでの分解能は0.2秒角、コンピュータによって大気のゆらぎを補償すれば、分解能をこれより1桁向上させられるということです。1秒角(1度の3600分の1)とは、月軌道上にある1.9kmの物体が見える視角に相当します。また、地球から見たときの年周視差が1秒角になる天体までの距離を1パーセク(=3.26光年)と定義しているので、1パーセクだけ離れた所にある1天文単位(=地球と太陽の平均距離)の長さのものは1秒角に見えます。こんにち生命探索を行っている天体の多くは十数〜数十光年の距離にありますが、仮に10パーセク(=32.6光年)の距離にあるものを0.1秒角の分解能で見たとすると、ちょうど1天文単位の間隔が識別できることになります。これでは天体上の観測データをもとに生物の痕跡を見いだすのは難しいでしょう(数光年の天体の場合でも、状況はたいして変わりません)。太陽系内の惑星ならばもう少し詳しく調べることもできますが、火星や金星に森林のような大規模な植生がないことはわかっており、存在する可能性があるのは微生物に限られているので、望遠鏡の観測ではどうしようもありません。
さらに、光量の問題もあります。すばる望遠鏡は数十億光年彼方の銀河を捉えることが可能ですが、これは銀河が強い光を発しているからできることです。生命探索の対象となるのは恒星の周りを回っている惑星であり、その方向に望遠鏡を向けても、恒星の強烈な光に邪魔されて充分な観測が行えません(恒星が暗い褐色矮星ならば多少は観測できますが)。望遠鏡で生命の痕跡を探すのは、現実問題として難しいようです。
【Q&A目次に戻る】

核分裂生成物(いわゆる死の灰)から出てくる放射線には、α線・β線・γ線があり、それぞれ、高いエネルギーを持ったヘリウム原子核・電子・光子が飛び出してくるものです。このうちα線は数センチの空気層で遮蔽することができる上、α線を出す物質は重い元素で拡散しにくいため、外部被曝に関してはそれほど心配する必要はありません(もちろん体内に入れば危険ですが)。放射線量を測定する場合は、健康への影響の大きいβ線・γ線に関して測定するのがふつうです。放射線測定器にはいくつか種類があり、γ線だけを測定するものや、β線とγ線を区別せずに測定するものがあります。よく知られている測定器にガイガーカウンター(ガイガー−ミュラー計数管)がありますが、これは、飛び込んできた高エネルギー粒子が内部の不活性ガスを電離したときに生じる電気パルスをカウントする装置で、放射線の種類やエネルギーによらず粒子の個数だけを数えます。また、シンチレーション検出器は、放射線を吸収した蛍光物質が発する蛍光を測定しており、使用する蛍光物質に応じてさまざまな種類があります。どの測定器にも一種の“癖”があり、感度の良い範囲が限られていたり、放射線の種類によって感度が変わったりするので、きちんとした較正が必要です(例えば、ガイガーカウンターはβ線とγ線で感度が異なるので、両者をまとめて測定したときと、アルミ箔などでβ線を遮蔽してγ線だけを測定したときの数値を比較して、較正しなければなりません)。自治体が発表する数値は、ちゃんと較正されているはずです(多分…)。
放射線が健康に与える影響は、放射線の種類や粒子が持つエネルギーによって異なっており、身体が吸収するエネルギー量(吸収線量)に放射線ごとに定められた換算係数を乗じることで、各種の放射線の影響を全て含んだ実効的な線量が求められます(健康への影響を正確に評価するには、さらに組織や臓器ごとの感受性を加味しなければなりませんが、通常はそこまで調べません)。この線量が、シーベルト単位で発表されている放射線量です。正確な放射線量を得るには、スペクトロメータを使って粒子のエネルギーを測定しなければなりませんが、簡易測定では無理なので、エネルギー(放射性物質の種類によって粒子の持つエネルギーは定まっている)を適当な値に仮定して線量を推定しています。
各地で測定されている放射線量を見ると、避難勧告地域以外では、外部被曝によって一般住民がガンになるほどの放射能はありません。測定されていない場所に放射能の強いホットスポットがあることも考えられますが、線量の分布から推測すると、住民にガンを生じさせるほどの放射性物質がどこかに集積していることはない思います。福島原発から放出された放射性物質の大部分は、地表に薄く降り積もっているだけであり、今後は雨によって表土が流されていくので、放射線量は徐々に低下していくはずです。
内部被曝に関しては、微量元素が体内のどの部位にどれほどの期間にわたって停留するか充分にわかっていないこともあって、外部被曝ほど確実なことは言えませんが、発表されている農産物などの放射線量を見る限り、取り立てて心配する必要はないでしょう。ただし、いま原子炉内部にたまっている汚染水が大量に海に流れ込んで海棲生物に取り込まれることがないかは、最後まで注視するべきです。
【Q&A目次に戻る】

福島第1原発事故とTMI(スリーマイル島)事故の大きな違いは、前者では冷却系に大きなダメージが生じて水を循環させられなくなったのに対して、後者では冷却系自体は稼働できる状態にあったという点です。TMI事故でも、冷温停止に至るまでの間に小さなトラブルが次々と起こりましたが、放射性物質の大量漏出という最悪の事態は避けられました。
TMI事故における冷却水の喪失は、加圧器内部の圧力逃がし弁が故障で閉じなくなって水が漏れたために起きたものです。このとき、弁が開きっぱなしになったことを示す表示がなかった上に、水位計が逃がし弁と連動した故障によって誤作動し、実際には圧力容器内の水が失われているにもかかわらず満水の表示をしたせいで、自動的に起動した高圧注水系をオペレータが手動で止めてしまいました。この結果、冷却水が補給されずに水位が低下して核燃料が露出、部分的な炉心溶融が起きたわけです。しかし、この過程は、福島第1原発ほど深刻な損傷をもたらしませんでした。水位計が満水状態を示しているにもかかわらず、温度が高く圧力が低いことを不審に感じたオペレータが、高圧注水系を断続的に起動して少しずつ水を注入したからです。水位が上がったり下がったりする間に炉心溶融が部分的にゆっくりと進行したため、一気に崩れ落ちた核燃料が圧力容器を破壊する事態は避けられました(バブコック&ウィルコックス社製圧力容器が充分に頑丈だったことも幸いしました)。その後、炉心損傷に伴って発生した水素がパイプ内部にたまって冷却水の循環を妨げるというトラブルは発生しましたが、途中の弁を開いてガスを抜くなどの対策を講じて乗り切りました(もっとも、このとき弁から大量の冷却水が漏れた上に、建屋内部に抜け出た水素が小規模な爆発を起こしており、事態を悪化させたという見方もあります)。冷却水の供給・循環をを行うポンプやパイプが壊れなかったこと、ガス抜きなどの対策をきちんと実施したことが、炉心溶融を起こしながら放射性物質の大量漏出を回避してレベル5に留まった要因でしょう。
福島第1原発では、冷却水の供給・循環システムが機能しなくなったので、TMI事故とは比べものにならないほど深刻な事態となりました。まず、地震で送電線の鉄塔が倒壊して外部電源が失われ、さらに、続く津波によって全ての取水ポンプと1台を除くディーゼル発電機(および電気系統の一部)が壊れてしまい、水と電気がなくなりました(緊急用の冷却水槽の水も短時間で失われています)。この結果、稼働していた1台のディーゼル発電機を使って冷却できた5号機・6号機は冷温停止できましたが、残りの4基は冷却水を循環させる方法が完全に失われ、手の打ちようがなくなりました。その後の水素爆発を招いたのは、水素ガスを抜くのが遅れたせいだという見方もあります(先日放送されたNHKスペシャル「シリーズ原発危機 ・第1回 事故はなぜ深刻化したのか」はこの立場です)。確かに、ガス抜きの遅れによって事故の規模が拡大しましたが、冷却系が機能しなくなった以上は大量の水素ガスの発生は避けられず、爆発を防ぐのは難しかったと思います(チェルノブイリ事故の先例があるにもかかわらず、なぜ東京電力の技術者が水素爆発を予期していなかったのか、よくわかりません)。地震・津波・炉心溶融・水素爆発で冷却系はボロボロになり、水をパイプに流しても途中で漏れだしてしまうといったありさまで、核燃料の冷却がほとんどできなくなりました。
福島第1原発の教訓は、どのような事態になっても、少なくとも1つの冷却系が生き残るようにしなければならないということです。稼働していた1台のディーゼル発電機が5号機・6号機の破局を回避しましたが、他の発電機が水冷式で海岸縁に設置されていたのに対して、この発電機だけが空冷式で内陸部にあったために難を逃れられたとのことです。今回の東日本大震災で被災した他の3つの原発のうち、女川原発(宮城)と東海第2原発(茨城)では、防波堤が津波をくい止めました。福島第1原発に近い福島第2原発は津波の直撃を受けましたが、機密性の高い原子炉建屋内に設置されていたディーゼル発電機が冠水を免れ、さらに、取水ポンプの一部が壊れなかったおかげで、冷却を行うことができました。冷却系が1系統でも機能していれば、たとえ核燃料の破損が生じてもレベル5程度で済んだと推測されます。
【Q&A目次に戻る】

ウランの原子核は核分裂すると正電荷を帯びた2つの分裂片となって飛び散るのですから、この分裂片の運動エネルギーをうまく利用すれば、発電ができそうにも思えます。例えば、分裂片が運動する領域に強い磁場を加えれば、電磁誘導の法則に従って起電力が生じるので、直接発電が可能になると期待されるかもしれません。しかし、この方法(MHD発電の一種)は、低密度の高温プラズマになら使えるものの、核分裂の場合にはうまくいきません(高温プラズマでも、実用化には技術的な課題が数多く残されています)。核分裂のエネルギーを持続的に取り出すためには、分裂の際に飛び出す中性子が別の原子核を分裂させるという連鎖反応を利用する必要があります。ところが、連鎖反応が起きるためには核燃料の濃度が臨界値以上に濃縮されていなければならず、荷電粒子が自由に飛び回る状態にはならないからです。薄いシート状にした核分裂物質を燃料とし、宇宙線などによって散発的に引き起こされる自然核分裂のエネルギーを取り出す方法としてならば、利用できるかもしれません。
核分裂ではなく、核崩壊の放射線を利用する方法ならば、電気に直接変換することは可能です。こんにち利用されている原子力電池は、プルトニウムなどのα崩壊によって得られた熱を熱電変換素子によって電気に変換するものですが、トリチウムのようにβ崩壊する物質を利用すれば、電子の流れであるβ線を半導体に照射することで、直接電力を作り出すことができるはずです。ただし、いずれの場合も、せいぜい数十ワット程度の電気出力しかなく、しかも危険な放射性物質を含んでいるので、無人探索機に搭載される長寿命の電池ぐらいしか使い道がないでしょう。
【追記】日経サイエンス(2011年7月号p.48-)に掲載された「今だから考えるエネルギー技術7」を読んでいたところ、連鎖反応によらず核融合で生じた中性子線を利用して核分裂を起こさせる原子炉のアイデアが紹介されていました。これは、核分裂の効率を上げるための技術として開発中のものですが、中性子線をウラン燃料のシートに照射すれば、飛び出してくる荷電粒子を使った直接発電ができるかもしれません。技術的にはきわめて難しいと思いますが。
【Q&A目次に戻る】

放射線に関しては、知識が充分に行き渡っていないせいで、さまざまな誤解が生まれているようです。ここでは、いくつか基本的な点を押さえておきましょう。
まず、放射線とは、高いエネルギーを持った粒子(電子・光子など)の流れであり、言わば目に見えない散弾のようなものです。一方、放射能とは放射線を放射する能力のことであり、放射能を持つ物質が放射性物質です。細胞に当たった高エネルギー粒子は、エネルギーを与えることによって染色体を傷つけるため、その結果としてガンが発生する確率が高くなります。ただし、1つの粒子がガンを引き起こす確率はきわめて小さく、数多くの粒子を浴びたときに初めて発ガンのリスクが問題となります。これが放射線の主たる危険性です(きわめて多量の放射線を浴びると、細胞の増殖能力が失われて急性の放射線障害を発症することもあります)。エネルギーを失った粒子は、止まった弾丸と同じで危険性はありません。
放射線によるガンの発生率は、数多くの粒子が人体に与えたエネルギーの総量で決まります。与えられたエネルギーの大きさ(体重1kg当たり)は線量(被曝線量)と呼ばれ、シーベルトという単位で表されます(厳密に言うと、放射線の種類によって人体への影響が異なるために、放射線ごとに荷重係数を乗じて換算しています)。ガン発生率の増加がはっきりするのは年間100ミリシーベルト(mSv)程度からで、100〜200mSvの線量を浴びると、ガンになる確率が浴びていないときの1.08倍になるとされます。これは、塩分の過剰摂取による発ガンのリスクより小さく、野菜不足と同程度です。通常でも、宇宙線や食物に含まれる放射性物質から年間で2.4mSv程度の線量を浴びていますが、こうした微量の放射線が健康にどのような影響を与えるかは、よくわかっていません(免疫系を活性化するので健康に良いという説すらあります)。私は、子供や妊婦は年間数mSv、大人でも10mSv程度から警戒した方が無難だと思います。また、放射性物質が体内に入り込んで細胞分裂の活発な組織(甲状腺や骨髄など)の近くに蓄積されると、危険性が格段に高まります。
福島第1原発周辺には、飛散した放射性物質が降り積もっており、放射線を出し続けています。原発から半径20km程度の地域(屋外)に1年間居住すると、周囲からの放射線をトータルで10〜20mSv程度浴びることになり、ガンになる確率がわずかに(はっきりしないが0.2%以下か?)増える可能性があります。半径20km以内の放射線量はさらに高く、また、ホットスポットと呼ばれる放射線の特に強い領域があるため、この範囲からの退避はやむを得ないでしょう。ただし、これはあくまで、この地域に何ヶ月も居住して四方八方から放射線を浴び続けた場合の危険性です。放射性物質が物質表面に付着することはありますが、そこから出る放射線を浴びたとしてもごく微量なので、福島出身の人(あるいは福島から来る電車)を警戒する必要は全くありません(原発の近くに長く放置されていた自動車が来た場合はちょっと心配ですが)。放射線測定器の感度がきわめて高いために、健康には全く影響しない程度の放射線でも派手に検出音が鳴ることがありますが、測定された数値を見てから心配するかどうか決めるべきです。
【Q&A目次に戻る】

量子論的なゆらぎの効果を無視する近似では、物理系の振舞いは基礎方程式(ニュートン力学の運動方程式や電磁気学のマクスウェル方程式)に厳密に従っています。しかし、だからと言って、長時間が経過した後にどうなっているか予測できる訳ではありません。同じ方程式に従う2つの系でも、初期条件が少しでも異なると、その後の時間発展がだんだんと違ったものになり、最終的には全く異なった状態に達することが、コンピュータ・シミュレーションによって示されています。こうしたカオス的な振舞いは、きわめて多数の自由度を持つ物理系が秩序構造を形成する場合には、ごくふつうに見られるものです。
宇宙の進化においては、量子論的な現象が重要な役割を果たしています。恒星のエネルギー源となる核融合や、惑星の内部構造にかかわる結晶化などの相転移は、いずれも量子論的な現象であり、不確定性を伴っています。したがって、たとえ同一のビッグバンから始まった2つの宇宙が存在したとしても、両者の間には量子論的な不確定性に起因する差異が生じ、この差異が巨視的な過程におけるカオス的な振舞いによって拡大していくはずです。宇宙進化の途中でも同様です。仮に同じ条件で超新星爆発が起きたとしても、核反応の違いから物質流のゆらぎ方が異なったものとなり、その結果として、一方の宇宙で太陽系が存在する地点に、他方の宇宙でガス雲しかないということもあるでしょう。
ただし、どこにどんな天体集団が形成されるかはカオス的ですが、天体集団の一般的な振舞いは物理法則に支配されています。G型やF型のようなタイプの恒星がどれくらいの割合で誕生するか、どのような銀河の中心部にブラックホールが形成されるか−−そうした性質はビッグバンの時点で決まっているはずです。
【Q&A目次に戻る】

質問にある確率は、「1ヶ月間の地震の発生確率が50%とされた(互いに無関係の)地域が100ヶ所あったとすると、1ヶ月の間に地震が起きる地域は50ヶ所になる」という意味のはずですが、実際には、それほど厳密な意味づけはできません。確率はもともと統計的な事象に付与されるもので、同じ現象が繰り返し起きることを前提としていますが、地震の場合、それぞれのケースで地盤の壊れ方などに特徴があるため、統計の手法だけでは扱いきれず、いろいろな経験則を織り込まなければならないからです。
ある震度以上の地震の発生確率を計算するには、特定の断層で前回の地震からt年後にマグニチュードMの地震が発生する確率(正確に言うと確率密度)P(t;M)と、断層からの距離の関数として与えられる地震動の減衰曲線が必要になります(実際には、震源となり得るあらゆるあらゆる断層からの寄与を加算して発生確率を求めますが、ここでは、話を簡単にするために、特定の断層だけを問題とします)。このうち、地震動の減衰曲線に関しては、かなり信頼できる経験則がありますが、P(t;M)には多くの不確定性が混入してきます。
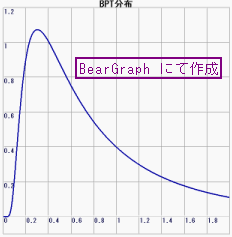
P(t;M)の推定には、2つの経験則を用います。まず、地震が起きてt年経過したときの地震発生の確率密度はBPT(Brownian Passage Time)分布に従うと仮定します。BPT分布とは右図のような曲線で表され、平均値(地震の場合は平均的な発生間隔)と標準偏差という2つのパラメータがあります(右図は平均値と標準偏差を1としたもの)。これらのパラメータは、過去のデータに基づいて決定されます。さらに、地震の発生確率はマグニチュードMに対して指数関数的に減少するという経験則があります。そこで、 exp(-aM) という関数形を仮定すれば、過去のデータからパラメータaも求められるはずです。
右図のBPT分布は、tがある値のときにピークを示し、それ以降は減少関数になっていますが、これは、地震が起きてt年後という条件での確率密度を表しているからであって、時間が経つと地震が起きにくくなる訳ではありません。実用的な発生確率は、前回の地震からt年間地震が起きなかったという条件の下で、それから一定期間のうちに地震が発生する確率なので、tとともに増加します。
このように、経験則に基づく関数形は与えられているのですが、大地震の場合、パラメータを求めるためのデータはごくわずかしかなく、信用できるフィットができません。また、経験則がどこまで正当かも問題となります。大地震の発生確率は、天気予報における降水確率よりもはるかに大ざっぱだと思った方が良いでしょう。例えば、今後30年間に東海地震が発生する確率として、地震調査委は、2004年に84%、2011年に時間経過を加味して87%と発表していますが、端数の修正などほとんど意味がないでしょう(1944年の東南海地震でどれだけひずみが解放されたかはっきりしていないため、計算の根拠となるモデルに関してもいろいろな議論があります)。
なお、1ヶ月間の発生確率が50%の場合、2ヶ月間での発生確率は、最初の1ヶ月で発生する確率50%と、最初の1ヶ月には発生せず次の1ヶ月で発生する確率50%×50%=25%の和なので、75%となります(地震の発生確率は時間とともに変動するために本当はこれほど簡単に計算できませんが、大地震の場合は時間変化が小さいので確率一定として求めました)。また、ひとたび地震が発生すると確率はリセットされるので、複数の地震が起きる確率は全く異なったものになります。
【Q&A目次に戻る】

質問にある手法は「地震・噴火予知方法」として特許が出願されていますが、それによると、GPSを用いて地表上の任意の3点の位置変化を測定し、面積変動率が一定値を超える、あるいは正負が反転することに基づいて地震・噴火の予知を行う手法だとのことです(ここで言う面積とは、測定する3点を頂点とする三角形を地球の重心を原点とする座標系の3つの座標面に投影した面積を指しています)。これまで、特定の基準点ごとに水平・垂直方向の精密測量を行ってデータを集めていたため、観測日時が異なり連続的な変動を正確に求められなかったのに対して、GPSによる継続的な観測を行えば多数のデータを統一的に扱うことが可能になり、正確な地震(および噴火)予知を行えると主張されています。
GPSによって連続的な変動のデータを集めることの重要性に関しては、おそらく異論はないでしょう。しかし、そのデータが地震予知と直ちに結びつくかというと、いろいろと疑問が湧きます。地震の発生には、地盤の構成や断層の有無、相互の固着の強さなどさまざまなファクターが絡んでおり、位置変化のデータだけから地震を予知するのは一般に難しいからです。地盤の状態によっては、スロースリップと呼ばれる大きな揺れを伴わない滑りによって歪みが解放されることもあります。位置の変動率が一定値を超えたからといってすぐに地震が起きるわけではなく、地域ごとに特徴的な振舞いが見られるので、地震予知を行うためには、その地域における過去のデータとの照合が必要になります。しかし、GPSの過去データは限られています。1994年から国土地理院がGPSの観測網を全国に展開しているものの、地震予知を可能にするような地盤の特徴はつかみきれていません(巨大地震予知に必要な海溝付近のデータを集める海底GPSの設置数は少数に留まっています)。こうした情報不足を埋めようと、これまで多くの地震学者が独自の予知方法を提案し、当たった事例を強調することでその方法の正当性を喧伝してきました。しかし、現実には、どの方法を使っても、当たったり当たらなかったりというところです。例えば、2002年に東海地震が起きるという何人かの地震学者の予想は、見事にはずれました。
今後数十年にわたってGPSによる観測を継続すれば、短い間隔で頻繁に地震が起きる地域での予知はかなり正確になると思いますし、その際に面積変動率を使う手法が役に立つかもしれません。それでも、百年に1回という大地震を予知することには、依然として困難が伴うでしょう。
【Q&A目次に戻る】

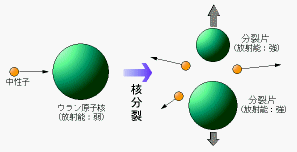
原子力発電所の事故で最も恐ろしいのは、強い放射能を持つ核分裂生成物(いわゆる“死の灰”)が環境中に放出されることですが、やっかいなことに核分裂生成物にはさまざまな核種があるため、いろいろなルートから放射能汚染を広めてしまいます。今回の事故では、圧力容器や原子炉格納容器に大きな損傷はなかったようですが、冷却水に混じった核分裂生成物が水と一緒にかなり漏出したと思われます。
核分裂とは、中性子がぶつかった衝撃でウランの原子核が2つの大きな塊に破裂することです。このとき分裂片となる原子核は、通常の原子核に比べると中性子を過剰に含んでいてバランスが悪いために不安定となり、内部から高エネルギー粒子を放射して核変換を起こします。この「高エネルギー粒子を
放射する
能力」が「放射能」です。飛び出した高エネルギー粒子が生物の体に当たると、細胞内部の染色体を傷つけてガンの元を作ることがあるため、核分裂生成物は人間の住む環境から隔離しておかなければなりません(核分裂生成物以外に冷却水や容器壁も、炉心から漏れ出る高エネルギー粒子の衝突によって放射能を帯びています)。
核分裂生成物は、通常は核燃料棒内部に蓄積されていき、最終的には使用済み核燃料として搬出・処分されます。核燃料棒は水に浸かった状態で圧力容器の中に設置され、圧力容器を含む装置類は原子炉格納容器の中に納められています。また、核燃料棒を冷やす水は放射能を帯びるため、外部に漏れないように閉じた配管の内部を循環させています。このように放射性物質を外界から遮断して安全性を保つというのが、原子力発電所の設計思想です。
しかし、現実には放射性物質が外部に漏れる事故は何度か起きています。
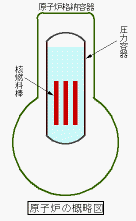
これまでに起きた最大の事故は、1986年にソ連(現在のウクライナ)で起きたチェルノブイリ原発事故です。ソ連製の黒鉛炉には原子炉格納容器がなく、圧力容器の代わりに強度の低い圧力管が使われていたため、オペレータの不適切な操作と制御棒の欠陥が重なって原子炉が暴走・過熱した際に、炉心が溶融して水蒸気爆発(引き続いて水素爆発)を起こし、内部の核分裂生成物が飛散する結果となりました。事故後30年間での致死性ガン発症数は、WHOの推定で4000〜9000人とされています。ただし、チェルノブイリ原発事故は、ソ連製原子炉の特性が引き起こしたもので、西側の原子炉で同じタイプの暴走事故は起きないと考えられます。
西側の原発事故としては、1979年に米ペンシルベニア州で起きたスリーマイル島原発事故が知られています。この事故は、圧力弁の故障とオペレータの判断ミスが重なって冷却水が失われたために、核燃料棒が過熱・溶融したものです。核燃料棒が崩れ落ちたものの圧力容器の底は抜けず、冷却水の循環システムも再稼働可能だったため、大量の放射能漏れは避けられましたが、微量の放射性物質が外部に放出されました。
スリーマイル島原発で放射性物質が漏れた経緯には、核分裂生成物の特徴が関与しています。金属であるウランと異なり、原子核が不均等に分裂してできる核分裂生成物には、放射性のヨウ素、セシウム、ストロンチウムをはじめ、多種多様な元素が混じっており、中には水溶性のものや揮発性のものも含まれています。核燃料棒が溶融すると、これらの物質が冷却水の中に漏れ出します。冷却水の循環システムが完全に閉じられていれば、これらが環境中に漏れることはなかったのですが、濾過装置を通過する際に揮発性の放射性物質が気体となって外部に放出されてしまいました。ただし、その量はわずかで、この事故が原因でガンになった患者は、いたとしてもごく少数(おそらくはいない)と推定されています。
今回の福島原発事故は、どれか1つでも動けば事故は避けられるはずの複数の冷却水供給システムが、津波によって全て使えなくなったために起きました。核燃料棒が過熱・溶融したところまではスリーマイル島原発と同じですが、冷却を再開させることができず、1号機と3号機が次々と水素爆発を起こして原子炉建屋が大破するという大事故になりました。圧力容器に大きな破損はなかったものの、冷却水を循環させられず外部から注水したため、核分裂生成物を含んだ汚染水が炉心から流れ出し、一部は海や地面に放出される結果になりました。これらの放射性物質がどのような健康被害を引き起こすかは、まだ充分には予測できません(農作物の汚染は過度に心配するレベルではなく、ガンの発症は原発作業員が中心になると思われます)。汚染水や破損した核燃料棒を搬出する方法も検討中であり、この地域一帯は放射能汚染ゾーンとして長期にわたり立入禁止になるでしょう。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
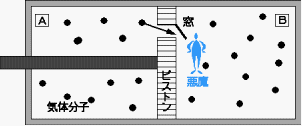 ところが、19世紀の物理学者マクスウェルは、次のような操作を行う仮想的な悪魔がいれば、高温・低温の領域がなくても熱エネルギーを仕事に変換できることを示しました。ピストンで隔てられたシリンダーの2つの領域AとBに等温・等圧の気体が封入されており、ピストンには悪魔が開閉操作をしている窓があるとします。悪魔は、気体分子が領域Aから領域Bに向かうときには窓を開けて分子を通過させ、逆向きのときには窓を閉めて通過させないようにしています(窓の開閉には、熱エネルギーよりも遥かに小さなエネルギーしか消費しないと仮定します)。すると、しだいに領域Bの圧力が領域Aよりも高くなるので、圧力差を利用してピストンを動かし、仕事の形でエネルギーを取り出すことができます。この過程は、高温・低温の領域がないにもかかわらず熱エネルギーを利用したことになるので、熱力学第2法則が破れたように見えます。熱力学第2法則を破る仮想的な悪魔は、「マクスウェルの悪魔」と呼ばれています。
ところが、19世紀の物理学者マクスウェルは、次のような操作を行う仮想的な悪魔がいれば、高温・低温の領域がなくても熱エネルギーを仕事に変換できることを示しました。ピストンで隔てられたシリンダーの2つの領域AとBに等温・等圧の気体が封入されており、ピストンには悪魔が開閉操作をしている窓があるとします。悪魔は、気体分子が領域Aから領域Bに向かうときには窓を開けて分子を通過させ、逆向きのときには窓を閉めて通過させないようにしています(窓の開閉には、熱エネルギーよりも遥かに小さなエネルギーしか消費しないと仮定します)。すると、しだいに領域Bの圧力が領域Aよりも高くなるので、圧力差を利用してピストンを動かし、仕事の形でエネルギーを取り出すことができます。この過程は、高温・低温の領域がないにもかかわらず熱エネルギーを利用したことになるので、熱力学第2法則が破れたように見えます。熱力学第2法則を破る仮想的な悪魔は、「マクスウェルの悪魔」と呼ばれています。
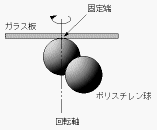 東大・中央大のグループが行ったのは、マクスウェルの悪魔を具現化する実験です。
東大・中央大のグループが行ったのは、マクスウェルの悪魔を具現化する実験です。
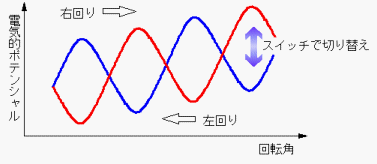
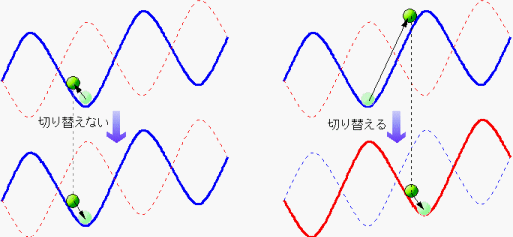
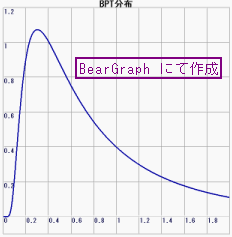 P(t;M)の推定には、2つの経験則を用います。まず、地震が起きてt年経過したときの地震発生の確率密度はBPT(Brownian Passage Time)分布に従うと仮定します。BPT分布とは右図のような曲線で表され、平均値(地震の場合は平均的な発生間隔)と標準偏差という2つのパラメータがあります(右図は平均値と標準偏差を1としたもの)。これらのパラメータは、過去のデータに基づいて決定されます。さらに、地震の発生確率はマグニチュードMに対して指数関数的に減少するという経験則があります。そこで、 exp(-aM) という関数形を仮定すれば、過去のデータからパラメータaも求められるはずです。
P(t;M)の推定には、2つの経験則を用います。まず、地震が起きてt年経過したときの地震発生の確率密度はBPT(Brownian Passage Time)分布に従うと仮定します。BPT分布とは右図のような曲線で表され、平均値(地震の場合は平均的な発生間隔)と標準偏差という2つのパラメータがあります(右図は平均値と標準偏差を1としたもの)。これらのパラメータは、過去のデータに基づいて決定されます。さらに、地震の発生確率はマグニチュードMに対して指数関数的に減少するという経験則があります。そこで、 exp(-aM) という関数形を仮定すれば、過去のデータからパラメータaも求められるはずです。
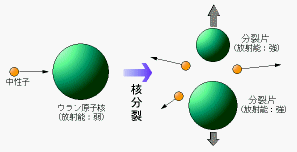 原子力発電所の事故で最も恐ろしいのは、強い放射能を持つ核分裂生成物(いわゆる“死の灰”)が環境中に放出されることですが、やっかいなことに核分裂生成物にはさまざまな核種があるため、いろいろなルートから放射能汚染を広めてしまいます。今回の事故では、圧力容器や原子炉格納容器に大きな損傷はなかったようですが、冷却水に混じった核分裂生成物が水と一緒にかなり漏出したと思われます。
原子力発電所の事故で最も恐ろしいのは、強い放射能を持つ核分裂生成物(いわゆる“死の灰”)が環境中に放出されることですが、やっかいなことに核分裂生成物にはさまざまな核種があるため、いろいろなルートから放射能汚染を広めてしまいます。今回の事故では、圧力容器や原子炉格納容器に大きな損傷はなかったようですが、冷却水に混じった核分裂生成物が水と一緒にかなり漏出したと思われます。
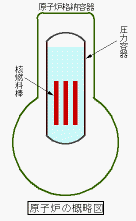 これまでに起きた最大の事故は、1986年にソ連(現在のウクライナ)で起きたチェルノブイリ原発事故です。ソ連製の黒鉛炉には原子炉格納容器がなく、圧力容器の代わりに強度の低い圧力管が使われていたため、オペレータの不適切な操作と制御棒の欠陥が重なって原子炉が暴走・過熱した際に、炉心が溶融して水蒸気爆発(引き続いて水素爆発)を起こし、内部の核分裂生成物が飛散する結果となりました。事故後30年間での致死性ガン発症数は、WHOの推定で4000〜9000人とされています。ただし、チェルノブイリ原発事故は、ソ連製原子炉の特性が引き起こしたもので、西側の原子炉で同じタイプの暴走事故は起きないと考えられます。
これまでに起きた最大の事故は、1986年にソ連(現在のウクライナ)で起きたチェルノブイリ原発事故です。ソ連製の黒鉛炉には原子炉格納容器がなく、圧力容器の代わりに強度の低い圧力管が使われていたため、オペレータの不適切な操作と制御棒の欠陥が重なって原子炉が暴走・過熱した際に、炉心が溶融して水蒸気爆発(引き続いて水素爆発)を起こし、内部の核分裂生成物が飛散する結果となりました。事故後30年間での致死性ガン発症数は、WHOの推定で4000〜9000人とされています。ただし、チェルノブイリ原発事故は、ソ連製原子炉の特性が引き起こしたもので、西側の原子炉で同じタイプの暴走事故は起きないと考えられます。