
1966年に公開されたSF映画「ミクロの決死圏」では、縮小された人間が血管内部を航行する潜水艇に乗って脳の疾患を治療しに行く過程が描かれていました。それから半世紀近くを経た現在、(人間のミニチュア化はともかく)血管を進む医療ロボットが開発される見通しはというと、いまだ空想の段階でしかありません。半導体の分野では、ナノメートルのオーダーで加工を行うナノエレクトロニクスが盛んになっているにもかかわらず、ロボティクスになると、ミクロンサイズの機械ですら実用化していません。これは、ロボティクスに必要な技術がナノエレクトロニクスとは異質だからです。ナノエレクトロニクスで用いられるのが薄膜上にパターンを転写する2次元的な加工技術であり、せいぜい薄膜を積み重ねて3次元構造を作り出すことしかできません。自己組織化の手法を用いてナノワイヤやナノドットを薄膜上に形成できるとはいっても、いずれもきわめて単純な構造でしかありません。数十分の1ミリ程度の歯車やポンプを作成したという報告はありますが、薄膜加工の技術を使って面上に形成するだけであり、単体で動作する医療ロボットの実現にはほど遠い状況です。
日経サイエンス2010年11月号に「のんで効く医療ロボット」という記事が掲載されています。それによると、現在開発中の医療ロボットは、飲み込むことが可能な大きさ2cm
3程度のカプセルで、分光カメラによって患部を撮像したり、医薬品投与や生検試料採取を行ったりできるとのことです。さらに、飲み込んだ十数個のカプセルを消化管内部で合体させ、外部からの無線でアクチュエータによる手術を遂行させる方法も提案されています。これが、現時点での技術の限界でしょう。
アクチュエータを備えた医療ロボットは消化管内部に進入させるのが精一杯であり、血管に入り込ませるには、リソソームに似た膜構造を持つ微粒子を利用することになると思います。例えば、血栓ができている部位で何らかの化学反応をもとに血栓溶解剤を放出させるといった方法が考えられます。
【Q&A目次に戻る】

1980年代に人工知能の研究がブームになったときには Lisp が大いにもてはやされ、私も少しかじってみましたが、最近はあまり人気がないようです。
Lisp とは、1958年に開発されたプログラミング言語で、その数年前に作られた FORTRAN とともに最古の高級言語です。FORTRAN は数値計算を簡単に行える言語であり、DO文を使った繰り返し演算など非常にわかりやすい構文になっているため、3日もあれば使えるようになります(学生の頃、翌週までに FORTRAN を勉強して数値積分を行い、結果を発表しろという課題を与えられたことがあります)。これに対して、Lisp は、
LISt
Processor という名称からもわかるとおり、リスト形式で表されたデータの処理に特化された言語だと言えます(開発の動機は別のところにあったようですが、人工知能用の言語として応用されたのは、この点が注目されたからでしょう)。
人工知能の研究に当たって問題となったのが、どうすれば人間が行うような推論をコンピュータに遂行させられるかという点です。人間はパターン認識などに基づく曖昧な推論をごくふつうに行っており、推論の結果だけ見ても、具体的にどのようなデータ処理を行ったのか判然としません。人工知能に何らかの推論をさせるためには、こうした曖昧さをすべて払拭し、単純なデータ処理に徹することが必要です。そこで、データ間の関係を、パターンの類似性といった曖昧な性質ではなく、ある集合に属すかどうかという正否が確定できる性質に還元してしまうという方法が採用されました。例えば、病気の症状として「高熱を発する」「発疹を生じる」「下痢がある」といった集合を定義すれば、これらの集合に属するかどうかを具体的な疾病ごとに確定できます。こうした知識ベースに基づいて、「熱は高く発疹があるが下痢はない」といった症状から病気の診断を行うプログラムが開発されるわけです(もちろん、実際の病気診断プログラムでは、複雑な組み合わせに対する何通りもの推論規則が使われますが)。
Lisp は、何重にも重ねられた括弧を使って表現されたリストを処理する言語です。Lisp の基本的な命令には、リストを作る関数 cons 、リストの先頭の要素を取り出す car、2番目以降の要素を返す cdr、リストの長さを返す length などがあり、これらを使ってリストを処理していくことができます。このため、特定のデータがリスト(例えば、ある症状を持つ疾病の集合)に含まれるかどうかを調べたり、リストにデータを付け加えたりするという推論規則は、ほとんどそのままの形で Lisp のプログラムに翻案できます。このことは、推論規則を考案する研究者が同時にプログラミングも行う場合、かなり便利な特徴だと言えます。
もっとも、Lisp を使って人工知能用の推論プログラムが書くことは、最近はあまりはやらないようです。容易に想像がつくように、さまざまな規則を組み合わせて人工知能に推論させるよりも、コンピュータはあくまでデータの呼び出しなどのサポートとして用い、重要な推論は人間が行うようにした方が、状況に柔軟に対応できる信頼性の高い結果が得られるからです。病気の診断に関してならば、何をやっているかよくわからない人工知能の推論に任せるよりも、同じ症状を持つ疾病をリストアップしたり、処方薬の副作用情報を呼び出したりするリレーショナルデータベースを援用しながら、最終的な診断は人間の医師が行う方が確実で安心できるはずです。
【Q&A目次に戻る】

粒子の交換によって力が伝えられるという素粒子論の命題は、あくまで話をわかりやすくするための便宜的表現であって、実際には、場が力を伝えていると言った方が正確です。
量子力学を勉強した人は、バネにおもりを取り付けた調和振動子のエネルギーがnhν(n:整数、h:プランク定数、ν:基準振動数)になることを知っていると思います。こうしたエネルギーの離散化は、量子力学的なシステムに見られる波動性の現れであり、持続的な共鳴パターンの形成として理解することができます。管楽器の内部に形成される定常波に典型的に見られるように、共鳴パターン以外の波は互いに干渉しあって短期間のうちに消滅してしまいますが、それと同じことが量子力学的なシステムでも起き、調和振動子ではhνの整数倍のエネルギー状態だけが持続的な共鳴パターンになるわけです。場を量子化する場合でも、同じように考えてみてください。例えば、電磁場を量子化した場合は、持続的な共鳴パターンとして調和振動子と同じくnhνのエネルギーを持つ状態が形成されます。ただし、電磁場が拡がりを持っているために、このときのエネルギー量子hνは調和振動子のときとは異なって一ヶ所に局在せず、ある運動量を持ってどこかに伝播していきます。これが光子と呼ばれる素粒子であり、あたかも粒子のように扱っていますが、実際には量子化された場が示す共鳴パターンと考えるべきものです。他の素粒子も基本的には同じです。
2つの素粒子の間に作用する力を計算する場合、場の量子揺らぎを求めなければなりませんが、こうした計算は実際問題として不可能です。そこで、量子揺らぎは充分に小さいものと仮定し、相互作用していないときの基本的な共鳴パターンを使って摂動論的に計算するのが一般的です。相互作用していないときの基本的な共鳴パターンは、自由に動き回る1個の粒子のように振舞います。したがって、力を計算するときには、あたかも1個の粒子が一方から他方へと飛んでいくかのような過程を調べることになるわけです。この状況を「粒子の交換によって力が伝えられる」と称しているのであり、実際に力を伝える粒子が飛び回っているのではありません。
【Q&A目次に戻る】

この質問を受けて、指摘された論文を初めて読んでみました(1998年に発表されて以降、ネット上で回覧されているようです)。この論文は、近年の気候変動を含むさまざまな異常現象が太陽圏のエネルギー異常に起因すると主張する内容で、私の知る限り、必ずしも学界で支持されているわけではありません。
著者によれば、1960年代に太陽系が高エネルギー荷電粒子を多く含む不均質領域に突入した結果として、太陽圏(heliosphere) 前面の衝撃波が強まってプラズマのエネルギーが増加しつつあるとのことです。星間物質の不均質領域が存在した場合、確かに、プラズマの周辺部でこうしたエネルギーの変化が生じることは充分に予想されます。質問にある磁場強度の値は論文中から見つけられませんでした(あまりきちんと読んでいません)が、たとえ5マイクロガウス(0.5ナノテスラ)であっても、太陽系全体が不均一な磁場内部を横切る場合は、太陽圏周辺のエネルギー状態を変える可能性はあります。しかし、こうした磁場の変動は太陽風などの荷電粒子の流れで緩和されるため、太陽圏前面のエネルギー異常が太陽系内部に侵入して惑星大気に影響を及ぼし、地球温暖化のような顕著な変化をもたらすことは考えにくいと思います。
全体的に言って、著者の主張は決して実証されておらず、根拠に欠けるものです。例えば、太陽圏エネルギー異常の結果として著者が上げている現象(土星でのオーロラ発生、天王星磁気圏の急変、海王星の光度変化など)は、著者が主張するほど劇的ではなく、また、太陽圏のエネルギー異常でしか説明できないものでもありません。仮説としてはおもしろいものの、信憑性は今ひとつというところでしょう。
【Q&A目次に戻る】

生命が他でもないこの地球に発生したのは偶然でしょうが、地球に似た惑星で生命が発生する確率は決して低くないと信じられる根拠があるので、銀河系だけでも数千億ある恒星系のどこかで生命が誕生するのは必然だと言えるでしょう。
生命の発生確率が低くないと予想されるのは、この世界の物理法則が自発的な秩序形成を進めるものだからです。ミクロの物理現象を支配する量子論は、粒子がバラバラに運動するニュートン力学などとは異なり、波動的な振舞いに基づく共鳴パターンを生み出し、秩序を持った構造を自然に作り上げていく性質があります。雪の結晶が美しい六方対称性を持っていることが、その代表的な例でしょう。こうした秩序形成によって長い炭素骨格を持つ高分子や脂質二重層による膜が形成され、これらが基本的な素材となって生命が誕生したわけです(もちろん、それまでに数億〜数十億年もの歳月が必要になるでしょうが)。
生命発生に至る有機化合物の分子進化が進行するためには、いくつかの条件が必要です。重要な条件の一つが、液体状態の水が安定して存在することです。液体のメタンが水の代わりに生命をはぐくむ可能性もありますが、水分子の双極子モーメントが有機反応で重要な役割を果たすことを考えれば、やはり宇宙に存在する生命の多くは水中で発生すると予想されます。水が液体でいられる範囲は比較的狭いので、生命が発生できる惑星の大きさや公転軌道に制約がつきます。
水の存在と並ぶ重要な条件が、熱力学的な非平衡状態が長期間にわたって維持されることです。生命体は熱力学的平衡から大きく逸脱した状態にあるため、その生存環境も非平衡でなければなりません。こうした非平衡状態が実現されるのは、熱源からの持続的な熱の流れが見られるような場所であり、候補としては、(1)恒星からの短波長光が届く浅い海(熱は赤外線によって宇宙空間に捨てられる)、(2)海底の熱水噴出口周辺(熱は周囲に拡散していく)の二つがあります。私個人は、海底の熱水噴出口は生命が誕生するほどの長期にわたって維持されるとは考えにくいので、浅い海の方が生命誕生の場としてありそうだと思っています。したがって、生命が発生するのは、数億年以上にわたって安定して短波長光を放出し続けるG型ないしF型の恒星の周りを回り、地表に水が存在できる岩石型惑星−−つまり、地球のような星に限られることになります。
想像するに、生命は次のようにして誕生したのでしょう。まず、地表付近の放電で生成されたり隕石に付着して飛来したりして、アミノ酸などの基本的な物質が海中に蓄えられます。これらが素材となって浅い海での光化学反応を含むさまざまな化学反応を続けていきますが、その過程でRNAのような自己複製能力を持つ高分子が生み出されると、すぐに壊れる他の分子と異なって自分をコピーしながらいつまでも存在し続けるでしょう。こうして自己複製するシステムが次第に複雑化して、生命としての形を整えていったと思われます。
【Q&A目次に戻る】

物理学者が力の統一を目指すのは、美しさの追求だけではなく、統一しなければ説明の付かないと思われる性質があるからです。例えば、電気素量を基準にすると、電子の電荷は-1、uクォークは+2/3、dクォークは-1/3ですが、電荷の大きさがなぜ3:2:1という単純な整数比になっているか、理由が全くわかりません。しかも、水星や月の公転周期と自転周期の比のようにきわめて整数に近いというだけでなく、厳密に整数比でなければ物質世界が成立しないというほどのものです。この理由を説明するためには、電子とクォークを何らかの形で統一的に扱うような理論がなければならないと考えられます。
量子重力理論になると、さらに根本的な問題があります。一般相対論に基づく重力理論は、ニュートン力学やマクスウェル電磁気学と同じく、厳密に成立する基礎方程式があり、重力に関与する物質の運動を含むあらゆる物理現象がこの方程式に従っていることが前提となっています。これに対して、物質に関する量子場理論は、場の方程式は厳密に成り立つのではなく、基本解の周りに方程式からのズレを表す量子ゆらぎが存在するとされます。この量子ゆらぎが素粒子を生み出しているので、われわれが物質と考えているものは、方程式が厳密に成り立たないことで存在を許されていると言っても良いわけです。重力場と量子場(電子やクォークなどのフェルミオンの場と光子やグルーオンなどのボソンの場)は、どちらも宇宙全体を覆い尽くす基本的な場であるにもかかわらず、方程式に厳密に従うかどうか、あるいは、量子ゆらぎが存在するかどうかという点で、物理学的な振舞いが根本的に異なっているのです。にもかかわらず、両者は密接な関係にあります。実際、恒星の内部では、物質が量子論に従って核融合反応を起こしている一方で、重力理論に従って重力場を生み出しており、天上世界と地上世界の法則というように、その適用領域が截然と分かたれるわけではありません。このような食い違いを解消するためには、重力場と量子場を統一するための何らかの理論が必要になるはずであり、その観点から、重力理論を量子化するという試みが真剣に検討されているのです。
なお、光速度の変化が見られなかったというデータですが、これは、数十億光年の遠方にある天体からやってくるガンマ線が、エネルギーによらず同時に観測器(NASAが打ち上げたフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡など)に到達することで確認されたものです(到達時刻に最大で0.859秒の時間差があったとのことですが)。エネルギーによって光速度が異なるというのは、非可換幾何学に基づく量子重力理論や、あるタイプのループ量子重力理論から予想されていました。したがって、光速度に差がないという観測データは、いくつか候補がある量子重力理論の選別を行う上で利用できるものであり、量子重力理論を全滅させることはありません。
【Q&A目次に戻る】

質問にあるのは、次の論文のことだと思います。
Gerrit L. Verschuur. 'High Galactic Latitude Interstellar Neutral Hydrogen Structure and Associated (WMAP) High-Frequency Continuum Emission.' (Astrophysical Journal, 671:447-457, 2007)
まず、この論文で何が問題になっているかを説明します。
ビッグバン理論によれば、宇宙はきわめて高温・高密度の状態から始まったと仮定されています。現在の宇宙では、この高温状態の名残が背景放射という形で残存しており、これを観測することによって、初期宇宙(ビッグバンの約40万年後)の状態がわかるというわけです。一方、ビッグバン理論以外の宇宙論(定常宇宙論、ヴァイツゼッカー模型、ルメートル模型の特定バージョンなど)では、宇宙全体が高温・高密度状態だったのではないため、一様な背景放射が存在しません。したがって、ビッグバンの証拠となるのは、一様な背景放射の存在です。すなわち、街灯や天体とは無関係にあらゆる方向から同じ強さで定常的に放射(主に観測しやすいマイクロ波)が送られてきており、その強度分布が絶対温度で数度〜十数度の黒体放射に一致すれば、ビッグバン理論が確からしいということになるわけです。この条件に合致するマイクロ波背景放射は、1964年にペンジアスとウィルソンによって偶然発見されました。
1960年代には、背景放射がほぼ一様であることが確実になり、ビッグバン理論以外の宇宙論はほとんどが淘汰されました。その後、ビッグバンの詳細(特に、銀河形成を引き起こす密度ゆらぎの存在)を調べるために背景放射のわずかな異方性(場所による背景放射強度の違い)を見つけることが重要なテーマとなり、COBE(宇宙背景放射探査機;1989年打ち上げ)やWMAP(ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機;2001年打ち上げ)などの人工衛星に搭載された観測機器で精密測定が行われました。精密測定といっても、観測されたデータからそのまま異方性がわかるわけではなく、天体や星間ガスなどに起因するノイズを差し引くなどのさまざまなデータ処理を施すことによって、初めて背景放射の異方性がはっきりするのです。
Verschuurの論文は、WMAPにおけるデータ処理に誤りがあり、求められた背景放射の異方性には、銀河内部に存在する中性水素からの放射のデータが混入していると主張するものです。その根拠は、WMAPのデータで一定の背景放射に対して過剰な放射があるとされる領域が、ちょうど中性水素が豊富にある領域と一致していることなどです。
私自身には、長くて専門的なこの論文の当否を判定するだけの能力はありません(有能な科学者がまじめに書いた論文だという印象は受けます)。Verschuurの論文が出たすぐ後に、何人かの科学者が、背景放射と中性水素の過剰領域が一致する場合はあるものの、それは偶然の一致と言える範囲であり、数多く存在する両者の過剰領域の間に明確な相関はないと主張しています。
この議論から3年経っていますが、異方性に関するWMAPチームの結論が訂正されたという話も聞かないので、Verschuurの主張は、結局、学界で受け容れられなかったのでしょう。ただし、彼の主張が正しかったとしても、ビッグバン理論そのものが覆されるわけではなく、あくまで銀河形成の標準的なシナリオに変更が必要になる程度だということは、頭に入れておいてください。WMAPのデータ処理には多くの仮説が組み合わされて使われており、(ダークエネルギーの存在比などの)最終的に示された値を即座に信じない方が良いという意見はしばしば耳にしますが、具体的にこの点が間違っていたと明らかにされたケースは、まだないと思います。
【Q&A目次に戻る】

ビル・ゲイツが出資しているのはテラパワーというベンチャー企業で、ここが進行波炉の開発を目指しています。私は原子炉の専門家ではないので断定的なことは言えませんが、炉の概略を見る限り、実用化には多くの困難が予想されます。
天然ウランには、核分裂の連鎖反応を起こすウラン235が0.7%しか含まれておらず、99.3%は核分裂しにくいウラン238です。このため、通常の原子炉(軽水炉)で使用する核燃料にするためには、ウラン235の含有率を数%まで濃縮する必要があり、その過程で生じる劣化ウラン(ウラン235が減損されたウランで放射能は弱い)は、おもりか放射線遮蔽材くらいしか使い道のない邪魔者になります。しかし、ウラン238が核燃料として使えるならば、エネルギー資源としてのウランの利用効率は一気に高まります(強い放射能を持つ核分裂生成物が生じるという問題はありますが)。進行波炉はウラン238を核燃料として使用する原子炉の一種です。
ウラン238は中性子の捕獲によって核分裂性のプルトニウム239に変わることが知られています。
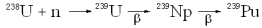
軽水炉でも、この反応で生じたプルトニウム239の核分裂が熱生成に関与していますが、プルトニウムに変わるのはごく一部のウラン238に限られるので、もっと積極的にウラン238をプルトニウムに転換する方法が検討されています。そうした中で、実用化に向けて日本・ロシア・インド・中国が開発を進めている(欧州諸国・アメリカは開発を中断)のがナトリウム冷却高速増殖炉であり、実用段階にはほど遠いが研究が始まっている炉の一つが進行波炉です。
ウラン235はスピードの遅い熱中性子を照射したときに核分裂を起こすので、軽水炉では、核分裂の際に放出される高速中性子を水で減速し、他のウラン235にぶつけて核分裂させます。これに対して、高速増殖炉では、炉心部にはプルトニウムを多く含有する核燃料を用い、高速のままの中性子を使ってプルトニウムの核分裂連鎖反応を引き起こします。さらに、炉心の周囲を劣化ウランで覆い、炉心から飛び出してくる高速中性子をウラン238に捕獲させてプルトニウムに変換します。このとき、炉心で消費されるよりも多くのプルトニウムが生成されるので、核燃料が増える「増殖炉」となります(“高速”増殖炉とは、高速の中性子を使う増殖炉という意味です)。軽水炉と異なって冷却と減速の機能を兼ね備えた水を利用せず、高温になる炉心部を効率的に冷やす冷却材として主に液体ナトリウムが使われますが、液体ナトリウムは空気中の水分と爆発的に反応するため、少しでも漏出すると火災事故を引き起こす危険があります。高速中性子の制御と液体ナトリウムの扱いが技術的に難しいため、高速増殖炉はまだ実用段階には達していません。
高速増殖炉では、周囲におけるプルトニウムへの転換と、炉心部におけるプルトニウムの核分裂が別々に行われています(周囲で生成されたプルトニウムも核分裂するが、出力への寄与は比較的小さい)。一方、転換と分裂をまとめて行うというのが進行波炉の基本的なアイデアです。簡単に言えば、劣化ウランで作られた円柱状の核燃料の内部で、ウラン238をプルトニウムに転換しながら、そのまま核分裂させるという一連の核反応を実現するものです。こうした核反応が生じる領域が、円柱状の核燃料の端から波面のように進行していくので、進行波炉と呼ばれています。また、ロウソクが燃える過程と似ていることから、CANDLE型炉と言うこともあります。このとき、最初に“点火”するために濃縮ウランが必要となりますが、それ以降は、劣化ウランの核反応による発熱が長期にわたって持続するとのことです。進行波炉の開発を目指すテラパワーのホームページでは、大型炉の場合、核燃料の交換なしに出力1000MW(通常の軽水炉と同規模)の状態を100年間維持できると主張されています。
もし進行波炉が実現されれば、エネルギー資源が枯渇する心配は当分なくなるはずですが、実用化されるまでには、まだ多くの障碍がありそうです。どうもよくわからないのが、核反応が面状の領域に集中して生じるメカニズムです。ロウソクの場合は、上昇気流が炎の形を上向きに整えるために上端部での安定した燃焼が維持されますが、進行波炉に核反応が安定的に進行するだけの自己制御性があるかのかどうか、私には何とも言えません。核反応の進行をコンピュータ・シミュレーションしたという論文(E. Teller et al., “Completely Automated Nuclear Power Reactors for Long-Term Operation”, Proc. Of the Frontiers in Physics Symposium 1995 )をざっと見ましたが、核燃料の構造を単純化したモデル計算なので、自己制御性に関してははっきりとしません。高速中性子の制御や冷却材の扱いに関しても、不明な点がいろいろとあります。
なお、東芝が開発しているのは、進行波炉ではなく小型のナトリウム冷却炉です。これは、液体ナトリウムを冷却材として用いる50MW程度の小型原子炉で、水で減速しない高速中性子による核分裂を利用しています。高速中性子は核分裂を引き起こす確率が低くなりますが、核燃料をじわじわと分裂させ続けることができるので、中性子の漏洩を抑制する設計が行えれば、数十年間にわたって核燃料棒を交換せずに運転ができるというメリットがあります。東芝は、送電網の整備が遅れている地域向けに2014年頃の実用化を目指しており、そのために、液体ナトリウムを扱う技術と長期間放射線に耐える素材の開発を進めています。ところが、これらは進行波炉でも必要なものなので、関心を持ったビル・ゲイツとテラパワー幹部が来日して、東芝と技術協力の可能性を探る検討を始めたというわけです。私の印象では、進行波炉はまだ海のものとも山のものとも知れませんが、ビル・ゲイツの来日によって東芝の新型炉に注目が集まったのは喜ばしいことです。
【Q&A目次に戻る】

物理学とは、物理現象をモデル化して数学的に分析する学問です。したがって、物理学者たちは、あらゆる物理現象を数学で表現するように努め、既存の数学で表現しきれない現象が見つかったときには、数学を拡張して数学的なモデルを作り上げようと試みます。もっとも、こうした試みがどこまで続けられるかは、明らかではありません。
数学を拡張した試みとしては、量子力学における非可換数の導入があります。ニュートン力学では、粒子の位置x や運動量p は確定した値を持つ物理量として実数で表現されますが、粒子が明確な軌道を描かない量子力学では、位置や運動量を実数で表すのは困難です。そこで、1926年にイギリスの物理学者ディラックが、積の順番を入れ替えると結果が異なるような数を導入し、これを使って物理量を表すことを提案しました。例えば、位置x と運動量p の間には、
xp - px = ih/2π
という交換関係が存在します。このように積が交換しない(非可換な)数を用いるフォーマリズムは、量子力学を発展させる上で決定的な役割を果たしています。特に、場の量子化に際しては、積の順番を入れ替える際に符号も変えて
xp + px = ih/2π
という形で定式化することにより、フェルミ=ディラック統計を示す粒子の扱いが可能になりました。
この他にも、アトラクタのトポロジーを使って「複雑さ」を定義したケースなど、表現困難だと思われた概念を数学を拡張することでモデル化した事例はいくつもあります。
数学を拡張する必要性は、近年、ますます高まっているように見えます。20世紀前半には、一般相対論の場合ように、数学(リーマン幾何学)の拡張が先行し、それを利用して物理学が発展することもありましたが、最近では、量子重力理論のように、物理学からの要請に応じて新しい数学分野が開拓される例も珍しくありません。それとともに、物理学で用いられる数学が難解になり、研究者を苦しめています。
数学とは、人間の思考における計量的手法を抽象化・普遍化し応用性を増強したものだと考えられます。それだけに、人間の思考様式に由来する制約を受けており、何にでも適用できるほど柔軟ではありません。例えば、実数を考えてみてください。人間が利用する連続的な数は、もともと基準の選び方に応じて目盛りが付けられるようにスケールの任意性を持っていましたが、連続的な数の概念を抽象化した実数体も、この性質を受け継いで、スケール変換によって代数的構造が不変に保たれるように定義されています。ところが、このような性質を持つ実数体を使って時空を表すと、どんなに微小な領域でもスケール変換すれば巨視的な領域と同等になるため、微小な領域における時空の量子揺らぎが(くりこみのテクニックなどでは)コントロールできないほど強く現れてしまい、計算を破綻させてしまいます。こうした事態を避けようとして、量子重力理論では、実数体とは異なる数学的な手法(例えば単体分割法など)を模索していますが、必ずしも成功していません。そもそも、最先端物理学で数学が異常なまでに難解になった背景には、対象となる物理現象が人間の思考様式を逸脱しつつあるという事情があるかもしれません。量子重力理論の現況を見ていると、「すべての物理現象は数学で表現可能か?」という問いに対して否定的に答えざるを得ないような気がしてきます。
【Q&A目次に戻る】

質問にある考え方は、おおよそ正しいと言えます。ここでは、他の読者のために、もう少し詳しく説明しましょう。
太陽系外の惑星(系外惑星)の観測には、一般に視線速度法とトランジット法が用いられます(2006年には系外惑星からの反射光を直接捉えることに成功していますが、レアケースです)。視線速度法とは、恒星が観測者に近づいているか遠ざかっているかによってスペクトル中の吸収線に生じるドップラーシフトを測定する方法で、現在では、1m/s 程度の速度変化を検出することが可能です。多くの系外惑星は、公転運動する惑星からの重力で恒星が揺さぶられる効果を視線速度法で測定することによって発見されています。一方、トランジット法とは、恒星の前を惑星が通過する際に見かけの明るさが減少する効果を捉える方法で、これを使って公転面の傾きや惑星の半径が推定されます。視線速度法とトランジット法を組み合わせれば、惑星の質量や密度も求められます。
さて、恒星が自転する影響を考えましょう。話を簡単にするために、恒星の赤道面と惑星の公転面は一致しており、地球上の観測者はこの面内にいるものとします(実際には、観測データから公転面の傾きを推定することが可能です)。自転するために恒星表面には観測者から見て近づく領域と遠ざかる領域があり、ドップラー効果によって、前者からの光は波長が短くなり、後者からの光は波長が長くなっています。したがって、惑星が恒星の前方を通過する際、どの部分を覆い隠すかによって、ドップラー効果の現れ方に差が生じます。これをロシター効果と言います。
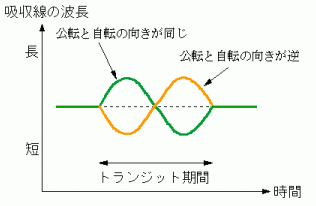
惑星の公転の向きは、ロシター効果がどのような順序で生じるかを見ればわかります。惑星の公転が恒星の自転と同じ向きのときには、まず近づく領域を覆い隠すので、波長が長くなる効果が強く現れ、その後、波長が短くなる効果が現れます。これに対して、自転と逆の向きに公転する惑星のロシター効果は、波長の変化が逆の順序で現れます。現在の観測技術では、吸収線の幅の中で光の強度がどのように変化するかを捉えることまではできないので、吸収線のピークの位置が時間とともにどのようにシフトするかによって、公転と自転の向きの関係を判定します。
すばる望遠鏡では、2008年5月30日に太陽系から1000光年の距離にある惑星系HAT-P-7の観測を通じて、世界で初めて恒星の自転と逆向きの公転を示唆するロシター効果が検出されました(発表されたのは2009年10月)。HAT-P-7の惑星はホットジュピターと呼ばれるもので、木星の1.8の質量を持つ巨大惑星が地球軌道の30分の1という小さな公転半径で恒星(質量が太陽の1.5倍あるF型の恒星)の周囲を回転しています。惑星が原始太陽系円盤の内部で形成されるという標準モデルでは、公転の向きは恒星の自転の向きと同じになるはずですが、おそらく惑星同士が接近し互いに散乱しあった結果として、逆行する惑星となったのでしょう。
【Q&A目次に戻る】

量子力学の原理に従えば、宇宙に存在する全粒子の入れ替えに対して波動関数を対称ないし反対称化しなければならないはずですが、実際には、ある程度以上の強さで相互作用している粒子の間の入れ替えを考えれば充分です。これは、ほとんど相互作用していないときには、全粒子の入れ替えまで考慮したときの(反)対称化の効果が、観測可能な物理量の期待値に何ら影響を及ぼさないためです。電子を例にとって説明しましょう。
何らかの装置を使って電子の測定を行う場合を考えます。装置を構成する物質の内部にも、電子は数多く存在します。しかし、これらの電子は原子に束縛されており、その波動関数はほんのわずかに物質表面から“染み出して”いるものの、距離とともに指数関数的に減少するので、測定対象となる電子の波動関数との重なりはないとしてかまいません。このとき、測定対象となる電子と物質内部の電子(あるいは測定装置の外側に存在する無数の電子)の間の相互作用は無視できるほど小さくなり、測定対象となる電子の波動関数は、他の電子の波動関数とは独立に求めることができます。
測定対象となる電子の個数を仮に2個として、その波動関数を
ψ(x
1,x
2)
と書くことにしましょう(2個以上のケースはトリヴィアルな応用問題です)。例えば、磁気でトラップした水素分子の2個の電子を測定するような場合です。ここで、ψは変数の入れ替えに対して反対称化されているとします。すなわち、
ψ(x
1,x
2) = -ψ(x
2,x
1)
ということです(式を簡単にするためにスピンについてあらわに書いていませんが、スピンの自由度を加えても以下の議論はそのまま成立します)。さらに、ψは正規化されており、
∫dx
1dx
2ψ
*(1,2)ψ(1,2) = 1
になるとします。ただし、いちいち x
1 などと書くのは面倒なので、ψの変数ではxの添字だけを表記しました(以下同様です)。
さらに、全宇宙にはN個の電子が存在しており、測定対象となるもの以外の振舞いは、Ψ(3,…,N) という(やはり反対称化・正規化された)波動関数で表されるとします。ψとΨは値を持つ領域が異なっており、ψは測定装置の内側の領域でのみ、Ψは逆に測定装置を含む外側の領域でのみ値を持つと仮定できます(この条件は、以下の議論で示されるように、重なった部分の積分がゼロになるという形に緩められます)。
ここで問題となるのは、測定対象となる2個の電子と他の電子との入れ替えを考慮しなくて良いのかということです。仮に、入れ替えを考慮しなくて良いとなると、宇宙には2個の電子しか存在しないものとして量子力学が適用でき、2個の電子がχ(1,2)という波動関数で表される状態である確率振幅wが、
w = ∫dx
1dx
2 χ
*(1,2)ψ(1,2)
で与えられることになります。そこで、他の電子との入れ替えを考慮したときにも、確率振幅が同じ式で与えられるかどうかを考えてみましょう。
式を簡単にするために、
A = Σ
P(-)
P P /N!
で定義される反対称化演算子Aを導入します。ただし、PはN個の変数を入れ替える演算子で、可能な順列を考えればわかるように、入れ替えの総数は N! で与えられます。Σ
P は全ての入れ替えについて足し上げることを表し、(-)
P は、考えている変数の入れ替えが2変数の置換を奇数回行ったことに対応する場合に負、偶数回の場合に正とします。簡単にわかるように、
A
2 = A
となります。
さて、宇宙に存在する全ての電子まで考慮して反対称化したときの波動関数Φは、
Φ(1,…,N) = c A ψ(1,2)Ψ(3,…,N)
で与えられます。cは、規格化条件:
1 = ∫dx
1…dx
N Φ
*(1,…,N)Φ(1,…,N)
を満たすための規格化定数です。Φの定義式を代入して計算すると、
1/c
2 = ∫dx
1…dx
N (Aψ
*Ψ
*) (AψΨ) = (*)
となります。ψ
*Ψ
*にAを作用させることは、積分変数を入れ替えれば、被積分関数の残りの項−−(AψΨ)−−にAを作用させるのと同じことなので、
(*) = ∫dx
1…dx
N (ψ
*Ψ
*) (A
2ψΨ) = ∫dx
1…dx
N (ψ
*Ψ
*) (AψΨ)
と書き換えられます(2番目の等式を得るのに、A
2 = A を使いました)。ここで、ψは測定装置の内側で、Ψは外側でのみ値を持つので、(AψΨ)の項の中で (1,2) と (3,…,N) の間で相互に変数を入れ替えているものは、ψ
*Ψ
* との積を取ったときに全ての積分範囲で値がゼロになり、積分に寄与しません(被積分関数がゼロになるのではなく、積分値がゼロになるように条件を緩めることも可能です)。したがって、積分全体に寄与するのは、ψ(1,2)の変数およびΨ(3,…,N)の変数をそれぞれ内輪で入れ替えたものだけです。しかも、ψとΨは既に反対称化されているので、Aの定義に含まれる (-)
P は相殺されてしまい、結局、積分に寄与する項は、
(-)
P P ψ(1,2)Ψ(3,…,N) = ψ(1,2)Ψ(3,…,N)
となります。こうした項が、(1,2)の入れ替えに対して2!個、(3,…,N)の入れ替えに対して(N-2)!個ずつ現れ、各項の積分値はψとΨが規格化されていることから1になるので、Aの定義に含まれるN!を併せれば、(*)の積分値として、
1/c
2 = 2!(N-2)!/N!
が得られます。
この結果を基に、測定装置の内側にある2個の電子がχ(1,2)の状態にある確率振幅w' を計算してみます。全宇宙の電子を考えたときの波動関数は
c A χ(1,2)Ψ(3,…,N)
なので、
w' = c
2∫dx
1…dx
N (Aχ
*Ψ
*) (AψΨ)
となります。
厳密なことを言えば、波動関数Ψを使って確率振幅を求めるのではなく、外側の電子が取り得る全ての状態の和を取って確率を計算すべきですが、式が長くなるだけで新しい知見は得られないので、話を簡単に済ませています。きちんとした議論が必要な人は、それほど難しくないので、自分で考えてみてください。
前の計算と同じように、χ
*Ψ
* に作用していたAを (AψΨ) に作用させ、A
2 = A を使い、積分がゼロにならない項を集めると、
w' = c
2∫dx
1dx
2χ
*ψ ∫dx
3…dx
NΨ
*Ψ × 2!(N-2)!/N!
と求められます。ここで、cの値を代入してΨが規格化されていることを使えば、
w' = ∫dx
1dx
2 χ
*ψ = w
が得られます。長々と計算してきましたが、外側にある全ての電子との入れ替えを考えても、物理的な結果は、測定対象となる電子だけ考えた場合と同じになるということです。
ここで気になるのは、波動関数の対称化・反対称化とはそもそも何かということです。量子力学の原理は、宇宙全体に存在するあらゆる同種粒子との入れ替えを考慮すべきだと要請していますが、実際には、相互作用している粒子だけを考えれば充分だというルースな結果になった訳で、原理と現実が食い違っているように思われるかもしれません。実は、これは、粒子を自立した存在と見なす量子力学の限界と言うべき結果なのです。量子力学は、粒子についてのニュートン力学に量子論のアイデアを適用して定式化したものですが、もともと電子はニュートン力学で扱える粒子ではありません。電子とは、量子論的な電子場の励起状態が粒子的な振舞いをしているのであり、粒子の入れ替えとは、局所的な場の性質を粒子概念を使って粗雑に言い換えた表現に他ならないのです。粒子概念を大前提とすると、全宇宙に存在するあらゆる粒子の入れ替えを考えなければならないという訳の分からない話になりますが、電子が粒子ではないという本来のフォーマリズムに立ち返れば、宇宙全体など考える必要はなく局所的な議論で話が完結するのです。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
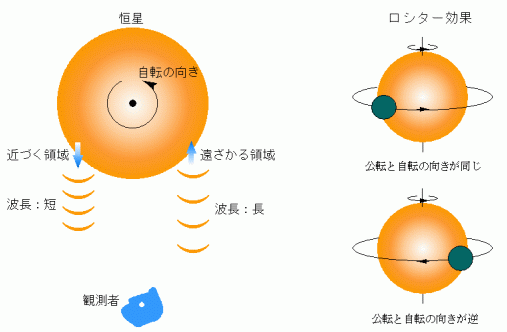
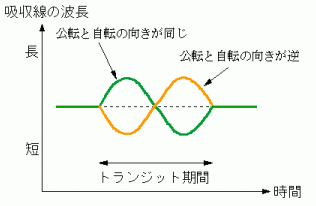 惑星の公転の向きは、ロシター効果がどのような順序で生じるかを見ればわかります。惑星の公転が恒星の自転と同じ向きのときには、まず近づく領域を覆い隠すので、波長が長くなる効果が強く現れ、その後、波長が短くなる効果が現れます。これに対して、自転と逆の向きに公転する惑星のロシター効果は、波長の変化が逆の順序で現れます。現在の観測技術では、吸収線の幅の中で光の強度がどのように変化するかを捉えることまではできないので、吸収線のピークの位置が時間とともにどのようにシフトするかによって、公転と自転の向きの関係を判定します。
惑星の公転の向きは、ロシター効果がどのような順序で生じるかを見ればわかります。惑星の公転が恒星の自転と同じ向きのときには、まず近づく領域を覆い隠すので、波長が長くなる効果が強く現れ、その後、波長が短くなる効果が現れます。これに対して、自転と逆の向きに公転する惑星のロシター効果は、波長の変化が逆の順序で現れます。現在の観測技術では、吸収線の幅の中で光の強度がどのように変化するかを捉えることまではできないので、吸収線のピークの位置が時間とともにどのようにシフトするかによって、公転と自転の向きの関係を判定します。