
地震とは、少しずつひずみが蓄積されていた岩盤が、ある段階で耐えきれなくなって剪断破壊を起こし、断層を境に大きく動きく現象ですが、地下への注水やダムの水圧が剪断破壊のトリガーになる可能性はあります。このように、人為的なトリガーによって発生する地震を誘発地震と言います。
ダムの水圧による誘発地震として、1940年にアメリカのフーバーダム周辺で起きたM5の地震を挙げる人もいますが、長期的に地震観測がされていたわけではなく、震源もかなり深いため、ダムとの関係は明らかではありません。日本では、宮城県釜房ダム周辺で1970年の湛水直後に震源の浅い群発微小地震が発生、さらに10年間にわたって間欠的に微小地震が起きた後に沈静化したことから、水の浸透に伴う過渡的な現象として地震が生じた可能性が指摘されています。もっとも、10年以上のタイムスパンで継続的にダム周辺での微小地震を観測したケースはこれ以外にほとんどなく、ダム誘発地震に関して明確な意見を述べられるほどのデータはありません。
一方、地下への注水による誘発地震に関しては、1960年代にアメリカ・デンバーで深井戸に廃液を注入した際に地震が多発したケースを皮切りに世界各地で報告され、多くのデータが集まってきています。日本では、1995年の阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)で震源となった野島断層への注水実験が1997年と2000年の2回にわたって行われ、注水地点から2.5〜4.5km付近を震源とする誘発地震の発生が確認されました。この実験では、深さ540メートルの地点から圧力3.0〜4.5MPa(30〜44気圧)で毎分10〜25リットルの水を4〜9日間にわたって注入する試みが3〜4回ずつ行われています。1997年の実験では注水後4〜5日を中心に最大マグニチュード0.6の、2000年の実験では注水後6〜7日を中心に最大マグニチュード0.3の極微小地震が多数観測されました。野島断層周辺では以前から極微小地震が続いていましたが、注水後に波形の異なる地震の回数が有意に増えたので、地震が誘発されたと結論づけられています(人体には全く感じられないきわめて小さな揺れなので、被害が発生する心配はありません)。2000年の実験では1997年に比べて誘発地震の発生時期が遅くなり規模も小さくなっていますが、これは、大震災で動いた断層が少しずつ固着しているためと考えられます。同様の実験は、1994年にドイツ南西部でも行われています。このときは、9030メートルという深さに野島断層の実験の10倍以上の圧力で大量の水を注入したせいか、注水後2時間で注水地点から50〜100メートルの近距離を震源とする最大マグニチュード1.2の誘発地震が発生しました。
このように、地下への注水が誘発地震を引き起こす可能性があるのは事実です。ただし、これはあくまで、ひずみが蓄積されている岩盤に水を注入すると地震のトリガーになり得るということであって、注水すればどこでも地震が起きるというわけではありません。圧力を加えた CO
2 を帯水層に送り込んで貯える地下貯留では、貯め込んだCO
2が地震をきっかけに噴出するリスクを減らすためにも活断層周辺は避けるので、充分な事前調査によって地震の起こりにくい地域であると確認されていれば、誘発地震の心配はあまりしなくても良いと思います(むしろCO
2 の噴出の方が心配です)。
【Q&A目次に戻る】

質問にもある通り、相対性原理とは全ての慣性系で物理法則が等しくなるという原理です。光が一定の速度cで伝播することは電磁気学の法則を数式化したマクスウェル方程式から導けるので、この方程式を正しいものと認めるならば、相対性原理によって全ての慣性系で光速は一定値cになります(マクスウェル方程式を認めない立場ならば、相対性原理とは別に、光速度不変の原理が必要になります)。これに対して、波長や振動数は、電磁気学の法則から導かれるものではなく、具体的な状態を表す量なので、全ての座標系で共通の値になることはありません。
数学的な電磁気学理論では、波長よりも波数ベクトルがよく用いられます。単色平面波の波数ベクトルは、大きさが波長の逆数、向きが波の進行方向になるようなベクトルですが、波長の逆数とは1を波長λ[m]で割ったものなので、波数ベクトルは進行方向1メートルあたり波が何個あるかという空間的な量になります。一方、振動数は1を周期T[sec]で割ったものなので、1秒あたり波が何個あるかという時間的な量です。相対論とは、1次元の時間と3次元の空間が一緒になって4次元の世界を形作るという理論なので、振動数と波数ベクトルも一緒になって波動ベクトルと呼ばれる4次元のベクトルを構成します。質量のようなスカラー量は座標変換しても値が変わりませんが、4次元ベクトルは異なる慣性系に移行する際にローレンツ変換と同じ形の変換を受けます。光のドップラー効果の公式とは、光源が静止している座標系での波動ベクトルを観測者が静止している座標系へ変換し、これに、「波長×振動数=光速」という一般的な関係式を当てはめたものに他なりません。波動ベクトルがローレンツ変換と同じ形の変換を受けるのですから、それに応じて振動数や波長も変換されます。
音波のドップラー効果では、音源や観測者が音波の媒質である空気に対してどのような運動をしているかが重要になりますが、光の場合は、媒質となる静止エーテルのようなものが存在しないので、光源と観測者の相対速度だけがドップラー効果の公式に現れます。ただし、一般相対論に従って宇宙全体が膨張するときには、光が伝播する過程で空間の膨張に伴って波長が伸びていく効果を考慮する必要があります。
【Q&A目次に戻る】

地上デジタル波は、テレビ塔から送信される極超短波(UHF波;470〜770MHz)という点で地上アナログ波(13ch〜62ch)と同じですが、符号化や変調という基本的な送信方式が異なっています。
電波に信号を載せて送るには、正弦関数で表されていた搬送波の形を信号に応じて変調させる必要があります。まず、アナログテレビについて説明しましょう。アナログテレビの場合、映像信号では搬送波の振幅を変えるAM変調、音声信号では搬送波の周波数を変えるFM変調が使われています。古いブラウン管テレビでアナログ放送の画面を見ると、横に何本もの線が走っているのがわかると思いますが、画面の左上からこの線に沿って順番に映像信号が送られてくるわけです。映像信号には、明るさを表す輝度信号と色合いを表す色差信号があり、搬送波の振幅の大きさでこの信号を表しています。例えば、振幅が大きいほど明るいといった感じになるわけですが、振幅の大小がそのまま信号となっている点が「アナログ」と言われる所以です。
一方、デジタルテレビでは、位相変調と振幅変調を組み合わせた変調方式が採用されています。位相変調とは、例えばサイン波を90°ずらしてコサイン波に変えるようなもので、このずれの有無で0か1かの信号を表します。さらに、振幅も段階的に変えており、どの段階かによって離散的な信号が表されます。このように、位相のずれや振幅の大きさがそのまま信号になるのではなく、0か1かといった離散的な情報に変換されるので、「デジタル」と呼ばれます。地上デジタル放送では、デジタル信号によって変調された数千の搬送波を重畳して送ることにより、大容量を必要とする映像データの送信を実現しているのです。
デジタルテレビの映像データは、アナログテレビのように端から順番に色合いと明るさのデータを送っているわけではありません。例えば、一つの画面で同じ色の画素が連続する部分や、何コマかにわたる動画で動きのない部分がある場合は、全ての画素についての情報を送るのではなく、「ここからここまでの部分は同一のデータで表される」という圧縮された情報に直して送信されます。このような動画圧縮のやり方にはいくつかの種類がありますが、世界各国のデジタルテレビ放送では、一般に、ISO(国際標準化機構)などで策定されたMPEG-2という方式が使われます。デジタル放送に対応したテレビでは、圧縮されたデジタルデータをコマ毎の画面のデータに変換しなければならないので、データ変換のための専用チップが搭載されています。
ちなみに、MPEG-2はDVDでも採用されている圧縮方式であり、デジタル放送を録画する場合は送られてきたMPEG-2のデータを(コピー制限に関する部分を別にして)そのまま記録するだけで済むので、地デジ専用のDVDレコーダには小型で安価な製品があるのです。
【Q&A目次に戻る】

結論から先に言えば、量子力学を応用する物理学者にとって、量子論理は何の役にも立っていません。量子論理とは、論理学者・数学者が量子力学の一部の性質を自分たちの言葉で表すために考案した非古典論理学の一変種で、あくまで、その分野の専門家にしか使われないものです。少なくとも、私にはそう思えます。
もっとも、私は量子論理を理解できていないのかもしれません。一般的な解説によると、量子論理は、量子力学における演算子の非可換性を命題の非共立性という形で表現しており、分配法則が成り立たたない点に特徴があるとされます。ある粒子の位置と運動量について考えてみましょう。位置の演算子qと運動量の演算子pは、交換関係:
qp - pq=ih/2π
を満たしていますが、このように演算子が交換しない(積の順番を入れ替えると作用が変わる)場合には、その物理量に関する不確定性関係が成り立つので、qとpの値は同時に確定できません。したがって、「粒子の位置は××(任意の確定値)である」という命題Qと、「運動量は△△である」という命題Pは、同時に成り立たないという意味で非共立的となります。ここで、「粒子の位置は××以外である」という命題をQ' とすると、
Q∨Q'
は恒真だろうと期待されるので、Pがどのような命題であろうとも、
P∧(Q∨Q')⇔P
が成り立つのではないかと思われます。しかし、Pとして上の運動量の命題を考えると、運動量と座標は同時に確定できないのですから、Pが真のときにはP∧QもP∧Q' も真ではありません。つまり、
P∧(Q∨Q')⇔(P∧Q)∨(P∧Q')
という分配法則が成り立っていないことになります。こうした論理規則を一般化したものが量子論理だ−−というのが教科書で見られる解説です。
さて、私はこの辺りでもう躓いてしまいます。確かに、位置と運動量を同時に測定しようとしても、測定操作に伴う擾乱で誤差が大きくなってしまうこともあって、確定した測定値は得られません。しかし、それならば、命題Qは「同時に測定できるとしたら、位置として××という値を得る」と表現しなければならず、さらに、命題Q'(「同時に測定できるとしたら、位置として××以外の値を得る」)の他にも、「同時には位置を測定できない」という命題Q" を考えなければならないような気がします。Q∨Q'∨Q" ならば恒真だと考えても良さそうなので、分配法則:
P∧(Q∨Q'∨Q")⇔(P∧Q)∨(P∧Q')∨(P∧Q")
が成り立つと思われます。では、分配法則が成り立たない量子論理とは、何だったのでしょうか?
実は、量子論理の元になっている1930年代のノイマン=バーコフの議論では、ヒルベルト空間の射影演算子と命題を対応させるという論法が採用されており、このことが分配法則を破綻させる原因になっていたのです。位置に関して、「××に射影する」という射影演算子Qと「××以外に射影する」という射影演算子Q' は直和が恒等演算子になるので、射影演算子と命題が1:1に対応するとすれば、Q∨Q' (それぞれの射影演算子と対応する命題を同じ記号で表した)は恒真と見なさざるを得なくなります。しかし、そもそも射影演算子と命題を対応させることに物理的な意味があるのでしょうか。実際、直和が恒等演算子になるような射影演算子の組は無数にあるので、量子力学的な状態は何通りもの選言命題の形で表されますが、この不定性が有名なEPRパラドクスの起源にもなっており、ノイマン=バーコフの議論はそのままでは受け容れられません。
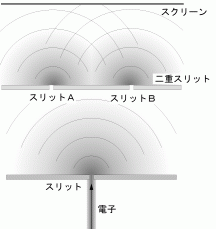
量子力学において古典論理が成立するような命題集合を構成する試みは、1970年代から80年代にかけて、グリフィス=オムネスによって行われました。ごく大ざっぱに言うと、互いに干渉しあわないような量子力学的過程と命題(事実を表す命題)を対応させるという方法です。量子力学はシステムの時間的な変動を扱う理論ですから、時間概念を含まない射影演算子を命題と結びつけるのが無理なのであって、時間とともに移り変わっていく過程全体を命題に対応させる方が理に叶っているのです。例として、二重スリットを通過した電子がスクリーンに到達するケースを考えましょう(図参照)。電子はAとBという二つのスリットが開けられた板を通過していきますが、グリフィス=オムネスの考えによると、中間での過程を
「電子はスリットAを通った」∨「電子はスリットBを通った」
という選言命題の形で表すことはできません。なぜなら、それぞれのスリットを通った波動関数は通過後に干渉しあうので、「互いに干渉しあわないような量子力学的過程に命題を対応させる」という条件が満たされないからです。中間段階で分割することはできず、「電子は二重スリットを通過してスクリーン上の位置××に到達して輝点を残す」という一連の過程全体を表す命題の集合によってのみ表されます。この命題の集合に関してならば、全ての命題の選言は恒真命題となり、分配法則は常に成り立ちます(厳密なことを言うといろいろ問題があるのですが、ここでは無視します)。グリフィス=オムネスの議論が正当ならば、量子論理というわかりにくい論理規則を使わなくても、明快な古典論理学に基づいて量子力学の命題を記述することができます。それだけではありません。彼らの議論は、単に命題が従う論理規則を明らかにしただけではなく、量子力学の計算に基づいて各命題に確率を与え、古典的な確率過程の議論を援用することを可能にしています。
ただし、これで全てが解決できたわけではありません。「あらゆる物理現象を互いに干渉しあわない量子力学的過程に分割する」ということが可能なのか、可能であるとしても一意的なのか、可能でないとすればどういう範囲で分割ができるのか、いまだに結論が出ていないからです。この問題は、量子力学における測度の定義とかかわっています。測度とは、積分計算を行う際に必要になる量であり、例えば、粒子がある位置に存在する状態と、それとは無限小の距離だけ隔たった位置に存在する状態とをどのように区別すべきかというときに、測度の定義が絡んできます。当然のことながら、こうした議論は、論理学の範囲では行いようがありません。量子力学の基礎に関する謎は、論理ではなく物理の課題なのです。
【Q&A目次に戻る】

この質問は、とても私の手に負えるものではありませんが、とりあえず、考えるところを書いておきます。
人類の進化の過程で、大脳新皮質の拡大に伴う脳容量の増大が重要な役割を果たしてきたことは間違いないでしょう。生物が採用する生き残り戦略には、身体の大型化や防御機能の強化などさまざまなものがありますが、樹上という不安定な環境で捕食者を避けつつ昆虫や果実を採取しなければならなかった人類の祖先にとっては、状況の変化を的確に予測できるような高い知能を持った個体の方が生存に有利です。特に、哺乳類の中では例外的に優れていた視覚からの情報を活用するために、大脳新皮質視覚野が発達したと考えられます。森林の後退を契機として樹から降りた後も、森林と草原の間のマージナルな環境に適応し、集団生活を営みながら生き延びることを選んだ種にとって、知能の高さは武器になります。おそらく、知能向上を促すこうした淘汰圧にさらされたために、霊長類の中で類人猿から人類につながる系統は、脳容量が増大し続けたのでしょう。
現生人類につながる系統は、チンパンジーとの共通祖先から約600万年前に分岐しました。脳容量で比較すると、約440万年前に生息していた Ardipithecus ramidus (ラミダス猿人)は300〜350cc、390〜290万年前の Australopithecus afarensis (アファレンシス猿人)は370〜430cc程度で、350〜400cc程度ある現在のチンパンジーと大差ありません。300〜200万年前の Australopithecus africanus(アフリカヌス猿人)でも400〜500cc程度です。しかし、250〜150万年前の Homo habilis (ヒト属ハビリス種、ハビリス原人)では500〜800cc、180万年前に登場した Homo erectus (ヒト属エレクトス種、ジャワ原人・北京原人を含む)では800〜1100ccとなり、現生人類である Homo sapiens (ヒト属サピエンス種)の1350ccに近づいています。
一般的に言って、脳容量が大きいほど高い知能を持つ傾向にありますが、必ずしも厳密な関係ではありません。例えば、約20万年前に登場して2万数千年前に絶滅したヒト属の一種 Homo neanderthalensis (ネアンデルタール人)は、 現生人類よりも脳容量が1割ほど大きいことが知られています。しかし、死者を埋葬し装飾品を身につける文化を持っていたと言われるネアンデルタール人は、同時期に生きていたホモサピエンスとは異なり、高度な文明を生み出せないまま最終氷期のさなかに絶滅しました。
さて、ここで改めて質問について考えてみたいと思います。論点として、次の3つを上げましょう。
(1)
脳容量が増大し続けた原因は淘汰圧だけか、それとも、何らかの遺伝的要因があったのか? チンパンジーから分岐した人類の祖先は、400万年以上にわたって脳容量を(おそらく断続的に)増大させてきました。これは、ほとんど脳容量が増えなかったチンパンジーとは、著しく異なっています。脳重量と体重の対数の相関を見ると、ヒトが真猿亜目のグループの中飛び抜けているのに対して、チンパンジーはリスザル(ヒトやチンパンジーと同じ真猿亜目だが、狭鼻下目ではなく広鼻下目に属する)などと同じ直線の上に乗っており、脳が巨大化する傾向は、チンパンジーとの共通祖先から分かれた後でヒトに生じたと推測されます。こうした増大傾向は、単純に、脳が大きい方が生存に有利になる環境にいた結果だと考えて良いのでしょうか? 私には、それだけだとは思えません。進化に一定の方向性があるという考え方は「定向進化説」と呼ばれ、現在の進化論では異端視されています。しかし、特定のパーツの巨大化に関して言えば、一定の大きさ以上に成長することを抑制する機能が可変的になり、わずかな塩基配列の違いで抑制レベルが大きく変動するようになったという可能性もあるはずです。言うなればタガがはずれやすくなった状態であり、淘汰圧が比較的小さくても、パーツの大きさが著しく変わってきます。チンパンジーと分かれた後で抑制機能をコードする遺伝子に変異が生じ、脳が巨大化しやすくなったと考えてもおかしくないと思います。ヒトとチンパンジーの塩基配列の差はごくわずかなので、この考えが妥当かどうかの検証は不可能ではないでしょう。
(2)
Australopithecus (アウストラロピテクス属)から Homo (ヒト属)に進化した後で、脳容量の増大傾向を加速する遺伝的変異が起きたか? 数字だけ見ると、 Australopithecus までは比較的緩やかだった脳容量の増加スピードが Homo になってから急に増えたようにも感じられ、ここで大きな変異が起きたと言えなくもありません。しかし、私はこれは後天的要因による変動の範囲であり、 Ardipithecus や Australopithecus に見られた増大傾向が少し顕著になっただけだと考えています。脳が巨大化することには、知能の向上というメリットだけではなく、(i)出産時の外傷による出血や産褥熱で女性が死亡するリスクが高い、(ii)頭蓋があまり成長しない段階で出産せざるを得ないために乳幼児の自活能力が低い−−などのデメリットが伴います。メリットとデメリットの効果が均衡するところで脳容量の増大は一時的に止まりますが、周産期の女性や乳幼児を社会集団で保護する文化が生まれると、デメリットが減殺されて脳容量が増大する傾向が再開されるはずです。Homo に見られる脳容量の急増は、文化の所産ではないかというのが私の考えです。
(3)
文明を生み出すことが可能になる臨界値はあるのか? 文明を生み出すには高度な知能が必要です。どんな環境に置いても、キツネザルやテナガザルには文明は生み出せないでしょう。しかし、例えば、「脳容量が1000ccを超えれば文明を生み出せる段階に到達した」といったわかりやすい線引きはできないはずです。脳容量が現生人類よりも大きかったネアンデルタール人のケースは、文明の発生には、解剖学的な脳の発達以外の何かが必要なことを示しているのかもしれません。もっとも、ネアンデルタール人が絶滅したのは単に運が悪かっただけで、最終氷期を生き延びていれば、その後に文明を発展させられたという見方もあります。また、ネアンデルタール人は頭頂部が扁平でホモサピエンスほど前頭葉が発達していなかったことから、前頭葉の発達こそが文明化に至る鍵だと考えることもできます。いずれにせよ、文明を生み出せた生物は地球史上ただ一種類しかないので、何が必要かを確定することは困難です。私は、脳の巨大化による高度情報処理能力の獲得とともに、前肢が物を掴むのに利用できたこと、集団生活を営んでいたこと、雑食性だったこと、そして、気候の安定化や生存競争相手の絶滅などいくつもの幸運が積み重なったことが、人類をして文明を生み出させたのだと思っています。
人類の文明は、遺伝因子と環境因子が絶妙に絡み合って誕生したものであり、今後どうなるかは簡単には予測できません。ただ一つ言えるのは、これまでのように幸運が続くとは期待しない方が良いということでしょう。
【Q&A目次に戻る】
 私が小学校の時に教わった定説は、次のようなものでした。
私が小学校の時に教わった定説は、次のようなものでした。
定説:河原の石は、丸いものが多くあります。しかし、よく見ると角張った石もあり、川を上流にさかのぼっていくと、角張ったものが多くなります。石ころは山をつくっている岩がくずれてできます。できたばかりの石は角張っていますが、大水が出るたびに流されて転がったり、ほかの石とぶつかったりしているうちに、少しずつ角がとれて丸くなったのです。
何時の頃から、この定説に疑問を持つようになりました。それは、大きな洪水を経験して感じたことです。上流の原石が下流の海まで流れて行き砂や丸い石となっていくことは、間違いありませんが、転がったり石や砂とがぶつかって丸くなると言う部分が、納得いきません。洪水直後に河原に行ってみると、下流付近でもごつごつした丸くない石が有ります。ところが、採掘などの際に、過去に同じように洪水によって流れてきたと思われる地下に埋もれた石が、丸くなっているのを発見しました。転がったり石や砂にぶつかることなく丸くなっていたのです。ほとんどの石は、普段の流れの強さでは下流に流れて行きません。大部分の石は、時折起きる洪水によって流させるのではないでしょうか。そうだとすると、過去に洪水によって一気に下流に流れ着いた石が丸くなっているのは、なぜでしょうか?
私の仮説:石は、転がったり石や砂にぶつかる必要がなく、地下水等の水があるだけで溶けて、丸くなるのではないでしょうか。
そして、流れの強い水は、より丸くするのではないかと思います。【その他】

この質問は3年ほど前に受け取ったものですが、適切な文献が見つけられず、なかなか解答できませんでした。最近になって、ようやく文献が見あたらない理由がわかりました。この種の問題に関しては、まだわからないことが多く、定説ができあがっていないようなのです。
河川で砂利が運搬される過程は、大きく二つに分けられます。一つは、平時の定常的な流れによる運搬。もう一つは、水量が臨界量を超えたときの流れによる運搬です。質問にもありますが、平時の定常的な流れでは、砂利の移動はほとんど起きません。これは、次のような理由によります。
河床の表面近くに粒径の小さな砂利があると、水流を受けて少しずつ移動しますが、そのうち、大きな石や砂利の隙間に入り、下に落ち込んでしまいます。こうして、川の流れを直接受ける表面部分に小さい砂利がほとんどなくなり、比較的大きな石が組み合わさって表面を覆った状態になります。こうなると、表面より下に入り込んだ砂利は、もう動けません。実験によると、一般的な河川の場合、平時の定常流で粒径数ミリ以上の砂利はほとんど運ばれないことがわかっています。ただし、移動しなくても隙間を流れる水の作用を受け続けるために、河床で安定するまでの間に、少しずつ丸くなっていくと考えられます(溶けるというよりは、水流によって尖った部分が削られていきます)。
砂利の移動が起きるのは、大雨などで水量が増加した際に、水流による摩擦が強くなって河床表面の覆いが壊されたときです。このときは、覆いの下にあった大小さまざまな砂利が、土や砂が混ざった濁流とともにいっせいに流れ出します。残念ながら、さまざまな砂利や土の粒子が互いに摩擦を及ぼしながら移動する過程に関しては、まだ理論的な解析が充分に行われていません。90年代に発表された論文でも、理論的予測と観測データの間に2桁のずれ(!)があるといったことが平然と書かれています。そこで、以下では、私の推論を交えた定性的な話をします。
河床は、表面を比較的大きな石が覆い、小さな砂利が下に落ち込んだ構造をしています。多くの砂利は、すでに水流によって丸くなっていますが、流されて間もない石の中には、まだ角張ったものもあるはずです。覆いが破壊されたときには、これらがいっせいに流れ出すわけですが、移動のしやすさには差があります。一般的に言って、丸くて小さな石ほど移動しやすく、遠くまで流されていきます(大きな石は、いったん転がり始めると、小さな石よりも移動距離が長くなる傾向がありますが、転がり始める頻度が低いので、一度の洪水における平均的な移動距離は短くなると考えられています)。このため、丸くて小さい石ほど下流の方に流されることになり、結果的に、下流ではこうした石の割合が多くなります。
質問にある定説は、原因と結果を逆に解釈しています。下流域の石は、長く移動したから角が取れて丸く小さくなったのではなく、角が取れて丸く小さいから長く移動して来られたのです。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
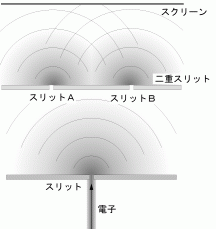 量子力学において古典論理が成立するような命題集合を構成する試みは、1970年代から80年代にかけて、グリフィス=オムネスによって行われました。ごく大ざっぱに言うと、互いに干渉しあわないような量子力学的過程と命題(事実を表す命題)を対応させるという方法です。量子力学はシステムの時間的な変動を扱う理論ですから、時間概念を含まない射影演算子を命題と結びつけるのが無理なのであって、時間とともに移り変わっていく過程全体を命題に対応させる方が理に叶っているのです。例として、二重スリットを通過した電子がスクリーンに到達するケースを考えましょう(図参照)。電子はAとBという二つのスリットが開けられた板を通過していきますが、グリフィス=オムネスの考えによると、中間での過程を
量子力学において古典論理が成立するような命題集合を構成する試みは、1970年代から80年代にかけて、グリフィス=オムネスによって行われました。ごく大ざっぱに言うと、互いに干渉しあわないような量子力学的過程と命題(事実を表す命題)を対応させるという方法です。量子力学はシステムの時間的な変動を扱う理論ですから、時間概念を含まない射影演算子を命題と結びつけるのが無理なのであって、時間とともに移り変わっていく過程全体を命題に対応させる方が理に叶っているのです。例として、二重スリットを通過した電子がスクリーンに到達するケースを考えましょう(図参照)。電子はAとBという二つのスリットが開けられた板を通過していきますが、グリフィス=オムネスの考えによると、中間での過程を