
不確定性原理は、「原理(principle)」と呼ばれているものの、実際には、量子条件から導かれる副次的な性質にすぎません。不確定性原理を用いた定性的な説明は全て、量子条件に基づいて定式化された理論(量子電磁気学など)から定量的に演繹できます。逆に言えば、量子電磁気学の定式化そのものに根ざしている無限大の困難を、不確定性原理を用いて解決することはできません。
量子電磁気学において、運動量(式を簡単にするため1次元で表記します)の値が p、エネルギーの値が E のとき、電子(あるいはその他の素粒子)は exp( 2πi (px-Et)/h ) という波動として表されており、「運動量が確定すれば(無限に拡がった平面波となって)位置が完全に不確定になる」という不確定性原理が満たされています。実際の素粒子反応について計算する際には、運動量やエネルギーに関して積分しますが、これらの積分は、運動量やエネルギーの値が確定しておらず、さまざまな値のときの寄与を全て加えあわせることに対応しています。不確定性原理とは、素粒子レベルでの物理現象が波動の積分として表されることを言葉で言い直したものに他ならないのです。
ある電子が放出した光子を再び吸収する過程を計算すると、運動量 p の積分において、p が大きくなる極限で被積分関数が 1/p のように振舞うことがわかります。∫dp/p は p が大きくなる極限まで積分すると対数発散するので、計算結果は無限大になって答えが出ません。運動量が大きくなる領域は、時間・空間で言えば無限に小さい領域に対応しているので、無限大の起源は瞬間的な自己相互作用にあると言うこともできます。これが無限大の困難であり、運動量やエネルギー(あるいは、それと共役な関係にある位置や時間)が不確定なので積分しなければならないとする理論の枠内で不可避的に現れるものです。
被積分関数の形や積分の定義を適当に変更すれば、無限大が現れないようにすることも可能です。こうした方法を「積分の正則化」と言います。しかし、こうした正則化は、物理現象の根本を解明しないまま恣意的に困難を回避するもので、現象の本質を追究する物理学者を満足させるものではありません。それでは、ミクロの極限まで明らかにする究極的な理論を構築しなければ無限大の困難は解決できないかと言うと、そうではありません。量子電磁気学がマクロな領域における近似として有効である以上、究極的な理論がどのようなものであれ、実際の観測にかかる素粒子現象について計算する方法があるはずです。こうして考案されたのが「くりこみの処方箋」であり、ミクロの極限に係わる過程の寄与を全て質量と電荷の定義にくりこんでしまうことで、無限大の含まれない結果を導き出すというものです。ここで重要なのは、計算の途中で厄介な無限大が現れないように恣意的な正則化を行っても、くりこみの処方箋を用いれば、計算結果は正則化の方法に依存しない(どんな正則化をしても同じ答えが得られる)という点です。このように正則化の方法に依存しないという特徴が、取りも直さず、ミクロの極限に関して詳細を知らなくても有用な計算を行えることを保証している訳です。
【Q&A目次に戻る】

実数の範囲で考えている限り、ネイピア数にさしたる重要性はありません。ボルツマン分布や放射性崩壊の式においても、温度や時間の単位を適当に選ぶだけで、e を含まない表記が得られます。e が数理の本質を際だたせるような重要な役割を演じるのは、複素数に拡張した場合です。
複素数は、絶対値と偏角の2つの自由度を持っており、実数が数直線上の点で表されるのに対して、数平面(複素平面)上の点で表されます。実数の場合、負数を掛けることは、数直線上で原点に対する位置を逆転させるという離散的な操作に対応するため、ある数の2乗は決して負になりません。ところが、複素数では、負数の乗算は位置の逆転ではなく複素平面上で180°回転させることであり、90°の回転を表す純虚数を2乗すると負になるので、負数の平方を定義することが可能になります。一般に、複素数の積では、絶対値は(正の実数と同様の)積を、偏角は和を取ることになるので、0以外の全ての複素数に対して、乗法の逆変換が定義できます。
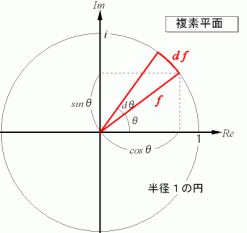
複素数の乗法で重要になるのが、絶対値が1の数です。偏角がθで絶対値が1の複素数を f(θ) と表しましょう。偏角を dθ だけ増やしたときの f の変分は、右図からわかるように、絶対値が半径 1、中心角 dθ の扇形の弧長、偏角が f に対して90°増えたものになります。従って、絶対値 1、偏角90°の複素数(虚数単位)を
i と表せば、
df =
i f dθ
となります。ここで、ネイピア数が登場します。上の式は、f を
i θ で微分しても関数形が変わらないという式なので、ネイピア数 e を使って、
f(θ) = e
i θ
と表すことができます。あるいは、オイラーの関係式:
e
i θ = cos θ +
i sin θ
を使えば、 e
i θ が絶対値1、偏角 θ の数であることが直接確かめられます。
e
i θ は、θ が増えるにつれて、原点を中心とする半径 1 の円周上を回転する数を表します。この数の特徴は、きわめて単純な形をしているにもかかわらず、振動の振舞いを表現できるという点です。実際、e
i θ の実部は三角関数になっており、調和振動を表す式です。にもかかわらず、e
i θ は三角関数よりも遥かに簡単で、加法定理のような厄介な公式を使わなくても、さまざまな計算が即座に遂行できます。e
i θ を使って振動現象を解析する方法として良く知られているのが、交流回路における電圧や電流を複素数で表す方法です。例えば、角振動数ωの交流で複素電圧・複素電流を
E = E
0 e
i ωt
I = I
0 e
i ωt
と定義すれば、インピーダンスマッチングなどの計算が三角関数を使う場合に比べて飛躍的に簡単化されます。
単に簡単化されるだけではありません。現在の物理学理論によれば、自然現象の根底にあるのは場の振動ですが、この振動を記述する際にも、ネイピア数を用いた表記は実にパワフルです。物理学における基礎方程式の多くは複素数で表記されていますが、私が想像するに
(←私だけかもしれません)、その理由は、根源的な振動現象を表すのに e
i θ という式が最も適切だからです。このように、ネイピア数は物理と数理を結びつける重要な役割を担っているのです。
ちなみに小川洋子の『博士の愛した数式』に登場する数式は、オイラーの関係式で θ=π と置いた式:
e
i π + 1 = 0
です(オイラーの等式と呼ばれます)。「全く起源の異なる無理数であるネイピア数 e と円周率 π を、空想によって生み出された虚数(imaginary number)
i によって結びつけ、そこに人の手で 1 を加えると、無が生まれる」−−まさに数学の至宝です。
【Q&A目次に戻る】

ホーキング放射(輻射)の理論は、完成された量子重力理論から演繹されたのではなく、いくつかの理論をつぎはぎして作り出した半古典的なものです。にもかかわらず、多くの物理学者は、その正当性を信じていますが、その理由は、ホーキングが用いた手法が、学識に裏打ちされた洞察力に基づいて現象の本質を適切に掴み取るものだったからです。
ホーキング放射の論文が出る数年前に、ホーキングとともに特異点定理を証明したペンローズが、(回転する)ブラックホールからエネルギーを取り出す方法を考案していました。ペンローズの理論によると、宇宙船を事象の地平面の近く(エルゴ領域と呼ばれる部分)まで到達させ、そこで積み荷の一部を地平面内に放り込み、その反動を利用して遠方へ脱出した場合、ブラックホールから離れたときに宇宙船が持っている総エネルギーは進入前よりも大きくなり得ることが示されます。ホーキングの研究は、この理論を参考にしたもので、事象の地平面のすぐ外側(エルゴ領域とは限らない)で粒子・反粒子の対生成が起き、その一方が地平面内に落ち込むケースが検討されました。対生成は量子論的な現象ですが、充分に巨大な質量を持つブラックホールの場合、事象の地平面は中心から離れた宇宙空間に形成され、重力場そのものの量子論的な揺らぎは無視できるので、物質的な現象に対する既定のバックグラウンドとして扱うことができます。ホーキングは、曲がった時空というバックグラウンド上で対生成が起きたときの波動関数の振舞いを調べ、ブラックホールから定常的に放出される粒子の流れが存在することを見いだしたのです。
外部からエネルギーが注入されない場合、対生成によって生まれた粒子・反粒子のペアは、いずれもごく短い時間しか持続できない仮想粒子にとどまり、一瞬のうちに消滅してしまいます。しかし、エネルギーが得られるならば、リアルな粒子となって遠方に飛び出していくことが可能です。実際に飛び出せるかどうかは、波動関数を計算して遠方に伝播する解の有無を調べることで判定できます。例えば、充分に大きなエネルギーを持った入射光子が実粒子である電子・陽電子ペアを生み出すことは、遠方に飛び出す電子と陽電子を表す波動解の存在によって理論的に示されます。さらに、その主張の正当性は、実験を通じて確認されています。ホーキング放射の場合、空間が曲がっていることに起因する振動モードの混合が生じ、平坦な空間とは異なって遠方に伝わる波動解が許されるので、光子が電子・陽電子ペアを生成するケースと同じ判定基準に従って、ブラックホールが粒子を放出すると結論できるわけです。
ホーキング放射の存在は、ブラックホールの統計力学を考える上でも重要です。現在の理論では、ブラックホールは、膨大な質量が流入した後でも、単純なシュヴァルツシルト解で記述されます。もし地平面内部に大量の物質が渦巻いているとすると奇妙な話ですが、アインシュタイン方程式によれば、ブラックホールの中心に特異点と呼ばれる一種の“穴”が開いて、流入した物質は時空の“外側”に放り出されてしまうため、単純な静的状態を保てるのです。しかし、これはおそらくアインシュタイン方程式の欠陥によるものであり、量子重力理論が完成された暁には、特異点は現れず地平面の内側に存在する物質の状態が記述されることになるはずです。このとき、ブラックホールは多数の自由度を持つ統計的システムとして扱われます。とすると、統計力学の一般論に従って、温度とエントロピーが定義されなければなりません。ホーキング放射は、ブラックホールが有限の温度を持つことに起因する一種の熱放射と考えることも可能であり、統計力学的な議論の端緒となるものです。このように将来への展望を与えてくれることもあって、ホーキング放射の理論は多くの物理学者に支持されています。
【Q&A目次に戻る】

標準理論の枠を拡張して重力を扱えるようにすることは無理だと考えられていますが、その理由は、重力が「くりこみ可能」ではないからです。
一般的な量子場の理論では、時空の全ての領域に稠密に場の自由度が存在しており、これらが互いに相互作用すると仮定されています。ところが、近接した場を介して自分自身と瞬間的に相互作用する過程をファインマン積分で求めようとすると、積分が発散して計算不能になります。これが「発散の困難」と呼ばれるものです。標準理論の場合、この困難は、朝永振一郎らによって開発された「くりこみの処方箋」によって回避されています。くりこみとは何かを説明するために、場の状態を観察する仮想的なモニターを考えてみましょう。このモニターは有限の解像度を持っており、瞬間的な自己相互作用までは映し出せないとします。標準理論の基礎となるヤン=ミルズ理論は、モニターの解像度を変えても、相互作用の数学的な形式は変化しません。ただ、電荷や質量の値が連続的に変化するだけです。細かな点を端折って言うと、「くりこみの処方箋」とは、解像度を変えたときの形式の不変性を利用して、ミクロ領域での自己相互作用の寄与を電荷や質量の値に「くりこんでしまう」手法です。これを使えば、ミクロの極限まで明らかにする(すなわち、無限大のモニターに映し出される現象を完全に記述する)ような究極の理論を知らなくても場の量子論的な振舞いが求められるので、発散の困難からは解放されます。しかし、重力にはこの手法が通用しません。
重力が「くりこみ可能」ではない原因は、一般相対論の形式そのものにあります。一般相対論とは、空間や時間がリジッドではなく歪みや捻れが現れるという理論であり、例えば、空間内部の2点間の距離を求めるのに、ユークリッド幾何学の定理であるピタゴラスの定理は使えません。相対論的な距離の定義には、ピタゴラスの定理からの僅かなズレが含まれていますが、このズレを表すのに、どうしても微分を用いた表記が必要となります。この結果、一般相対論は、多数の微分を含んだ数式の集まりになっています(一般相対論で用いられる数学が「微分幾何学」と呼ばれる所以です)。宇宙論や天体力学を考える場合、宇宙空間における重力場のなだらかな変化を考えれば良いので、微分の値は小さくなります。ところが、ミクロ領域での重力場は、量子論的な揺らぎのせいで激しく変動しているので、微分の寄与はどこまでも大きくなっていきます。直観的に言えば、ミクロ領域での重力場の振舞いを観察しようとしてモニターの解像度を上げていくと、相互作用の形がどんどんと変化して見えるという訳です。これは、重力が「くりこみ可能」ではないことを意味します。標準理論は、くりこみ可能性に基づいて計算を進めるものなので、くりこみ可能でない重力をそのままの形で取り込むことはできません。
くりこみ不能性は、ミクロの極限での重力理論がアインシュタイン方程式で記述できないことをも意味します。量子電磁気学は、古典的なマクスウェル方程式に基づいて作られています。しかし、ミクロの領域における重力は、マクロの領域を記述するアインシュタイン方程式とは大幅に異なった方程式に従うはずです。重力の振舞いを高解像度モニターで見ると、この未知の方程式に従う量子論的な揺らぎが観察されるものの、解像度を下げていくと揺らぎが均されていき、最終的には近似的にアインシュタイン方程式に従う滑らかな重力場が見えてくるはずです。こうした振舞いを正しく導くためには、ミクロの極限でも発散の困難が現れないような理論を作り、解像度を上げると量子論的な揺らぎがきれいに均されることを示す必要があります。これは、標準理論で用いている手法とは全く別のものです。
重力場を含む量子論の候補としては、(超)ひも理論((超)弦理論)があります。これは、相互作用が1点でのみ行われるとする従来の量子場の理論に対して、1次元的な拡がりを持つ相互作用域を考える理論(のはず)です。ただし、理論として完成している訳ではなく、候補として有力だというだけです。これ以外にも、時空の拡がりに最小の単位があるというループ量子重力理論も有力候補の1つとされていますが、やはり理論としては未完成です。重力理論はあまりに難しく、候補となる理論を考案するだけでも、抜群の数学能力を持つ優秀な理論物理学者が何年も研究を続ける必要があるため、新しい候補はなかなか生まれません。また、理論の正当性を検証する実験も、人類の手に余るような巨大なエネルギーを必要とするため、全く行われていないというのが現状です。
【Q&A目次に戻る】

固体内核融合に関しては、「追試が充分でない」「理論的な裏付けがない」などの理由で、大半の物理学者は批判的です。ただし、マイナスイオンのような擬似科学とは異なり、一応の考慮に値する現象であることを認めた上で、こんにちの物理学の規範に照らして受容できる水準に達していないという見方をしていると思われます。
核融合を起こすには、重水素などの原子核を原子半径の数万分の1という近距離まで接近させなければなりませんが、原子核は正に帯電しており強いクーロン斥力によって反発しあうため、簡単には近づけられません。通常は、一方ないし両方の原子核を加速し勢いをつけてぶつけるという方法が採用されます。日米欧で開発が進められている熱核融合炉では、プラズマの加熱によって原子核をまとめて加速します。また、電場を使って加速した原子核のビームを標的にぶつけて核融合を引き起こすことも可能です。ただし、いずれの場合も、加速のために注入するエネルギーよりも大きなエネルギーを生み出せるほど高い確率で核融合を生じさせるのは難しく、巨大な熱核融合実験炉を用いて1をわずかに越えるエネルギー増倍率がやっと実現できるというのが現状です。量子力学のトンネル効果によれば、加速させなくてもクーロン障壁を乗り越えられますが、核融合が起きる確率は非現実的なほど低くなります。ミュー粒子(質量が電子の200倍で負電荷を持つ素粒子)を使ってクーロン斥力を抑える方法もありますが、ミュー粒子は宇宙線の中にごくごく微量に含まれるだけなので、核融合の確率を劇的に高めることはできません。
常温核融合は、高温のプラズマを用いなくても高い確率で核融合が起きるという現象だとされています。もし、何らかのメカニズムによって一部の原子核にエネルギーが集中してこれを加速することができるならば、核融合も不可能ではないでしょう。しかし、現在の科学的知見の範囲では、こうしたエネルギーの集中は、簡単に入手できる装置を用いた小規模実験では起こりそうもないと言わざるを得ません。2002年には、超音波の投射で水中に生じた気泡が高速でつぶれる際のエネルギーによって核融合が生じるとの報告がありましたが、現在では、これは放射性同位元素の混入に起因する誤解だと見られています。
質問にある公開実験は、水素を吸蔵する能力の高いパラジウム合金の微粒子に重水素ガスを吹き込んだところ核融合が起きたというものです。公開実験を行った荒田氏は文化勲章も受章した著名な金属工学者であり、その結果を即座に否定することはできませんが、既存の理論から予想されない現象であるだけに、単なる確認実験とは異なる厳格な検証作業が必要となります。少なくとも私には、今回の(および過去に行われた)実験だけでは、以下のような理由で検証が不充分だと思われます。
- 生成される核種が核融合反応とは異なる。重水素の核融合では、主に三重水素とヘリウム3が生成されますが、今回(および過去に行われたいくつか)の実験では、ヘリウム3ではなくヘリウム4が観測されています。核融合が起きていることを検証するためには、ヘリウム3の生成を確認する必要があります(ちなみに、自然界にヘリウム4は豊富に存在しますが、ヘリウム3はごく僅かしかありません)。
- 実験方法が一貫していない。荒田氏は、過去にパラジウムの微粒子に重水素ガスを吸蔵させた上でレーザー照射を行って核融合を起こすという実験を行っています。レーザーを照射してもしなくても核融合が起きるというのでは、実験結果の信憑性が低く見られても致し方ありません。多くの常温核融合実験では、パラジウムと重水素の組み合わせが使われますが、どちらも使わずに核融合が起きたという報告もあり、混乱に拍車を掛けています。まずは、何をすれば常温核融合が起きるかを確定する必要があります。
- 過剰熱に関しては、核融合以外にも説明が可能である。常温核融合に関する多くの実験では、入力エネルギーを上回る過剰熱が測定されています。しかし、実験装置に使用された素材の化学反応による熱と解釈することも可能であり、核融合の証拠にはなりません(今回の荒田氏の実験では、正確な熱測定は行っていないようです)。
常温核融合が本当に起きていると確認されれば、物理学の一大革命になるばかりか研究機関に巨額の資金が流入することは確実ですが、それだけにインセンティブが強すぎて、厳密さに欠ける実験が横行しているというのが実状です。1989年に学界を揺るがした常温核融合騒動の前例もあり、多くの物理学者は、この話題に関して敬遠気味の態度を示しています。
【Q&A目次に戻る】

脳波のコンピュータ解析やfMRIによって、近年、脳がどのように機能するか解明が進んでいますが、それによると、覚醒中の脳は、きわめて“雑音”の多い状態のようです。ここで“雑音”と言ったのは、同期性が乏しく振幅が不安定に変化するように見える低振幅の高周波のことです。きわめて単調な作業を行っているときには、振幅が大きめの脳波が比較的広い領域で同期して現れますが、意識レベルが高まると“雑音”が増えてくるのです。このデータをそのまま受け容れると、1つの課題を真剣に考えているつもりであっても、脳は、並列的に多様で統一性に欠ける情報処理を行っているものと解釈されます。こうした“雑音”があるからこそ、課題に対する視点を無意識に変更したり、他のデータとの類似性をふいに思いついたりして、新たな発想を得ることができるのでしょう。
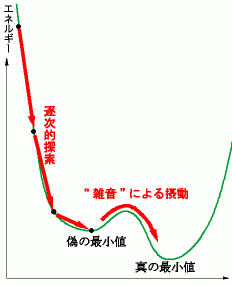
それでは、コンピュータの演算にこうした“雑音”を加えることは可能でしょうか? 例として、ある条件下でタンパク質がどのように折り畳まれるかという問題をコンピュータに解かせる場合を考えてみましょう。あらゆる折り畳み方を網羅的に調べるのは現在のコンピュータでも不可能です。そこで思いつくのが、逐次的なアルゴリズムに基づいて、少し折り畳んではエネルギーを計算し、その値が前よりも小さくなるならば、さらに折り畳みを続けていくという方法です。しかし、実際には、このやり方で最適解を見つけることは一般にできません。たまたまエネルギーが極小値を取る折り畳み方に到達すると、そこから先に進めなくなってしまうからです。人間ならば、考えが行き詰まっても視点を変えるなどして先に進むことが可能ですが、コンピュータはそうは行きません。そこで、人間の脳に見られる“雑音”と同じ効果を持つ摂動を加える必要があります。
タンパク質の例で言うと、いったん極小値に到達した時には、そこから少し折り畳み方を変えて、改めてエネルギーを計算してみるというサブプログラムを用意しておきます。折り畳み方を変える方法が多すぎて網羅的に計算できないならば、乱数を使ってルートを選んでしまうというのも一つの手でしょう。このサブプログラムがうまく働けば、図のように偽の最小値から脱出できるはずです(うまく働かないケースも少なくないでしょうが)。一般的に言って、きわめて多くの変数を持つシステムに関して特定の目的に適合する状態を探索するという課題では、状況に応じて(時には乱数を使ってランダムに)条件を変えながらシミュレーションを行うことが有効な場合が少なくありません。
もっとも、こうしたプログラムを制作する際に、どのように条件を変えるかという点で人間の経験知が必要となります。実際、複雑なシステムでは、闇雲に条件を変えるのではなく、実現されているパターンに応じて探索ルートを選別するといった手法を用いないと、なかなか最適解に到達できないからです。どうすればコンピュータに経験知を教え込むことができるのか、今のところは想像の埒外です。
【Q&A目次に戻る】

日常的なイメージによると、時間反転された現象とは、ビデオ撮影した映像を逆回ししたときに見えるものです。こうした逆回しの映像は、多くの場合、現実には起こりそうもない奇妙な光景なので、「世界は時間反転に対して対称ではない」と思いがちです。しかし、実は、こうした逆回し映像の奇妙さは、初期条件としてきわめてエントロピーの低い状態を用意したという統計的な要因によるものであり、基礎的な物理法則とは関係ありません。基礎法則に時間反転対称性の破れがあるかどうかを調べるためには、こうした統計的な要因を排除して考える必要があります。
高エネルギー加速器研究機構で行われたK中間子のβ崩壊に関する実験を例に取ることにしましょう。K
+の一部はμ
+(μ粒子の反粒子)とν(ミューニュートリノ)を放出してπ
0に変わります。反応式で書くと、
K
+ → π
0+μ
++ν
です(素粒子の反応式では“+”は書かないことが多いので、これ以降は省略します)。さて、この過程が時間反転に対して対称かどうかを見るには、どのような実験を行えば良いのでしょうか?
ちょっと考えると、π
0μ
+ν→K
+ という実施困難な実験を行わなければならないような気がしますが、そうではありません。われわれの世界では、π
0μ
+ν→K
+ という反応は統計的な理由でほとんど起きませんが、統計的な要因は無視すべきなので、仮に起きたと仮定して映像を逆回しすることにします。すると、時間が反転した世界での K
+→π
0μ
+ν という“β崩壊”になります。問題にしなければならないのは、われわれの世界での K
+→π
0μ
+ν と時間反転した世界での K
+→π
0μ
+ν の違いなのです。
頭でイメージしていると混乱するので、式で話を進めていきましょう。時間反転した世界での方程式は、われわれの世界での方程式における時間変数t が -t に置き換わったものになっています。その結果、運動量
p は(速度を含んでいるので)
-pに、角運動量
L とスピン
s は(回転の向きを含んでいるので)
-L と
-s に変わります。ただし、この変換は、β崩壊によって生成した3つの粒子の運動量分布には影響を及ぼしません(運動量分布とは、運動方向の角度と運動量の大きさに関する分布なので)。われわれの世界と時間反転した世界で差を見るには、別の量を考える必要があります。
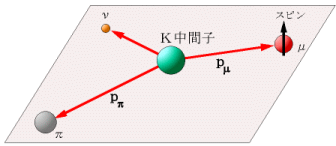
重心系で考えることにすると、初めにK中間子が静止しているので、崩壊によって生成されたπ,ν,μの3粒子は同じ平面内に放出されます。ここで、μのスピンが、この平面に対してどちら向きに偏極しているかを問題にしましょう。式で表すと、これは
R =
sμ・(
pπ×pμ)/|
pπ×pμ|
と置いたときの R の正負を考えることに対応します(添字は素粒子の種類を表す)。時間を反転すると、スピン
s と2つの運動量
p の符号が反転し、これに対応して R の符号も変わるので、もしわれわれの世界で R が正(もしくは負)ならば時間反転した世界では R が負(もしくは正)になる訳です。従って、われわれの世界で K
+→π
0μ
+ν という過程に関する測定を行って R がゼロでないという結論が得られたならば、時間反転の対称性が破れていることになります。
高エネルギー研では1996年から5年間掛けてデータが集められましたが、その結果は、
R = -0.0017±0.0023(統計的誤差)±0.0011(系統的誤差)
というもので、R がゼロでないかどうかはわかりませんでした。ノーベル賞の対象となった小林・益川理論でも時間反転対称性の破れが生じますが、その予測値は10
-7程度で、この実験では測定できません。結局のところ、小林・益川理論以外に時間反転対称性の破れをもたらすメカニズムがあるかどうか良くわかっていないというのが現状です。
ちなみに、時間反転に対する対称性が破れていることは、理論的には既定の事実とされています。現在の素粒子論の基礎になっている場の量子論によると、理論がローレンツ不変性を満たすと仮定した場合、C(荷電共役),P(空間反転),T(時間反転)の3つの変換を全て行ったとき、現象を記述する方程式が変換前と同じ形になることが示されています。これをCPT定理と言います。CPT定理によると、CP対称性が破れているならば、その破れを相殺するように時間反転の対称性も破れていなければなりません。CP対称性の破れが実験によって観測されている以上、時間反転対称性も必然的に破れているという訳です。
【Q&A目次に戻る】

「宇宙が一様に膨張している」というのは、あくまで近似でしかありません。銀河同士の合体が観測されていることからもわかるように、詳細に見ると、宇宙のエネルギー分布にはムラがあり、一様な膨張からのズレが存在しています。ただし、このズレは、一様膨張に対する微小な補正でしかありません。「宇宙全体は(ほぼ)一様に膨張している」ものの、「近隣の銀河同士は万有引力の作用によって引き合い衝突・合体する」というわずかなズレが見られる訳です。一般相対論の基礎方程式(アインシュタイン方程式)を解くことにより、全体として膨張しながら一部で天体の凝集が起きる過程を明らかにしたピーブルスは、宇宙のエネルギー分布にムラがあるさまを「しなびて皺の寄ったリンゴの表面」に喩えています。
宇宙に見られるムラには、さまざまな階層があります。銀河レベルのムラは、宇宙初期における暗黒物質の揺らぎに起因するものと考えられています。ビッグバンで誕生してから数十万年間は、宇宙に強い光が満ちていました。強い光は物質分布のムラをならすような作用があり、ちょうど砂場を箒で掃いたときのように初期宇宙では物質分布でこぼこがなくなっていきますが、光を吸収も放出もしない暗黒物質は、この均一化の作用を受けないため、ビッグバンの当初からあった不均一性が保たれることになります。宇宙が冷えて光が失われると、暗黒物質が周囲よりも多く存在する領域に物質が集まってきて天体集団を形成します。これが数万から数十万個の恒星を含む球状星団です。近接する球状集団は合体して渦巻銀河・楕円銀河などの銀河を作り、銀河同士はさらに合体して大型の楕円銀河になっていきます。銀河同士の合体は今も続いており、われわれの住む天の川銀河にも、おおいぬ座矮小銀河(というより銀河の残骸)が合体しつつあります。
宇宙にはさらに巨大なムラもあります。例えば、銀河の分布には1億光年以上のスケールで不均一性があり、銀河があまり存在しないボイド(空洞)が銀河密度の高い領域に囲まれていることがわかっています。これもビッグバンの当初から存在していたムラの名残ですが、宇宙が始まってからまだ137億年しか経っていないので、はっきりした構造が形成されていません。
【Q&A目次に戻る】

銀河内部に存在する星間ガスの大部分は、質問文にもあるように、凝集することなく気体のまま漂っています。天体を作ることができるのは、いくつかの条件が重なって凝集したガス雲だけです。ここでは、惑星の形成にまで至るプロセスを3つの段階に分けて説明しましょう。
- ガス雲の形成 : 気体というと、容器に入れられて密度や温度が一様になった状態を思い描きがちですが、宇宙空間を漂っている星間ガスの場合は、重力や恒星風などの作用を受けながら運動しているので、密度は場所によって異なっています。密度が高い領域では、気体分子同士が頻繁に衝突し、電子が高いエネルギー準位に遷移しやすくなっています。遷移した電子はすぐに電磁波を放出して基底状態に戻りますが、容器内部の気体の場合とは異なり、このとき放出された電磁波は宇宙空間の彼方にエネルギーを運び去ってしまうので、星間ガスは次第に冷却され、星間ガスは収縮してますます密度が高くなっていきます。このような冷却過程の結果、星間ガスの内部に比較的低温(絶対温度で100K程度)で高密度(1立方センチ当たり水素原子が10個以上)の領域が生じます(実際には、恒星の光や宇宙線による加熱過程もあるので、話はこれほど単純ではありません)。この低温・高密度領域が星間ガス雲です。温度が低い大量のガスが狭い領域に集められると、収縮したときの重力の上昇(高密度なので大きい)が圧力の上昇(低温なので小さい)を上回るようになるため、何かの拍子に少し圧縮されると、さらに小さくなろうとする重力の作用が勝って、どこまでも収縮していきます(この収縮は、核融合による熱源が誕生したり、固体の核が形成されたりするまで止まりません)。典型的な星間ガスの場合、太陽の1000倍程度の質量が集まると、際限のない収縮を始めます。
- 原始太陽系星雲 : 収縮し始めた星間ガス雲は、全体の自転による遠心力のために、ある段階まで収縮すると、自転軸に近づく方向にはなかなか収縮できなくなります。一方、自転軸に平行な方向は重力でどこまでもつぶれていくので、最終的には、きわめて薄い円盤状の星雲になります。ガスの大部分は中心部に集まって高温・高密度の状態を作り、ついには核融合を行う原始太陽を生み出します。
- 微惑星の成長 : 原始太陽の周囲にある薄い円盤状の星雲内部では、密度が高くなるにつれて塵や氷などの固体成分が現れます。重力と(星雲全体の自転による)遠心力がほぼ釣り合ったまま原始太陽の周りを回っているため、これらの固体は、互いに小さな相対速度でしか運動していません。その結果、会合するうちにくっつきあって成長し、微惑星と呼ばれる小さな天体になります。微惑星は互いに合体するとともに、重力で周囲のガスを集めて、さらに成長していきます。木星や土星のようなガス惑星は、固体の核がガスを集めて巨大化したものです。火星軌道より内側では、温度が高くメタンやアンモニアが氷にならないため、巨大なガス惑星は形成されません。
【Q&A目次に戻る】
©Nobuo YOSHIDA
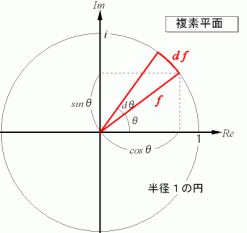 複素数の乗法で重要になるのが、絶対値が1の数です。偏角がθで絶対値が1の複素数を f(θ) と表しましょう。偏角を dθ だけ増やしたときの f の変分は、右図からわかるように、絶対値が半径 1、中心角 dθ の扇形の弧長、偏角が f に対して90°増えたものになります。従って、絶対値 1、偏角90°の複素数(虚数単位)を i と表せば、
複素数の乗法で重要になるのが、絶対値が1の数です。偏角がθで絶対値が1の複素数を f(θ) と表しましょう。偏角を dθ だけ増やしたときの f の変分は、右図からわかるように、絶対値が半径 1、中心角 dθ の扇形の弧長、偏角が f に対して90°増えたものになります。従って、絶対値 1、偏角90°の複素数(虚数単位)を i と表せば、
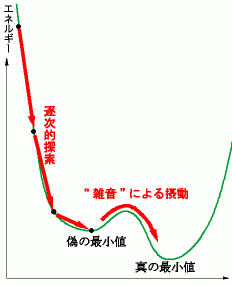 それでは、コンピュータの演算にこうした“雑音”を加えることは可能でしょうか? 例として、ある条件下でタンパク質がどのように折り畳まれるかという問題をコンピュータに解かせる場合を考えてみましょう。あらゆる折り畳み方を網羅的に調べるのは現在のコンピュータでも不可能です。そこで思いつくのが、逐次的なアルゴリズムに基づいて、少し折り畳んではエネルギーを計算し、その値が前よりも小さくなるならば、さらに折り畳みを続けていくという方法です。しかし、実際には、このやり方で最適解を見つけることは一般にできません。たまたまエネルギーが極小値を取る折り畳み方に到達すると、そこから先に進めなくなってしまうからです。人間ならば、考えが行き詰まっても視点を変えるなどして先に進むことが可能ですが、コンピュータはそうは行きません。そこで、人間の脳に見られる“雑音”と同じ効果を持つ摂動を加える必要があります。
それでは、コンピュータの演算にこうした“雑音”を加えることは可能でしょうか? 例として、ある条件下でタンパク質がどのように折り畳まれるかという問題をコンピュータに解かせる場合を考えてみましょう。あらゆる折り畳み方を網羅的に調べるのは現在のコンピュータでも不可能です。そこで思いつくのが、逐次的なアルゴリズムに基づいて、少し折り畳んではエネルギーを計算し、その値が前よりも小さくなるならば、さらに折り畳みを続けていくという方法です。しかし、実際には、このやり方で最適解を見つけることは一般にできません。たまたまエネルギーが極小値を取る折り畳み方に到達すると、そこから先に進めなくなってしまうからです。人間ならば、考えが行き詰まっても視点を変えるなどして先に進むことが可能ですが、コンピュータはそうは行きません。そこで、人間の脳に見られる“雑音”と同じ効果を持つ摂動を加える必要があります。
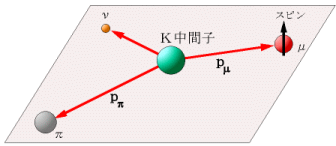 重心系で考えることにすると、初めにK中間子が静止しているので、崩壊によって生成されたπ,ν,μの3粒子は同じ平面内に放出されます。ここで、μのスピンが、この平面に対してどちら向きに偏極しているかを問題にしましょう。式で表すと、これは
重心系で考えることにすると、初めにK中間子が静止しているので、崩壊によって生成されたπ,ν,μの3粒子は同じ平面内に放出されます。ここで、μのスピンが、この平面に対してどちら向きに偏極しているかを問題にしましょう。式で表すと、これは